| �����L>>�@ |
| 20�P1�N12��2���i���j |
| �g�o�̈ꎞ�I�s�ǂ���� |
|
|
|
| 2011�N12��1���i�j |
| �t���ƂȂ�܂����B�@ |
�@�������̂ŁA��������t���ɂȂ�܂����B�N�ƂƂ��ɁA�P�N�����������Ă����悤�Ɋ����Ă��܂��B�N�����A�N��̋t���ŁA�N�͂����Ă����Ƃ����Ă����B���̂P�N���v���o�����Ƃ��Ă݂Ă������ɂ͋L�����o�Ă��Ȃ��B�L�^�����āA���߂Ďv���o�����Ƃ��ł���B���̂��Ƃ��A�P�N�����������Ă����悤�Ɋ����錴���ł��낤���A����Ƃ��A����̂̓������x���Ȃ��Ă��������ł��낤���H�����A�����ł���Ǝv���B
�@����́A���ŊO���A���쏜�̃{�����e�B�A�����Ă���O���[�v�̒��H����s���A�P�N�̊�������߂��������B
�@�����̌ߑO���́A�J�̂��߁A�u�A�������v�ł̊����͒��~�����B�ߌ�́A�V����܂ŁA���p�ŏo�����܂����B
�@��́A�O��s�l�b�g���[�N��w�ŁA�u��l�̂��߂̊��w�u����P�����l���͂Ȃ��K�v�H�E�E�E��ƂƏ���҂Ɗ��Ɓv����u���܂����B
|
|
|
|
| 2011�N11��30���i���j |
| �䒃�m���̕a�@�܂ŁA�o�����Ă��܂����B |
�@����A�ߑO���A�䒃�m���̕a�@�܂ŁA���Ȃ̒���f�f�ŏo�����Ă��܂����B�P�O���P�V���Ɏ�f�����l�ԃh�b�N�̌��ʂ������Ă����܂����B�������܂��A���t���������Ă��������܂����B���ʂ́A����܂łƁA�傫�ȕω��͂Ȃ��A�R���X�e���[�����������𑱂��邢�Ă���̂ŁA�������ʂƂȂ��Ă��܂��B
�@�����O����A�������C���Ȃ̂ŁA�T�����̕��ז�����������Ă��܂����B
�@�����t�߂̃C�`���E���́A�܂��F�Â��Ă��܂���ł����B |
|
|
|
| 2011�N11��29���i�j |
| �J�����i�f�V�R����� |
�@�����̌ߌ�A�����_�Ƒ�w�ɂ��f�����āA����w�m�������A������̃J�����i�f�V�R�����������Ă����B�Z���g���[�̌��i��Q�D�T�����p�j�Q�O�ɁA�Q�T�ԑO�i�P�P���P�R���j�ɁA�Q�����̎��A���Ă���A���肵�ĊԂȂ��̏�Ԃł���B���̃J�����i�f�V�R�̎�́A������w�_�w���̂j�������A����s�t�߂̑�����Ŏ��n���ꂽ���̂ŁA�m���Ȃ��̂������ł��B
�@�厖�ɁA����Ɏ����A��A��������A��Ɉ�Ă邱�ƂɂȂ����B�������Ȃ��悤�ɂQ���ɂP����x�̐���������邱�ƁB�J��������Ȃ��悤�ɁA������p�[�S���̉��ɒu���B��������̂悢�Ƃ��낪�����B�N�������āA��������A�T�t���炢�ɂȂ�����A���a�P�T�������x�̃|�b�g�ɐA���ւ���B���̌�A���A����傫�ڂ̔��ɐA���ւ��Ă��悢�Ƃ����������������B
�@
�@���ꂩ��A�����A�ώ@���Ȃ���A��ĂĂ��������B�����Ɉ���āA�Ԃ��炫�A�킪����������E�E�E�Ɗ���Ă���B
|
|
|
|
| 2011�N11��28���i���j |
| �H���F�v���u�|�Ƃ�ڂ���̔��z�v������ |
�@�O��s�̂r�m�r�|�L�l�b�g�́u�Ƃ������v�̓��L����m�����A�H���F�v���u�|�Ƃ�ڂ���̔��z�v�̕����ł���肵���B���̖{�́A�u�k�ЁE�u���[�p�b�N�X�u�|�Ƃ�ڂ���̔��z�v���{�ɔ��^��傫�����ĕ������ꂽ���̂ł���B�P�P���P���ɕ����̏��ł��A������Ѓh�b�g�R�����甭�s����Ă���B
�@���e��
�P�|�Ƃ�ڂ̍�i���낢��
�Q�|�Ƃ�ڂ̃��[�c�����ǂ�
�R���z�H�[
�S�ڂ����l�����u�|�Ƃ�ڂ̉Ȋw�v
�T�|�Ƃ�ڂ��ł���܂�
�U�肪�l���č��
�ƂȂ��Ă���B
�@���҂́A�T�N�ԂɂW�O�O�@�قǍ�肠���������ł���B
�@�����͂P�@���P���Ԃقǂō���Ă��������ł��邪�A�Ō�ɂ͂P�@�U���Ԃ����āA�V��ł���Ƃ̂��Ƃł���B���ׂČ`���قȂ邷�炵���|�Ƃ�ڂ̎ʐ^����R�f�ڂ���Ă���A��ς��炵���{�ł���B
|
|
|
|
| 2011�N11��27���i���j |
| �J�����i�f�V�R����Ă鏀�� |
�@�H�̎����J�����i�f�V�R�̕c�������Ă��������A����ň�ĂāA����Ƃ�A���₵�Ă������Ƃ��A�v�悵�Ă���B���N�����邱�Ƃł��邪�A�����Ă���������̂͋M�d�ȑ�����̎����̃J�����i�f�V�R�ł���̂ŁA�T�d�ɐi�߂����Ǝv���Ă���B
�@�����A�i�}�[�g�ŁA�ԋʓy�ƕ��t�y�Ɩ������w�������B�J�����i�f�V�R�͓���������D�ނ悤�ł���B�Ƃ肠�����́A���A�������āA��������̂悢�Ƃ���ɂ��������B
�@��R���₹��A����߂��ł̂��낢��ȂƂ���ŁA�Ԃ��炩���������B�l���Ă��邾���ŁA���邢�C�����ɂȂ�܂��B
�@
�@������A���C���ŁA�A�����������B�Ђǂ��Ȃ�O�Ɏ��������̂ŁA�����́A���d���Ă���B |
|
|
|
| 2011�N11��27���i���j |
| ���j���̒��́ATBSTV�́u�������k�v������B |
�@�����i���j���j�̒����A�s�a�r�s�u�́u�������k�v�������B
�@�i��͌����̓��勳����~�M����B�����̃Q�X�g�́A�Δj����ƕЎR�P������B�b���
�@���W�Q�O�O�~����A���B���Z��@�ǂ��Ȃ�
�A����u�d�����v�A�ˑR�u�N�������v�̗��Ȃ�
�BTPP���A����Ȃ��a�A�u�������v���K�^�K�^�A�u�ʒ��F�����v���āE�E
�C�˓��u����Ő��ǁv�I�I�A�ǂ�ǂ�u���ݍ���v�ŁE�E�A�����Łu����Q��v�A�����O�́u���}�v�́E�E
�Ȃǂł������B
�@�Ō�́u�Ɉꌾ�v�ł́A�ЎR����́u����}�͏���ł��グ�Ȃ��Ƃ����Đ����Ƃ����B����ł�����Ȃ�A���̑O�ɑ��I���������v�ƁA�Δj����́u����łƎЉ�ۏ�̖{���I�ȋc�_�𐳖ʂ�����v�Ɣ����B |
|
|
|
| 2011�N11��26���i�y�j |
| ����u�K��u�A�������v |
�@�ߑO���A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̙���u�K��A�u�A�������v�ł������B�u�t�́A�O���[���A�h�o�C�U�[�̉�����������B�e�[�}�́u���ؕʂ̎����v�ŁA�������P�T������u�����B
�@�����́A�R��̘A���V���[�Y�̂Q��ڂł���A����͂P���P�W��(�y�j�Ɂu���t���̐��}����v���\�肳��Ă���B
�@�O���̂P���Ԃ́A�u�`�ŁA�㔼�̂P���ԗ]��́A���`�m�L�̙�����K���s�Ȃ����B
|
|
|
|
| 2011�N11��25���i���j |
| �x�m�R�ɁA�k�����ӂ��Ă���悤���B |
�@�ߑO���A�����V����̗��̍������R���̏ォ��x�m�R��]�B�x�m�R�ɂ͕Б��ɁA�_���������Ă����B�k���������Ă���悤�Ɍ�����B���ꂩ��A�����Ȃ�ɂ�A�܂��܂��x�m�R���������茩���Ă���悤�ɂȂ�B
|
|
|
|
| 2011�N11��24���i�j |
| ���Ԍ����ƍr��͐�~�ł̖쒹�ώ@�� |
�@�����́A�������{�����e�B�A�쒹�O���[�v�̖쒹�ώ@��i���匤�C�j�ŁA���������ƍr��͐�~�Œ��������܂����B
�@���������̒r�ł́A�����J�����A�q�h���K���A�z�V�n�W���A�L���N���n�W���A�I�i�K�K���A�o���A�I�I�o���A�J���Z�~�Ȃǂ��A�r��͐�~�ł́A�`���E�Q���{�E�A�^�q�o���A�C�\�V�M�A���Y�A�x�j�}�V�R�Ȃǂ��ώ@�ł��܂����B�S���ŁA�R�O��ł����B
�@���V�C���悭�A�y�����ώ@��ƂȂ�܂����B
|
|
|
|
| 2011�N11��23���i���j |
| ��H�ŁA�V�h�̍������P�R�K�܂ŏo�����Ă��܂����B |
�@�����́A�����̉�H�ŁA�V�h�̍������P�R�K�ɂ��鎩�R�h�C�^���A�����X�g�����܂ŁA�o�����Ă��܂����B
�@�X�̖��O�́A�J�m�r�G�b�^ �^�J�}�T �E�G�^�P�B���i�����[�Y�i�u���ŁA�������Ƃ��āA���������A�ƂĂ��悩�����ł��B |
|
|
|
| 2011�N11��22���i�j |
| ��������ӂ̃n�P�̓����ӂ���� |
�@�ߌ�A��여��A����Ȃ��Ƃ�����̃t�B�[���h���[�N�ŁA������̃n�P�̓����ӂ�������B
�@�ߌ�1���ɁA���̐��V�䋴�ɏW�����āA�O�����w�Z�̘e�ɂ���u�̖̂��v���݂āA�ێR���Ŗ��ƕʂ�A���������������J���@�̗N�������w�����Ă����������B
�@�ш�_�Ђ̗N���A�����o�ϑ�w�̐V���Y�r�������B
�@
�@�@���̌�A�������s���̖�������\��ɂȂ��Ă������A���́A�s���ŁA���炳���Ă����������B
|
|
|
|
| 2011�N11��21���i���j |
| �����̖��̗��ʑ���i11���j�@ |
�@�����́A�����̖��̗��ʑ�����A�O��s���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ł����Ȃ����B�����́A�����悤�Ȃ̂ŁA�������������A�܂��܂��Ȃ����ɑ�������悤�Ǝv�����B�����́A��l�����̑���ł���B���āA�v������肢���V�C�ŁA��Ƃ͏�����2���Ԕ��ŏI�������B
�@���ʂ́A�挎���́A10������P�T�����x�������Ă��邪�A�܂����Ȃ萅������Ƃ�����ۂ���B
�@
�@�t�߂ł́A���̐앝�́A��W������A���[�͕��ςŖ�20�������ł������B�앝���T�������āA�����𗬂��āA�����𑪒肷��B�ł��������͏������x���A�E����������̂ŁA�����������Ƃł���B
|
|
|
|
| 2011�N11��20���i���j |
| �����s�܂ŁA�L�O�u����u�s������Ă�̂܂��Â���v���ɍs���ė��܂����B |
�@�ߌ�A�����s�̌b�w����w�̂i�Q�O�Q�����ŊJ�Â��ꂽ�A�����O���[���{�����e�B�A�X�؉��Â̋L�O�u����u�s������Ă�̂܂��Â���v���A�����ɍs���Ă��܂����B
�@
�@�����O���[���{�����e�B�A�X�؉�̊�����10���N���}����B�����̂��������́A�u�݂ǂ�̐R�c�ψ��v3�����A�r��Ă��������E�Βn���A���犾�𗬂��ĎG�ؗт̕ۑS��}�钇�Ԃ𑝂₷���߂ɕ���14�N�Ɂu�����O���[���{�����e�B�A�u���v���n�߂����Ƃł������B���̌�10�N�ɁA10��̍u�����J����A�u����u��344���̓���200�����A��ɏ������āA���������Ă�����Ƃ̂��Ƃł����B
�i�P�j�O���́A�����O���[���{�����e�B�A�X�؉�̊�����1����15���قǂ���A9�̃{�����e�B�A�c�̂̊������������B
�i�Q�j��u���Ƃ��āA�����s�s��w�����w�������O��j�Y����́u�s������Ă�̂܂��Â���v����1���Ԃقǂ������B
�@��u���́A�n���̗��j����n�܂������A���ŁA��ۂɎc�������t�������Ƃ߂��B
�@�u��X�̐����́A�������l���������炷�V�X�e���̏�Ɏx�����Ă���v�A
�u�������̂Ɋw�Ԃ����Ȃ��v
�u�L������ǂ����߂鎞��͏I������B���ꂩ��́A�L������[�߂鎞��ł���v
�i�R�j�Ō�ɁA1���ԂقǁA���J���k��������B
�@
�@�O��s�ŁA�̃{�����e�B�A���������Ă��鎄�ɂ́A�����̋L�O�u����́A��������Ƃ��āA��ώQ�l�ɂȂ���̂ł������B�@
|
|
|
|
| 2011�N11��20���i���j |
| �u�[�^���Ɋw�ԁA�����́u�K���v |
�@���o�Ƃ��ė�������Ă���u�[�^���̃����`���N�����v�Ȃ́A�挎��������A������������� �V�����s�ƂȂ邻���ł��B���Ƃ́A���N�T���ɗ�������\�肾�������A�����{��k�Ђ̔����ʼn������Ă������̂��ƁB
�@17���ɂ́A�����K��A�O�c�@�{��c��ʼn������s���܂����B�i�����̑S���͉��L���猩�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�j�R�j�R����j���[�X�@�@ http://news.nicovideo.jp/watch/nw147415�@�@�j http://news.nicovideo.jp/watch/nw147415�@�@�j
�@18���ߌ�A��Вn�E������K�ꂽ�B���w�Z�ł́A�q�ǂ������̑劽�}����B�u���v�������Ƃ̍����̔����́A�q���������������܂����B
�P�W����A���s���肵�A�P�X�����ɂ́A���t����K��܂����B
�P�X���A�؍ݐ�̋��s�ł̊��}�s���ɘa���p�ŏo�Ȃ��A�W�҂������ւ����܂����B
�@
�@���A�u�[�^�������ڂ��W�߂Ă���̂́A�f�m�g�i�������K���j���A�����̒��S�ɂ����A�����i�߂Ă��邱�Ƃł��B�f�m�o�i���������Y�j���d�����鑽���̍����A�Q�l�ɂ��邱�Ƃ��K�v�����m��Ȃ��B
�@�u���̖̂L�����v�ł͂Ȃ��A�u�S�̖L�����v���ɂ��邱�Ƃ̏d�v�Ȃ��ƂɋC���t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�����ȍ�������A�ł��邱�Ƃ����m��܂��A�]��ɂ��������d���������Ă����o�ώЉ�V�X�e���́A���A�Ȃ���p�ɗ��Ă���Ǝv���܂��B
|
|
|
|
| 2011�N11��19���i�y�j |
��Ȏ蒠�� �Y��,�d���Ȃ����R�ώ@�����ň����߂��B
|
�@�܂����厸�s�ł������B�{�����e�B�A�������I���A�A��ɁA�悭�������u�C�^���A���H���p�b�p�p�X�^�[�v�ŁA���H��H�ׂ��B�ӂƎ蒠�����悤�ƃU�b�N�̒���T���Ă��A�T���Ă��A�蒠�͏o�Ă��Ȃ��B���܂����I�@���b�l��̌�ŁA�蒠���U�b�N�ɂ��܂��̂�Y�ꂽ�悤���Ǝv���A������T�������A�o�Ă��Ȃ��B��������߂āA�悢�����R�ώ@���܂ň����Ԃ����B
�@����܂����B�U�b�N�������Ă����I�Ɏ蒠��Y��Ă��܂����B���łɌ����Ă���Ă����̂ŁA�����ł����B
�@����ɂ��Ă��A���N�ɂȂ���2�x�ڂł���B�N�ƂƂ��ɁA���ӗ͂������Ă���悤���B�C�����Ȃ���I�Ǝv���܂��B |
|
|
|
| 2011�N11��19���i�y�j |
| �J�̒��A�{�����e�B�A�������s�Ȃ��B |
�@�����́A��R�y�j���A�������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ�����B���̏�A�����́A���̐��b�l�������A�o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�o�����鎞�ɂ́A�J�͂��ł������A�荏��9��������ɂȂ�ƁA�����~��o�����B�Q�������{�����e�e�B�A�́A������菭�Ȃ��A�Q�O�����܂�ł������B�����̍�Ƃ́A�t�G���X�ɂ���ނ�A���̏����ł������B
�@��Ƃ����Ă��邤���ɒi�X�ƉJ���~��o�����B�ʍs�l���A�C�̓łɂ������̂��A�u����J����v�Ɛ��������Ă����B���߂ɐ�グ�A���R�ώ@�Z���^�[�ɖ߂����B
�@11��������A���b�l��n�܂������A�����͋c�肪�����A1���Ԕ��̉�c�ɂȂ����B�����A�w��Ǘ��҂ƃ{�����e�e�B�A�̐��b�l���b�������āA���߂Ă������ƂŁA�^�c������Ă���B |
|
�@ |
|
| 2011�N11��18���i���j |
| �s����w�F�w���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���v�A |
�@�ߑO���A�O��s�Љ���ق̎s����w�����R�[�X�u���R�Ɛl�Ԃ̋����v�ł́A�������q��w���_�����L���O���搶�́u���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���v�Ƒ肷��u�`�̂Q��ڂ��������B���Ȃ�ɗ����������Ƃ��������Ă݂�B
�@�@�ً}���Ԃɒ��ʂ��āu������v���Ƃ����ł���Ƃ̕��͂ł������B�ً}���Ԃɒ��ʂ��ĂȂ�Ƃ������̂т����Ƃ̈ӎ��������Ƃ���ł��邪�A���ۂɂ́A��i���ł́A�����ⓦ���͋N���Ȃ��B�p�j�b�N�◪�D���N���Ȃ��B�ނ�����ۂɂ́u������Ă��܂��v�B�����ē����x��Ă��܂��B����͓����́u�[���v�ƊW������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B���ۂɂ́A���ӂ�ł͂Ȃ��A�����Ȃ��̂ł���B���̂ق����A������m���������邱�Ƃ���A�����̖{�\�I�ȍs���ł���B���̂��Ƃ��A�l�Ԃ̐i���̒��ł��A�܂��̂����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl�����邻���ł���B
�@�X�D�P�P�ŁA���E�f�ՃZ���^�[�r���ł́A�ŏ��ɍU�������k���Ƃ��̌�ɍU�������쓏�ł́A���̗l�q���قȂ��Ă����悤�ł���B�r�����̎c�����̎��ԕω����������ʂł́A�ڂ̑O�Ńr���ւ̍U����ڎ������쓏�̕����A�ɂ��ẴC���[�W���ł��Ă��镪�A�c�����͒Ⴍ�A��������i�߂Ă����B���Ԃɑ���C���[�W�i�����j���ł��Ă������ǂ����ŁA���ɍ��������Ă����B���̏�A�k���ł́A���w�K�̐l���u������āv���āA���������x�������ƍl������Ƃ̂��Ƃł������B
�@�A�ЊQ���̑����ƃ��f�B�A�A�ĂƂ̊W�ɂ��ẮA����܂łɒÔg������̌Ăт�����m���Ă������ɂ��Ă̒������ʂł́A�����߂����m��Ȃ������Ƃ̂��Ƃł������B�����ƂȂ������ɂ́A�����ŏ������W���A�����̔��f�ōs�����邱�Ƃ��K�v�ŁA���ȐӔC�̎���ł���Ƃ����̂��A�搶�̂��l���ł������B
�@�B�����Ռ��̌�̐S�����l����ƁA�܂��́u���E�v�A���̌�A�S�������n�߂āu��펞�K�́v����������B�ڂ����݂�ƁA�^�������̈ӎ��̐����A��펞�K�͂̐����A���ݕ}���E�����s�ׁA����K�͂̉A������H�̎Љ�����Ƃ̌o�߂��o��B�Ō�ɁA�B�ЊQ�nj�Q�i���₷���A���ɂ�����A�݂��ɂށA�Ȃǁj���������琔�T�ԑ����A�啔���͉��邪�APTSD�S�I�O����̃X�g���X��Q�������Ԏc��P�[�X���A�ߍ��Ȍo���������ꍇ�ɂ͍ŏ��R������ő�łT�W�������Ǐ��悷��Ƃ̂��Ƃł������B
�@
�@��X�́A���̂悤�ȁu�c�߂�ꂽ�F�m�v��u�S�����ꂽ�s���v�̂��Ƃ��A�ӎ����āA�s��������悤�ɂƂ߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł��A������Ƃł���B |
|
|
|
| 2011�N11��17���i�j |
| �g�ˎ��ŁA���F�Ƃ����̉�H |
�@�����́A���߂���Q���Ԏ�A�g�ˎ��̃��X�g�����ŁA��w�̗F�B�Ɖ�H�����āA���낢��Ɗ��k�������B��w�@�C�m�ے����I�����āA�ꏏ�ɓ����ɏo�āA�A�E�������̂ŁA�t�������͒����B���݂��ɁA�傫�ȕa�C�����Ă��Ȃ��̂��A�����ł���B
�@���铹�ŁA�o�X����O�ł���āA��̓��̒r�̂܂���������B���N�̏H�X���Q�V���i�y�j�Q�W���i���j�̑�Q�X��S���Ή��t�F�A�[TOKYO�̊Ŕ��o�Ă����B���̈�̓����������̂ЂƂɂȂ�悤���B
�@
���䋴�́A���C����Ă����B�����l�q����������ς���Ă��āA�Ȃ��߂Ȃ��B
|
|
|
|
| 2011�N11��16���i���j |
| ���̂Ȃ��Ƃ����ʂ̑��� |
�@�����́A��여��A����Ȃ��Ƃ������Â̖��̈�ė��ʑ���ɎQ�������B���̒S���́A�O��n��̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�̗��ʂ̑���ł���B���ǂɕ�����āA���̏㗬���牺���̑S��ŁA���������B�p�x�́A�N�ɂR����S������Ă���B�����R�N�ɂ��Ȃ�B
�@�����́A��l�ő���������B���ƃy�A�ɂȂ����̂́A�����s�̉͐암�v��ۂ̐E���ł���B�����������������A���̂����V�C�ŁA��Ƃ͏����ɐi�B
�@�O��̕t�߂̖��̐앝�́A�S������Wm���x�ł���A�����̐��[�́A�P�T��������T�O�������x�ł������B�[���Ƃ���́A���C�ł́A����Ȃ��B
�@���ʂ́A�挎���́A�Q�O�����x�������Ă��邪�A�܂����Ȃ萅������Ƃ�����ۂ���B���́A������������A���ꂢ�ł���B
|
|
|
|
| 2011�N11��15���i�j |
| �A���ώ@������� |
�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n�������Â̐A���ώ@��s�Ȃ�ꂽ�B�u�t�͐��c��������A�s���P�R�����Q�������B����������ɂP�O���ɏW�����āA������B�n��AA�n��A�Ō�Ɏ��R�ώ@�����ώ@���A�ߌ�R���ɉ��U�����B
�@�A�J�V�f�A�C�k�V�f�A�N�}�V�f�̋�ʁA�A�J�}�c�A�N���}�c�̋敪�A�N�k�M�A�R�i���Ȃǂ̂ǂ�̂��낢��A�~�̃T�N���i�W���E�K�c�U�N���A�R�u�N�U�N���j�A�m�R���M�N�A���E�K�M�N�Ȃǂɂ��āA���[���A�����Ղ�̒����Ԃ̉���������������B
|
|
|
|
| 2011�N11��14���i���j |
| ���T���A���������ANHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�̉��o�ɒ��ځI |
���j����NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�ł́A���T���A���o�u���B������v�ƂłĂ����B���������O�ł��邪�A�u������v�́A�{���ł���B
�@���T���A���������A���o�ɒ��ӂ��Ă݂悤�Ǝv���B�@���a�̘a�����A�Ⴂ�l�X�̋����������Ă���Ƃ̘b������܂��B�܂��܂��ʔ����Ȃ肻�����B |
|
|
|
| 2011�N11��14���i���j |
| ���ɒ����A�N���ʂ̑���i�P�P���j |
�@�����́A���P��̖��ɒ����N���ʂ̑�����s�Ȃ����B���₩�ȓ��ŁA��Ƃɂ͉��K�ȓ��a�ł������B
�@����́A���̖����t�߂̂ق���삩��A�����̐Y�V���㗬�܂ł̂P�P�ӏ��ł���B�X�^�[�g���x�������̂ŁA�Q�ӏ������́A������ɑ�������邱�Ƃɂ����B����ɗv�������Ԃ͂S���ԗ]��ł������B
�@�P�O�����{�̑���l���́A��������Ă����B
�@
|
|
|
|
| 2011�N11��13���i���j |
| ��������A�쑽���܂ŕ����܂����B |
�@�����͂��V�C���悩�����̂ŁA���W�����ɉƂ��łāA���̑���牺���̐��c�J��̖��_���܂ŕ����A�������̊쑽���w�ɏo�āA���߂��ɋA���Ă��܂����B
�@�r���J���Z�~�̎p�͂Q�x�݂܂����B�A�I�T�M�A�R�T�M�A�_�C�T�M�A�I�i�K�K���A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�A���Y�A�J�����q���A�R�Q���A�V�W���E�J���Ȃǂ��������܂����B�c�O�Ȃ���A�����J�����̎p�͌������܂���ł����B
�@�����ł́A�A���`�E���̌Q�����c���Ă���A�Ԃ��炫�A�������Ă��܂����B
���_���߂��ł́A�O����̃Z�C�o�������R�V����ʂɐ����Ă���Ƃ��������A�����Ă��Ă��܂��B
�@�����~�ł́A�n��̃{�����e�B�A�c�̂̂���������̉�A���������Ă���p���������܂����B
|
|
|
|
| 2011�N11��12���i�y�j |
| �쒹��T�����I���������쒹�ώ@�� |
�@�����́A�������̖쒹�ώ@��A�ߑO�X������P�Q���܂ł������B��ʎQ���҂͂Q�O�����A����Ƀ{�����e�B�A�̃X�^�b�t�P�O������Q�����Ă���B�e�[�}�́u�~����T�����I�v�ŁA���N�P�O�����痂�N�̂S���܂ŁA�����P���Q�y�j���ɍs�Ȃ���BPR�́A���������̂V�ӏ��Ƀ|�X�^�[�W�������邾���ł��邪�A�Q�O�N�߂����{���Ă���̂ŁA�悭�m���Ă���B
�@�X���ɁA���R�ώ@�Z���^�[�O���o�����āA���R�ώ@���������A�킫���L�ꂩ����̉E�݂�܂ʼn���A���̌�A������B�n��ɓ���A���ꂩ��A�n�����܂ŕ����A�Ō�Ɏ��R�ώ@�Z���^�[�̃��N�`�����ŁA�����킹�i�������̊m�F�j���s�Ȃ��B
�@�C��͑啪�����Ȃ��Ă������A�܂��~���́A�������t�߂ɂ͏��Ȃ��B����ł����N���߂ăV�����P�H�m�F�ł��܂����B�L�Z�L���C���m�F�ł��܂����B�}�K�������܂����B��N�������Ɋm�F�ł����W���E�r�^�L�A���Y�A���}�K���A�A�I�W�Ȃǂ́A�c�O�Ȃ���m�F�ł��Ȃ������B��������J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�I�I�^�J�A�R�Q���A�J�����q���ȂǁA�S���łP�X����m�F�ł��܂����B�������ł́A�R�u�N�U�N�����炢�Ă��܂����B
�����̖쒹�ώ@��́A�P�Q���P�O���i�y�j�X������s�Ȃ��܂��B
�@
|
|
|
|
| 2011�N11��11���i���j |
| �s����w�F�u���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���i����Љ�ƍЊQ�j�v |
�@�����̎s����w�����R�[�X�ł́A���R�ЊQ����̊w�K�Ƃ��̑�`���R�ЊQ�̒��Ő����c�邽�߂̕���i����ҎЉ�ƍЊQ�j�`�ɂ��āA�������q��w���_�����L���O���搶����u�`���������B
�@�搶�ɂ��Ɓu������w�����o���ꂽ�ꍇ�ł��A�����T�O�����邱�Ƃ͂܂�ł���B���퐫�o�C�A�X�E������nj�Q�Ȃǂ̃q���[�}���t�@�N�^�[�Ȃǂ��e������v�����ł���B
�@�������������͈͂ł́A����x�点�錴���̂ЂƂ��u�o�C�A�X�̂����������X�N�F�m�i���퐫�o�C�A�X�j�v�ł���A�܂��u�}�����ꂽ�s���v�ł���Ƃ̂��ƁB�l�Ԃ́A�����ɂ������`�ŔF�����Ă��āA�ُ�𐳏�͈͓̔��̂��ƂƑ����Ă��܂��悤�ȍ�������邱�Ƃ�����B���ɂ́A�u������nj�Q�v������B�ً}���Ԃɖʂ��ĐS���I�A�����I�������łāA�}�q��ԁA��R�����ƂȂ��Ă��܂��B
�@���̂悤�Ȃ��ƂŁA�����x��邪�������Ă��܂��Ƃ̂��Ƃł������B
�搶�ɂ́A�R�̎����̃r�f�I�i�@���߂��ăK�b�e���A�A���E��������ƁA�B����ȁI�j�������Ă��������A��ϋ���������A�킩��₷�������B
�@�l�Ԃ́A�C���[�W�ł�����̂����F���ł��Ȃ��悤�ŁA����܂ł̌Œ�ϔO�ɂƂ���A��R�ƂȂ��Ă��܂��Ă��ẮA���s�����Ƃ�Ȃ��B���ӂ��ׂ����Ƃł���B
|
|
|
|
| 2011�N11��10���i�j |
| ����쒹�ώ@�������� |
�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̉�̌���쒹�ώ@���������B�{�����e�B�A�P�R�����A���R�ώ@���A������B�n��AA�n��ƂQ���Ԕ�����A����T�����B�~���͏��Ȃ������B�ł��A�L�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�W���E�r�^�L�A�A�I�T�M�A�J���Z�~�ȂǂP�X����ώ@�����B
�@
���̌�A���������쒹�O���[�v�̃~�[�e�B���O���s�Ȃ����B�ߌ�́A���o�[�h�T���N�`�������̂����r�̐�����Ƃ������B
|
|
|
|
| 2011�N11��9���i���j |
| �Z�L���C�̒��� |
�@���̋G�߁A���t�߂ł́A�Z�L���C�̒��Ԃ̃n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�L�Z�L���C�ƃ^�q�o�����悭��������B
�@�^�q�o���́A���̒��ł���ԏ������A�X�Y�����炢�̑傫���ł���B���̂���A������̐X�����̒��z��s�ꉡ�̃O�����h�ł悭��������B
���x�A�C�i�r�̎���̃��[�v�ɁA�Z�O���Z�L���C���~�܂��āA����ɋ����Ă����B�{�ɂ́A�u�W�[�s�[�`�`���W�[�W�W�v�Ȃǂƕ��G�ɂȂ��Ə����Ă��邪�A�������́A�L�����ł��Ȃ������B�X�Y����菭���傫���B�n�N�Z�L���C�ɂ悭���Ă���B
���łɁA���Y�̎p�����������B
�C�i�r�ɂ́A�������S�O�H�ȏ�̃q�h���K���������B�J�C�c�u���������B
�@���������Ă���A���z��s��߂��̃v���y���J�b�t�G�ŁA�̂�т蒋�H��H�ׂ��B
|
|
|
|
| 2011�N11���W���i�j |
| �~�̃J������ |
�@����̌ߌ�A�v���Ԃ�Ɉ�̓������ɗ���������B�䒃�m���r�̐��͂ɂ����Ă��āA�悭�Ȃ��B�f���ɂ��ƁA���낢��Ȑ������P�̑s�Ȃ��Ă���悤�����A�ƂĂ��[���ȑ�ɂȂ��ĂȂ��悤�Ɍ�����B����ł́A���N��̊J���P�O�O�N�܂łɁA�r�̐������ꂢ�ɂȂ�̂́A�Ȃ��Ȃ�����悤���B
�@���̂悤�Ȓr�ɂ��A�L���N���n�W���A�n�V�r���K���A�I�i�K�K���A�I�I�o���A�J�C�c�u���Ȃǂ������B�a��������l�́A�قƂ�nj������Ȃ����A�J�������́A�ݕӂ̉�X�̕��ɁA�ߊ���Ă��āA�a���ق������ł���B���̎p������ƁA��X�̂��Ȃ��Ƃ��ɁA�a�������Ă���ЂƂ�����悤�Ɍ�����B
|
|
|
|
| 2011�N11��7���i���j |
| �v���Ԃ�ɑ��������� |
�@�ߑO���A�Q���ԗ]��A�v���Ԃ�ɑ������������B�G�m�R���O�T��V�̐쌴���L�����Ă����B
���̕��́A�I�I�^�J���R���B����A�_�C�T�M��J���E�̌Q�ꂪ���ł����B
�쌴�ł́A�^�q�o���A�n�N�Z�L���C�����������B�����ł́A�x�j�}�V�R�����X�p�������āA����Ă��ꂽ�B�K�^�ɂ��A��u�ł͂��������A�Y�Ǝ������邱�Ƃ��ł����B�ܘ_�ʐ^���Ƃ��Ă���]�T�͂Ȃ������B���̑��A���Y�A�J�C�c�u���A�I�I�o���A�z�I�W���A�A�I�T�M�A�C�\�V�M�Ȃǂ����������B
|
|
|
|
| 2011�N11��7���i���j |
| NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�̍��T�̉��o�ɒ��ځI |
�@NHK���h���́A��������U�T�u�����̐^�S�v��R�P������ł���B���j���̒��h���𒍈Ӑ[�����Ă���ƁA���T�̉��o�҂̖��O���ł�B���T�́A���̉�ʂ���킩��悤�ɁA�u���B������v�ƂłĂ���B
�@���T�́A���ɁA���ӂ��Ă݂悤�Ɖ����Ă���B�܂��܂��ʔ����Ȃ肻�����B
|
|
|
|
| �@���j |
| �u����u���]�̐��݂��ƗN���̍Đ��v |
�@�����́A�ߌ�Q������A���]�s�̃G�R���}�z�[���ōs�Ȃ�ꂽ�u����u���]�̐��݂��ƗN���̍Đ��v���ɍs���Ă��܂����B�u�t�́A�_�J������i���݂��������\�j�ł����B
�@��ȓ��e��
�P�j���݂��Ƃ�
�Q�j���̗��j���猩�鍝�]
�R�j���]�̐��݂��̍Đ�
�S�j�N���E���݂��̕ۑS�ƉJ���̊��p
�@�ł����B
�@
�@�P���Ԕ��̍u���̌�A����̎��Ԃ�����A�Q���҂̖��ӎ������悭�����Ă����B
�@���̂̐�����̂̂����ꂽ���R�ȗN�����ɁI
�@���s�����̌��������Ă��Ƃ��ɗN���o���N�����A�N��U�Q���g������A���͉����ɗ���Ă���B��������p���铹�͂Ȃ��̂��H
�@������͂ǂ��Ȃ��Ă���H
�@�Ȃǂ���܂����B
��ϕ��ɂȂ�܂����B |
|
|
|
| 2011�N11��5���i�y�j |
| �������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ���� |
�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł������B���́A���o�[�h�T���N�`�����ɂ���u�����r�v�̕ێ��Ƃɉ�������B���́u�����r�v�́A�������Ȃ��A���Ƃ����P���悤�Ƃ����Ƃł���B����ꓬ�ŁA��Ǝ��ԂQ���Ԃł͕s���ł���A�ߌ�Ɏc���l�ŁA�����邱�ƂɂȂ����B���́A�ߌ�ɕʂ̗\�肪����̂ŁA���炳���Ă����������B
�@�ߌ�́A�P������A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A�����Â̍����V������̒|�і��x�Ǘ�����������A�Q�������B�Q�����Ɉ�x�̃{�����e�B�A�����ł��邪�A��V���w�Z�O�̒|�т̖��x�Ǘ����s�Ȃ��Ă��āA�������Â悭�Ȃ��Ă���B�����́A�Q�O�������Q�����A�Q���Ԃ��������������B
|
|
|
|
| 2011�N11��4���i���j |
| ��쎩�]�ԎU���F�L�`�W���E�\�E�A�����h�E�Ȃ� |
�@�����́A���]�ԂŁA�����A�㗬�̂�Ȃ������牺���̌䓃�⋴�Ԃ𑖂����B�r���ŁA���������R�ώ@���═����̐X�����ɂ�����������B
�@�㗬�E�݂̐��ԏ����o�c�_�Ƃł́A���Ԃ̓��͂��g���Đ��ĂȂǂ̔_��Ƃ��Č�����A��������R���Ԍ��w�ł���悤�ł������B�ߑO���́A���O�\�����݂��Ȃ��ƑʖڂƂ̂��ƂŁA�c�O�Ȃ��猩�w�������Ă��������Ȃ������B�ēx�A�s�����Ƃɂ������B
�@�������̎��R�ώ@���̂Ȃ��ł́A�Ԃ����Ȃ������ł��邪�A�L�`�W���E�\�E�A�����h�E�A���N�V�\�E�A���E�K�M�N�A�z�g�g�M�X�A�A���R�K�l�M�N�A�V�������i�A�^�C�A�U�~�A�c���u�L�Ȃǂ��炢�Ă����B
�@������X�����̒r�ł́A�q�h���K������R�����B�J�C�c�u�������āA����ɐ������Ă����B���z��s��̐��̖��̑f�X�^�W�A���ɒʂ��铹�ł́A�^����̑��ނ�Ń^�q�o���̎p�����������B�^�q�o���́A�������C�ɂ��Ă���悤�ŁA��r�I�悭��������B
�@
|
|
|
|
| 2011�N11��3���i�j |
| �u�A�������v�̋��ʎ��劈���� |
�@�����A��P�ؗj���́A�{�����e�B�A�����Ă���u���،����v�̋��ʎ��劈�����ł���B���̓��́A�e�l������I�Ɋ�����������ł���B�����́A�R���������ŁA�v���v���̊����������B
�@���́A�X���O�Ɍ����ɍs���A�Q���Ԓ��A�����̎��ɂ��Ă��閼�D�̊m�F��Ƃ��s�Ȃ����B�Ώۂ̎��͖�T�O�O�{����B�䕗���̉e�����āA���D���A�����Ă��܂����Ƃ�����B�C�����A���ɖ߂��Ă��邪�A����A�S���m�F�����邱�Ƃɂ����B���ʂ́A�S���قǂɁA���炩�̌��ׂ��������B
�@
�@�����ł́A�������A�T�U���J���悭�炢�Ă���B
�@
���̂ق��ɂ́A�A�x���A���炢�Ă���B�쑐�ł́A�{�����e�B�A���厖�Ɏ��������Ă���L�`�W���E�\�E���A�炫�n�߂Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N11��2���i���j |
| �T�U���J�̎� |
�@���A�T�U���J�����ꂢ�ɂ����Ă��܂��B���������炫�����Ȃڂ݂���R���Ă��܂��B
�@�ł��A�悭����Ǝ������Ă��܂��B�k���͂����āA�킪���������Ȃ��̂�A���łɎ킪�����Ă��܂������̂�����܂��B
�@�ԂƎ��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���́A�O�N�炢���Ԃ̂��̂̂悤�ł��B�����Ԃ��ԁA�������Ă��闝�R����������̂ł��傤�B
|
|
|
|
| 2011�N11��1���i�j |
| �T���g���[���B�������Ɍ��w���s���Ă��܂����B |
�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̌��C��̂��߁A�R�����k�m�s���B���ɂ���T���g���[���B�������ɏo�����Ă��܂����B�Q���҂͑S���łS�O����ł����B���B����������́A�����x�����ꂢ�Ɍ����Ă��܂����B
�@�T���g���[���B�������́A�b���P�x�̘[�ɍL����L��ȐX�̒��ɂ���A�L���Ȏ��R�Ƌ�����}��Ȃ���A�o�[�h�T���N�`������ݒu���A�X�ѕی�ɂƂ߂Ă����܂��B���̐X�ѕی�̎w��������Ă��铌���_�Ƒ�w�����_����א搶�̈ē��ŁA�P���Ԕ��قǏ����̎��т����w�����Ă����������Ƃ��ł��܂����B
�@���̌�A�H�ꌩ�w�����āA�E�C�X�L�[�������������Ă��������܂����B�V���O�������g�E�C�X�L�[�u���B�v�������ŁA���Y����Ă���A�����������Ă��������܂����B
|
|
|
|
| 2011�N10��31���i���j |
| �T�U���J�����ꂢ�ɍ炢�Ă��܂��B |
�@�����A������A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�ɗ���������B�ړI�́A���ɂ��Ă��閼�D�̊m�F�����邽�߂ł���B�䕗�̉e�����āA��������D���������̂ŁA��x�S���̊m�F�����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ����B�����́A���̂P���iA-zone�j�̊m�F���s�Ȃ����B
�@�����ł́A���炢�Ă���̂́A�T�U���J�ƃA�x���A�ł������B�T�U���J�́A�����ł͈�ԑ������ł���B�T�O�{�ȏ゠��B�]�˂̉��|��Ƃ��Ĕ��W���A�����̕i�킪����悤���B�ڂ݂���R���Ă��āA�Ԃ̏��Ȃ����̎����A���ꂩ�炵�炭�y���߂�悤���B
|
|
|
|
| 2011�N10��30���i���j |
| ICU�Ղ����Ă��܂����B |
�@����h�b�t�̓�����ɊŔ��o�Ă����̂ŁA�����͂h�b�t�Ց�Q���ڂɏo�����Ă��܂����B���A�l�ŁA��ϊy������������������Ă��������܂����B
�@�ߑO���A�{�قŁA�e�K�̓W�������܂������A���ł��A���y�̐����t�����Ă��炦��u�[�X�𒆐S�Ɍ��邱�Ƃɂ��܂����B
�@�܂��́A�j���R�[���X�ł����B
���ŁA�N���V�b�N�̉��t���܂����B
�S�K��Jazz�̉��t�����邱�Ƃ��킩�����̂ŁA�����҂��ĕ����܂����B
�����ɂȂ����̂ŁA����ŁA�Ă����ǂ�A�Ă����A�`�W�~���ĐH�ׂ܂����B
�@�R�������Ă���A�����Ă���ƁA�V�����H�������������̂ŁA�R�[�q�ň�x�݂����܂����B�����Ԃ�L�����h�ȐH���ł����B
�@�����҂��āA�ߌ�Q������́A��w��q���ōs�Ȃ�ꂽ�p�C�v�I���K���R���T�[�g���܂����B�T�l�����ɉ��t���āA��P���ԂQ�O���قǂ̉��t���Ԃł����B���߂ăp�C�v�I���K���̐����t���āA�喞���ł����B
|
|
|
|
| 2011�N10��30���i���j |
| ���j���̒��́A�s�a�r�́u�������k�v���݂�B |
�@�����i���j���j�̒����A�s�a�r�s�u�́u�������k�v�������B
�@�i��͌����̓��勳����~�M����B�����̃Q�X�g�́A����T�v����ƕЎR�P������B�b���
�@�u�����v�̕��˔\
�A��B�d�͂̂�点
�B�N��U�W
�C�s�o�o
�D����ő���
�Ȃǂł������B
�@���䂳��́A�u�����̕ǂ��������͐��ނ���v�A�ЎR����́u�́A���S�^�]�ł͂Ȃ��A���X���X�Ƌc�_���Ăق����v�Ɣ����B |
|
|
|
| 2011�N10��30���i���j |
| �O��s�̉H�̓�q�T�M���A�S���{�w�����R���������s�A�m���召�w���̕��łQ�ʂ� |
�@�����V���̕ɂ��ƁA��U�T��S���{�w�����y�R���N�[���i�����V���Ў�Áj�������̖{�I�V���[�Y�S���ڂ̂P�O���Q�X���ɂ́A�����s�`��̃T���g���[�z�[���E�u���[���[�Y�Ńs�A�m���召�w�Z�̕����s���A���w�Z�͐X�c�₳��i���E�}�Ԏs����c�U�N�j���P�ʂɑI�ꂽ�B�Q�ʂɂ́A��q�T�M����i�����E��������w���O��s���H��U�N�j���I�ꂽ�������B
�@�P�`�R�ʎ�҂��A�S�����ɏo�ꂷ�邻�����B��q�T�M����́A�Q�N�O�u���̉́v����Ȃ��Ă��ꂽ�O��s�H�w�Z�̏��w���A���͂U�N���ł��B
�@�S�������撣���Ă��������I
�@�Q�l�ɁA��q�T�M���A�Q�N�O�ɍ�Ȃ��Ă��ꂽ�u���̉́v�́A���L���猩�Ă��������B
���̉�
 http://www.youtube.com/watch?v=ccGwrB4CocI http://www.youtube.com/watch?v=ccGwrB4CocI
|
|
|
|
| 2011�N10��29���i�y�j |
| ������s�̖��킫���܂�ɎQ�����Ă��܂����B |
�@�ߌ�P������S���߂��܂ŁA������s�O���b��W��{�݂ōs�Ȃ�ꂽ��Q�T����킫���܂�ɎQ�����ė��܂����B��ẤA���ق��鑺�A�㉇�͏�����s�Ə����䋳��ψ���ł��B
�@�����z��ꂽ�����ɂ��ƁA���ق��鑺�́A�P�X�W�U�N�U���ɁA�����s�������̗v���ɂ��A���̎��ӂ̎��R�ی�c�̂ɉ������Ă���l�X���������̒����I�����v��ɋ��͂��ׂ��������Ƌ��c���āu���ق��鑺�v��ݗ������ƋL����Ă���B
�@
�@�v���O�����̊T�v��
�P�j��Î҈��A
�Q�j������
�@�@�͂��ƗN���̐������́@�@�����@���s�@
�@�@���̗��ʒ����@�@�@�@�@�R�c�@����
�R�j���̊O���������l����@�ē��@�G��
�S�j����@�@������̂������ȃ|�X�g�@�R�c�@����
�T�j�Q���ҍ��k
�@�ł������B
���̗��ʑ���̕��Ċ��S�����B�����P�W�N���疈���P��A���ʑ��������Ă����B���������́A���̏t��̐���ł������Ƃ̂��ƁB���ɗ������鐅�̗ʂ��S�����i�V���Y�r�A�ш�N���A��g�A�������p�فj�Ŗ����P�������Ă����B���x�ɂ͌��E�����邻���ł����A�Ɣ������i�㗬���j�Ə�����V���i�������j�ŁA���ʂ��������Ă���B���Ȃ킿�����R��Ă����Ă���Ƃ݂邱�Ƃ��ł���悤���B
�@
�ē��G�����̖��̊O���������l����̍u���ł́A�������l����n��̐��Ԍn�Ɋւ��āu�n��炵�����ێ�����邽�߂ɊO�������̑�v���u�����ǁv�̗\�h�E���ÂƂ��ĕK�v�ł���Ƃ̎|�̘b�ł������B
�Q���ҍ��k�ł́A�O���A���i�A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�j��������s�̖�여��ł��A�ڗ����Ă��Ă���A��莋����Ă��邱�Ƃ��킩�����̂́A���Ƃ��Ă͎��n�ł������B
|
|
|
|
| 2011�N10��29���i�y�j |
| �����������܂ŕ��� |
�@�����́A������s�ŗp��������A�ߑO���������܂Ŗ���������B������s�ł́A���ق��鑺��Ấu���킫���܂�v�����邽�߂ł���B
�@���V�C���悭�A�����Ă��Ă��C�������悩�����B�~���㗬�ŁA�����A�J���Z�~�ɏo�������B���炭����ƂQ�H���邱�Ƃ��킩�����B��������C�ɂ��Ȃ������̂ŁA�P�O���قǂ́A�J���Z�~���ώ@���A�ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B
�@���������R�ώ@���̑O�ł́A���x�A�O��s�̐V��E�����n��̏��w�����U�O���قǁA���R�ώ@�������w����Ƃ̂��ƂŁA���������B�ē����̖������{�����e�B�A�l�����P�O�����Ǝ��R�ώ@���̃X�^�b�t�Q�����Ή������Ă����B���w�̑O�ɁA���w�������́A�܂��g�C���Ɍ��������B�������炢���A�o�������悤�������B������������Ă����̂ŁA���R�Ȃ��Ƃ��B
�@����������������āA������V������́A���̗l�q���A�ς���Ă���B���̒ᐅ�H�ɂ��A�I�M��V�����炵�Ă����B�����~�̒[�̕��ɂ́A�I�V���C�o�i���߂����Ă����̂��C�ɂȂ����B
�@���x�P�Q���ɁA�������w�ɒ����A�w�r���̗m�H���u���[���X�ŁA������H�ׂāA������Ɍ��������B
|
|
|
|
| 2011�N10��29���i�y�j |
| NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v���A�܂��܂��ʔ����Ȃ肻�� |
�@���̂���A�ł��邾���A�V��������a�r�ŁANHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�����Ă���B�����͓��j���Ɗ��Ⴂ���āA�Ȃ��Ǝv���Ă�����A�m�g�j�����ŁA�W������n�܂����B�������A�����́A�x���i���͖������x���ł����E�E�j������ǁA�y�j���������B
�@���悢��A�P�T�Ԃ̐搶�̗m�ق̊�{�Ɏ��Ƃ��I����āA�����A�V���̃j���[�X����A�S�ݓX�̓X���̗m���̐������v�����B�v�����A�����s���ɂł�B���Ă��āA����₩�ł���B
���̔ԑg�̏��������P�U�D�P�������������ł���B���̌㑝���Ă���Ǝv�����A�ǂ����ׂ�����̂��킩��Ȃ��B
�@
�@mix�ł́A�u�J�[�l�C�V�����v�̃R�~���j�e�C������A��������̐l���Q�����Ă���悤���B�ɂ����Ĕ`���Ăނ݂邱�Ƃɂ������B |
|
|
|
| 2011�N10��28���i���j |
| �s����w�F�u���q��������ɋy�ڂ��e���v�@ |
�@�ߑO���A�Љ���ق̎s����w�����R�[�X�u���R�Ɛl�Ԃ̋����v�ŁA���C��w���������s���搶�́u���q��������ɋy�ڂ��e���v�Ƒ肷��u�`�����B�搶�ɂ��Ɓu���q����́A��i�������ł͂Ȃ��r�㍑�ł��i�s���Ă�����A���܂�O���[�o���Ȍ��ۂł���B����ł����E�̐l���͑������Ă���A�����\�ȊJ�����d������A���E�I�ȏ��q����́A�]�܂����B�o�����͌��ł���B�v�Ƃ̎咣�ł������B
�@���{�ɂ��čl����ƁA�����D�ɗ����Ȃ��̂́A�����́A���̑̒����u���Ă����v�����ł��������߂��H
�@�������Ԃ�u���āA�ēx�l���Č��悤�B
�@�ڂ����m�肽�����́A�����s���u���q����Ǝ����\�ȊJ���Ƃ̊W�v���C��w���{�w���I�v�@��R�U�S�i�Q�O�O�T�j���P�P�T�`�P�R�X�����Ă��������B
�@�ߌ�A�C�ɂȂ��Ă����A�u��S���O��s��{�v�捜�q�āv�̃p�u���b�N�R�����g���o�����B���ߐ�͍������ł���B |
|
|
|
| 2011�N10��27���i�j |
| ���̗��ʑ���i�P�O���j���s�Ȃ��܂����B |
�@�����́A�������܂����̂ŁA�����̖��̗��ʂ̑�����R�ӏ��i�x�m���勴�A�A��j�ōs�Ȃ����B���̗��ʂ́A�挎���A�T�˂Q�O���قǑ������Ă���B
�@���̍����~���E�I�[�L���O���Ă���l�����́A���ʑ�������Ă���ƁA�������Ă���̂��Ǝv���悤�ŁA�u�����Ƃ��Ă���̂ł����H�v�Ƃ悭�������B�u���̗��ʂ̑���������Ȃ��Ă���v���ƁA�u���̗��ʂ́A�R�`�T�����낪���Ȃ��A�P�P�����������v���ƁA�u���́A�N���̐�ł���v���Ƃ��������悤�ɂ��Ă���B
�@�s�̋Ǝ҂ɂ��A���N�R��ڂ̖��̑������A����������Ԃ̉E�݂ōs�Ȃ��Ă����B
�@�������A���ԏ����̋߂��ŁA�J���Z�~�̎p�����������B
|
|
|
|
| 2011�N10��26���i���j |
| ��삪�A���w���ł����ς��ɁI |
�@�ߌ�A���������キ�Ȃ��Ă����̂ŁA���]�ԂŖ������ĉ�����B���V�C�ł������B
�@�Q���߂��A�㗬�ŁA���E�݂̍����~���A�߂��̏��w�Z�̊w���̏W�c���A�����������āA�����Ɍ������ĕ����Ă����B���̏�̕������A���]�ԂɁA�C�����������Ȑ��k���悹�āA�����Ă��镛�Z���搶�̎p�����������̂ŁA����������ƁA����������̋A�肾�����ł���B�S�Z���k���A�����Ă����̂��B���������A����̐V���ɁA���Z���搶�́A�������������āA��ς��Ƃ̋L�����̂��Ă������A���̒ʂ肾�Ɗ������B
�A���ăC���^�[�l�b�g�Œ��ׂČ���ƁA�����͑S�Z�����ŁA�s����͖������ƂȂ��Ă����B�S�Z���k�Ƃ���ƂR�O�O���ȏ�ɂȂ�B�����ł��Ă����͂��ł���B
���ł́A���k�̂����O���J���Z�~�����ł������B�I�i�K�K���U�H���A�W�܂��Ă����B�P�H���A������̗l�q���f���悤�Ȋi�D�����Ă����B
�����ɂ́A�R�K�����Q�H�����B
|
|
|
|
| 2011�N10��26���i���j |
| ���������̂ŁA����̒�̎���������B |
�@�����́A�����Um�Ƌ����A�������ʼne������̂ŁA���̗��ʑ���͉��������B���̑���A�K�[�f���V�N�������̈ڐA�ƒ�̙�����s�Ȃ����B ���AJ-�}�[�g�ɕ��t�y���ɍs���A�|�b�g�A���̃K�[�f���V�N��������傫�ȓ��ꕨ�Ɉڂ��ς����B
�@���̌�A���������A�@�}���~�A�A�c�o�L�̙�����s�Ȃ����B
�}���~�ɂ́A���������ł��邪�����Ȃ��Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N10��25���i�j |
| �T���r�A�ƃ}���[�S�[���h |
�@�䂪�Ƃł́A�ԂƗ̂܂��O��n�������Â̍u�K��ŏK���āA�킩���Ă��A�T���r�A�ƃ}���[�S�[���h���A�悭�炢�Ă���B����|�b�g�ɐA���āA���肳���A�Ԓd�ɈڐA�����̂ŁA�ЂƂ������ꂵ���B
��ł́A���A�z�g�g�M�X���炫�o�����B
|
|
|
|
| 2011�N10��25���i�j�@ |
| �䒃�m���̕a�@�Ŏ��̃N���[�j���O�A���̌���̕s�E�r�֒����� |
�@�T�C�U�����ɂP�x�A�䒃�m���̕a�@�܂ŁA���̃N���[�j���O�ɏo�����Ă���B����҂������̎����Q�O�͎c�����Ƃ��E�߂��Ă���B��������Ɗ��ނƂ����@�\���A�ꉞ�A�����Ȃ��ʂ�����Ƃ̂��Ƃ��������B���₵�������A�����ɔ������āA��t�̎��ÂɌ��т��Ă����B���A�l�ŁA�����A����ȏ�͎c���Ă��邪�A��ɂ������B
�@�A�蓹�A�����V�_��ʂ�A���̕s�E�r�ɏo�������B
�@�����V�_�ł́A�L�N�̏������A�_�БS�̂Ői�߂��Ă����B�����́A�炭�̂�������ɐݒ肳��Ă���悤�ł���B�ł��A���ɂ͍炫�͂��߂Ă�����̂��������B
�@���̕s�E�r�ł́A�����قǁA�n�X�̗t���A�r�������ۂ蕢���Ă����B�r�ɁA�L���N���n�W���A�n�V�r���K���A�I�i�K�K���A�J���K���������B���ɂ�����Ǝv�����A�n�X�̗t�Ɏז�����āA�悭�킩��Ȃ��B�����̃J���́A�a��^����l���������߁A�l�ɂȂ�Ă���悤�������B
�@�X�Y���ɁA�a��^���Ă���l�������B����X�Y���ł���B�߂��ɂ́A�����˂���ď��Ԃ�҂��Ă���悤�ȃX�X�������H�����B
�@�A��́A��k���w�ɂłċA���Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N10��24���i���j |
| �ߑO���A���ɒ����N���ʂ̑���i�P�O���j�������Ȃ��܂����B |
�@�Q�N�O����s�Ȃ��Ă�����ɒ����N���ʂ̑�����A�ߑO�������Ȃ��܂����B�O��n��ł́A�h�b�t�⍑���V����̑傫�ȗ�����A�����ɂ��鍑�����R������̗N���́A���������̗N���L��t�߁A�t�߁A���̗��t�߂ŁA���ɑ����̗N�����A���ɒ����ł���B�M�d�Ȑ��ł���B���̂悤�Ȑ����W�܂���̐����́A���������݂₷�����ƂȂ��Ă���B������˂���āA�R�T�M�A�_�C�T�M�A�J���Z�~�Ȃǂ��A���ŁA���邱�Ƃ��ł���B
�@����܂ł̑���f�[�^�ɂ��ƁA���̗N���ʂ́A�R���`�T���������Ȃ��A�P�P�����낪�����Ȃ�B
�@�����́A�P�R�������P�O�ӏ��̑��肪�I������Ƃ��ł��邪�A�P�O���̑���l�́A�T�˂X���̌��ʂ��A�������Ă����B
�@����@�́A�ꏊ���ƂɓK�������@���̗p���Ă���B
�@�����@
�@���𗬂��ė����𑪂�A���킹�ĕ��Ɛ[���𑪂�A�v�Z�ŁA�N���ʂ����߂�B�z�^����ł́A�����@���̗p���Ă���B
�@
�A�e�ʖ@
�@���X�V�����_�[�̂悤�ȗe��Ɉ��̎��ԗN�����W�߂āA�N���ʂ����߂���@�B�Ђ傤�����ł́A�e�ʖ@���̗p���Ă���B���̕��@�̕����A�킩��₷���A���x���ł�悤���B
�@
��������Ă��Ă��A�A���`�E����I�I�u�^�N�T���C�ɂȂ�B������ƁA����̍��ԂɁA���������Ă��܂��B����Ȏ����ł��A�A���`�E����I�I�u�^�N�T�̉萶����������B
|
|
|
|
| 2011�N10��23���i���j |
| ���̓~�� |
�@�����Ȃ��Ă����̂ŁA���낻����ɂ��~�������Ă��܂��B���łɔ㗬�ł́A�I�i�K�K���A�}�K���A�R�K���Ɩ��̓~�̃J�������낢�܂����B�����㗬�ł́A�J���K��������Ƀ~�]�\�o��H�ׂĂ��܂����B
�@ �J���K���ƃ~�]�\�o
�J���Z�~�����܂����B
�@�����s�̋Ǝ҂ɂ����̉͊ݓ��̍��N�R��ڂ̑����́A�����Ԃ̉E�݂ŏI����Ă��܂������A���݂͂܂ňꕔ�����ł����B
������̐X�����̒r�ɂ́A�~���̃q�h���K���Q�O�H�����܂����B
�o���A�J�C�c�u���i��j�A�J���K���A�R�T�M�����܂����B
��s��̉��ŁA�^�q�o���ƃJ�����q���̎p�����邱�Ƃ��ł��܂����B
|
|
|
|
| 2011�N10��22���i�y�j |
| �ߑO���A�J�ŁA���ԔG��� |
�@�����́A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̒�ኈ�����A�J�̗\��Œ��~�ƂȂ����B�ō��������ł����邱�ƂɂȂ�A�O��x�@���߂��̃R�[�q�X�ɐ������W�܂�A�P���Ԕ��قǑł����킹���B
�@�s���́A�قƂ�ljJ���~���Ă��Ȃ������̂ŁA���]�Ԃŏo���������A�����A�A�育��ɂ͂܂��J�ƂȂ��Ă����B�d���Ȃ��J�̒����]�ԂŁA����܂ő����ċA���Ă����B���A�l�ŁA���Ԃʂ�ɂȂ��Ă��܂����B�J�[�ł��Ђ������ς��B
|
|
|
|
| 2011�N10��22���i�y�j |
| �O��E���ƉF���̓��@�Q�O�P�P |
�@������������ł��邪�A�����V���䑼��Ấu�O��E���ƉF���̓��Q�O�P�P�v���A�J�Â��ꂽ�B���C���e�[�}�́u�������͂ǂ����炫���̂��`���f�͉F�����߂���`�v�ł���B���i�͗������邱�Ƃ��ł��Ȃ��G���A�����J����Ă����B�ߌ㌩�ɍs���Ă��܂����B
�@�u����A�~�j�u������������A���Ԃ��Ȃ������̂ŁA��ɓW�������ĉ�����B�����ɃX�^���v�����[�ɂ��Q�������B
�@�ŋߕ����I�ɉғ����n�߂��A���}�]�����ɂ��āA�A���}���i���̂�A���}���ŁA�ŐV����������B�U�U��p���{���A���e�i���g�����u�A�^�J�}��`�~���g�T�u�~���g���v�v�̃Z���T�[�����Ɏg���Ă���r�h�r�f�q�ɋ������������B���̑f�q�̓j�I�u�̒��`���̂Ǝ_���A���~�j�E���̔����ō\������Ă���Ƃ̂��ƁB�t�̃w���E�����g���ē��R��Ή��x�̂S�x���x�̋ɒቷ�ɗ�p�����B���̗�p���u���A��σR���p�N�g�Ɏd�オ���Ă���̂ɁA�����̐i���������B���̂悤�ȑf�q�܂ŁA�����V����̂Ȃ��Ő��삳��Ă���悤�ł�B
�@�܂��A�W���ɂ��ƁA���N�̂Q�O�P�Q�N�T���Q�P���ɓ��{�ŁA�����H���݂���悤�ł���B
�@�O��s�̊G�{�فi���ƐX�ƊG�{�̉Ɓj�ł��A�W����͋[�X���s�Ȃ��Ă����B�r�����̖����ɃT�[�r�X���������B
�@
|
|
|
|
| 2011�N10��21���i���j |
| ���u����R��ځu�O���A���̋쏜�͂ǂ�����v |
�@�ߌ�A�R������A���Љ���قŁA���Љ���فE���Z�����c���Â̊��u���u���̊O���A���ɂ��čl����v��R��ځu�O���A���̋쏜�͂ǂ�����v�����{���ꂽ�B�u�t�́A�����_�Ƒ�w�������{���V�搶�ł���B
���e��
�P�j��썂���~�̐A��
�@�����~�ɂ͂P�N���A���N���A�c���Ƃ��������j���^�̈قȂ�A�������炵�Ă���B�P�N���A���N���A�c���ł͋쏜�̎d�����قȂ�ł��낤�B�ݗ���ł��A�N�Y�A�J�i���O���̂悤�ȔɐB�͂������ő���Ƃ̋�����������{������B
�Q�j�ݗ��킪�D�肷�鍂���~�ɐN�������O���킪�ɐB���郁�J�j�Y��
�R�j�O������쏜������@
�@�@�O����ƍݗ���̐�������̈Ⴂ�𗘗p��������
�@�A�O�����������Ւn��ϋɗ��p
�@�@�i����̉͐여��ɐ��炷��ݗ���̎�q���̎悵�A�c������A�A���A����I�ȑ����Ǘ�������j
�@�B�O���A���̐����j�������l�������쏜
�@�@�E�P�N���F�J�Ԍ�������O�ɏ�������B
�@�@�E���N���F�G��Đ����Ă��Ȃ������̍����Ǝ���
�@�@�E�c���F�Đ���}�����銠����@�̊J��
�S�j�����~�v���X����������������B
�@�܂��̓t�W�o�J�}�̕c��A����̂��������낤�B
�@�������n�ł́A�I�~�i�G�V��L�L���E���K����B
�Ƃ����悤�ȓ��e�ł������B
�@�ȏ�̐搶�̂��b����A�P�ɃA���`�E����I�I�u�^�N�T���������Ă��A�܂��ʂ̊O���킪�N�����Ă��āA���̂܂܂ł́A�ݗ��킪�����Ă��Ȃ��悤���B���낢��l�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�����悤���B
|
|
|
|
| 2011�N10��21���i���j |
| ��쎩�]�ԎU���F�s�̑��� |
�@��������A���N�R��ڂ̑������n�܂����B�ꏊ�́A���̔������t�߂̍��݂���A�㗬�̔Ɍ����Đi�߂āA���̌�́A�䓃�⋴����㗬���ɐi�߂�悤�ł���B
�@�㗬�ŁA�}�K�����S�H���������B�����������悤���B�R�K���͂Q�H�����A�I�i�K�K�����Q�H���������p���Ȃ������B
�������Ȃ��ł́A���ʉ�������Ă���l�����l�����B
�����݂̍L��ŁA�T�N�����炢�Ă����B�i�햼�́A�悭�킩��Ȃ����E�E
|
|
|
|
| 2011�N10��20���i�j |
| �ߌ�A������ŁA�T�������܂����B |
�@�����q�܂ŏo�������A��ɁA�Q�������닞�����̓d�Ԃ��A���Ս����u�w�ł���A�Q���ԂقǁA������ŁA�T�������܂����B
�@�ނ�Ⓤ�Ԃ�����l�́A���l�������A�T�������Ă���l�̎p�́A�������Ȃ������B
�@���̎p�́A���Ȃ��A�C�\�V�M�A�n�N�Z�L���C�̎ʐ^���B�ꂽ�����ł������B�C�\�V�M�ɂ͔����A�C�����O������܂��B
|
|
|
|
| 2011�N10��20���i�j |
| ���������q�w�߂��́u�̂����T�Ɓv�ŁA��H�����܂����B |
�@�����́A�����q�܂ŏo�����A���������q�w�߂��̉����ƒ뗿���u�̂����T�Ɓv�ŁA��������Ђ̐l�Ɖ�H�������B���̓X�́A��������R�n�����������āA�w���V�[�ȃ��j���[����Ă��邻���ł��B�����́A�����`�R�[�X�����肵�A���C�������������܂����B�̘̂b�A�ŋ߂̘b�A���낢�남����ׂ���y����ł��܂����B���݂��A�ŋ߂́A�A���R�[���͍T���߂ɂ��Ă���B
�@�����P���ԂقǁA�ؓ��g���[�j���O�����Ă��邱�Ƃ��āA���̔S�苭���Ɋ��S������܂����B���������k�l�ł���B |
|
|
|
| 2011�N10��19���i���j |
| ���ɁA�}�K��������Ă����B |
�@���A���]�ԂŁA���̌䓃�⋴����㗬�̕�����������̂�܂��܂ŏo�������B
�@���̔㗬�ŁA���N���߂āA�}�K�������������B�}�K���̗Y�́A�����ΐF�ŁA������ւ�����B
�@�J���Z�~�ɂ͂Q�x�o�������B�P�x�͐����������A�Q�x�ڂ́A�����ł���B
�Z�O���Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�I�i�K�K���A�R�K���A�R�Q���Ȃǂɂ��������B�Z�O���Z�L���C�́A�n�N�Z�L���C�Ƃ悭���Ă��邪�A�Ⴂ�́A�n�N�Z�L���C�ɂ́A��͔����č����ߊ��������B
�@���d�b�ŁA���������R�ώ@��������̕\���ɁA�����̖쒹�ώ@��̓��ɂ����o�Ă��Ȃ��Ƃ̂��m�点������A�P�P���P�Q���̐������o���Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N10��18���i�j |
| ���ŁA���N�Ō�̃A���`�E���̏������� |
�@�ߌ�A�P��������A���̌䓃�⋴�㗬���݂ŁA�ɖ���A���`�E���̏������s�Ȃ����B�Q�������̂́A�X���ł������B����́A�݂������̉�̃����o�[�͂R���A�����s�k�����암���ݎ������Ɍ��C�ɗ��Ă��铌���s�̖{�N�x�̗p�̐V�l�E���R���ƕt���Y���̐E���Q���ł������B���̃A���`�E���̏����������A���C�v���O�����̒��ɑg�ݓ����ꂽ���Ƃ́A��X�ɂƂ��ẮA�劽�}�ł������B
�@�P���Ԓ��̏��������̌�A�R�O���قǁA����ŁA���ɂ��Ă̐����A����A���z�Ȃǂ���荇�����B�u�ƂĂ��������������܂����v�Ƃ̊��z���������Ă��������܂����B
�@�������݂́A�X�O�k�|���܂ɂQ�T���ł܂����B
|
|
|
|
| 2011�N10��18���i�j |
| ���̒� |
�@�����̌ߌ�A�����s�̕��ƁA�A���`�E���̏����̎��K�̂����b�����邱�ƂɂȂ��Ă���ŁA���ɉ����ɂ������B
�@�R�K�����S�H�����B
�@���ӂɂͤ�~�]�\�o���A�ɖ��Ă����B
�@�n�L�_���M�N���炢�Ă����B
�@���Ԃ��������̂ŁA�E�݂̃A���`�E�����������Ă������B
�@�@ |
|
|
|
| 2011�N10��17���i���j |
| ���ʉ惂���E�W���f�B�W |
�@�ȑO�ʂ��Ă��āA���́A���x�݂����Ă��鐅�ʉ拳���̃O���[�v�W�E��R�Q���E�W���f�B�W�i�����́A�ؗj����ɂ���̂ŁA�����E�W���f�B�W�j�����ɍs���Ă����B�R�O�N�ȏ㑱���Ă���̂ŁA���܂ł������Ăق������̂ł���B�ꏊ�́A�����Q�|�V�|�P�P�̂��ڂ�������[�Q�K�ŁA�Q�R���܂ŊJ�Â���Ă���B
�@���́A�����ɒʂ��Ă��Ȃ����A�ȑO�ʂ��Ă����l�����ʏo�i���Ă��āA�P�V���̍�i���W������Ă����B������̌��r�̐��ʂ���I����Ă��āA�y�����q�������Ă����������B��i�́A�P�O������傫�Ȃ��̂ł͂S�O���܂ł̍�i�ł������B�@
�@�@�@�@������̂��ĊŔ�
�@�@ �@�@��i�W���̗l�q �@�@��i�W���̗l�q
�@�@�@�@��i�W���̗l�q
|
|
|
|
| 2011�N10��17���i���j |
| �䒃�m���w�E�G |
�@�����́A�l�ԃh�b�N�ŁA�䒃�m���̕a�@�ɏo�������B�����̌��ʂ́A�P�����قǂ��ƂɗX���ő����Ă��邪�A���t�����Ȃǂ̌��ʂ͂����ɏo��̂ŁA������݂Ȃ���A��t�Ƃ̖ʒk���������B���ʂ́A�̋@�\�̒l�����������Ȃ��Ă���̂������ẮA��N���́A���ɂ͈����Ȃ��Ă��Ȃ��悤���B������ɂ��Ă��A�P������Ɍ��ʂ����������āA�厡��Ƒ��k���邱�ƂɂȂ�B
�@�䒃�m���w�̐����ŁA�u����\���v�s���̃o�X���~�܂��Ă����B����Ȃ�m���Ƀm���X�g�b�v�Łu����v�ɁA�͓����B
�_�c��̕������āA�����҂��Ă���ƁA�i�q�������̓d�Ԃ��z�[���ɓ����Ă����B
��ɂ͑傫�Ȓ������ł������A�o�ዾ�������Ă��Ȃ������̂ŁA��ނ͂킩��Ȃ������B
�����w�܂ŏo�āA�u�b�N�Z���^�[���̂����Ă݂��B�{�R���i�G�E���́u���ސ}�Ӂv���C�ɓ����āA�����ė����B����͓��{�쒹�̉�s�́u�쒹�v�ɘA�ڂ��ꂽ�u�쒹�X�P�b�`�}�Ӂv�̑啝�ȉ��M�E�������s�Ȃ������̂̂悤���B
|
|
|
|
| 2011�N10��16���i���j |
| �S�N�O�̖��t�߂̕��i�ƍ����̖��̕��i |
|
�@��̎ʐ^������܂��B�@�Q�O�O�V�N�X���P�V���ƇA�Q�O�P�P�N�P�O���P�U���i�����j�̖��㗬�̍��݂�������ʂ������̂ł��B�ʐ^�ł́A���̍��̕��ɁA�l�����n�邽�߂̑傫�Ȋ₪�ʂ��Ă��܂��B
�@
�S�N�O�ɂ́A���̖��̔㗬�̉͐�~�i�����~�j�ł́A�I�I�u�^�N�T����ʂɔɖ��Ă��܂����B�������w��قǂ���܂����B���̌�A�݂������̉�A�O���A���i�I�I�u�^�N�T�A�A���`�E���Ȃǁj�̏������s�Ȃ��悤�ɂȂ������ƂƁA�Q�O�O�X�N���瓌���s��������N�Q��N�R��ɕύX���Ă��ꂽ�̂ŁA�����~�̗l�q���ς���Ă��܂����B�A�̎ʐ^�ł��킩��悤�ɁA���̕t�߂ł́A���́A�I�I�u�^�N�T�́A�P�{������܂���B�萶���̖��x���A�啝�Ɍ����������ƂƁA�����萶���Ă��Ă��A��������Ă��܂�����ł��B
�@���̂悤�ȕ��i������ƁA�C���������炬�܂��B�����̐l�X���A���������y���������Ă��܂��B���̐l�X�ɁA���̂������i���y����ł��炤���߁A���܂ł��A���̕��i���ۑS����邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�@�������A���ł́A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�J���Z�~�A�R�K���A�J���K���A�n�N�Z�L���C�����܂����B�X�Y���������т����Ă��܂����B
�@�@�@
|
|
|
|
| 2011�N10��16���i���j |
| ���j���̒��́A�s�a�r�s�u�́u�������k�v���悭����B |
�@���j���̒��́A�s�a�r�s�u�́u�������k�v���悭����B�i��́A���勳���̌�~�M����B��~����́A�����[�Ȋw�����Z���^�[�����ŁA�I�[�����q�X�g���i����j�̂��߂̌��q�L�^�j�̒��������鑖�鐭���w�҂ł���B
�@�����̑Βk�҂́A�쒆�L������i�������}�������j�Ƒ��c���炳��i����茧�m���j�ł������B�悭���̔ԑg�Ō���A��A�剉�ҁB
�����̘b��́A
�@����
�A�N���U�W��
�B�́u�k���N�K��v����
�C�Ċe�s�`
�Ȃǂɂ��ẮA���k�ł����B
�@���k�Ȃ̂ŁA�����C�y�ȋC�����ŕ����Ă���B |
|
|
|
| 2011�N10��15���i�y�j |
| �����̖������{�����e�B�A��ኈ���́A�J�̂��߉e��������܂����B |
�@�����́A�������̃{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł��邪�A�����J�ƂȂ��Ă��܂����B����ł��A�{�����e�B�A�����́A��S�O���قǂ��A�荏�ɂ́A�W�܂��Ă����B�ł��J�̂��߁A�唼�̃O���[�v�́A��ኈ���𒆎~���āA����������ӂłł����Ɓi�����E���ڂȂǁj���s�Ȃ����B
�@�����̐��b�l��́A������葁�߂̂P�P��������{�������A���\�c�肪�����I�������̂́A�����Ɠ������P�Q�����߂��ƂȂ��Ă��܂����B���̐��b�l��̃����o�[�́A�������Ǘ�������R�C�S���A�{�����e�B�A������́A��\���b�l�A����\���b�l�A�����ǐ��b�l�A�T�O���[�v�̐��b�l�Ȃǂ��o�Ȃ��āA
�i�P�j�����\��
�i�Q�j�Ǘ�������̗\��A�w���A�A��������
�i�R�j���c�A�v�]�A�A�������A���̑�
�̋c����A�ł����킹�Ă���B
�@
�@�����Q�R�N�S����������̎w��Ǘ��҂��A�����s��������琼���E������o�[�g�i�[�Y�ɕύX�ɂȂ��āA�Ǘ��̎p�����ς���Ă��Ă���A���́A�悭�Ȃ��Ă���Ɗ����Ă���B
�@���̂ЂƂ̎���Ƃ��āA���A�������ł́A�u���������p�Җ����x�A���P�[�g�����v���s���Ă���B���̐ݖ��
�P�j�ɂ���
�Q�j�������ɂ���
�R�j���S���ɂ���
�S�j�Ή��̂悳�ɂ���
�T�j���p�̂��₷���ɂ���
�U�j�Â����ɂ���
�V�j�\�t�g�̉^�c�ɂ���
�W�j�S�̓I�Ȉ�ۂɂ���
�X�j�F�m�x�ɂ���
�Ȃǂ����e�ƂȂ��Ă���B
���̂悤�Ȍڋq�����x�����̌��ʂ��悭���͂��āA�p���I�ȉ��P���s�Ȃ����Ƃ́A��ς������Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B |
|
|
|
| 2011�N10��15���i�y�j |
| �m�g�j���h���u�J�[�l�C�V�����v�͖ʔ����I |
�@�P�O���R������n�܂���NHK���h���u�J�[�l�C�V�����v�́A�P�Q�b�܂ł��������ꂽ�B����́A�������ǂ��S�����Ă���B���N���ƂɁA�����Ƒ��Ō�サ�āA��������Ă���悤���B���������Đ��삷�邱�Ƃ́A�������Ƃ��B
�@�t�A�b�V�����f�U�C�i�[�̐��҂ł��鏬���q����(�P�X�P�R�N�`�Q�O�O�U�N)�̎d���Ǝq��Ă̕����L�̂悤���B�ޏ��́A�������t�A�b�V�����f�U�C�i�[�ł���A�R�V�m�q���R�A�R�V�m�W�����R�A�R�V�m�~�`�R�̂R�o������Ă�������e�ł���Ƃ̂��ƁB�����`�Ɂu���Ƃ͂��݂Ƒ��Ɓv������悤�ɁA�������̉ƂɈ�������A�~�V���������̏��_���W���Ǝv���āA�m���̓��Ɏ����̉^�����J���Ă����A�p�C�I�j�A�ƌ�����B�̂́A�_���W���Ղ�ŗL���ȑ��̊ݘa�c�s�ɂ��X���J���Ă����Ƃ̂��Ƃł���B
�@�������������A�V��������̂a�r�����ŁA�y�����A�������Ă��������Ă���B
�@���\����Ă��鏉���̎������́A���łP�U�D�Q���A�֓��łP�U�D�P���ƁA�O�́u���Ђ��܁v�̂P�T�D�U�����́A���������B
���̓ƒf�I�ȗ\�z�ł́A���ꂩ��A�������͏オ��Ə���ɍl���Ă���B����A��ς���₩�Ȋ��z�������āA���I����Ă���B�@���́A�������ǂ̃h���}���암�ɂ́A�g�߂Ȑe�ʂ̂��̂����āA���o��Ƃ��Ċ撣���Ă���̂ŁA��������̂́A������O�̂��Ƃ��B
|
|
|
|
| 2011�N10��14���i���j |
| �s����w�F�h�Љے����畷���u�O��s�ƎO��s���̖h�Б�v |
�@�����̎s����w�����R�[�X�ł́A�O��s�������h�Љے��̑�q��������u�t�Ɍ}���A�u�O��s�ƎO��s���̖h�Б�v�ɂ��Ă��b���f�����B�ȉ������S�������Ă��鎖�����L���B
�P�j��_�E�W�H��k�ЂƓ����{��k�Ђ̋��P�Ƃ��āA�u���v�Ɓu���ꏊ�v�̍������������悤���B�܂�������邽�߂ɂ͔��ꏊ�ɓ�����K�v������B���ꏊ�ɂ́A�L����ꏊ�i�L���I�[�v���X�y�[�X�j�ƈꎞ���ꏊ�i�w�Z�̍Z��Ȃǁj������B���́A����������A�����ňꎞ�����ł���ꏊ�ł���A�w�Z�Ȃǂ������w�肳��Ă���B�܂��́A���ꏊ�ɓ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�Q�j�O��s�ł́A�ǂ̒n�k���N���肻�����H
�@�@��s�������n�k�E�E�R�O�N�ȓ��ɂV�O���̊m���ŋN����B�O��ł͂l�U��Ɛ��肳��Ă���B
�@�A���C�n�k�E�E���������Ă��A�O��ł́A�l�T��Ɨ\�z����Ă���B
�@�B����f�w�n�k�E�E����f�w�тł́A�����l�V�D�S���x�̒n�k���N����\��������B�{�f�w�т̍ŐV�̊����́A��Q���N�O�����P���R��N�O�̊ԂŁA���ϊ����Ԋu�͂P���N����P���T��N�ł������Ɛ��肳��Ă���B���ۂɂ́A������N���邩�́A����͓���B����f�w�̑����Ă���ꏊ���A��܂��ɂ����킩���Ă��Ȃ��悤���B�ł��ŋ߁A����f�w�n�k�ɂ��Ă̎s�����ւ̖⍇���́A���������ł���B
�R�j���ۂɍЊQ�ɂ������ꍇ�A�܂������ł���B�����ɐ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�������Ȃ��Ə������闧��ɂȂ��Ă��܂��B���ŋ����ł���B�����Č����ƂȂ�B
�S�j�Q�Ă�Ƃ���ŁA�n�k�ɂ����ƁA������̂ɂ̓X�j�[�J���ق����B�f���ł́A���̗���Ă��܂����Ƃ������B
�T�j�d�b���A�g�т��ʐM�s�\�ɂȂ�̂ŁA�n��̏��A�����ǂ����邩���A�d�v�Ȗ��ƂȂ�B
�U�j�O��s�̒n��댯�x�ɂ��āA�����댯�x����ԍ����̂́A�w�ɋ߂���A���T���ڕt�߂ł���B���̏Z��ł���n��́A��r�I�����댯�x�͒Ⴂ�悤���B
�V�j�u�t�Ɏ��₵�܂������A�����_�ł́u�O��s�n��h�Ќv��v�ɂ́A�����ɂ��ЊQ�̑�́A�܂܂�Ă��Ȃ��悤�ł��B�����ɂ��ЊQ�ɑ���h�Ќv����܂߂邱�Ƃ��K�v�Ǝ��͊����܂����B |
|
|
|
| 2011�N10��13���i�j |
| ���̓~���F�R�K���A�I�i�K�K�� |
�@����A���̔ɏo�����Ă݂�ƁA�R�K�����R�H�����B����A�����̐��c�J��ŃR�K���R�H���������A�㗬�̔t�߂Ō���̂́A���N���߂Ăł���B
�����O���痈�Ă���I�i�K�K�����A�H�̗l�q���G�N���v�X����~�H�ɕς���Ă��Ă���B
�j
�߂��ɁA�R�T�M�Q�H�A�J���Z�~�P�H�A�J���K���W�H�������B
|
|
|
|
| 2011�N10��13���i�j |
| ���́A�����ł����B |
�@�[���A���̋�ɂł���������B�܂�ۂł����B
�@���͖����̂悤�ł����B
�@ |
|
|
|
| 2011�N10��12���i���j |
| ���ɂ��R�K��������Ă����B |
�@�����́A��여��A����Ȃ��Ƃ�����̃t�B�[���h���[�N�ŁA���̍דc�����琢�c�J��̒J�ˋ������̐��c�J�g���X�g�܂ŕ������B���c�J�g���X�g�̉�c���ŁA�݂�ȂŁA�������Ō��������R�O���قǂŁu�������}�v�ɏ������B
�@�r���A��삩�痣��āA���ҏ��H���ċL�O���������w�����B���Ԑ�ɂ́A�����́A�����������B
�@���̖��a���㗬�ŁA�R�H�̃R�K���̎p���m�F�ł����B���ł́A���N���߂Ăł���B
�@
�J���Z�~�ɂ��S��o�������B�דc���㗬�A�n���㗬�A�咬�������A�J�ˋ������ł���B
���勴�����ł́A�A�I�T�M�������B
���ҏ��H���ċL�O�����ɂ͈�x�s�������Ǝv���Ă������A�s���āA�L������B
�@
|
|
|
|
| 2011�N10��12���i���j |
| �����̒|�Ƃ�ڂ��� |
�@�挎�̃K�[�f�j���O�t�G�X�^�ŁA�̃{�����e�B�A������A�|�H�̌��R�[�i�[���o�����B�Q���҂̊�]����ԑ��������̂͒|�Ƃ�ڂ���ł������B�ł��A�ł������̂́A��s���\�́A���ЂƂł������B����Ȃ��āA�����A�|�Ƃ�ڂ̂�����ׂĂ݂��By-tube�ɂ��|�Ƃ�ڂ̂�������̂��Ă����B
http://www.youtube.com/watch?v=EqZQuV0nf_o
��Ԃ̖��́A���̃o�����X�ł���Ɗ������B�������A�V���������w�������B
������Q�l�ɂ��č���Ă݂��B�����́A��B����ŁA���P�������Ă����A���Ƃ��Ȃ肻���Ɋ������B
|
|
|
|
| 2011�N10��11���i�j |
| �T�b�J�[�A�W�A�n��\�I�^�W�L�X�^���� |
�@ ����́A�T�b�J�[�A�W�A�n��\�I�^�W�L�X�^���킪����B�U�b�N�W���p���ɂ́A����܂ŕ������Ȃ��B�ꂵ�݂Ȃ�����A��Ε����Ȃ��ŁA�����_���d�˂Ă������̎p���A������������B
�@�����́A�ߌ�V������A�����J�n�́A�ߌ�V���S�T���B�V���T�U���n�[�t�i�[�}�C�N�̃w�f�B���O�ŃS�[���A���{�P�|�O�B�W���R���A����̃S�[���œ��{�Q�|�O�B�W���Q�O�����̃S�[���łR�|�O�B�W���Q�U������̃S�[���łS�|�O�D
�@�W���T�O���㔼�X�^�[�g�A�����n�[�t�i�[�}�C�N�̃S�[���T�|�O�B �n�[�t�i�[�}�C�N�����ƌ��B�W���T�X���������S�[���U�|�O�B�X���P�P������̃S�[���łV�|�O�B����̃w�f�B���O�S�[���łW�|�O�B
�����I���B�叟�ł����B
|
|
|
|
| 2011�N10��11���i�j |
| ���]�ԎU��F�����쉀�A����������A�������A���䓃�⋴�� |
�@�W��������Ƃ��łāA���]�ԂŁA�����쉀�A����������A�������A���̌䓃�⋴�Ɖ�����B
�@�����������́A���Y�A�I�i�K�A�W�V���E�J���A�R�Q���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�A���W���A�J���K���A�R�T�M�A�J���Z�~�A�o���ł������B
�@�����쉀�̕�n�͑傫�Ȃ��悪���������A�����͕Ǖ�n���������B�Ő��̒��ɁA�������ł���A�W����n�ł���B
����������ł́A�R�X���X�����ꂢ�������B
���\�Y���������݂Ɩ쐅���㗬���݂ɃA���`�E�����ڗ����Ă���
�̂ŁA���ꂼ��A��Q�O�`�R�O���ԁA�����������B
�߂��Ƀn�L�_���M�N�ƃ~�]�\�o���悭�炢�Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N10��10���i���j |
| ����V���ڂ܂ŁA���ʉ�W�����ɍs���Ă��܂����B |
�@���ʉ拳���̐�y�Ɉē������������̂ŁA����V���ڂP�O�|�P�P�̂�����[�T���z�[���܂ŁA�u���ʂS�l�W�v�����ɍs���Ă��܂����B�����������ŁA�P�T���܂ōs�Ȃ��Ă���B
�@����́A���s�ғV���ł����B�ł��̂قǂ̐l�ł͂Ȃ������B
�@
�@
�A��ɁA����J�����ɗ���������B�R�쑐�W���s���Ă����̂ŁA���Ă��܂����B
�@�@�@
�Ђт₳���ŁA��x�݂��Ă���A�A���Ă��܂����B
|
|
|
|
| 2011�N10��9���i���j |
| �o���t�G�X�^���_��A������ |
�@�s���_��A�������ł́A���A�o���t�G�X�^���s�Ȃ��Ă���B�����A�X��������̊J�����ԂɂP�O�����x�ꂽ���A���傩��������B�����ł́A�N�ԃp�X�|�[�g���w�����Ă���̂ŁA�C���˂Ȃ����x�ł������B
�@�܂��t�W�o�J�}��T�����B�쑐�]�[���ł́A�}���o�t�W�o�J�}�i�O����j�����������A�t�W�o�J�}�͌�������Ȃ������B
�@�@�@�C�k�V���E�}
���x�K�C�h����̎p�����������̂ŁA�����Ă�������A���Ȃ藣�ꂽ�A���X�ɋ߂��ꏊ�ɂ���A�W�����������B�ł��A���̂����N�́A�R�O�������x�ɂ�������ĂȂ��A�Ԃ͂Ȃ������B�ł�����A���{�ɌÂ����炠�鎩���^�C�v�̃t�W�o�J�}�ł���̂ŁA�悭�ώ@�����B
�Ő��L��ł́A�p���p�X�O���X���A����L���Ă����B
�Ő��L�ꂩ��o�����Ɍ������r���ŁA�傫�Ȗ]�������Y�������J�����}���̎p�����������B�����Ă݂�ƁA�N�}�m�~�Y�L�Ɏ���H�ׂɃR�T���r�^�L�ƃL�r�^�L���A���Ă���悤�������B�ł��̗t�ɉB��āA�Ȃ��Ȃ��ʐ^�ɂ͔[�܂�Ȃ��悤�ł������B
�@�o�����ł́A�����̐l�X���A���Ă����B�o�����ł́A�{�����e�B�A�������A�����Â��ē����āA�o���̐��������Ă����B���NHKTV�̒��̕����ŁA�������������̃{�����e�B�A�̕����A�ē������Ă���ꂽ�B���R�A�m�l���ē��{�����e�e�B�A�����Ă���Ƃ�������������B
�@
�P�P�������R�O���ԁA�o�����̑O�ŁA�u���m��{�����݂䂫�i�{�[�J���j�̃o�����R���T�[�g���s�Ȃ��AYou are My Sunshine�Ȃǂ̋Ȃ��y���܂��Ă��ꂽ�B����́A�����P�������̃C�x���g�̂悤�ł����B�K�^�ł����B
�@ |
|
|
|
| 2011�N10��9���i���j |
| ��쎩�]�ԎU���F�L�Z�L���C |
�@�����̖��ł́A�ɂ̓I�i�K�K���͂R�H�����A������ŁA�����~�ɍ~��āA�����̊Ԗ쑐���ώ@���܂����B�Ԃ��炢�Ă���̂̓Z�C�^�J�A���_�`�\�E�A�c���N�T�A�c�^�o�E�������A�C�k�^�f�A�}���A�T�K�I�Ȃǂł����B
�䓃�⋴�����ł̓L�Z�L���C���p�������A���炭�y���܂��Ă���܂����B�܂��c���悤�Ȋ��������܂����B
�@
�J���Z�~������悤�ŁA���l�̃J�����}�����A�J���Z�~���_�C�r���O����̂�҂��Ă��܂����B
|
|
|
|
| 2011�N10��8���i�y�j |
| �܂��Â��荧�k����n�� |
�@�O��s�ł́A��S����{�v��i���i�āj���܂Ƃ܂�A���A�s���̈ӌ������낢��Ȍ`�ł������Ƃ��Ă���B
�@�p�u���b�N�R�����g��A�͂����ɂ��A���P�[�g�����{���Ă���悤�����A���̑��A�R�~���j�e�C�Z�悲�ƂɁu�܂��Â��荧�k��v����������V�̏Z��Ŏ��{�����B
�@���̍ŏ��̍��k��A���n��̑�n�����Ōߌ�Q������S�����܂Ŏ��{���ꂽ�B�Q�������s���́A�����������Ƃ���ł́A�P�R���قǂł������B�ŏ��R�O���قǁA�s�̐E�����玑���u��S���O��s��{�v�捜�i�āv�Ǝ����u���[�N�V���b�v�ŏo���ꂽ�A�C�f�A�̑�S����{�v�您��ьʌv��ɂ�����Ή��\���̌����v�̑��n��Ɋւ�镔���𒆐S�ɐ������������B�s�����̐E�����قړ������o�Ȃ��Ă����B�S������̃O���[�v�ɕ�����ĂP���ԂقǍ��k�����B�Ō�ɂ��ꂼ��̃O���[�v�ł܂Ƃ߂����ʂ��A���ďI���ƂȂ����B
�@�P�O���P�R���̍L��݂����́u��S���O��s��{�v�捜�i�ē��W���v�ŁA�͂����ɂ��A���P�[�g���Y�t����邱�ƂɂȂ��Ă���B�p�u���b�N�R�����g���P�O���R�P���̊����ŁA�ӌ����o����v���Ƃ��ł���B
�@���̃O���[�v�łł��ӌ��́A���̃����ɂ���
�@�R�~���j�e�B
�A�n��̊�
�B���Ɨ�
�C�h�Ɓi�Ƒ�ȁj
�D�������
�Ɋւ�����̂ł������B
�����ЂƂ̃O���[�v�ł�
�@�Ί֘A����
�A�������v��
�B�ό������̊��p�i�ό����[�g�j
�C�_�n�i�n�Y�n���j
�D�n��P�A
�E�O���i���j
�Ɋւ�����̂ł������B
�@�Q���l�������Ȃ������̂ŁA��l�����蔭���̎��Ԃ͂��Ȃ肠�����B
|
|
|
|
| 2011�N10��8���i�y�j |
| ����u�K��u�A�������v |
�@�@�����́A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̒�ኈ�����B�W�����Ɍ����ɏo�����A�܂����؊ώ@������B���炢�Ă���̂́A�L�����N�Z�C�A�n�M�A�e�C�J�J�Y�������ł���B
���N�Q�́A�����͍炢�Ă��Ȃ��������A�ڂ݂�����A�܂��炭�悤���B
�@�R�����T�L�A�E�����h�L�A�n�i�~�Y�L�A�E���V���E�~�J���A�J�L�A�J�����A�U�N���Ȃǂ̎����Ȃ��Ă����B
�P�O������ԂƗ̂܂��O��n�������Â̙���u�K��n�܂����B�u�t�́A�O���[���A�h�o�C�U�[�̉�����������B�o�����������ŁA�킩��₷�������Ă����������B�O���S�O���قǂ́A������ɂȂ��b�m���ł������B
�@�@�}�̏o��
�@�A��̎��
�@�B����̎�ށi��߁A�}�����A�肩���j
�@�C��ʒu�Ǝ���
�@�D��̈ʒu�Ƃ����
�@�E�}����
�@�F�}�����̐��
�@�G�肩������
���b�R�N�̙���̎��K�i���b�R�N�Q�{�j
�@�ł������B
|
|
|
|
| 2011�N10��7���i���j |
| ��쎩�]�ԎU�� |
�@���߂��A���]�ԂŖ��ɏo�������B�㗬�ł́A�I�i�K�K���R�H���A�J���K���̌Q��ɍ������Ă����B
�䓃�⋴��������Ԃ��A�㗬�̖��u�����R�ώ@���ɗ��āA�Z���ԁA������������B�t�W�o�J�}������̂���ړI�ł���B�t�W�o�J�}�̉Ԋ��́A����������Ă����B
�@�V���E�J�C�h�E���炢�Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N10��7���i���j |
| �s����w�F�u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���A�v |
�@�ߑO���A�s����w�����R�[�X�ł́A��T�Ɉ������A����c��w��w�@���E�G�l���M�[�����ȋ����g�c���v����́u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���A�v�̍u�`���������B
�@�������������Ƃ���ł́A�傫�Ȗ��́A
�i�P�j�o�ώY�ƏȁA���{�o�c�A�A���Ȃ̎O�ɂ��A���g����̐����I�ӎv����ɍۂ��đΗ����Ă���B
�i�Q�jCO2�r�o�ʂł́A��P�ʂ̒����A��R�ʂ̃C���h�����s�c�菑�ł́A�팸�`�����Ă��Ȃ��B�����̍����ɂ��āA���g����͂ł��Ȃ�
�@���Ƃł���悤���B
�@�����܂ł̓��̂�͉����B |
|
|
|
| 2011�N10��6���i�j |
| �u���u�ߖ����Ɍ����������̂܂��Â���Ƃ́H�v |
�@����́A�O��l�b�g���[�N��w���u���O��̖��������߂鎋�_�̑�R��u�ߖ����Ɍ����������̂܂��Â���Ƃ́H�v�����B�u�t�́A�����_�Ƒ�w�����_����א搶�ł���B
�@���������A�����Ƃ������t���A�ŋ߂悭�����悤�ɂȂ����B�ł��A�����̍u�����ƁA�u���v���Ƃ͉����A�Ȃ��Ȃ���`��������Ƃ̂悤���B���R���ɂ́A�u���v�u��v�͂Ȃ��B
�@�搶�ɂ��Ɓu�l�Ԃ����R�̒�����łĂ���B���낢��Ȃ��̂�����Ă��܂����B�l�ԁA���R�A�Љ�̃o�����X���悢�Ƃ��ɍ����ƂȂ�̂ł́H�v
�@�܂��A�u���́A�������̂��g�����͋C�ɂȂ��Ă��Ă���B�v
�@�u�����Ɖ��K���Ƃ͈Ⴄ�̂ł́H�v
�@�u���̂P�N�́A�l�Ԃ̂P���ɓ�����B���́A�������Ԃ̒��ŁA�����Ă���B�v
�@���낢��ƍl��������邱�Ƃ����������B |
|
|
|
| 2011�N10��6���i�j |
| ����쒹�ώ@������� |
�@���A���̔㗬�ɂ́A�I�i�K�K�����R�H�ɑ����Ă����B
�@�����́A�����̌���쒹�ώ@�ٓ��ł���B�{�����e�B�A�P�T�����Q�����āA�X������Q���Ԕ��A���R�ώ@���A������B�n��AA�n��Ɖ��B�����͂P�U����ώ@�����B�J���Z�~�A�A�I�T�M�A�_�C�T�M�A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�J�P�X�Ȃǂ��m�F�����B
�@�P�P��������A�P���ԂقǁA�쒹�O���[�v�̃~�[�e�B���O���s�Ȃ����B��Ԃ̖��́A�����r�̐����A�i�X�Ə��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂��A�ǂ��邩�̖��ł���B�b�������̖��A�b��I�Ȑ��̂ݏ����邽�߂ɁA�ߌ�A�݂�ȂŁA��������ɍs�����Ƃɂ����B
|
|
|
|
| 2011�N10��5���i���j |
| �ԂƗ̃T�|�[�g�����P��𗬉� |
�@�ߑO���A�P�O������P�Q���P�O������܂ŁA�ԂƗ̂܂��O��n������́u�ԂƗ̃T�|�[�g�����P��𗬉�v���������B�����Q���]��Ƌ���E���W�����Q�������B
�@���e�́A������̂��̂Q�N���̐U��Ԃ�Ǝ��ȏЉ����̃Q�[���u����͒N�̃J�[�h�ł��傤�H�v���s���A�Ō�Ƀt���[�g�[�N�ŁA����܂ł̋�����⍡��̊����ɂ��Ęb�������B�y�����ЂƎ��ł������B
�@����܂ł̋���̐U��Ԃ�ł��邪�A
�����Q�P�N�S���Q�P���ɃX�^�[�g
�����Q�P�N�W���ɂm�o�n�@�l�o�^
�����Q�P�N�X�������ǂ��X�^�[�g
�����Q�Q�N�R���ԍL�ꂪ�J��
�����Q�Q�N�X���ԂƗ̃t�G�X�e�o���i�v���C�x���g�j�J��
�����Q�Q�N�P�Q������̃��S�}�[�N����
���݂̊�����
�@�̃{�����e�e�B�A����
�A�Ԓd�{�����e�B�A�������
�B���R�ώ@��i�N�R��j
�C�̕ۑS�Ή�����
�D�����n��̉����v���W�F�N�g
�E�s���_���̉^�c
�Ȃǂł���B
���݁A����͂P�R�V���A���̓���́A������Q�X���A�T�|�[�g����R�U���A���͉���U�U���A���^����U���ƂȂ��Ă���B
�@����E���́A�P�W���ł��邻�����B
�����́A�����Ȃ���݂𑱂��Ă��Ă��邱�Ƃ��A���߂Ċ������B
�ڂ����́A����̂g�o�����Ă��������B
�@http://hanakyokai.or.jp
|
|
|
|
| 2011�N10��5���i���j |
| �|�Ƃ�ڂ̍��� |
�@����̃K�[�f�j���O�t�G�X�^�ł́A�m�o�n�@�l�ԂƗ̂܂��O��n������̗̃{�����e�B�A����́A�|�H�̌��R�[�i���J�������A��Ԋ�]�����������̂́A�|�Ƃ�ڂ���ł������B
�@�ł��A�g�����������A�]��悭�ꂽ���������߂��A�����̎��Ԃ�������A�ł����|�Ƃ�ڂ̔�т������ЂƂł������Ɣ��Ȃ��Ă���B�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂���A�|�Ƃ�ڂ̍����ɂ��Ă̌f�ڂ��������������A���L��u-tube�̍�i�́A��Ԃ킩��₷�������B
http://www.youtube.com/watch?v=EqZQuV0nf_o
�����������B
�H�̃o�����X�̂Ƃ���́A�Q�l�ɂȂ�܂��B
|
|
|
|
| 2011�N10��4���i�j |
| �u���u�������̂܂��Â�����߂����āv���w�����B |
�@����A�O��l�b�g���[�N��w�ցA�l�b�g���[�N��w���u���u�O��̖��������߂鎋�_�v�`��S����{�v�����Ɍ����ā`�̑�Q��u�������̂܂��Â�����߂����āv���ɂ����Ă����B�u�t�́A���[�e���w�@��w�Љ���w�ȋ����a�c�q������B
�@�搶�ɂ��Ɓw���э\���������㓯���^����A�v�w�̂ݏ��сA�P�Ə��тɕω����Ă��Ă���B�ߗW�������Ă��Ă���B�n�敟���A�n���P�A�[�̎������d�v�ł���B�A���P�[�g�ł́A�u���������ɕ�����ᕉ�S�Łv���s���̖{���̂悤�ł��邪�A�u���Q���ō�������ڎw���v���Ƃ��d�v�ł���x�Ƃ̂��Ƃł����B
�@���w�Z�̊w����x�̏��n��ŁA�Z�������̌q������č\�z���A��̓I�ȉ��������āA�n��̕����I�@�\�����߂銈������Ă���Ă��邻�����B
�w�n��̃R�~���j�e�B�̒S����ɂ��ẮA�Z�����c��E����̂悤�ȁu�n��^�E�R�~����e�B�g�D�v�ƃ{�����e�B�A�c�́E�m�o�n�Ȃǂ́u�S�E�A�\�V�G�[�V�����^�g�D�v���A�A�g�A�����A�������Ȃ���n��̃R�~���j�e�B��W�J���鎞��ɂȂ��Ă����x�Ƃ̂��ƁB�w�قȂ������l�̑��݂̏��F�Əd�ׂ����ɒS�������Ƃ����悤�ɕω����Ă��Ă���x�Ɛ搶�͂��������B
|
|
|
|
| 2011�N10��4���i�j |
| ���̐A������ |
�@�ߑO���A�݂������̉�̖��̐A�������ɎQ�������B���N����A�t�A�āA�H�̔N�O��A����I�ɖ��̐A���ώ@���s�Ȃ��v��ł���B���N�́A�Ă���͂��߂��̂ŁA����Q��ڂł���B
�@�����́A�P�O������P�Q�����̂Q���Ԕ��A���̑���牺���̌䓃�⋴�Ԃ̉E�݂̐A���ׂ��B�Q�������̂́A�T���ł������B���{�Ɩؖ{�ŁA��P�Q�O����ώ@�����B
�@�A�蓹�ŁA�J���Z�~�ɂł������B
|
|
|
|
| 2011�N10��4���i�j |
| �X�Y�J�P�m�L�̎� |
�@����̑䕗�̓��ɁA�������ŃX�Y�J�P�m�L�̎������������Ă����B
�@�E���Ă�����ɂ́A��������̎킪�l�܂��Ă���悤�ł���B
�@�����A�ł�������������Č���ƁA�݂�݂���ɁA��������̎킪�o�Ă����B
�@�@�@�X�Y�J�P�m�L�̎�����킪�o�Ă���
|
|
|
|
| 2011�N10��3���i���j |
| �����������܂ŕ��� |
�@�W���O�ɉƂ��łāA�������Ɩ��̍����~���������܂ŕ������B
�Ƃ̋߂��ŁA�L�����N�Z�C���炢�Ă����B
�X�����{�ɓs���Q��ڂ̑������s�Ȃ������̂����̂����㗬�ŁA�A���`�E���ƃu�^�N�T�̉萶�����ڗ������Ƃ��낪�������B
�@
���ɋ߂����ӂł́A�~�]�\�o�̌Q�����������B
����������ł́A�R�X���X�����ꂢ�ɍ炢�Ă����B
�������ɂ́A�P�P����������̂ŁA�s���a���J�˒뉀�����w�����B�H�̎������W�߂��R�[�i�[�������B���t�W�̎R�㉯�ǂ̉̂��f������Ă����B���̒뉀�́A�ŋ߁A���w�薼���ƂȂ����悤�ł���B
�������̉w�r���ɂ���m�H���u���[���X�ŁA���[���L���x�c�̃����`��H�ׂ��B���Ɛ��̃J�{�`���v�������������������B�P�O������A�g�ˎ��ɂ����X�i�g�ˎ��쒬�P�|�W�|�P�O�j���I�[�v�������悤�ŁA�r�[���̃^�_�������������Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N10��3���i���j |
| �K�}�̎��@ |
|
|
|
| 2011�N10��3���i���j |
| ���ɃI�i�K�K��������Ă����B |
�@�k�̍�����I�i�K�K�������ɂ���Ă����B�����A���̌��싴�t�߂ŁA�J���K���̌Q��ɍ������Ă���I�i�K�K���P�H���A�m�F�����B���ł́A���N�A���߂Ăł���B
�@�߂��ŁA�L�Z�L���C���P�H�����B
�@
|
|
|
|
| 2011�N10��2���i���j |
| �J���X�E���̐Ԃ��� |
�@�����A��ɂł��Ă����J���X�E���̐Ԃ��������n�����B
�@�J���X�E���̎��̒��ɂ́A�킪�A�R�Q�����Ă����B�R�O�������A�Q�����������B
���̎�́A�单�l�̑ŏo�̏��ƂɎ��Ă���̂ŁA���N���Ƃ���A���z�̒��ɓ���Ă����ƁA������������i�H�j�Ƃ������Ă��邻���ł���B
|
|
|
|
| 2011�N10��2���i���j |
| �������l���ɂ��Ă̍u���� |
�@�ߑO���A�s���̑��{���ɂP�K�Q���z�[���ōs�Ȃ�ꂽ�A�����s�P���̃{�����e�B�A�w���҂̌��C�ŁA�����_�Ƒ�w�����_����א搶�́u�������l���ɂ��āv�Ƒ肷��u�������B
�@�����L�^���������ɂ���
�w�������l���Ƃ́A�u���v�Ɓu�Ȃ���v�ł���A��`����Ɓu���ׂĂ̐����̊ԂɈႢ������v���ƂɂȂ�B
�@���l���ɂ́A�@���Ԍn�̑��l���A�A��̑��l���A�B��`�q�̑��l��������B
�@�l�Ԃ́A�������l���̉��l����肭���p���Ă���B��������_�������A�@�B���A��Ɖ������������Ƃɖ�肪����B���p�ɗ]��ɂ��U���Ă���B
�@�l�́A���R�ɋt�炤���ƂŁA�l�ƂȂ����B�������A���R�̒��ɂ����������Ȃ��B
�@���R�Ɏ���Ă���l�̕�炵�ɂ́A�،h�̔O������B�l�����R�̈���ł���A�댯�̗\�m�E�@�m��h�q�̔\�͂�����B�ł��A�ŋ߂̎Ⴂ�l�́A�Ⴆ�A�ڂɂ͉��s����������Ă���A�댯�\�m�\�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�x�Ƃ����悤�ȁA���b���������B
|
|
|
|
| 2011�N10��1���i�y�j |
| �A���`�E���̎��Ԃ���ʎ��ւ̕ω��@ |
�@���A���ł́A�A���`�E���̗Y�ԁA���Ԃ��炢�Ă���B���Ԃ́A�₪�āA�ʎ��ɕς���Ă����B���̎ʐ^���݂Ă���������A���̗l�q���A�킩��Ǝv���B
�ʎ��̎h�́A���������h���č���҂ł��B
|
|
|
|
| 2011�N10��1���i�y�j |
| ��������A���c�J��̊쑽���܂ŕ��� |
�@�����́A�����V�C�������̂ŁA���A�v�����āA�����������A�����̐��c�J��܂ŕ������B
�@��̉H�w�Z�ł́A�J�Z�R�O���N�L�O�^����̓��ł������B�O�����h�ɁA�S�Z���k�A�搶�A���Z���W�܂��Ă���ꂽ�B�J�Z���������w�����Ă����������B
�@���̍����~�ɍ~���ƁA�����A�A���`�E�����C�ɂȂ����B�����������������Ă������B
�@�����~�̃I�I�u�^�N�T�́A���̊Ԃ̑䕗�ɂ�鑝�����A���̗͂łقƂ�Ǔ|����Ă����B
�@�J���Z�~�̎p�����x�����������B�ŏ��́A���z�s�̒��k�n���㗬�ł������B�J���Z�~�̎ʐ^���Ƃ��Ă���J�����}�����R�l�����̂ŁA�C���t�����B�Q��ڂ́A�b�B�X�����������A�ԋ��������������ł������B����ɖ��Ă����̂ŁA�T���ƌ��������B�Q�H�����B�߂��ɁA�L�Z�L���C���p���������B
�R�x�ڂ́A�m���A���勴�����ł������B
�S�x�ڂ́A���c�J�g���X�g�������āA���c�}���߂��̖��_�������������B�J�������\���Ă���l�������̂ŁA�����Ă݂���A�Ί݂ɃJ���Z�~�����邱�Ƃ��킩�����B
���̏����㗬���ŁA�_�C�T�M�ƃA�I�T�M�̎p�����������B
���̏��c���Ŗ��ƕʂ�A���c�}���̊쑽���w�ɏo�āA���]�w����A�o�X�ŁA���z�ɏo�āA�o�X�Ŏ���ɋA���Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N9��30���i���j |
| �䕗�œ|�ꂽ�u���،����v�̎��̉� |
�@�ߌ�A�{�����e�B�A�����Ă���u���،����v�ɁA�ԕւ���f�����ɍs���Ă����B
�@�����̒������肷��ƁA�䕗�œ|�ꂽ���Q�{�i�x�j�o�i�g�L���}���T�N�ƃT���X�x���j���A���łɁA���ʂ�ɒ�����A���h�Ȏx�����ł��Ă����̂ɂ͋������B�{�����e�B�A�ł́A��ɕ����Ȃ��̂ŁA�s�̗ƌ����ۂɁA���肢���Ă������A�v���ȑΓ������Ă����������悤���B
�@ |
|
|
|
| 2011�N9��30���i���j |
| �O��s��S����{�v��i���i�āj |
�@�P�O���Q���t�����u�L��݂����v�ɁA�O��s��S����{�v��i���i�āj���܂Ƃ܂�܂����Ƃ̋L�����f�ڂ���Ă���B���ꂩ��V����Z�����c��P�ʂɁA�u�܂��Â��荧�k��v�����{����A�p�u���b�N�R�����g�́A�P�O���R�P���i���j�������ɁA��t���܂��B
�@�����A�����A�s�����Q�K�̑��k�E���Z���^�[�Ɂu�O��s��S����{�v��i���i�āj�v�����������ɍs���Ă��܂����B
�@�܂��A���N�x����E����\��̌ʌv��ɂ��Ă�����������������̂ŁA�u����{�v��Q�O�Q�Q�v�Ɓu�Ɛ��̊�{�v��Q�O�Q�Q�v��������i���i�āj�����������Ă��܂����B
�@�����́A�Q�O�Q�Q�N�x�܂ł́A�v�P�O�N�Ԃ̎O��s�̊�{�I�čs�����^�c�̎w�j�ł���A��Ϗd�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ���A�����̎s���̊S���W�߂������̂ł��B
�@�O��s�̂g�o�́u�p�u���b�N�R�����g�v�ɂ��A�O��s��S����{�v��i���i�āj�v�̑S���́A�f�ڂ���Ă��܂��B ���L�̂t�q�k�ł��B
�@�@�@http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_pubcome/028/028415.html
|
|
|
|
| 2011�N9��30���i���j |
| �s����w�F�u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���@�v |
�@�����̌ߑO���A�s����w�����R�[�X�ł́A����c��w��w�@���E�G�l���M�[�����ȋ����g�c���v����́u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���@�v�肷��u�`���������B
�@�搶�̂��b�ł́A�u�n�����g���̉Ȋw�Ɛ���́A�����ċc�_�ł��Ȃ��v�Ƃ̂��ƁB���{�ł́A�b�n�Q�̔r�o�ʂ͈���Ɍ��炸�A�ނ��둝�����Ă���̂�����ł��邻�����B
�@�O���̖�P���Ԃ́A���N�C�Y�R�U����P�T�����ʼn��A����ɑ������Ɛ�����������A�����ɐ��k�S���̉��W�v���āA��܂��Ȋ�����ʂ̊S�x�������ꂽ�B�ڂ������ʂ́A���T�̍u���ł���������悤�ł���B
�@����c�̊w���̕��ϓI�Ȑ��𗦂́A�R���̂P�������ł���B������́A�s����w�̎�u���̐��𗦂́A�悳�����ł������B |
|
|
|
| 2011�N9��29���i�j |
| �u�A�������v�̉ԕւ� |
�@�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̎��̉Ԃ��炭�������ώ@���Ă���B���̃f�[�^�[���A�ЂƂ̕\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B���̎�ނ͂P�O�O�{�߂����邪�A��r�I�Ԃ��ڗ����̂����ɍi�����B������x�[�X�ɍ�����A�ώ@�𑱂��Ă��������B�N�ɂ���āA�C�ω�����̂ŁA�Ԃ̎������ς��Ǝv���B
�@
�@�@ �ԕւ�
|
|
|
|
| 2011�N9��29���i�j |
| �H����̓��A���]�ԂŁA���U�� |
�@�����́A���₩�ȏH����̈���ƂȂ����B���]�ԂʼnƂ��o�āA�Ƃ���ǂ���ŁA���]�Ԃ�u���āA�����U���B
�@�����̒��k�n���܂ł����A�����Ԃ��B�J���Z�~�̎ʐ^���B��ЂƂƁA�ނ������ЂƂ����������B�����A�Ί݂���J���Z�~�̎ʐ^���B�����B�J���Z�~�́A�Q�ӏ��ŁA���������B�R�T�M�������B
�@�@�@�J���Z�~
�@�@�@�R�T�M
���̍����~�ł́A�X�X�L���悭��������B�J�[�N�T���Q�����Ă���B�L�N�C�����炢�Ă����B
�@�@�@�X�X�L
�@�@�@�J�[�N�T
�������̗N���L��ł́A�c�t�������A�������āA�N���̂Ȃ��ɓ����ėV��ł����B�搶�̃x�X�g�ɖ��O��������Ă��āA�������s���痈�Ă���悤�ł������B
|
|
|
|
| 2011�N9��28���i���j |
| ���N�Ō�̊O���A�������̒�ኈ�� |
�@�����́A�݂������̉�̊O���A�������̍��N�Ō�̒�ኈ�����ł������B���ԂU�����W�܂�A���̐Y�V�����玟�̎��̑�܂ł̊Ԃ̍��݂̃A���`�E���̏����������Ȃ����B
�@���N�́A�V�����疈�T���j���̒��A�V������P���Ԕ��A���̕x�m���勴�����̊Ԃ̊O���A���i�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�A�I�I�t�T���Ȃǁj�̏������s�Ȃ��Ă����B�������P�P��ڂł������B
�@�S�N�ڂ̊������I���A�I�I�u�^�N�T�́A�啪���Ȃ��Ȃ����B�A���`�E���́A���f������Ƃ܂������ɔɖ��Ă���B����ʂ��Ȃ��悤�ɁA����������ɏ������邵���Ȃ��B
�@�@�@��������
|
|
|
|
| 2011�N9��28���i���j |
| ���̍u���u�O��̖��������߂鎋�_�v |
�@���A�O��l�b�g���[�N��w�ցA�l�b�g���[�N��w���u���u�O��̖��������߂鎋�_�v�`��S����{�v�����Ɍ����ā`�̑�P��u�R��P�P�Ȍ�̎Љ�f�U�C�����疢�����l����v���ɂ����Ă����B�u�t�́A������w��w�@�Q�P���I�Љ�f�U�C�������Ȉψ����E���������z�ꂳ��ł������B��������́A�O��s�Ƃ͂Q�O�N���O����A�W�������������ŁA�O��̂��Ƃ��悭�m���Ă�����悤�ł������B�ł��A�Ɠ��̒��ۓI�ȕ\����p���Ęb�������̂ŁA���ɂ́A�Ȃ��Ȃ�����������B
�@�Z�����Ԃɑ����̓��e�����b�ɂȂ�A�[�������ł����킯�ł͂Ȃ����A�u����v����Ƃ��������Ȃ�Ȃ��p���p���āA����͐V�����L���������߂�����Ɉڍs���Ă������Ƃ�������ꂽ�悤���B
�@�O�Y�W���̏�����ǂ߂A�u����v�ɂ��Ă̗������A�ł������ł���B |
|
|
|
| 2011�N9��27���i�j |
| ���̗��ʑ��� |
�@�����́A���P��̖��̗��ʑ�������܂����B�O��s�̗�����̂R�ӏ��i�x�m���勴�A�A��j�ő���������B����l�́A��������啝�ɑ������Ă����i�挎�̖�Q�{�j�B���ꂩ��P�P�����܂ŁA�����̌X���������ƍl���Ă���B
�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q�B �@�㗬�ł̑���̗l�q�B
�@�䓃�⋴����㗬�̔܂ł�S�����Ă��铌���s�̑����̋Ǝ҂��A�����������ō�Ƃ����Ă����B�Ō�̔܂ŁA�����ɂ��I��肻���ł���B�Ǝ҂̑����ɂ��A��ϖ��̕��i�����ꂢ�ɂȂ��Ă����̂́A���ꂵ�����Ƃł���B
�@�@ �@�Ǝ҂ɂ�鏜���̗l�q�������B �@�Ǝ҂ɂ�鏜���̗l�q�������B
�@�@ �@���̕��i���㗬�B �@���̕��i���㗬�B
|
|
|
|
| 2011�N9��26���i���j |
| ���ɒ����N���ʂ̑��� |
�@������A���P��̖��̗N���ʂ̑�����s�Ȃ����B���������̃��i�M���t�߂���A�����́A���싴�㗬�̊Ԃ̂W�����ƁA�����R���̗N���̑���������B�r���ŏ��J���U��o�����̂ŁA�����̂R�������c���āA�����̑���͒��~�����B
�@����l�́A�挎�̐��l���A���Ȃ葝�����Ă����B���ł��N���L��̗N���ʂ́A�挎�̔{�ȏ�ɑ����Ă����B
�@�@�@�@�@�Ђ傤����r�̗N���ʑ���̗l�q�@
�@�x��Ă����Ǝ҂ɂ�鑐���́A�Ō�̔���쐅���ԂŁA�s�Ȃ��Ă����B
�@�L�o�i�R�X���X�����ꂢ�ɍ炢�Ă����B�X�X�L�̕�����ꂢ�ł������B
�@�@�@�L�o�i�R�X���X�̉�
|
|
|
|
| 2011�N9��25���i���j |
| �u�A�������v�ɂ��䕗�̉e�����E�E |
�@����̑䕗�̉e���ŁA�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�ɂ��䕗�̉e���ŁA���R�{���|��A�P�{��������܂ꂽ�B
�@�@�@�@�@�|���ꂽ�x�j�o�i�g�L���}���T�N
�@�����̒��ŁA���炢�Ă���̂́A�T���X�x���A���N�Q�A�n�M�A�A�x���A�A�e�C�J�J�Y���A�ł���B�A�J���K�V���̐Ԃ���������������Ă����B
�@�@�@���N�Q�̉�
�@�@�@�@�@�A�J���K�V���̎�
|
|
|
|
| 2011�@�N9��24���i�y�j |
| �K�[�f�j���O�t�F�X�^�Q�O�P�P |
�@�����́A�O��s�s���Ή����i�ψ���ƎO��s�̎�Â���K�[�f�j���O�t�F�X�^�̂���`���������Ȃ��܂����B
�@���C�����ł́A���[�f�B�j���O�t�F�X�^�ق̎ʐ^����҂ւ̋L�O�i���掮���s�Ȃ�ꂽ�B
�@�@�L�O�i���掮�ł��_��ψ����̈��A�B
�@�@�@�L�O�B�e
�@���̌�A�K�[�f�j���O�u���A�p�l���W���A�𗬃R�[�i�[�A�̑��k�R�[�i�[�A���Ԍ�����A�|�H�̌��R�[�i�[�A�n�[�u�e�B���n�[�u�e�B�N���t�g�̔��Ȃǂ̊�悪�����Ȃ�ꂽ�B��X���A�Q���c�̂̂ЂƂA�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����Ƃ��ĎQ�����A�|�H�̌��R�[�i�[���s�Ȃ����B
|
|
|
|
| 2011�N9��24���i�y�j |
| �q�K���o�i�����������R�ώ@�� |
�@���A���]�ԂŖ������ɏo�������B���R�ώ@���́A���q�K���o�i���悭�炢�Ă���B�䕗�̉e���ŁA���̎}�����������ŁA�댯�ȉӏ�������A���R�ώ@���́A�q�K���o�i�̂Ƃ��낾���J�����Ă��邪�A�قƂ�ǂ́A���Ƃ̕\�����o�Ă����B
�@�@�@�q�K���o�i
�@�@�@�ꕔ�J���̕\��
�������A�_�C�T�M�������B
�@�@�@�@�@�@�_�C�T�M
|
|
|
|
| 2011�N9��23���i���j |
| �䕗�̉e�� |
�@���A�������Ɏ��]�ԂŁA�l�q���݂ɂ������B�䕗�̉e���ŁA���Ȃ�傫�Ȏ����A�|��Ă����B�N���L��ł́A�}���~�̖��|��A���i�M�̖̑傫�Ȏ}���܂�Ă����B�����㗬�ł́A�L���̖��|��A�X�Y�J�P�̖̑傫�Ȏ}���܂�Ă����B
�@�@�@�}���~�̖�
�@�@�@�@�@���i�M�̖�
���̂���������N���Ԃ̐�ӂ̃I�I�u�^�N�T���A���̐����ŁA�قƂ�Ǔ|����Ă��āA�v���Ԃ�ɁA��ӂ��������肵�������ł������B
�@�䂪�Ƃ̒�̃A�����J�n�i�~�Y�L�i���̎��͖�T�O�����A������T���j���A�䕗�ɂ��A�n��T�O�����̂ǂ̍����ŁA�܂�āA�|��Ă��܂����B
�@�ߑO���P�O������P�Q���܂ŁA�ԂƗ̂܂��O��n������̍u�K���ŁA�����́u�K�[�f�j���O�t�G�X�^�v�̏����������B�̃{�����e�B�A����ł́A�|���g�����N���t�g�̌��R�[�i�[�������B���̏����ł���B�����̕��X�����Ă����Ƃ��ꂵ�� |
|
|
|
| 2011�N9��22���i�j |
| �є\�s�V���R���Ӗ쒹�ώ@�� |
�@�䕗���ʂ�߂����̂ŁA�є\�s�̓V���R�i�����P�X�T���j�^�J�̓n������ɍs���Ă����B�V���R����̒��߂͑�ς悭�A�����P�U�N�ɖ����V�c���A���̎R����̒��߂��u�悢�i�F�v�Ƃ���ꂽ�̂ɂ��Ȃ�ŁA���̎R�̖��O�������悤�ł���B��������͎l�������A�X�J�C�^���[���������B
�@�@�@�V���R����̒���
�@�@�@�V���R�Ńg���݂�����l�X
�����Ƀm�X���A�T�V�o�A�g�r�̂悤�Ȏp���݂邱�Ƃ͂ł������A�������āA���ɂ͖��m�ɂ͎��ʂł��Ȃ������B������̋G�߂ɂ́A��������㏸�C���ɂ̂��āA��̕��Ɍł܂��Ĉړ�����p�i�^�J�̓n��j�����邱�Ƃ��ł���ꏊ�ł��邪�A�����͎c�O�Ȃ���A�݂邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������B
|
|
|
|
| 2011�N9��21���i���j |
| �����x�̊h���������B |
�@�J�Ȃ̂ŁA�ƂŖ{��ǂ�ł���B
�@�A���̘b�ł��邪�A�u�h����������A�h���Ɏア�킪�N���ł��Ȃ����ߑ��l���͒Ⴍ�Ȃ�B����A�h���̂܂������Ȃ����肵�������ɂ����Ă��A��Ԃ̋������͂������Ȃ邽�ߋ����Ɏア�킪���ł��āA���l�����Ⴍ�Ȃ�B�E�E���̂��߁A�����x�̊h�����N�����Ă���Ƃ���ŁA���l���������Ƃ����X�����F�߂���v�Ƃ̂��Ƃł���B
�@�{�����e�B�A�̏W�c�ł��A���낢��Ȉӌ����ł邪�A�قǂقǂ̈Ⴂ������l�X�̏W�܂�ł�������A���܂������悤�Ɏv���B�]��ɂ��ӌ����Ⴂ������ƁA�ʂ̏W�c�ɕ�����Ă��܂��������A�����̂ł͂Ȃ����Ɗ�����B���Ƃ��ƁA��������K���ĂȂ��ƁA�c�_�������Ă��A�܂Ƃ܂�Ȃ��̂ŁA���ʂȓw�͂ƂȂ��Ă��܂��B
|
|
|
|
| 2011�N9��20���i�j |
| �䕗�ڋ� |
�@�䕗�ڋ߂ŁA�O����A�����́A�����珬�J�ł���B���邩�疾���̒��Ԃ́A�J�����Ȃ�~�肻�����B
�@���A���]�ԂŖ��̒�@�ɏo�������B���͂ɂ����Ă��Ȃ��B���J�̒��A�����s�̋Ǝ҂��x��Ă��鍂���~�̑������s�Ȃ��Ă����B���̌䓃�⋴����㗬�̔܂ł́A�X�����{�܂łɁA��Q��ڂ̑������I��鎖�ɂȂ��Ă���Ȃ��ł��邪�A���̌䓃�⋴���甪�����Ԃ��A�قڏI����Ă��邾���ŁA����������㗬�̔Ԃ́A���ꂩ��ł���B�Ǝ҂ɋ}���ł��炢�����|�����������B
�@
�@�@�@���������牺��������B�@�����͑啪�i��ł���B
�@�@�@����������㗬������B�����́A���ꂩ��B
�@�@�@�Y�V������㗬������B�����́A�肪���ĂȂ��B
�@�@�@�쐅������㗬������B�����́A�肪���ĂȂ��B
���A���̋��́A��������㗬�ɁA�䓃�⋴�A�H�A�������A��A�������A�Y�V���A�쐅���A�ł���B
|
|
|
|
| 2011�N9��19���i���j |
| �J���Z�~�̃z�o�����O |
�@�������A���̑��\�Y�������E�݂ŁA�ɖ��Ă����A���`�E���̏������A��l�ŁA�P���Ԃقǂ����B
�@�@�@�A���`�E���̏�������
�@���������̑��̗��ł́A��肪�s���Ă���悤�ŁA���������̑����̏����ŋ}���������ł������B
�@���ł́A�J���Z�~������Ƀz�o�����O�����ẮA��э���ł���悤�ŁA�J�����}�����R���ꐶ�����ʐ^���Ƃ��Ă����B�������̊Ԃɓ���Ă��������āA�P�������ʐ^���B�������A�A���Č���ƁA�s���Ƃ̓J���Z�~�ɂ͍��킸�A���̕��ɂ����Ă����B�ł��z�o�����O�̗l�q�͂킩��B
�@�@�@�J���Z�~
�@�@�@�J���Z�~�̃z�o�����O
�@�ߌ�A����ɁA��������������݂̊m�F�ɏo�������B�������݂̉�����Ǝ҂ɂ��肢���Ă������A��������������Ă����B����ŁA�P���������� |
|
|
|
| 2011�N9��18���i���j |
| �O���A���Ƃ� |
�@�Q���O�̊��u���u���̊O���A���ɂ��čl����v�̑�Q��ڂł́A�u�O���A���Ƃ́v�Ƒ肷�铌���_�Ƒ�w�������{���V�搶�̍u�`�����B�@�����́A���̃��W����ǂݕԂ��Ă���B
���W���̍\���́A
�P�O���A���̒�`
�@�P�|�P����O�������Ƃ�
�@�P�|�Q�O���A���ƋA���A���̈Ⴂ
�@�P�|�R���C���h�t�����[�Ɠ���O���A��
�Q�N���N��ɂ��O���A���̋敪
�@�@�j�O�A���A��
�@�A��A���A��
�@�B�ߐ��A���A��
�@�C���A���A��
�R���ɐN�������O���A��
�@�R�|�P���x�o�ϐ�����
�@�R�|�Q�����u�[��
�@�R�|�R�K�[�f�j���O�u�[���E�E�K�[�f�j���O�̖ړI�ŁA��v�ŁA���ꂢ�Ȃ��̂��g���B�}����⊔�������₷�����̂������B
�@�@�@�@�@���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�S���{�̊O���A���̌��Y�n�E�E���[���b�p���Y�������Ƃ��������B���Ŗk�A�����J���Y�ł���B
�T�͐�ő�Q�����`������O���A���E�E�ŋ߂̉͐�́A�@�������̊����ɂ��h���p�x���ቺ���Ă��Ă��āA�A�y��̕x�h�{����
�@�@�@�@�@�i��ł���̂ŁA�����ɐN�����Ă����A���`�E���A�Z�C���E�J���V�i�A�Z�C�_�J�A���_�`�\�E�A�I�I�u�^�N�T�A�L�N�C���A�C�k�L�N�C���Ȃǂ�
�@�@�@�@�@�O���A���̐���ɂƂ��čD�K�Ȋ��ƂȂ��Ă���B
�U�ȒP�ȐA�������̎d��
�@�ł������B
|
|
|
|
| 2011�N9��17���i�y�j |
| �q�K���o�i�����������R�ώ@�� |
�@�����́A�������{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł���B�X���������P���Ԕ��A���͐��o�[�h�T���N�`�����̃t�G���X�ۂ̒ʘH�̏����������B�P�P�������琢�b�l������B
�@���������R�ώ@���ł́A���N�X���̉��{�ɂ̓q�K���o�i���Q������B���N���A�ꕔ�ŁA�炫�͂��߂��B
�@�@�@�炫�͂��߂��q�K���o�i
�@�ߌ�́A�����V����̒|�ъǗ���Ƃ��Q���ԂقǍs�Ȃ����B
|
|
|
|
| 2011�N9��16���i���j |
| �@���u���u���̊O���A�����l����v��Q�� |
|
�@�ߌ�A���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v��Q��u�O���A���Ƃ́v�Ƒ肷��u�`���������B�u�t�́A�����_�Ƒ�w�������{���V�搶�A�ꏊ�́A�O��s���Љ���قł���B��u�o�Ȏ҂́A�R�R���]��A�O��s�����ł͂Ȃ��A���c�J��⍑�����������u�҂����݂��ɂȂ����B
|
|
|
|
| 2011�N9��15���i�j |
| ����܂ŁA�����{�����e�B�A�ł��o�����B |
�@�悭�m���Ă���l�̓y�n�ɁA�w�������G�����ɖ��Ă��܂����Ƃ̂��ƂŁA����ƍ����́A����܂ŁA�����ɏo�������B���̏t�ɍX�n�ɂ����y�n�ł��邪�A���N�̊ԂɁA�т����肷��قǎG�����A�������Ă��܂����B
�@�����́A�Ȃꂽ�����ł��邪�A���̏����̂Ȃ��A����̌ߌ�P���Ԕ��A�����́A�ߑO���P���Ԕ��A�ߌ�P���Ԕ��A���v�S���Ԕ��̏����ł������B
�@�ł��A�M���ǂɂȂ炸�A�����I�������B�I�������A���̂��A�[�������������B
�@�ł����������݂̉�����A�ʂ������̂ŁA�܂����ł���B�s�����̒S���ۂɕ����ɍs�������A�s�̔p���������Z���^�[�܂ŁA�������ޕK�v������A����́A�c�O�Ȃ���Ǝ҂ɂ��肢���邵���Ȃ��悤���B
|
|
|
|
| 2011�N9��14���i���j |
| �A���`�E���ɉʎ������n�߂��B |
�@�����́A�݂������̉�̒�ኈ�����B���ԂS�����A�V������P���Ԕ��A�O���A���̏��������������B�A���`�E���ɂ́A�W������Ԃ��炢�Ă������A���悢��ʎ������������B���Ȃ�傫�Ȃ��̂�����B�����`�ŁA�\�ʂɂ��炩���h�Ɩтɕ���ꂽ���̂����W�܂��āA�R���y���g�E�̂悤�ȉʎ��ł���B
���̎h�́A�ׂ����A�ߕ��ɂ��ƁA���������h���č�����̂ł���B�����Ă��Ȃ��Ȃ��Ƃ�Ȃ��B��{�A��{�ʂ������Ȃ��B���N���������B
�@ �A���`�E���ɉʎ�
|
|
|
|
| 2011�N9��13���i�j |
| �G�N�Z���̕\�쐬�ň��J |
�@�������������ł������B�����ɁA���]�ԂŖ��ɒ�@�ɏo������B�����̒�ኈ�����̉����ł���B�����́A�쐅������Y�V���Ԃ̗��݂ŁA�O���A���̏���������B�A���`�E�����������ŁA�ɖ��Ă����B�A���`�E���̉Ԃ��炢�āA�������̂ł́A�����Ȏ����t���n�߂Ă���B���̎��̐j�́A�ߕ��ɕt���ƁA���������Ƃ��đ�ύ���҂ł���B���������Ӗ��ł��A�������}�����Ƃ��K�v�ł���B
�@�ƂɋA���āA�A�������̃f�[�^�[����������B���u���u���̊O���A�����l����v�̍u�t�̐搶�̎w���ŁA�������傫�ȃG�N�Z���̕\������āA������A��������ɕ����āA�������x�̕��ϒl���A��������B��є�т̍s�ł̕��ς��v�Z������A�f�[�^�[��]�L������ƁA�ԈႢ�₷����Ƃ��A�J��Ԃ��s�Ȃ��B
�@�{�P�h�~�ɂ͂Ȃ�B |
|
|
|
| 2011�N9��12���i���j |
| �ԍL��̏H |
�@�����́A�ԍL��̗̃{�����e�B�A�]�[���̏������s�Ȃ����B�������Q�����A�܂��c�����������̂ŁA��Ƃ́A�P���Ԏ�ŏI���Ƃ����B�̃{�����e�B�A�]�[���ł́A�I�~�i�G�V���悭�炢�Ă����B���̋߂��ɂ́A�����͂���̃A�W�T�C�E�X�~�_�̉ԉ��悭�炢�Ă����B���N�ڐA�����̂ŁA�����ɊԂɍ��킸�A�x���炢���悤���B
�@�@�@�@�I�~�i�G�V
�@�@�@�@�X�~�_�̉ԉ�
�L��̒[�̃t�G���X�ۂł́A�X�X�L�ƃn�M���炢�Ă����B
�@�@�@
|
|
|
|
| 2011�N9��11���i���j |
| ���@�����{�����e�B�A�̒�ኈ���� |
�@���A�v���Ԃ�ɖ��Ń_�C�T�M�̎p���݂��B
�@�@�@�@�_�C�T�M
�����́A�c�������������A�������{�����e�B�A�̒�ኈ�����s�Ȃ����B���́A���Ԑ����Ɠ��o�[�h�T���N�`�����̍�ƒʘH�t�߂̏������s�Ȃ����B�؉A�ɂȂ��Ă������A���x�������悤�ŁA�����������������B
|
|
|
|
| 2011�N9��10���i�y�j |
| �n�����ۑS�A���Z�~�i�[����u���܂����B |
�@�ߌ�A���c�J�g���X�g�E�r�W�^�[�Z���^�[�ōs�Ȃ�ꂽ�A��Q��u�n�����ۑS��n��h�ЂɊ������v�Z�~�i�[�ɎQ�����܂����B�ŏ��A��P���Ԕ��A������w���_���������O�B�搶�́u�s�s�̐��z�̗���������[�n��̐���ӂƐ��c�J�[�v�Ƒ肷���u�����������B�n�����͉��B�ł͌��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��邪�A���{�ł͂܂������Ȃ��Ă��Ȃ��B�Q�O�N�x��Ă��邻���ł���B
�@�����ŁA�b��Ƃ��ĂQ���A�u���_�̐X�݂r�̗N���Ɛ������̂����v�Ɓu���c�J�_���ɂ�鍋�J��ƗN���ۑS�v�̕��������B
�@���̌�A�p�l���f�B�X�J�b�V�������������B |
|
|
|
| 2011�N9��9���i���j |
| �߂��̏��w�Z�S�N���̊��w�K�̂���`�� |
�@�ߑO���A��R�����Ƒ�S�����Ɂi�P�O���S�T������P�Q���P�T���j�ɉH�w�Z�S�N���̊��w�K�u�����悭���銈���F�O���A���̏����v�̂���`�������܂��B�Q���������k�́A��S�O���B�S�ǂɕ�����āA�����������B�搶���R���Q�����ꂽ�B�u�݂������̉�v����͂S�����Q�����A�O���A���̏����i�R�O���ԁj�̎w���ƍݗ��A����T�����i�Q�O���ԁj���A�s�Ȃ����B�O���A���̏����́A�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�A�I�I�t�T�������������ł����B�ݗ��A����T�����ł́A���k�������W�߂Ă����g�߂Ȑ�̐A���ɂ��āA�A���ɏڂ��������o�[���A�ȒP�Ȑ������s�Ȃ����B
���������́A���C�Ɋ��������Ă��ꂽ�B
�@�@�@�����O�@�i�A���`�E���������ς��j
�@�@�@�@�@������i�A���`�E���������ł����j
|
|
|
|
| 2011�N9��8���i�j |
| �X���̌���쒹�ώ@ |
�@�����́A�X���̌���쒹�ώ@���s�Ȃ����B�������V�C�ł������A���̎p�����Ȃ��A�܂��������C���o�Ȃ������B�����Ɋ��҂��������B
�@�P�O���W���i�y�j�X���ɁA���������R�ώ@�Z���^�[�ɏW���ŁA��ʌ����̖������쒹�ώ@��s�Ȃ���B���̌�A�S���܂ŁA�����s�Ȃ���B���̃|�X�^�[�́A�����쐬��S�����Ă���B
�@�@
|
|
|
|
| 2011�N9��7���i���j |
| ���̊O���A�������̒�ኈ���� |
�@�����́A�T���́A�݂������̉�̒�ኈ�����ŁA���V������P���Ԕ��A���̔���쐅���Ԃ̗��݂ŁA�O���A���i�A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�j�̏����������s�Ȃ����B�����o�[�U�����Q�������B���̊��o�́A���̃��W�I�̑��̂悤�̂��������ł���B�����͏I���ƁA����₩�ȋC���ɂȂ�B
�@
�@�@�@�@�������̌f����
�@�@�@�@�������݂̕\��
���ł́A���A�L�N�C���̉Ԃ��炢�Ă���B�C�^�h���̔����Ԃ��炢�Ă���B
�@�@�@�L�N�C���̉�
|
|
|
|
| 2011�N9��6���i�j |
| ���̃t�W�o�J�} |
�@���Ńt�W�o�J�}���������Ă���ꏊ�����邱�Ƃ��킩�����B���Ƃ��ۑS�������Ƃ������ƂŁA�܂����ɂȂ����̂́A�����s�ɂ��N�R��̑����ł���B�����̎����Ɋ����Ă��܂��ƁA�Ȃ��ȉԂ��炭�܂łɂȂ�Ȃ��悤���B
�@
�@�@�@�@�t�W�o�J�}
�@�����A���肢���āA�s�̒S���҂Ɍ�������Ă����������B���N�Q��ڈȍ~�̑����̍ۂɂ́A���̃]�[�������͑��������Ȃ��悤�ɂ��āA����Ɏs�����A���������邱�Ƃ��A�b���������B��������ƁA���N���y���݂ł���B
|
|
|
|
| 2011�N9��5���i���j |
| �c�O�I�߂��̏��w�Z�́u���w�K�v�͂܂����� |
�@�����A�U��������A�߂��̏��w�Z�̊��w�K�̏����������B
���Ƃ͂R�C�S�����ł���B
�@�J���Z�~�̎p�����������B
�@�J���Z�~
�@���̉J�ŁA���̐��������Ă���̂ŁA���ɂ͓���Ȃ��悤�ɂ��āA�O���A���̏����̌�������悤�ɁA�l�����B�A���`�E���̔ɖ��Ă���Ƃ��낪��������B�I�I�u�^�N�T������B
�@�����\��n�̗l�q
���ӂ̃I�I�t�T���͍���́A������������߂邱�Ƃɂ����B�������݂̒u���ꏊ�̕\���A�����͈͂̕\���A�ʘH�̑����ȂǂP���Ԕ����������B
�@��������Ƃ̋A���āA�x��ł���ƁA�X�����납��J���~��o�����B�{�~��ł���B�c�O�Ȃ���A����ł́A���{�ł��Ȃ��B�܂����A�����Ŏc�O�B���ԂɒN���J�j������悤���B�@ |
|
|
|
| 2011�N9��4���i���j |
| ���p�ŁA�V����܂ł��o���� |
�@�����́A�V����܂ŁA���p�ŏo�����Ă����B�������w����o�X�œc���w�ɏo�āA�����V�h���ŁA�V����܂ōs���B�w�O�ɂ́A�r������A�������̒������������B�̎��Ԃ�葁�������̂ŁA�x���`�ŁA���炭���Ԓ��߂������B
�@�J�����������Ă��Ȃ������̂ŁA�g�тŎB�e�����B���Ƃ��ʂ��Ă���B
�@
�@�@�@�@�@�V����w�O
|
|
|
|
| 2011�N9��3���i�y�j |
| ���̓��̎G�� |
�@�����́A�䕗�P�Q���̉e���ŁA��������������A���X�J���~��A�s����Ȃ��V�C�ł����B����قƂ�ljƂŁA�̂�т肷�����B
�@�������ɏo������Ƃ��ɁA������킹��ƁA�����A�͂�����u����ɂ��́v�ƁA���A�����Ă����ߏ��̎q��������B�����́A���Ɍ������ĎP�������V�т����Ă���B�������Ԃƈꏏ�ɂ��킢���Ȃ��悤�Ȃ��ƂŁA�ꐶ�����V��ł���B���̏W���͂́A�����������̂��Ɗ�����B�Ƃ̒��Ɉ�������ł���q�����A�O�ŗV��ł���q���̎p���A�����Ǝv���B
�@�ŋ߁A�T�b�J�[�̌���̂��y���݂ł���B������Ȃł����̊؍��킪�A�ߌ�W�����炠��B�X�P�W���[�����������悤�ő�ς����A����́A�x�X�g�����o�[�̂悤���B
�@����̒j�q�̂v�t�k���N����A�Ō�ɂ����Ƃ���������Ă���āA�悩�����B |
|
|
|
| 2011�N9��2���i���j |
| �䕗�̉e���ŁA�u���w�K�v�̂���`������Ȃ��B |
�@���T�̌��j���i�T���j�ɋ߂��̏��w�Z�́u���w�K�v�̂���`������v��ɂȂ��Ă��邪�A���V�C����ϐS�z�ł���B
�@���̕����ƁA�܂�����������Ȃ��悤�ȋC�z������B�����A��������Ƃ����H�̋�ɂȂ��Ăق����B |
|
|
|
| 2011�N9��1���i�j |
| �H�@ |
�@�����A���]�Ԃő����Ă���ƁA���X�A�I�̖���������B�H�̖��o�ł���B
�@�@�@�I�̎�
�@���T�A���w�K��������̏ꏊ�̉����ɍs�����B�䕗�̉e���ŁA�����̓������x��Ă���悤�ŁA�����������ŁA�������Ƃ܂��Ă���B�������ȁ[�Ɗ������B���x�H���𐿂������Ă���Ǝ҂̎p�����������̂ŁA��������b���āA�z�������Ă��������邱�Ƃ��ł����B����S�ł���B
�@
�@�w�K�\��ꏊ�ɂ́A�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�A�I�I�t�T�����ɖ��Ă���B�S���Ƃ�̂́A���������A��Ƃ𗝉�����̂́A�������鋳�ނ�����B
�@���̏ォ�猩�Ă���ƁA�R�T�M���A����Ă����B�ł��Ȃ��Ȃ��l���̏����́A���Ȃ������B
�@�@�R�T�M
|
|
|
|
| 2011�N8��31���i���j |
| �����̊O���A���������� |
�@�����́A�����V������A���̑��\�Y������Ԃ̗��݂́A�I�I�u�^�N�T�ƃA���`�E���̏����������s�Ȃ����B���������Ă����B���Ԃ͑S���łU���B���̂P���Ԕ��A���������������B
�@�V�C�\��ł́A�J�őʖڂ��낤�Ǝv���Ă������A���S��������������ƁA�����������B�\�z�O�ł������B
�@
�@�@�@�@���\�Y�����牺��������B�������Ă���B
�@��������ƂɋA���āA�P�O�������납��A�k�����암���ݎ������ɏo�����A�X���T���ɍs�Ȃ��߂��̏��w�Z�̊��w�K�u������銈���F�O���A���̏����v�̂��߂ɂ��肢���Ă����͐�ꎞ�g�p�͂����Ă����B
�@���A�J�ŁA�����ɂȂ��Ă���̂ŁA���x�́A�����Ɏ��{�ł��邱�Ƃ��肤�B
|
|
|
|
| 2011�N8��30���i�j |
| ���z��s�� |
�@�����A���̕x�m���勴�t�߂ŁA�I�I�u�^�N�T�̏������P���ԂقǍs�Ȃ����B������̌i�F������ƁA�����ق��Ƃ���B
�@�@�@������̌i�F�@�i���݂������j
�@��������ɋA���āA�P�O���߂��ɁA�܂����ɏo�Ă����B�N���L��t�߂ɂ́A�����������̎q�����ꂪ�A�V��ł���B
�@�@�@���ʂ����㗬�̎q������
�@�v���Ԃ�ɁA������̐X�����ɗ������A���z��s�ꂪ�悭������v���y���E�J�b�t�G�ŁA�����`�X�W�O�~��H�ׂ��B�����̃����`�́A�Ԃ��J���r���ł������B�X�[�v�A�h�����N�t���ł���B�ׂ́A�����H��i�H�j������A�S��̃v���y���@���i�[����Ă����B���F����s�@���C�ɂ����̂ŁA�ʐ^�Ɏ��߂��B
�@�@�@���F����s�@
�����H���ł́A���h�Ԃ��Q�䂢�āA�����̐l���W�܂��Ă����B
�@�@�@���h�P���i�H�j
|
|
|
|
| 2011�N8��29���i���j |
| ���̗��ʑ���i�W���j |
�@�����A�����́A���̗��ʑ�����R�ӏ��i�x�m���勴�A�A��j�ōs�Ȃ����B�R�ӏ��Ƃ��V���̑��莞���A�S�O���قǑ������Ă����B
�@�x�m���勴�̑���_�t�߂ł́A�W���Y�_�}���ڂ����Ă����B
�@�@ �@�x�m���勴�̑���̗l�q �@�x�m���勴�̑���̗l�q
�@�@ �@�W���Y�_�} �@�W���Y�_�}
�@�@ �@�W���Y�_�} �@�W���Y�_�}
|
|
|
|
| 2011�N8��29���i���j |
| �T���R�E�`���E�̗c�� |
�@����HP�i�V�j�A����j�̌f���Ɏ�]���q���A�T���R�E�`���E�̗c���̎ʐ^�𓊍e����܂����B���̃y�[�W�ł݂��܂��B
�@�@http://8926.teacup.com/adam/bbs
�������ɂ́A�������A�H�̋G�߂����Ă���悤�ł��B |
|
|
|
| 2011�N8��28���i���j |
| ���̒����N���ʂ̑���i�W���j |
�@���A�V�������A�������̃z�^����ɂ����B�z�^����̐��́A���������B
�@�@�@�@
�@��������N���͏o�Ă��āA���ɕ��s�ɂR�Om�قǗ���āA���ɂ������B�z�^����́A�{�����e�B�A���U�N�قǑO�ɍ�����A���Pm�قǂ̏����ȗN���̏���ł���B�@
�@�����́A���P��́A���ɒ����N���ʂ̑�����s�Ȃ����B���ς���A�قڐ挎���݂̗N���ʂł������B
�@
�@�@�@�@�N���L��ł̑���̗l�q
�@���낢��Ƃ����������āA�N���ʂ̑��肪�x��Ă������A�����ł��Ăق��Ƃ��Ă���B
�@�����́A���̗��ʂ𑪒肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�J���~��O�ɁA���邱�Ƃ��ł������ŁA���������B
|
|
|
|
| 2011�N8��27���i�y�j |
| �u�A�������v�̉ԁF�A�x���A�A�t�W�A���N�Q�A�e�C�J�J�Y�� |
�@�����́A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�̒�ኈ�����ł������B���́A�T�U���J�̐��_�̊��荞�݂��s�Ȃ����B
�@���A�u�A�������v�ł́A�A�x���A�A�t�W�A���N�Q�A�T���X�x���A�e�C�J�J�Y���̉Ԃ�������B
�@�@�@�A�x���A�̉�
�@�@�@�t�W�̉�
�@�@�@�J�����̎�
�@�@�@�u���[�x���[�̎�
|
|
|
|
| 2011�N8��26���i���j |
| ���̃t�B�[���h���[�N�������I�� |
�@�啪�O����A���������Ă������u���u���̊O���A���ɂ��čl����v�̑�P��u���̃t�B�[���h���[�N�v���A�����Q�U���i���j�̌ߑO���ɖ����I�������B
�@����͉J�A�����̌ߌ�R�����납��J���~��o�����B���ƍ����́A����Ă���ď��������B
�@�����̎Q���\��҂́A�S�O���]��A�P���̒��s�ǂŁA���O�Ɍ��Ȃ̘A�������������A����ȊO�́A���ׂĂ̕����o�Ȃ��ꂽ�B�ӎ��̍��������Ď���B
�@�P�O�������ɁA�����n�_�̖��E�݂̊~���ƟK���̊ԂɏW�܂�A�����_�Ƒ�w�������{���V�搶�̎w���ŁA�S�ǂɕ�����āA�u�I�I�u�^�N�T�̒����v�Ɓu�A���`�E�����z�����v���s�Ȃ����B�搶�́A���������Ȃ���Ɠx����A�y�됅������A�y��d�x����A�I�I�u�^�N�T�i�A���`�E���j�O�̎G���̑���Ɣ�x�i���j������s�Ȃ�ꂽ�B�ܘ_��w�@���P���Ǝ�u�҂��⏕���s�Ȃ������A�S�����̑���͏����Ȃ��A�����⋋�����Ȃ���̑�ςȍ�ƂɌ������B��u�������́A��L�̑��肪���Ƃ���́A�I�I�u�^�N�T�̑���A�s���a�A�t���A���d�ʂ̑�����s�Ȃ����B
�@�A���`�E���ɂ��Ă��A���l�Ɏ�u���͑���A�t���A�S�d�ʂ̑���������B
�@
�@�@�@�A���`�E�����z�����̗l�q
�@�Ō�ɁA���������R�ώ@�Z���^�[�̃��N�`�����ł܂Ƃ߂��s�Ȃ������A���̍ۂɁA�搶����u�O���A���������Ĉ��S�ƌ����̂ł͂Ȃ��A���Ƃ��Ɩ��ɂ������I�~�i�G�V�̂悤�Ȗ쑐��u�������邱�Ƃ�����̂������B���̂��߂ɂ́A�킩��A�c������A�u���������Ƃ��s�Ȃ����ƂɂȂ�v�|�̂��b�����������āA�����悪���邭�Ȃ������������B
|
|
|
|
| 2011�N8��25���i�j |
| �����ł����̑������n�܂����B |
�@���̉E�݂ŁA�����̌䓃�⋴���琴�����Ԃł��s�̑����肪�n�܂����B���̍��݂͉����̌䓃�⋴����H�Ԃ��I����Ă���B
�@�@�@�H���牺��������
�@�Ǝ҂��Ⴄ���A�㗬�ł́A���݂�����������瑐���n�܂����B�����́A�����x�m���勴�܂łł��邾�낤�B
�@
�@���\�Y�������ŁA�_�C�T�M�������B����Ɋl����_���Ă����B
�@�@�@�@�_�C�T�M
|
|
|
|
| 2011�N8��24���i���j |
| ���̑������n�܂��� |
�@��������A���̔㗬���݂ŁA�����s�̋Ǝ҂���������͂��߂��B���N�Q��ڂ̑����ł���B�f�����ꂽ�\��\�ł́A�W�����{����X�����{�ɍs�Ȃ��ƂȂ��Ă���B���̑����́A���ӂP�D�T���́A���������Ȃ��Ŏc���B���̂P�D�T���̕��ɁA�I�I�u�^�N�T�͔ɖ��邱�ƂɂȂ�B
�@
�@�@�@���̑������n�܂�
�@�@�@���̑������n�܂�
�@�����́A�݂������̉�̏T�P��̒�ኈ�����B�����o�[�W���S�����Q�������B���ꂵ�����ł���B�x�m���勴������싴�Ԃ̗��݂̊O���A���i��ɃA���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�j�̏����������Ȃ����B�����J���Z�~�̎ʐ^���B���Ă���l�������A�u�����̂ɑ�ς��ˁv�u���ꂢ�ɂȂ����B����J�l�v�Ƃ̐��������������B��������ꂵ�����Ƃł���B
|
|
|
|
| 2011�N8��23���i�j |
| �����͑�ρI |
�@�W���Q�U���i���j�ɁA�O��s���Љ���قƑ��Z�����c��������Â̊��u����P��ځu���̃t�B�[���h���[�N�v���s�Ȃ��B�u�t�̐搶�ƘA�����Ƃ�A�u�I�I�u�^�N�T�̌̒����v�Ɓu�A���`�E�����z�����v���S�O���̎�u�҂ŁA�s�Ȃ����߂̒i�����s�Ȃ��̂����̖����ł���B
�@�u�t�̐搶�Ƙb�����āA�S�ǂŁA��L�̒������s�Ȃ����Ƃɗ����������B�u�I�I�u�^�N�T�̌̒����v�ł́A�O�D�T�����O�D�T���͈̔͂̑����A�s���a�A���d�ʁA�t���𑪒肷��B����𐔉ӏ��ōs�Ȃ��B�u�A���`�E�����z�����v�ł́A�������A�O�D�T�����O�D�T���͈̔͂̌Q�����A�t���A�S�d�ʂ𑪒肷��B
�@�����̌��ʂ́A��Q��̍u�`�ŗ��p�����\��ł���B
���Ƃ��Ӗ�������A�t�B�[���h���[�N�ƂȂ�悤�ɁA�Ō�̓w�͂����Ă��܂��B |
|
|
|
| 2011�N8��23���i�j |
| �䒃�m���̕a�@�܂ōs���Ă��܂����B |
| �@�����́A���Ȃ̒���f�f�ŁA�䒃�m���̕a�@�܂ŏo�����Ă��܂����B�������ł���̂ŁA�R���X�e���[���l�͐���Ɉێ�����Ă���B |
|
|
|
| 2011�N8��21���i���j |
| �߉������{��C�`���E�̏C���ɂ��� |
�@�ߑO���A�ԂƗ̂܂��O��n������̂R�K�ŁA�����_�Ƒ�w�����_����א搶�́u���̈琬�Ǘ��ɂ��āv�Ƒ肷��u����������B���̍Ō�̂P���ԂŁA�@�u�߉������{��C�`���E�̏C���ɂ��āv�Ɓu�����{��k�Ђ̂܂v�Ƒ肷��Q�̋������邨�b�����Ƃ��ł����B
�@���������ł������Ƃ́A�߉������{��C�`���E�́A������̐����⋋���A�\�f�������Ȃ����������B
�@���O���c�s�̎c�����P�{�܂́A���������܂ŁA�n�ʂ��V�O����W�O�����������Ă���ꏊ�ɂ���B���̂܂��c�����̂́A�Ôg�Ƃ̊ԂɌ���������A�Ôg�̉e�������Ȃ��������߂ł͂Ȃ����Ǝv����B�܂̍��͂Q���ȏ�͂̂тȂ��Ƃ���Ă���B���܂������z���グ���邩�A�ǂ������d�v�B�ł��������͓̂���悤���Ƃ̂��ƁB
�@�Ō�ɁA�u�l�͎��R�ɋt�炤���ƂŐl�ɂȂ������A���R�̂Ȃ��ł����������Ȃ��Ƃ����������������Đ����Ă���v�ƍ��ɏ����Ē��߂�����ꂽ�B |
|
|
|
| 2011�N8��20���i�y�j |
| �Ԓr�ɐ����I |
�@�����́A�������{�����e�B�A�̒�ኈ�����B�X�����Ɏ��R�ώ@�Z���^�[�ɏW�܂����{�����e�B�A�́A�܂�������s�Ȃ��B�Z���^�[����̘A���A�����ǂ���̘A���A�e�{�����e�B�A�O���[�v����̘A���̌�A�{���̍�Ƃ����肷��B
�@����̂��ƁA���W�I�̑������āA���ꂼ��ɕ�����āA�Q���ԑ��炸�̊������s�Ȃ��B
�@���́A���o�[�h�T���N�`�������̂����r�̐�����Ƃ��s�Ȃ����B���ꍞ�ސ������Ȃ��A�ď�́A���͂�ɋ߂��Ȃ�B�M�d�Ȑ������Ƃ��A���ɗ��ߍ��݁A�L���ɗ��p���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�����́A�r�̒[�̃h���グ���s�Ȃ����B
�@�P�P��������P���ԂقǁA�����̐��b�l�����A�����̎w��Ǘ��҂ƃ{�����e�B�A�̐��b�l�Ƃ̊Ԃ̂��낢��Ȏ�����ł����킹�Č��߂Ă���B |
|
|
|
| 2011�N8��19���i���j |
| �v���̗N���ʂ̑�������w |
�@�����s�̋Ǝ҂��A�����ƍ���A���̗��ʂƖ��ɒ����N���ʂ̑���������B���A���́A�������āA�O��̕t�߂ł́A�v���ɂ��N���ʂ̑�������w�����Ă����������B��ώQ�l�ɂȂ����B
�@���ł́A�J���Z�~���A���x�������Q�b�g�����Ƃ���ł������B�Ȃ��Ȃ����ݍ��܂Ȃ������B
�@�@�@�J���Z�~
���������A���̂��ʂ����㗬�ŁA�I�I�u�^�N�T�̖��x�A�����A�d�ʂȂǂ̑�����A�s�Ȃ����B
�@���x�́A��U�O�{/�@����m�������B
�@�@�@�@�I�I�u�^�N�T�̖��x����
|
|
|
|
| 2011�N8��17���i���j |
| �������A���̊O���A���̋쏜���� |
�@�T���݂̂������̉�̊O���A���̏�����Ƃ��P���ԂقǍs�Ȃ����B�����́A���ӂ��̃I�I�u�^�N�T���啔���ł������B�Q���������Ԃ͂T���A�u���������������v�Ƃ̐����������B
�@��Ƃ��I����āA���߂�ƁA�m���ɂ悭�Ȃ����B
�@�@�ƂɋA���āA�V�����[�𗁂сA�ꑧ���Ă���A�e�[�u���̘e�ɂ����Ă������m�[�g���Ƃ�ƁA�m�[�g�ƃm�[�g�̊Ԃ��畴�������Ǝv���Ă����\���蒠���o�Ă����B�悩�����B���I
�@���S�z�����������Đ\����܂���ł����B |
|
|
|
| 2011�N8��16���i�j |
| ����������������ł����B�@ |
�@���������ς�炸������A�������ł����B
�@�ߑO���A�����s�k�����암���ݎ������ɁA���̊O���A���̏�����Ƃ̊֘A�ŏo�����Ă��܂����B���������������ł����B
�@�A��́A�������̒��z�o�R�ŁA�w����͏��c�}�o�X�ŁA����߂��̃o�X��u�V���䗠�v�܂ŋA���Ă��܂����B���H�́A���z�w�O�̒��ؗ����X�Ń����`���j���[�ʼn�����H�ׂ܂����B�����̖��X�͓��ʂȖ�������̂ŁA�C�ɓ����Ă��܂��B
�@�Ƃň�x�݂��Ă���A�ߌ�́A�W���Q�U���ɍs�Ȃ��u���u���F���̊O���A���ɂ��čl����v�́u���̃t�C�[���h���[�N�v�̏����ɂ��낢�듪���g���B����u�t�̍��{�搶�ƂR�O���قǑō���������v�������ł������A�搶�̂��w���ŁA�搶�́u����́A���̐A���ώ@��ł͂���܂���B�Q�������F����ɊO���A���̐i���̎��Ԃ��ł��邾����ʓI�ɔc�����Ă��炢�����Ǝv���܂��v�Ƃ̎v�����A�Q���҂ɒʂ���t�C�[���h���[�N�ɂȂ�悤�A�����ɖ��S���������Ɠw�͂��Ă��܂��B���̂��߂̑�����p��̏�������ςł��B�܂����������Ȃ̂ŁA�M���ǂɂ����ӂ��K�v�ł��B���̂悤�ɁA�ړI������A�������Ă���ƁA�����������́A���̂��܂��B
|
|
|
|
| 2011�N8��15���i���j |
| �I��̓��@�U�U�N�O�̋L�� |
| �@�����́A�U�U�N�O�ɑ��m�푈���I��������ł���B�a�J���̎��́A�{�Â̕������ŁA���a�V�c�̋ʉ����������B�搶����A�푈���I������Ƃ̐������āA���߂ē��e���킩�����悤�Ɏv���B�Ă̏������ł������B
|
|
|
|
| 2011�N8��14���i���j |
| ���̃I�I�u�^�N�T�̏d�ʑ��� |
�@���̒��q�����Ă����̂ŁA���V���ɁA���]�ԂʼnƂ��o�āA���̃I�I�u�^�N�T�̗l�q�����ɂ����B���x�̐��j���̒�ኈ���ŏ���������͈͂̔��������玟�̑�̊Ԃł���B�܂��A�������R���قǂɂȂ��Ă���I�I�u�^�N�T�S�{�Ƒ����������قǂ̃I�I�u�^�N�T�P�{�́A�����A�s���a�A�d�ʂ𑪂����B
�@�����R���̑����ł��A�d�ʂɂ́A����������A�d�ʂ͂T�{�قǂ̊J�����������B��R���̑����ł��A�d�����̂łS�D�V�����A�y�����̂łO�D�X�����ƊJ�����������B
�A�����Əd�ʂ̊Ԃɂ́A�������֊W���������B
�@�@�s���a�͂P�D�W��������R�D�T�����܂ł������B
�@�S���O�܂ł́A�C���t���Ȃ��������A�I�I�u�^�N�T�ɉԂ����n�߂Ă����B�A���̕ω��͑����B
�@�@�@�I�I�u�^�N�T
�@������Ƃ̂Q�K���珗���̐��ŁA�u�������[��@�Ƃ̑O�̃u�^�N�T�ɉԂ����������B���̊Ԃ̑����Ŋ����Ă���Ȃ������B�v�ƁB�u�����́A���j���̉����ŁA���j���̏����̍ۂɂ͎�`���Ă��������B��X���{�����e�B�A�ł��B�v�Ɖ����Ă������B
�@�����͌����Ă��C�ɂȂ����̂ŁA���Ƃŗl�q�����ɍs�����B���Ȃ�I�I�u�^�N�T�������Ă����̂ŁA�R�O���قǏ�������H�ڂɂȂ��Ă��܂����B
�@�����㗬�ŃJ���K���P�Ƃ����������B��������傫���Ȃ����q�i�V�H���A�e�́A����葱���Ă����B�Ȃ��Ȃ��ЂƂ藧���ł��Ȃ��悤���B
�@�@�@�@�J���K�����
�@�㗬�̖��������̖��̍����~�ŁA�~�\�n�M���炢�Ă����B���̋߂��ɃZ�~�̔����k���������B
�@�@�@�~�\�n�M�ƃZ�~�̔����k
|
|
|
|
| 2011�N8��13���i�y�j |
| �厸�s�I�\���蒠�� |
�@����A�ߌ�A�s�����ɏo�������B���̂Ƃ��Ɏ蒠���݂��L��������B���̌�́A�蒠�������L�����Ȃ��B
�@��ɂȂ��āA�K�v�������āA�蒠��T�������A������Ȃ��B
���������A�s�����ɏo�������B������x�݂ł��邪�A��q���ɂ́A��q������B�f���Ă݂����A�Ō�ɐ��|������Ǝ҂���́A�͂��o�͂Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B���j���ɁA���ʎ�t�ɗ��āA�����ōēx�f���Ă��������Ƃ̏����������������B
�@���j���̒��Ɋ��҂����邵���Ȃ����A�o�Ă��Ȃ����Ƃ��l���āA�Ώ����邵���Ȃ��B�������B�������B
|
|
|
|
| 2011�N8��12���i���j |
| �M���ǂ̑�́u���������Ȃ��v���� |
�@�P�O���i���j�̒��̖��ł̏��������̋A��́A���̂�i�z���j�́A���͂Ŏ��܂������A���ł��ؓ��ɂ��c���Ă���B�����s�̔M���ǂ̒��o�Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�M���ǂ��̂��̂ł������̂����m��Ȃ��B
�@����Q��������S�Ǘ��u�K�̎����ɂ́A�M�z���̌����́A�����s���Ə����Ă���B
�@�\�h�ɂ́A�@�X�q�����Ԃ�A�A��������������Ƃ�A�B����₷�A�C���Ȃ��ɒ����ԂłȂ��A�D���������Ȃ��A�E�ߕ����H�v����A�Ƃ���B
�@�������炭�́A��O�ł̊������A�ł��邾�����l���邱�Ƃɂ��āA���P��}�邵���Ȃ��ƌ��߂��B
�@���~��������A�����͗������Ȃ邾�낤�B |
|
|
|
| 2011�N8��11���i�j |
| ����쒹�ώ@�������� |
�@�����́A�������{�����e�B�A�쒹�O���[�v�̌���쒹�ώ@�̓��ł������B�������A�ߑO�X�������Q���Ԃ��܂���������R�ώ@���A������B�n��AA�n��Ɖ��A�Ō�Ɏ��R�ώ@�Z���^�[�ŁA�g�����킹�������B���������Ȃ̂ŁA���̎p�����Ȃ��A�m�F�ł�����ނ́A�P�Q�킾���ł������B�ł��A�I�I�^�J���A���R�ώ@�����̒r�Ő�������ł�p���A�擪�̂Q�l�ɂ��m�F�ł����B�c�O�Ȃ���A���́A�x��āA�I�I�^�J�������Ă��܂������Ƃ������̂ŁA���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@���̌�R�O���قǁA�쒹�O���[�v�̃~�[�e�B���O���s�Ȃ����B
����A�����������́A�����́A�ؓ��ɂ��c���Ă���B�悭�Ȃ�ɂ́A�����Q�C�R�������邾�낤�B�ł��A�����邱�Ƃ͂Ȃ��B
|
|
|
|
| 2011�N8��10���i���j |
| �O���A���쏜�̒�ኈ���� |
�@�����́A�݂������̉�̏T��x�̒�ኈ�����ł������B���ԂU�����A��P�����܂�I�I�u�^�N�T��A���`�E���̏����Ɋ��𗬂����B
�@���̐Y�V���Ɣ������Ԃ��������肫�ꂢ�ɂȂ����B
�@
�A�肵�ȁA�t�G���X���܂������A���ɋْ����������B���̂Ƃ��́A����Ŕ[�܂������A���]�ԂʼnƂɋA��r���A��ő������Ă��܂����B�d���Ȃ��A���]�Ԃ�����A�����ɂ����āA�����ĂȂ�Ƃ�����ɋA���Ă����B
�����́A�����āA��Ƃ������������悤���B |
|
|
|
| 2011�N8��9���i�j |
| ���̊O���A���̏��� |
�@���U������W���܂ł̂Q���ԁA���̂Q�����ŁA�O���A���i�I�I�u�^�N�T�A�A���`�E���A�I�I�t�T���j�̏�������l�ōs�����B
�ꏊ�͇@���싴�㗬���݂ƇA�Y�V�������E�݂ł���B
�@�������I�I�t�T�����A���싴�㗬���݂ɂ���A�C�ɂȂ��Ă������A�����ł��āA�悩�����B���̕t�߂ł́A�J���Z�~�̎ʐ^���B���Ă���J�����}�����������S�������B���A�����Ă���A�������ꂽ�Ƃ���ŁA�����������B�A��Ɏ��������̑O�́u������Ă����́H�v�Ƃ̍Ñ����������B������́A�ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ɋC���g���Ă���̂ŁA�u�[���ł����܂���B�v�ƌ��t��Ԃ�����A�u�ߌ�͂��Ȃ���v�Ƃ̌��t���Ԃ��Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N8��8���i���j |
| �u�A�������v�̉ԁF���N�Q�A�T���X�x���A�I�M |
�@��������������A�u�A�������v�ɂ́A���͖�P�O�O��ނقǂ��邪�A���炢�Ă���Ԃ́A���N�Q�A�T���X�x���A�n�M���炢�ł���B�쑐�ł́A�L�L���E�A�m�A�U�~�A�z�^���u�N���ł���B�E���V���E�~�J����C�`���E�ɂ́A�������Ă����B
�@�@�@�T���X�x���̉�
�@�@�@�E���V���E�~�J���̎�
�@�X������P���ԁA�߂��ɂ���ԂЂ�Ɉړ����āA�̃{�����e�B�A�]�[���̏����������B�{�����e�B�A�̃����o�[�R���ƉԂЂ�̐E���Q���́A���v�T���ōs�Ȃ����B���ɂP����x�ł̍�ƂȂ̂ŁA�����Ă��鑐�ɂ͕�����B
�@�@�@�ԂЂ�̗̃{�����e�B�A�]�[�� |
|
|
|
| 2011�N8��7���i���j |
| �u�ċG�E���̐������̊ώ@��v |
�@�����͏��������B�ߑO�P�O������P�Q���܂ŁA���̖����̃z�^����t�߂ŁA��여��A��������̕��ȉ��Ấu�ċG�E���̐������̊ώ@��v������A�X�^�b�t�Ƃ��ĎQ�������B
�@���߂ɁA���������R�ώ@�Z���^�[�̃��N�`�����ŁA��샋�[���̐����A�A���̌㌚���̊O�ɏo�āA�����^���A�z�^����Ɉړ����āA�R�O���قǃz�^����̕�C��Ɓi�����ł��A������y�̕�[�j���s�Ȃ�����A�R�O���قǃz�^����Ɩ��̐������̊ώ@���s�Ȃ����B�̎悵�����̂̐��������ނƂ܂����Ƃ̂Ƃ���ɕԂ��Ă�����B
�@
�@�@�@�@�J�n�O�̐���
�@�@�@�@���ō̏W��
�@�@�@�@�̎悵�����̂̐���
|
|
|
|
| 2011�N8��6���i�y�j |
| �̃{�����e�B�A�̈��S�Ǘ��u�K�� |
�@�����́A�������{�����e�B�A�̒�ኈ�����ł������B���́A�X��������P�P���܂ŁA���o�[�h�T���N�`�����ŁA�O���A���i�����i�X�r�j�̏������s�Ȃ����B�P�P������P�Q�����ɂ́A���S�Ǘ��u�K��������B�����Q��������T�O���̃{�����e�B�A�̂قƂ�ǂ����S�Ǘ��u�K��ɎQ�������B�u�t�́A�����Y����i�X�у{�����e�C�A�j�ł���B�̃{�����e�B�A�̎w���҂Ƃ��ẮA��]��������ł���B���e��
�@���S�Ǘ��̐S�\���@
�@�E��O�{�����e�B�A�����̊�{
�@�E��O�{�����e�B�A�̊������ɑz�肳���W�̊�@
�A�Ă̈��S��
�@�E�M���Ǒ�
�@�E�n�`��i�|�C�Y�������[�o�[�̎g�����j
�@�E�~�}���`�G�b�N
�B����̎�舵��������̎d��
�@�ł������B
�@���ɁA����̊Ǘ����A�悭�Ȃ��Ƃ̎w�E�����B
�@�ߌ�P��������R�����̂Q���ԁA���������Y������u�t�Ƃ��āA�ԂƗ̂܂��O��n�������ÂŁA���S�Ǘ��u�K�����A���e���قړ����͈͂ł��������A���Ԃ����������A���e�����������B�P�X������u�������A�Ō�܂Ől���Ђ�������e�ł������B
�@���́A�Q�����̂ŁA���ꂾ���ɗ�����[�߂邱�Ƃ��ł������A������A�n���̒|�т̊Ǘ���A����̎����̎��ۂɂ��āA�X�Ȃ邲�w���������Ƃ̎v���ł������B
�@��u�҂̔����́A�T�ˍD�]�Ȃ悤�Ɏ�����B |
|
|
|
| 2011�N8��6���i�y�j |
| �L�������̓� |
�@�����́A�U�U�N�O�ɁA�L���Ɍ��������Ƃ��ꂽ���ł���B��������A���S��[���l������Ƃ������B
�@�픚�҂̕��ϔN��͂V�V���������ł��B
�@�W���P�T���@�ٓ��B |
|
|
|
| 2011�N8��5���i���j |
| �u�߉������{�̑��ǂɍĐ��ɂ��ĂȂǂɂ��āv���_����ד����_�勳���̍u���� |
�@�u�߉������{�̑��ǂɍĐ��ɂ��ĂȂǁA���̈琬�Ǘ��ɂ��āv�̍u����A�ԂƗ̂܂��O��n������̎�ÂŊJ�Â���܂��B�u�t�́A�����_�勳���_����א搶�ł��B
�@�_��搶�́A��N�R���P�O���ɓ|�����A����P�O�O�O�N�Ƃ������銙�q�̒߉������{�̑��ǂ̍Đ��ɂ��āA�w���w���ɓ�����ꂽ�搶�ł��B
�@�����F�Q�P�O�O�N�W���Q�P���i���j�P�O�F�O�O�`�P�Q�F�O�O
�@�ꏊ�F�O��s�b��Ǘ��n���R�K���C��
�@�Q����F���:�T�O�O�~�i������͖����j
�@����F�V�O���i�撅���j
�@�\���F�W���W���i���j����A�d�b�ŁA�����̂X�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�A�P�R�F�O�O�`�P�V�F�O�O�̊ԂɉԂƗ̂܂��O��n������i�O�S�Q�Q�|�S�T�|�W�R�T�P�j�ɓd�b�Ő\�����������B
��낵���@���肢�������܂��B
�ڂ����́A
http://hanakyokai.or.jp/165.html
���݂Ă��������B
|
|
|
|
| 2011�N8��5���i���j |
| ���~�W�A�I�C |
�@�����A���N���A���~�W�A�I�C���炢�Ă���̂ɋC�������B
�@�Q�O�O�S�N�ɐ_��A�����Ŕ����Ă��āA��̋��ɐA�����B
�@�Q�O�O�T�N�W���P�V��
�@�Q�O�O�U�N�V���R�O��
�@�Q�O�O�V�N�V���R�P��
�@�Q�O�O�W�N�V���R�O��
�@�Q�O�O�X�N�V���R�P��
�@�Q�O�P�O�N�W���S��
�@�Q�O�P�P�N�W���T���@
�ɁA���N�炫�n�߂Ă����B���ꂵ�����Ƃł���B
�@�@�@���~�W�A�I�C |
|
|
|
| 2011�N8��4���i�j |
| ���Ŋ؍�TV�̎�ނ��������B |
�@�ߌ�A��여��A����A�؍���TV���KNN�̎�ނ����B���������R�ώ@�Z���^�[�̃��N�`�����[���Ɏs���ψ����U���قǏW�܂������A���ǁA��l����\���āA��ނ������邱�ƂɂȂ����B�u���ԉ͐����i���{�I�ɂ͐������l���̐�Â���̈Ӗ��j�v�̂悢��Ƃ��ďЉ�����Ƃ����̂��A��ނ̈Ӑ}�ł������B
�@
�@�@�@��ނ̗l�q
�A��ɁA���ŁA�J���K����Ƃɂł������B�������S�H�̃q�i�͌��C�ł������B
�@�@�@�J���K�����
|
|
|
|
| 2011�N8��4���i�j |
| �O���A���������݂̉�� |
�@�@����́A���ŁA�O���A���̋쏜�������s�Ȃ������A���������A���`�E����I�I�u�^�N�T�Ȃǂ̏������݂́A�͐�Ǘ��҂ł��铌���s�k�����암���ݎ������ɂ��肢���Ă���B����̏ꍇ�A����ӏ��́A�U�����ł������B
�@�����A����̗l�q�����ɍs�������A���łɉ������Ă����B�����v���ȉ�����s�Ȃ��Ă��������Ă���A��ϗL����Ƃ��B
�@�����́A�������̂ق����t�߂́A�I�I�u�^�N�T���Ȃ��A��ς������肵�����i�ɂȂ��Ă���B
�@�@�@�������̂ق����t�߂̕��i�@
�@�@�@�������̂ق����t�߂̕��i�A
|
|
|
|
| 2011�N8��3���i���j |
| �O���A���쏜�̒�ኈ�� |
�@�����́A�݂������̉�̏T��x�̒�ኈ�����ł������B���ԂV�����A�P���Ԕ��I�I�u�^�N�T��A���`�E���̏����Ɋ��𗬂����B�Ă₷�ݒ��Ȃ̂ŁA�q���R�����A�e�ɂ��Č��w�ɗ����B
�@���̖쐅���ƐY�V���Ԃ��������肫�ꂢ�ɂȂ����B
�@
�@��Ƃ��I����āA�A����A�ӂƋC���t���ƁA�q�i���S�H�ꂽ�J���K����Ƃ̎p�����������B�܂����܂�āA����Ȃɓ��ɂ��������Ă��Ȃ��悤�Ɋ������B�e�͑�ϗp�S�[�������B
�@�@�@�@�J���K�����
|
|
|
|
| 2011�N8��2���i�j |
| ���u���u���̊O���A�����l����v�̐\����t���n�܂����B |
�@���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v�̐\����t���n�܂����B�\�����Ԃ́A�W���P������P�S���܂łł���B
��ẤA�O��s���Љ���قƑ��Z�����c�������̘A�g���Ƃł���B�����ŁA�N�ł��Q���ł���B
�@���̍u���́A�u�t�ɂ́A�G���w�̑�Ƃ̓����_�Ƒ�w�������{���V�搶���}���A�S�R��ŁA
��P��ڂ͂W���Q�U���ߑO�P�O���`�P�Q�����u���̃t�C�[���h���[�N�A
��Q��͍u�`�u�O���A���Ƃ́v�X���P�U���ߌ�R���`�T��
��R��͍u�`�u�O���A���̋쏜�͂ǂ����邩�v�P�O���Q�P���ߌ�R���`�T���ł���B
�@�\���ݐ�́A���Z�����c����ǁ@�i�d�b�O�S�Q�Q�|�R�Q�|�U�X�W�U�j�ł��B�ڍׂ́A�Y�t�̃p���t���b�g���݂Ă��������B
�@
|
|
|
|
| 2011�N8��2���i�j |
| �����������܂ŕ��� |
�@�����A�����������܂ł��邢���B�r�����\�Y���t�߂ł́A�R�O���قǏ�����������ƁA�������������B
�@�������̒��̖��ł́A��ӂɂ́A�I�I�u�^�N�T���ɖ��Ă����B���̑��������i�W�����{����X�����{)�܂łɂ́A����ɐ�������Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�I�I�u�^�N�T���ɖ��Ă����B
����������ɓ���ƁA���N�ŏ��̑������I���������̂悤�ł������B�f���ł́A��P��ڂ��V����{����W����{�ŁA��Q��ڂ��X�����{����P�O�����{�ƂȂ��Ă����B�����ł́A�����͔N�Q���ł���B
�@����������̒[�̏�����V����������ƁA�����͂܂��N�R��ɂȂ��Ă����B�C�k�L�N�C���̉��F���Ԃ��炢�Ă����B���̋��ɂ��Ă̌f�����������B
�@�@�@�C�k�L�N�C���̉�
�@�@�@���̐���
�ш�_�Ђ̗N�����A���ɒ����ł���Ƃ��낪���邪�A�����́A��������N�����o�Ă����B
�@�@�@�ш�_�Ђ̗N��
�@�@�@�Ɣ���������݂������̖��
�Ƃ��o�Ă���A��R���Ԃō������̒��J�ˋ��ɂ����B���̕ӂ́A�����A������R�ʒ���̃R���N���[�g�̒��𗬂�Ă��āA��ׂ�ɓ����Ȃ��A��쉈����������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B
|
|
|
|
| 2011�N8��1���i���j |
| ���ŊO���A���̏����A�Ƃ̒�ł����� |
�@�ߑO���A���̖����̃z�^����i�{�����e�B�A��������N���̏���j�t�߂̊O���A���i�I�I�u�^�N�T�j�̏������A�P���Ԕ��قǍs�Ȃ����B���̃z�^����ŁA�W���V���i���j�̌ߑO���ɁA�u���̐������̊ώ@��v���A��여��A��������̕��ȉ��Âōs�Ȃ���B�����X�^�b�t�Ƃ��ĎQ������\��ł��邪�A�����ł��������ŁA�ώ@������{�ł���悤�ɁA��̕t�߂̊O���A�����������Ă������B���N�A�������s�Ȃ��Ă���̂ŁA���͂Ƃ́A��r���āA�I�I�u�^�N�T�̉萶�������Ȃ��Ȃ��ė��Ă���B
�@�@�@�@�z�^����i�����O�j
�@�@�@�@�z�^����i������j
�@�ʐ^�̔����܂́A���ɁA��C�p�̍��������Ă���A���܂ł��B�@
������A���̏��������̑�t�߂ŁA�J���K����Ƃɏo�������B�q�i�W�H�͂�����������傫���Ȃ��Ă������A�܂��e�ƈꏏ�ɍs�������Ă����B
�@�@�@�J���K�����
�@�Ƃ̋A���āA�ߌ�A��̏������A�P���ԂقǍs�Ȃ����B
|
|
|
|
| 2011�N7��31���i���j |
| NHKTV�u�S�̎���v |
�@�����A�J�ł������̂ŁANHK�u�S�̎���v��r������݂��B�����́A�ĕ����ŁA���c�O������́u���̂��Ƃ̏o��v�ł������B�r������ł��������A�ƂĂ��������b�ł������B
�@�g�́i������j�B�g�S�i���o�j�A�g�Z�i���i�j�Ə����ꂽ�p�l����������Ă����B
�@�l�́A�����ЂƂ�Ő����Ă��Ȃ��B�݂�Ȃ̂Ȃ��Ő����Ă���B����ɂ��Ă���l������A���̐l�͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���Ă��������Ȃ����肷��B�u����v�ł���B�܂悢��������B�ł������Ȃ�ɑO�ɐi�ށB�l�̐l���͓�Ȃ��A�V����i�ionly
one�j�ł��B
�@���ʁi�A�~�_�j�A��@�A���N�A���́A�@���Ƃ��b�������B
�͂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂��ЂƂɂȂ�������A�傫�ȗ͂ɂȂ�B���ꂪ���͂ł���B���߉ޗl�́A���߂Ă��̖@���𖾂炩�ɂ��ꂽ�B
�@���̂悤�Ȃ��b�ł������B
�ڂ����́A�u�v�l�̕����v�Ƃ���HP�ɁA�L�������邱�Ƃ��������̂ŁA�S��������́A����������Ă��������B
URL��
http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/43957bce622f31b7541e6029bb685a35
�ł��B
|
|
|
|
| 2011�N7��30���i�y�j |
| ������s�����n�����ʂ̑��� |
�@������s���s����c�@���@�u������ρv�ŐV����P�S���́A���W�u�n��������Ɋւ���āv���f�ڂ���Ă���B
������s���s����c�@�n�������蕔��̂T�N�Ԃ̑��茋�ʂ�����Ă���B
�@�n�����́A�s���Q�O�ӏ��ȏ�A�N���ʂ̂́A�R�����𑪒肵�Ă��܂��B
�@���̂悤�Ȓn���Ȏs���̊������p������Ă��邱�ƂɌh�ӂ�\�������Ǝv���܂��B
�@�u������ρv��P�S��PDF�ł́A������s���s����c��HP�̉��L�̃y�[�W����_�E�����[�h�ł��܂��B
�@http://www.koganei-kankyo.org/kaiho/kaiho.htm
|
|
|
|
| 2011�N7��30���i�y�j |
| �@�J�̌�A���ŊO���A���̏��� |
�@���A�J�̉��Ŗڂ��o�߂��B�����~���Ă����B���������J�ł͂Ȃ��������A���ɏo������̂��A�����҂����B�P�O���ɉƂ��o�āA���̕x�m���勴�������݂ŃI�I�u�^�N�T�̏����������B��Ȃ��݂̖������{�����e�B�A��ƃO���[�v�̖ʁX���A���̊Ǘ����H������āA�����̖�������ђn�Ɍ������Ă��邢�Ă������B���ɋC���t���āA���������Ă��ꂽ�B
�@�����́A��l�ŁA�P���Ԕ��̏�����Ƃ����āA��Ƃ��I�������B
�@
�@�@�@�������̐���A�x�m���勴�̕����݂�
|
|
|
|
| 2011�N7��29���i���j |
| ����ɁA���p�ł��o�����B |
�@�����́A����ɏo�������܂����B����s�����́A�������̍q������w�O�ɂ���܂��B�w���o��ƁA��㏉�߂č��Y�@YS-11�̎������A�����Ă��܂��B��ω���������s�@�ł��B
�@�@�@�@�@�����p�l��
�@�@�@�@�@���Y�@YS-11
����ł́A�}���قŁA�Z�������Z��n�}���Â�������A�ŋ߂̂��̂܂ŁA���N������Ă����B�W��̐l�͑�ϐe�ŁA���p���₷���A���������B�s�����ł��A�e�ȑΉ��ɁA���ӂł������B
|
|
|
|
| 2011�N7��28���i�j |
| ����́A����n��t�B�[���h���[�N |
�@����̌ߌ�A��여��A��������ȉ����A����ɏo�������B
�@�w�K��u���c�J�_���v�Ɓu�J�̌��z���v�̂��ƁA���c�J�n����A�������R�������ɁA�쑽���s�����݂r�����c�J�g���X�g�r�W�^�[�Z���^�[�ƕ����āA�Ō�ɁA���݂r�̉�@���c����́u�~�J�ʂƂ݂r�̗N���ʁv�̕����B
�@
�@�@�@�@�쑽���s���̈ē���
�@�@�@�݂r
�@�@�@�݂r�Ő����������o�[
�@�@�@�݂r
|
|
|
|
| 2011�N7��27���i���j |
| ���J�̒��A���̊O���A���̏����������s�Ȃ��� |
�@�������A���J�̒��A���̊O���A���i�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�Ȃǁj�̏����������s�����B�@���V���ɁA���̔t�߂Ƀ����o�[�S�����W�����āA��P���Ԕ��A���̖쐅���Ă܂��܂ł̊Ԃ̗��݂̏������s�Ȃ����B
�@�����s���N�R������s�Ȃ������~�́A�I�I�u�^�N�T�̐�����Ϗ��Ȃ��B�����́A�����ɁA�����s�����������Ȃ���ׂ�i��P�D�T�����͈̔́j��ᐅ�H�ɂł����B�̕����ɂ��ẮA�A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�̏������s�Ȃ����B�������A��X���P�{�P�{���������Ă���̂ł���B
|
|
|
|
| 2011�N7��26���i�j |
| ���̗N���ʑ��� |
�@�ߑO���A���P��̖��ɒ����N���ʂ̑�����s�Ȃ����B����͂P�O�������܂�ŁA��������A�U���̑���l�ɑ��Ė�R�O���������Ă���B���̌X���́A������肵�����̗��ʂ̌X���ƈ�v����B�W���́A�ǂ��Ȃ�̂��H��N�ʂ肾�ƁA�W���A�X������ɒꂪ���āA�N���Ɍ����đ����ɓ]���邱�Ƃ��\�z�����B
�@�N�ɂ���Ď�Ⴄ���A�傫�ȓ����́A�ǂ��ɂ��������ł��n�߂��悤�Ɏv���Ă��邪�A�z���g�͂܂����������m��Ȃ��B
�@
�@���肷��Ƃ��ɂ��낢��ȍH�v�����Ă���B���ۂ̑���̎�������݂����܂��B
�@
�@�@�@�Ђ傤�����ւ̃p�C�v�o��
�@�@�@����̗l�q
�@�@�@�����A���ł���ȉԂ����������B |
|
|
|
| 2011�N7��25���i���j |
| ���̗��ʑ��� |
| �@���Ɉ��̖��̗��ʑ�����R�ӏ��i�x�m���勴�A�A��j�ōs�Ȃ����B����̑䕗�̉e���ŁA�����͉J�����������A���̗��ʂ́A�U���̑���l���A�������Ă����B
|
|
|
|
| 2011�N7��24���i���j |
| �J�����q���ƃI�I�C�k�^�f |
�@�P�P���A���]�ԂʼnƂ��o�āA���𑖂����B
�@�������̖����t�߁A�N���L��t�߁A�x�m���勴�t�߂ŁA�q�����������ŗV��ł����B�e���ꏏ�ł���B
�@�@�@�@���̕��i
�@�����t�߁A�N���L��t�߂Ƃ��A��ӂP�D�T���͂܂���������������Ă����A�{�����e�B�A�ɂ�鏜�����Ȃ��̂ŁA�I�I�u�^�N�T���傫���Ȃ��Ă���B�A���`�E���������Ԕɖ��ė��Ă���B
�@�x�m���勴�t�߂��牺���́A��X���I�I�u�^�N�T�ƃA���`�E�����������Ă���̂ŁA�����͖ڗ����Ȃ��B�₳�������i�ɂȂ��Ă��āA�S���x�܂�B
�@���������R�ώ@���ł́A�m�J���]�E�̌Q���������B����͂������悤�����A�܂��܂��悭�炢�Ă���B
�@�@�@�m�J���]�E
�@�����̑�t�߂ł́A�J�����q���̎p�����������B�I�I�C�k�^�f�̉ԁE����H�ׂĂ���悤�ł���B��ԂƉH�����ꂢ�ł������B
�@�@�@�@�J�����q��
|
|
|
|
| 2011�N7��23���i�y�j |
| �R�A�W�T�V�̕����@ |
�@�����́A�����s�̊C�ӂ̌����ɏo�������B�C�ӂɗ�������֎~�̃��[�v�������Ă������B�����ŁA�����̃R�A�W�T�V���������Ă����B�c�O�Ȃ���A���́A�q�i�̎p���݂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�߂��ɁA�P���̗�����������Ă���悤�Ɍ������B���炭���āA�R�A�W�T�V����H�A���Ă����B��������Ă����悤�Ɍ����������A�A���Ă����R�A�W�T�V���A�������͂��߂��̂ŁA�������B
�@�@�@�R�A�W�T�V�̗�
�@�@�@�A���Ă����R�A�W�T�V�Ɨ�
�@�@�@�@�R�A�W�T�V���������͂��߂�
�@���ɁA�A�J�K�V���T�M���͂��߂Ă݂邱�Ƃ��ł��܂����B�n��̓r����������Ă��ꂽ�悤�ł��B
�@�@�@�A�J�K�V���T�M
�Z�C�^�J�V�M���߂��ł݂邱�Ƃ��ł��܂����B
�@�@�@�Z�C�^�J�V�M
|
|
|
|
| 2011�N7��22���i���j |
| adobe Illustrator CS5 |
�@�O����g�������Ǝv���Ă���adobe Illustrator CS5���A�������߂Ďg�킹�Ă����������B
�@�ԂƗ̂܂��O��n������ł́A������g����o�b������A�����ɍŋ�adobe Illustrator CS5���C���X�g�[�����ꂽ���Ƃ�m�����̂ŁA�ߑO���Q���Ԃقǎg���ɍs�����B
�@�}���ق���u���߂Ă�Illustrator CS5�v����āA������݂Ȃ���A�u�A�������v�̒n�}������͂��߂��B
�@�����͉��Ƃ��A���͂̐��_�������쐬���邱�Ƃ��ł����B����́A���H���v�Ȏ�������������������ł����\��ł���B
�@��ρA���̑̑��ɂ��Ȃ����悤���B���܂��g���鎩�M���ł���A����ł��ł���悤�ɁAadobe Illustrator CS5���₷���w��������@��T���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|
| 2011�N7��22���i���j |
| �J���Z�~ |
�@�䕗�̉e���������������̂ŁA���O�Ɏ��]�ԂŖ��ɏo���B���������R�ώ@�Z���^�[�ł́A�������{�����e�B�A���o�Ă����B
�@�����̏ꏊ�ŁA�J���Z�~�̎ʐ^���Ƃ��Ă���J�����}���������B
�@�s���ɒʂ������Ɏ}�ɃJ���Z�~���Ƃ܂��Ă������A�Q�O���قǂ������A��ɂ������}�ɃJ���Z�~���Ƃ܂��Ă����B�Ⴂ�J���Z�~�̂悤�Ɍ��������A�ʂ����ē����J���Z�~���A�ʂ̃J���Z�~���́A���ɂ͂킩��Ȃ������B�ł��A�ǂ����ʂ̂��̂��Ǝv���Ă���B
�@�@�@�J���Z�~�i�s���ɂ݂����́j
�@�@�@�J���Z�~�i�A��ɂ݂����́j
|
|
|
|
| 2011�N7��20���i���j |
| ���u���u���̊O���A���ɂ��čl���悤�v |
�@�O��s���Љ���فE���Z�����c�������̎�ÂŁA�A�g���ƁE���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v�S�R�s�Ȃ���B�\���ݐ�́A���Z�����c����ǁ@�i�d�b�O�S�Q�Q�|�R�Q�|�U�X�W�U�j�ł��B�W���P������P�S���܂łɐ\����ł��������B�ڍׂ́A�Y�t�̃p���t���b�g���݂Ă��������B
���̍u���������ł������u���ɂȂ�悤�ɁA���ݓw�͒��ł��B
�@�@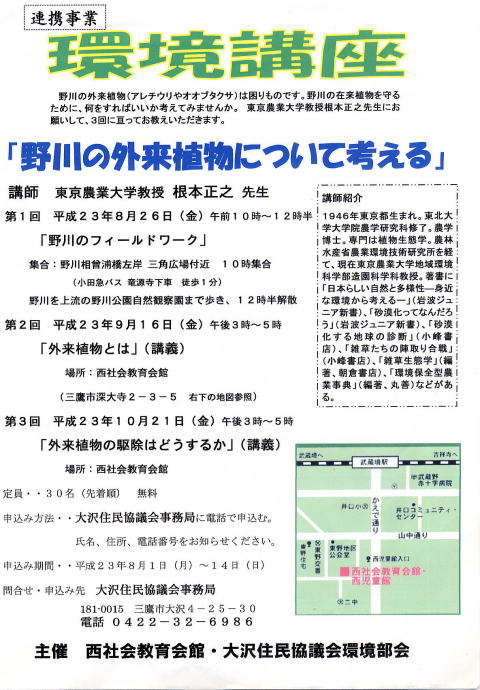 ���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v ���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v
|
|
|
|
| 2011�N7��19���i�j |
| �䕗�̉e���ŁA�߂��ɏ��w�Z�́u���w�K�v�̂���`���͒��~�B |
�@�����̌ߑO���́A�߂��̏��w�Z�̂S�N���̊��w�K�u�����悭���銈���F�O���A���̏����v�̂���`��������\��ł��������A�䕗�̉e���Œ��~�ɂȂ����B�J�̂��߂Ɩ��̐��������A�댯�Ȃ��߁A�d�����Ȃ����Ƃł���B�ł��c�O�Ȃ��Ƃł͂���B�܂����������炵�āA�ēx�v����ł�����ꂵ���Ǝv���Ă���B
�@����A�����̂��߂ɁA���̐�̒�������Č�����A�Ƃ���ǂ���[���Ƃ�����������i�ł��[���͂T�O�������炢�j�B�܂��A�L�̎��̂�������ł���̂��������̂ŁA�r�j�[���܂ɂR�d�Ɏ��e���āA���̉��t�߂̂킩��₷���Ƃ��Ƃɂ����Ă���A�߂��̌�ԂƉ͐�Ǘ��҂̖k�����암���ݎ������ɘA�������āA���u�����肢�����B
�@�����́A�䕗�̉e���ŁA���������A�����Ɛ[���A������}�Ȃ悤�Ɍ������B���~�͓��R�ł������B |
|
|
|
| 2011�N7��18���i���j |
| �Ȃł����W���p���D�� |
�@���N�����āA�R���̕����J�n����݂Ă��܂��B�v���Ԃ�ɂ킭�킭�����C�����ł��B�Ȃł����W���p�������I
�@���炵���@�N���[�Y�C���O�Z�����j�[�B
�O���A�ꂵ���������O�|�O�B
�㔼�Q�R���@���_�@�O�|�P�B
�R�T���@���{�{�ԁ@���_�@�P�|�P�B
������@�O���P�S���@�A�����J�@���_�B
���{�P�|�Q�ƂȂ�B
�����㔼�@��S�[���@�Q�|�Q���_�B
������b�h�J�[�h�ޏ�B
�����Q�|�Q�I���B
�o�j��B�I��ɏΊ炠��B�悭�������B
�C�@�@�i�C�X�u���b�N
���{�D���@���I
��@���_��
�Ẵ\���@�x�X�g�S�[���L�[�p��
��@MVP �ŗD�G�܁@
|
|
|
|
| 2011�N7��17���i���j |
| �����̊O���A�����̑���� |
| �@���A�U������V���R�O���̂P���Ԕ��A���̃I�I�u�^�N�T�ƃA���`�E���̏����������B�ꏊ�́A���\�Y�������Ɩ쐅���㗬���B�Ȃǂł���B�����ł��邪�A�����o��B�ł��A��ƂŖ��̕��i���悭�Ȃ�ƁA�C�����������B
|
|
|
|
| 2011�N7��16���i�y�j |
| �������̃{�����e�B�A���� |
�@�����́A�����珋���������A�������{�����e�B�A�̒�ኈ���ɂ͑�R�̒��Ԃ����܂����B���̃~�[�e�B���O�̎i��҂���͂ł��邾�����A�̍�Ƃ�����悤�ɂƂ̘b���������B
�@���́A�X���������P���Ԕ��A���o�[�h�T���N�`�����̒r�Ɉ炿�������~�N���̐������s�Ȃ����B���ʂ������A�쒹���r�ɗ��₷�����邽�߂ł���B
�@�P�P��������R�O���قǂV���̐��b�l��������B�ۑ莖�������Ȃ��A���߂ɏI������B
�@�v���Ԃ�ɂV�H�̑傫���Ȃ����q�i���ꂽ�J���K����Ƃ����������B�O�͂W�H�̃q�i���������A��H���������āA�V�H�ɂȂ��Ă����B�悭����Ă���Ɗ�����B
�@�@�@�J���K�����
|
|
|
|
| 2011�N7��15���i���j |
| ���ŁA�S�C�T�M�̗c�������������B |
�@���A���̑�����ŁA�S�C�T�M�̗c�������������B�ڂ̑O�ŁA�l�������Ƃ߂��B�Ί݂�ʂ�l�̋C�z�ŁA�����ɔ�ы����Ă��܂��āA�c�O�ł������B
�@
�@�@�@�@�S�C�T�M
�@�@�@�@�S�C�T�M
�@�@�@�@�S�C�T�M
|
|
|
|
| 2011�N7��14���i�j |
| �Ȃł����W���p���A�X�G�[�f����ɂR�|�P�ʼn����I |
�@�ߑO�R������N���āA�Ȃł����W���p���̑X�G�[�f�����NHKBS�ł݂Ă��܂��B�������������J�n�ł��B����̃h�C�c����݂āA�������܂����B������Ăق����B�F���Ă܂��B
�@���{�͍����̓u���[�̃��j�z�[���ł��B
�P�O���߂��A��̃p�X�~�X�̌���_��ꎸ�_�A�P�W���쐟�̃S�[���œ��{�ǂ����B
�@�O���I���P�P�B�{�[���L�[�v�͓��{�������B
�㔼�P�S���A��̃w�f�B���O�ŁA�Q�|�P�Ə����z���B�P�X���A�쐟�̃S�[���łR�|�P�D�Ō�́A�{���o��̑I�����コ���A�]�T�̏����B���I���I
|
|
|
|
| 2011�N7��13���i���j |
| ���̊O���A���̏������� |
�@�������A���̊O���A���i�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�Ȃǁj�̏����������s�����B�@���V���ɁA���̑��\�Y���Ƀ����o�[�S�����W�����āA��P���ԁA���̔Ă܂��܂ł̊Ԃ̉E�݁A���݂̏������s�Ȃ����B
�@�����s���N�R������s�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���A���N���R�N�ڂł���A�s�̑������s�Ȃ��Ă��鍂���~�́A�I�I�u�^�N�T�̐�����Ϗ��Ȃ��B�����́A�����ɁA�����s�����������Ȃ���ׂ�i��P�D�T�����͈̔́j�ɂ��ẮA�I�I�u�^�N�T���������Q���ɂ��Ȃ��Ă��Ă���B�ᐅ�H�ɂł����F�ɂ́A�A���`�E���������ԏo�Ă��Ă���B�������A��X���P�{�P�{���������Ă���̂ł���B
�@�I�I�u�^�N�T���ڗ����Ȃ����ӂ̌i�F�́A�����낪�x�܂�B |
|
|
|
| 2011�N7��12���i�j |
| ���̗��ʑ��� |
| �@��여��A����Ȃ��Ƃ�����ł́A�قڂR�����Ɉ�x�A���̑S����ňψ������S���āA���̗��ʂ̑�������Ă���B�����́A��l�ŁA�X�������납��A���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�̗��ʂ𑪒肵���B
|
|
|
|
| 2011�N7��11���i���j |
| ���̖쑐���� |
�@�Ƃ��Ă��������ł��������A�ߑO���Q���Ԃقǖ��̖쑐�����̑�P��ڂ����{�����B���ꂩ��A�t�A�āA�H�̂R����{����\��ł���B
�����́A�����䓃�⋴�܂ł̖�썶�݂ŁA���������{�����B�Q���҂݂͂������̉�̂U���ł������B
�@�O���A���̑����ɂ͂����Ȃ�����������B���̒��ł��A�����ł������̍ݗ��A�����ۑ�����邱�Ƃ�����Ă���B
�@����́A��여��A����̐������̕��ȉ���z�̂��Â���ł���A�o�Ȃ���\��ł���B |
|
|
|
| 2011�N7��10���i���j |
| ���ƐX�ƊG�{�̉� |
�@�v���Ԃ�ɋ߂��́u�O��s���ƐX�ƊG�{�̉Ɓv�ɍs���Ă݂��B�����ɂ͎�x��̈�˂�����B�������āA�[����P�O���̈�˂ɒ|�̃J�b�v�����Ă݂��B�����グ�Ă݂�Ƃ����Ԃ萅���͂������Ă���B�\�z�ʂ�ł������B�߂��ɂ����X�^�b�t�ɕ����Ă݂���A�ꎞ�R�����{����T�����܂ł́A��������Ă��������ł���B���̗��ʂ̓������炤�Ȃ�����ϓ��ł���B
�@�@�@�@���
�@�Ђ傤����̗̃J�[�e��������Ă������B
�@�@�̃J�[�e��
|
|
|
|
| 2011�N7��9���i�y�j |
| ���N�Q |
�@���A���N�Q���炢�Ă���B�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�ł��炢�Ă����B
�@�@�@���N�Q
�@�����ߑO���̊����ł́A�݂�ȂŁA�T�U���J�S�{�̈ڐA���s�Ȃ����B
�@�ߌ�́A�ꏊ���ς���āA�ԂƗ̂܂��O��n�������Ấu�����؍u�K��v�ɎQ�������B�u�t�̓O���[���A�h�o�C�U�C�U�[������������ł����B���̙���ɂ��ڂ������ł���B�����̊�{���w�сA���K�́A�A�W�T�C�̂����ł������B
|
|
|
|
| 2011�N7��8���i���j |
| �s����w�F�A���A���ƕ����z�� |
�@�����̎s����w�ł́A�u�A���A���ƕ����z�v�Ƒ肵�����ˏ��V�搶�̍u�`���������B
�@���������w�傫�ȓ_�͂Q�_��
�@�A���A���ɂ́A���H�A���ƕ��H�A��������A���ݐl�Ԃ́A���̐H���̑啔���H�A�����炦�Ă��邪�A���H�A���ł����y�̂悤�ɒP�ʖʐς�����ɂ́A�傫�ȐH���̎��n�����҂����̂ŁA���H�A���͏����̐H�����Y�ɑ傢�ɖ𗧂\��������B
�A�������ł̒��f�̏z�ɗ��ꂪ�����Ă���B��C���̒��f�K�X���A�H�ƓI���f�Œ�ɂ��A�A�������j����A�����j���E���C�I�������Y����A�엿�Ƃ��ĐA���̗^�����邱�ƂŁA�������Œ��f���ߏ�ɂȂ��Ă��Ă���B����͐[���Ȃ��Ƃł���B
�@�u���I�����A�搶���͂�ŁA���H�������Ȃ��獧�k�����B���낢��ȍl�����f���āA�悩�����B |
|
|
|
| 2011�N7��7���i�j |
| ���w�K�̌�������w |
�@���O�A�߂����{�\��̊��w�K�u�O���A���̏����v�̌���̉��������Ă����B����O�������̃A���`�E���A�I�I�t�T���A�I�I�J���a�V���������Ă���B�I�I�J���a�V���͂܂��Ԃ��炢�Ă���B
�@�I�I�J���a�V��
�v���ӊO�������̃I�I�u�^�N�T�������Ԃ��Ă����B
�@���̍����~�ɂ́A��q����~��邱�ƂɂȂ邪�A�͐�Ǘ��҂���J�M�����肷�邱�Ƃɂ��Ă���B
�@
���炭�Ԃ�Ƀq�i�Q�H���ꂽ�J���K����Ƃ����������B
�@�@�@�J���K�����
|
|
|
|
| 2011�N7��6���i���j |
| ���N���A���̊O���A���̏������n�߂� |
�@���N���A�V���ɂȂ����̂ŁA�u�������̉�v�ł́A��������\��ʂ�A���̊O���A���i�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�Ȃǁj�̏����������n�߂��B�@���V���ɁA���̕x�m���勴�����Ƀ����o�[�T�����W�����āA�P���Ԕ��A���̐܂ł̊Ԃ̖��̉E�݁A���݂̏������s�Ȃ����B
�@�u�݂������̉�v�ł́A�����Q�O�N���疈�N�A�V������P�O���̊Ԃ́A���T�P�j���ɁA�����������s�Ȃ��Ă����B���N�łS�N�ڂɂȂ�B�����s���N�R������s�Ȃ��悤�ɂȂ��Ă���A���N���R�N�ڂł���A�������s�Ȃ��Ă���͈͂́A���ɃI�I�u�^�N�T�̐�����Ϗ��Ȃ��Ȃ��������B���̂��Ƃ������f�[�^�[�������Ă���B�����s�����������Ȃ���ׂ�P�D�T�����ɂ��ẮA��X�����������Ă���̂ŁA�I�I�u�^�N�T�̖��x�͈ȑO��茸�����Ă���悤�Ɋ����Ă���B
�@���̂悤�ɁA��X�̊����̌��ʂ��A�������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��āA��ς��ꂵ�������Ă���B |
|
|
|
| 2011�N7��5���i�j |
| ���̖�� |
�@�����́A�V���O�ɉƂ��o�āA�V�����ʂ��Ė��̍����~���A�㗬���̖��������R�ώ@���܂ŕ����A�����Ԃ��đ�܂ł�������B�P�O��������ƂɋA�����B�����Ȃ���C�ɂȂ�I�I�u�^�N�T�ƃA���`�E���̏��������Ă������B
�@�r���ŁA�Q�x�A�ʂ̏ꏊ�ŁA�q�i�W�H�̃J���K����Ƃ����������B���������Ă���ԂɁA�ړ������ƍl���Ă���B
�@�@�@�J���K�����
�@�@�@�@�J���K���̃q�i�Q�H
�J���Z�~�̎�����������B
�@�@�@�@�J���Z�~ |
|
|
|
| 2011�N7��4���i���j |
| ���̒ʐM�� |
�@�ߑO���i�X������P�Q���߂��܂Łj�A���̏�����V���t�߂ŁA������s�쏬�w�Z�̂U�N����X�O���ɁA��Ƃ̂ӂꂠ���̌������Ă����������B��Â͖�여��A����ł���A�����X�^�b�t�̈�l�Ƃ��ĎQ�������B
�@�q���������S�O���[�v�ɕʂ�A�u�����v�u���������v�u�A���v�u���v�̂S�̍��ڂ̓��R���ڂ��S�O�����������āA�ώ@���ʂ��܂Ƃ߂�B
�@
�@�@�@�Ō�ɍu�t�̍u�]�����Ă���l�q
�A�蓹�ŁA�q�i�W�H���ꂽ�J���K����Ƃ����������B
�@�@�@�J���K�����
|
|
|
|
| 2011�N7��3���i���j |
| �u���ւ̑z���v |
�@����̂U���Q�T���i�y�j�ߌ�A�O��s�Y�ƃv���U�ŁA�u�݂������t�H�[�����Q�O�P�P�v���J�Â���܂����B���̍Ō�ɁA�p�l���f�B�X�J�b�V����������A�O���Ɋ����������H���Ă���U�����p�l���[�ɂȂ�܂����B�ŏ��Ɋe�p�l���[����T���قǂŁA�����̊T�v�A�z���A�ۑ�ɂ��Ęb�����ƂŁA�n�܂�܂����B���L�́A���̍ۂ̎��̔����̂��߂̃����ł��B���ۂ́A���������c��܂����b�ƂȂ�A���Ԃ��I�[�o�[�����̂ŁA�Ō�܂ł��b���邱�Ƃ͂�߁A�r���őł���܂����B
***************************************************************
�@�V�N�قǑO�Ɏd������߂Ă��疈���̂悤�ɖ�������悤�ɂȂ�܂����B���́A���A�g�߂Ȗ��⍑�����R���ɑ傫�ȊS�������Ă��܂��B
�S�N�O�̕����P�X�N�̏H�A���̑��V�̗��t�߂ŁA�I�I�u�^�N�T��A���`�E������ʂɔɖ��Ă���p�����āA�u����͉��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƌ��������܂����B
�@����͂Q�N�O�̕����Q�P�N�̂W���̎ʐ^�ł��B�ꏊ�͔����ł��B�A���`�E���́A�k�A�����J���Y�̂鐫�̂P�N���A���ł��B���������[�g���ɍL����A�������킢�s�����Ă��܂��B
�@�@�@�@ �A���`�E��
�@������Q�N�O�̂W���̎ʐ^�ł��B�ꏊ�͖������̎��R�ώ@���̉��ł��B�I�I�u�^�N�T�́A�k�A�����J���Y�̈�N���A���ŁA�ق��Ă����Ɣw�������Q����R���[�g���ɂȂ�܂��B���ł��S���[�g���ɂ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
�@�@�@�@�@�@�I�I�u�^�N�T�Ǝ�
�@�S�N�O�́A���̓������������ɁA�I�I�u�^�N�T��A���`�E���Ȃǂ̊O���A���̋쏜���n�߂܂����B�ŏ��͈�l�ł������A�K���A���N�̕����Q�O�N�āA�s����w�����R�[�X�u�g�߂Ȑ��ƒn�����v�̃N���X���[�g�̎^���āA�����o�[�U���Łu�݂������̉�v���X�^�[�g���邱�Ƃ��ł��܂����B���N�łS�N�ڂŁA���N�V������P�O���̊ԁA���T�P��A�����P���Ԕ��قǁA�����������s�Ȃ��Ă��܂��B�͈͂́A�������H�̕x�m���勴����A�����̑�܂ł̖�Q������ł��B
���ł́A�O�������@�œ���O�������Ɏw�肳��Ă���P�Q��̐A���̂����S�킪�����Ă��܂��B�A���`�E���A�I�I�t�T���A�I�I�J���a�V�@�A�I�I�L���P�C�M�N�ł��B���̑��A�v���ӊO�������ł���I�I�u�^�N�T�ł��B���̂悤�ȍ������O���A�����쏜���邱�ƂŁA�ݗ��̐A������萶�炵�₷���������邱�Ƃ�����Ċ��������Ă��܂��B����ɂ�萶���̑��l�������シ�邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@���̂悤�Ȋ����́A���낢��ȕ��X�Ƃ̘A�g���K�v�ł��B
�@ �܂��n���̎s���c�̂ł����A���������邾���łȂ��A�쑐���悭�m��A�e���ނ��߂ɖ��̖쑐�ώ@����s�Ȃ��Ă��܂��B�N�Q���ł����A�A���ɏڂ����u�O��̐A����m���v�̕��X�̂����͂āA����܂łV��s�Ȃ����Ƃ��ł��܂����B
�A�܂��A�s���ł����A���̉͐�Ǘ��҂ł��铌���s�k�����암���ݎ���������A���̊����͊O�������@�ɂ��ƂÂ��h���̊����ł��邱�Ƃ�F�߂Ă��������Ă��܂��B�����āA�������݂̏������s�Ȃ��Ă��������Ă���܂��B
�B���A��여��A����̏��ʂ��āA���̊����́A���S����Ŋ�������s���c�̂ɗ������Ă��������Ă���܂��B���c�J��ł��A��N����A���`�E���̏������͂��܂�܂����B
�@�C�q�������̊��������ł��B�s���̉H�w�Z�ł́A���N�A�S�N���̑����I�w�K�̎��ԂɁA���̊O���A���̏����̑̌��w�K�����グ�Ă��������A�ꏏ�ɏ��������܂����B��������������ɁA�q���������u���̉́v���쎌�E��Ȃ��āA�̂��Ă���܂����B�O�[�O���Łu���̉́v�ƌ�������ƁAyou-tube�Ŏq�������̉̂����Ƃ��ł��܂��B���N���܂����l�̏����̑̌��w�K�̌v�悪�i�߂��Ă��܂��B
�@�D���Ƃ̂��w������ł��B���A�l�ŁA�����_�Ƒ�w�̐搶�̂��w�������������@��ł��܂����B
�A���̐��Ԃ͕��G�ŁA�A���`�E����I�I�u�^�N�T�������Ă��A����ɊO���A���̃l�Y�~���M��z�\���M���ɐB���Ă��邱�Ƃ�����܂��B�ݗ���̃N�Y���ɐB���Ă��邱�Ƃ�����܂��B�w��荇��ł��B���̂��Ƃ͂���ȂɒP���ł͂���܂��A���ꂾ���A�ω��ɕx��Ŗʔ����̂ł��B
�@��g�ނׂ��ۑ肪��������܂����A�L�����͂̏����n���A���Ƃ̒m�b������A�悭�l���A�@���s�́A�܂��͎����̐g�߂Ȃ��Ƃ���͂��߂��炢���ƍl���܂��B�����˂��l�߂Ă������ƂŁA���ׂƂ̂Ȃ��肪���܂�A���낢��Ȋ������L�����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
�����������A�����𑱂��邱�Ƃ���ł��B
�@
���̈�Ԃ̊肢�́A�u���̎��R�����v�Ƃ������Ƃł��B�@
*****************************************************************
|
|
|
|
| 2011�N7��2���i�y�j |
| �������{�����e�e�B�A��ኈ�����F�o�[�h�T���N�`���A���̏��� |
�@�����̖������{�����e�B�A��ኈ���ł́A�o�[�h�T���N�`���@�����̏������s�Ȃ����B��Ƃ͂X��������P�P�����ł���B
�@��ኈ����A�ߌ�P������A�쒹�O���[�v�̎��匤�C�̉��ł����킹���P���Ԃقǂ����Ȃ����B
�@�A�蓹�A���̖쐅���߂��ŁA�J���K���e�q�̎p�����������B���͂Q�H�Ƃ����C�������B
�@�@�@�J���K���e�q
���������ł́A�J���Z�~�̎p���������B
�@�@ �@�@�J���Z�~ �@�@�J���Z�~
|
|
|
|
| 2011�N7��1���i���j |
| �s����w�F�ߌ��㕶���ɂ�����l�ԁ[���R�̊W��₤ |
�@�ߑO���̎s����w�����R�[�X�ł́A�����_�H�勳�����֎���搶�́u�ߌ��㕶���ɂ�����l�ԂƎ��R�̊W��₤�v�̍u�`���������B
�@��w�ł��Ƌ��{�̓N�w�̐搶������Ă������ŁA�N�w�̗��j�������炢���A�Ō�ɁA�Q�O���I�u�L���ȎЉ�v�̕a������A�Q�O���I�㔼�ɁA���R�ی�̂R�̎v�z�I���ꂪ���邱�Ƃ�b���ꂽ�B
�i�P�j�l�Ԓ��S��`
�i�Q�j���R���S��`
�i�R�j�l�ԂƎ��R�̋����v�z
�搶�́A�i�R�j�̗���ŁA�E�ߑ���A�u����̕����E�����̎厲�͍H�I��������_�I�����֓]������v�u���R�̃��Y������݂��������E�����v�ƂȂ�B
������A�搶�́A�u�_����b�ɂ����G�R���W�[�����ցv�Ɛ������ꂽ�B
�@�Ō�̐搶�̐��������Əڂ����m�肽���������A�������Ԃ�����Ȃ������̂��c�O�ł����B |
|
|
|
| 2011�N6��30���i�j |
| �����������܂ŕ��� |
�@�����T���P�O���ɉƂ��o�āA�����������܂ł��邢���B������R�̕��������Ă���B���Ȃ̂ŁA�܂������Ȃ��̂�������B
�@�@�@ ������̏㗬������
�������A����������̒��̖����A������V���ŏI���A���̗l�q���ς��B
�@�@�@������V������㗬������
�r���ٓV���߂��ŁA�ш�_�Ђ̗N�����A���ɒ����ł���B
�@�@�@���ɒ����ш�_�Ђ̗N��
�Ɣ������ŁA���͂R�ʒ���̐�ɂȂ�A�Z��n�̒��𗬂�Ă���̂ŁA������쉈���͕����Ȃ��Ȃ�B
�@�@�@�@�Ɣ������̉���
�@�@�@�Ɣ������̏㗬
�Ō�ɍ������w�O�̓a���J�ˌ����̑O�ɂV���P�O���ɂ���ɂł��B�A��́A�i�q�ŋA�������A�������Ȃ̂ŁA��肽���Ȃ������B
�@�@�@�a���J�ˌ����̓���
|
|
|
|
| 2011�N6��29���i���j |
| ���c�J�_���H�\�z�@ |
�@�����́A��여��A��������ȉ�́u���t�B�[���h���[�N�i���c�n��j�v�ɎQ�������B���J��Ƃ��āA��여��ʼnJ�������邱�Ƃ�_�����������A�����̐��c�J����͂��߂悤�Ƃ̍\�z�ł���B
�@�͐�≺�����̐����ɉ����A�J���Z���{�݂�J���^���N�̐ݒu�ɂ��āA���c�J��̏������x�����p���āA�斯�ɂ��肢���āA�����߂�B
�@���ɁA���ׂĂ̏��тłR�O�O�k�̉J���^���N��ݒu����A��P�R���������[�g���̐������߂���B��̋���ȃ_�������܂�邱�ƂɂȂ�B����𐢓c�J�_���ƂȂ����āA���̎����̂��߂ɁA���c�n�悩�炷���߂čs�����Ƃ������̂ł���B
�@�����́A���c�斯�W������肵�āA��여��A��������ȉ�̃~�[�e�B���O�������ꂽ�B
���e��
�i�P�j���c�J�n�捋�J��A���c�J�_���\�z�ɂ��ā@��P����
�i�Q�j�t�B�[���h���[�N�Ƃ��ă��f���n��i���c�n��j��k���Ō��w�����B��P���Ԕ�
�i�R�j�ӌ������@��P����
�ł������B
�@�s���Ǝs�����ꏏ�Ɍ��w���āA�b���������ł��邱�Ƃ́A�������Ɍ�������P���ł���Ɗ����Ă���B
�@�@�@�@���w���̎Q����
|
|
|
|
| 2011�N6��28���i�j |
| �Ǐ��u���{�炵�����R�Ƒ��l���v |
�@���{���V���u���{�炵�����R�Ƒ��l���v��g�W���j�A�V����ǂB
�������s�Ȃ��Ă���O���A���i�I�I�u�^�N�T�Ȃǁj�̋쏜�����ɂ́A��͂���Ƃ̒m�b������邱�Ƃ��K�v���ƒɐɊ������{�ł���B
�@�u���́A�A���A�����ʂ��Ƃ邱�Ƃ́A�A���Ǘ��Ƃ����h���ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B�h����ɐ������c�h�f�i���x��ˑ��I�ȃM���b�v�j�́A�ӂ����т܂�肩�����Ă���A���A���ɂ��݂�����Ă���̂ł��B�ؑ]��ł̎����ł��A�I�I�L���P�C�M�N���ʂ��Ƃ������Ƃɂ́A��N�����N���̋A���A���̎�ނ�������X�������邻���ł��B�v�u�A���A���̏ꍇ�́A������ʂ��Ƃ����Ւn�ɂ��Ȃ炸�ݗ���̃^�l���܂��Ƃ��A�c��A����Ȃǂ��āA�ʂ��Ղ��ł��邾���������߂�K�v������ł��傤�B�v�Ə�����Ă���B
�@�W���A�X���A�P�O���ƂR��A���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v�ŁA�搶���狳���Ă���������@��ł����̂ŁA�悭�w�˂Ȃ�Ȃ��Ɗ����Ă���B |
|
|
|
| 2011�N6��27���i���j |
| ���̐������̊ώ@�� |
�@����A��여��A��������̕��ȉ�s�Ȃ�ꂽ�B��ȋc��́u���̑����v�ł������B�����T��قnj������d�˂Ă������A���悢��܂Ƃ߂̎����ɓ����Ă����B���ꂻ��
�@�@���S�E���S
�@�A�������̗̂���
�@�B�l�̗��p�i�ӂꂠ���j
�̊ϓ_����A��{�I�ȗ��O�Ǝ��{���j�ɓ����镔�����A�킩��₷���܂Ƃ߂邱�Ƃ�_���Ă���B�����́A�n��̗v�]������āA�ꗥ�ł͂Ȃ��A�]�[�j���O�̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ̍l�����ł���B���̍ۂɊ�{�ɂȂ�l�������͂����肵�Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ�ƍl����B
�@���̑��̋c��́u��́A�ċG�E��쐶�����̊ώ@��̊J�Âł���B�����́A�W���V���i���j�W���́A���������R�ώ@�Z���^�[�O�ɂP�O���i��t�͂X���S�T������j�A�V����{�̊e��s�̍L��Ɍf�ڂ����B��ẤA��여��A��������̕��ȉ�ł���B�����ǂ́A�����s�k�����암���ݎ������ɂ���B |
|
|
|
| 2011�N6��26���i���j |
| �O���A���̉萶���̖��x���� |
�@���ŁA�A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�Ȃǂ̊O���A���̋쏜�̊��������N�łT�N�ڂɂȂ�B���ƃI�I�u�^�N�T����R�����Ă����Ƃ���U�����i���P�����͂���ꂪ�쏜�̊��������Ă���͈͊O�j�̉萶���̖��x����������Ȃ����B
�@���̏ꏊ�́A�����s�ɂ�鏜�����A�R�N�O����N�R��i����ȑO�́A�����m���Ă���͈͂ł́A�N�Q���j�s�Ȃ��Ă���Ƃ���ł���B�A���A��ӂP�D�T���[�g�����́A�����̂��߂ɏ�������Ă��Ȃ��B
�@�x�m���勴�����̂R�����A���\�Y���������݂̂Q�����A�Q�l�ŕx�m���勴�㗬�E�݂ł���B
�@��������A�I�I�u�^�N�T�͂قƂ�lj萶���Ă��Ȃ������B���̌��ʂ�����ƁA�ǂ�����Ԍ��ʂ��������̂́A�����s�̑������N�R��ɂȂ��āA���̂Q��ڂ��A���x�Ԃ��炫�A�����Ȃ鎞���̑O�ɍs�Ȃ��邱�Ƃ̂悤���B
�@�����s�̑������s�Ȃ��Ă��Ȃ����ӂP�D�T���[�g���͈̔͂́A���R�A��X�����������Ă���Ƃ���ƁA�����łȂ��Ƃ���ł́A�����o�Ă��邪�A����͓���B����̉ۑ�ł���B
|
|
|
|
| 2011�N6��25���i�y�j |
| �݂������t�H�[�����Q�O�P�P |
�@�u�݂������t�H�[�����Q�O�P�P�v������Q�������B ���e��
�ߌ�P��������W��\����
�@�s���܂́u�G�R�����@�O��̐X�Ɂ@�Z�ތւ�v
�@��������p�ψ����� �́@�u�c������@���̐����@�P�����v
�ߌ�P���R�O������Q���R�O���@��u���@�u�K���Ȓn��̂��߁@�������̂ł��邱�Ɓv���W���[�i���X�g�@�}�A�~�q����
�@����������܂ł��ǂ��Ă���������n�܂�A���݈�ԊS�̂�������܂Řb���ꂽ�B�L���Ɏc�������t���L����
�@�u�Ў�͂��������Ă����v
�@�u�g�D���肪�d�v�v
�@�u�n���̑傫���͌��܂��Ă���v
�@�u���炵�ς��@�Z�p��ς���v
�@�u��ڂ���^�̎Љ�v
�@�u�����ĕ�点��܂��v
�@�u����Ȃ�����ҁv
�@�u�f�m�o���f�m�g�ihappiness)�v�@
�@�u�R�E�F��炵�̒E���L���G�K���̒E�������i�Ȃ���⎩�R�E�_�։�A�j�G�l���̒E�ݕ����i���_�A���w�j�v
�@�u�_�E���V�t�^�[�Y�v
�@�u���Ȃ₩�ȋ����v
�@�u���l���Ə璷�����L�[�v
�ߌ�Q���S�T������S���܂Ńp�l���a�B�X�J�b�V����������A�����p�l���X�g�̈�l�Ƃ��ĎQ�������B |
|
|
|
| 2011�N6��24���i���j |
| �s����w�F�u�k�ЂŎ������̂ł��邱�Ɓv |
�@�����̎s����w�����R�[�X�ł́A����w�K�ŁA�O���́A�O��s�Љ�����c��̖x�����x����T���̂T���U���́u�k�Ўx���̑̌��k�v�����B
�@�㔼�́A�O���[�v���[�N�ŁA�R�O���[�v�ɕ�����āA����̐k�ЂŊ��������ƁA�v�����Ƃ�b���������B
�@�݂�Ȃ��A�k�Ђ̏������L���邱�Ƃ́A�Ӗ�������Ɗ������B |
|
|
|
| 2011�N6��23���i�j |
| �v���Ԃ�ɃJ���K���̃q�i�V�H�ɉ |
�@�v���Ԃ�ɁA�J���K���̃q�i�V�H�����邱�Ƃ��ł����B�V�H�͂�������傫���Ȃ��Ă������A�V�H�Ƃ����C�Ɉ���Ă����B�e�̈�ĕ����A�悩�����悤���B
�@�@�@�J���K���̃q�i�V�H
���������R�ώ@�����̖��ł́A��������̗c�t�������A���ɓ����āA��������T���Ă����B�[���Ȃ��A���x�������炢�̐��ʂŁA�q�������͊y�������ł������B
�@�@�@���ŗV�Ԏq������
|
|
|
|
| 2011�N6��22���i���j |
| �i�c�c�o�L�̉� |
�@���A�{�����e�B�A�����Ă���u�A�������v�ɏo�������B�����ł́A���A�i�c�c�o�L�̔����Ԃ��炢�Ă���B
�@�@�@�i�c�c�o�L�̉�
�@���ɍ炢�Ă���̂́A�U�N���A�n�N�`���E�Q�A�e�C�J�J�Y���A�A�W�T�C�A�c�c�W�ł������B
�@���O�A���ɏo���B��������i��ŗ����s�̑������A�쐅���Ɣ̊Ԃ̉E�݂ōs�Ȃ��Ă����B
�@�x�m���勴�����E�݂́A�����W������ɕʂ̋Ǝ҂����������Ă��ꂽ�Ƃ���ł���A������A�����A�Q�T�ԂɂȂ邪�A�萶���Ă��Ă���̂́A�J�^�o�~�A�����T�L�J�^�o�~�A�V���c���N�T�A���u�K���V�A�����M�ȂǂŁA���̂Ƃ���I�I�u�^�N�T�́A�قƂ�Ǐo�Ă��Ă��Ȃ��B�A���`�E���������ł���B���ӂP�D�T���[�g�����́A���������Ȃ��̂ŁA�����ɂ͎��X�I�I�u�^�N�T�������Ă���B�P���[�g���قǂɂȂ��Ă�����̂�����B��͂�C�ɂȂ�̂ŁA�������݂łR�O���قǁA�I�I�u�^�N�T�̏��������Ă������B
|
|
|
|
| 2011�N6��21���i�j |
| ���n��W�����ɋ���ɂ��o���� |
�@�����́A����P���ڂ܂ŁA�S���{���n��W�����ɏo�����Ă��܂����B��w�̗F�l�����I�����̂ŁA�ƘA�������ꂽ�̂ŁA���ɂ����Ă��܂����B�u�����x���]�v�Ƒ肷���i�ł������B�Ⴂ���A���䍂�ɓo�������Ɍ����A�����x�̎p���v���o�����B
�@�ߌ�A�g�߂ȂƂ���ŁA�l�W�o�i���炢�Ă���̋C���t�����B�E�����̂悤�������B
�@�l�W�o�i
|
|
|
|
| 2011�N6��20���i���j |
| �N���ʂ̑���i�����j |
�@���A����A���c�����ӏ��̗N���ʂ̑�����s�Ȃ����B�N���L��̗N���ł���B�����P�X���b�g���قǂ̗N��������Ă����B
�@�@�@�N���ʑ���̗l�q
�߂��ɃT���K�j�����邱�ƂɋC���t�����B�����͂��ł���悤�ł������B�Y���̋G�߂ł���B���炭������p�������Ȃ��Ȃ����B�����Y���ł��邱�Ƃ��F�肽���B
�@�@�@�T���K�j
|
|
|
|
| 2011�N6��19���i���j |
| ���̗N���ʂ̑���i�U���j |
�@�����́A���P��̖��ɒ����N���ʂ̑�����s�Ȃ����B�N���ʂ��A�挎���ɂ��āA�����ɓ]�����B
�@�@�@�N���ʑ���̗l�q
�@���̍����~���q���W���I���̌Q��������ꂽ�B
�@�@�@�q���W���I��
�c�O�Ȃ��Ƃł��邪�A�J���K���̃q�i�͂Q�H�����ɂȂ��Ă����B
�@�@�@�J���K���̃q�i
|
|
|
|
| 2011�N6��18���i�y�j |
| �������{�����e�B�A��ኈ���� |
�@�ߑO���A������ł��������A���Ƃ��J�͖Ƃꂽ�B�����́A�������{�����e�B�A��ኈ�����ł���A���́A�X������莩�R�ώ@�����̃q�K���o�i�̉��̃h�N�_�~�Ȃǂ̏�����Ƃ��s�Ȃ����B�������̃q�K���o�i�̌Q���n�́A�Ԃ̎����́A��ς��ꂢ�ŁA��������������A�����̕������w�ɂ�����B���̂��߁A���i�̎���ꂪ��ł���B
�@�P�P�������琢�b�l�����A�ߌ�P������́A�쒹G�̕��X�Ǝ��匤�C�̂����ߕ��ɂ��āA�ł����킹���B
�@���̂��߁A�w�O�R�~�Z���ōs�Ȃ��Ă����u�Ԃ̂܂��𗬉�v�ɂ́A�啪�x��ĎQ�������B |
|
|
|
| 2011�N6��17���i���j |
| �s����w�F�������̂����݂Ɣ������̓��� |
�@�ߑO���A�Љ���َ�Â̎s����w�����R�[�X�u���R�Ɛl�Ԃ̋����v�̍u�`�ɂł��B�����̓��C���u�t�̐��ˏ��V�����_�H��w���_�����́u�������̂����݂Ɣ������̓����v�ł������B
�@��C�̓�_���Y�f�̂��ẮA�����̌ċz����̕��o�A�C��������̕��o�A���ΔR���̔R�ĂȂǂ���̕��o�����ʂƁA�������ŋz���A�C�����ւ̗n���Ƃ̔����ȃo�����X�ɂ��Đ��������B�܂��������ɂ��Ă̐������������B�ہA����ہA���ށA���������A�E�C���X�ł���B
|
|
|
|
| 2011�N6��16���i�j |
| �����_�吢�c�J�L�����p�X��K�₵�܂��� |
�@�����́A�ł����킹�ɓ����_�吢�c�J�L�����p�X��K�₵���B�͂�߂ɉƂ��o�āA�o�X�ō��]�ɏo�āA���c�}���ɏ��A����w���O�w�ł���A�������������Ă���A���c�J�ʂ艈�����m�����Ɍ����A���c�J���p�ق̌����������m�F���āA�����_�吢�c�J�L�����p�X�܂ŕ������B�P���Ԕ��قǂ̃E�I�[�L���O�ł������B
�@�K���́A�����_�呢���Ȋw�Ȃł���B�P�P���قɂ������B�ƂĂ������搶�ŁA��ϗL�Ӌ`�ȑł����킹���ł������Ƃ́A���ꂵ�������B
�@�搶����A���{���V���u���{�炵�����R�Ƒ��l���`�g�߂Ȋ�����l����`�v��g�W���j�A�V�����������߂����������̂ŁA�A��ɖ{���ōw���A�����ǂ�ł���B |
|
|
|
| 2011�N6��15���i���j |
| ���̗��ʑ��� |
�@�ߑO���A���̗��ʂ��A�R�ӏ��i�x�m���勴�A�A���V���j�ő��肵���B������̉ӏ��ł��A�挎�i�T���j�̑���l���A�啝�ɑ��������B
�@�r���A�J���Z�~�����������B�����~�̎��́A�قƂ�ǔ��̂���Ă��܂��Ă���̂ŁA�J���Z�~���Ԃ��炢�Ă��鑐�̏�Ɏ~�܂��Ă����B
�@�@�@�J���Z�~
�������A�J���K���̃q�i�����������B�q�i�͂R�H�Ƃ����C�ł������̂ŁA�����ق��Ƃ����B���̂܂܈���Ă����ΗL����A���͑����������ł��傤�B
�@�@�@�J���K���̃q�i�R�H
�C�ɂȂ��Ă����I�I�t�T�����������Ă������B�R�O���قǂ����������A�������肵���B
|
|
|
|
| 2011�N6��14���i�j |
| �݂������t�H�[�����Q�O�P�P�̎����쐬 |
�@�ߑO���A�U���Q�T���i�y�j�ߌ�ɍs�Ȃ���u�݂������t�H�[�����Q�O�P�P�v�`�݂�ȂłȂ���������`�̐ȏ�z�t����鎑���̍쐬�������B���R�����̊W���鎑�������ł��邪�E�E�EA4�ꖇ���A���ɂ���������X�y�[�X�ł���B�ʐ^���R���g�p���āA�킩��₷�������ƂȂ�悤�ɂƂ߂��B
�@���O�A�Ƃ��łĖ��ցB�������J���Z�~�ƃJ���K���̃q�i�ɉ���B
�@�@�@�@�J���Z�~
�@�@�@�@�J���K���̃q�i�R�H�i�P�H�����Ă��܂����j
|
|
|
|
| 2011�N6��13���i���j |
| ���N���A�I�I�u�^�N�T�̏����@ |
�@�ߑO���A���ɁA�����s�̑�����̔�������ɍs�����B�x�m���勴����Ԃ̍����~�́A�������U���W������ɍs�Ȃ��Ă����̂ŁA���̌�T���قnjo�߂��Ă���B�x�m���勴�����⑊�\�Y���������݂Ȃǂł́A�I�I�u�^�N�T��A���`�E���̔���͂قƂ�nj����邱�Ƃ��ł��܂���ł����B���������P�C�Q�T�ԃ`�G�b�N���邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A��������������B
�@����������ĂȂ���ӂŃI�I�u�^�N�T���C�ɂȂ�Ƃ��낪�������B���\�Y���������݁i���V�̗��̓c�ނ̑O�j�ł���B�Q�O�{�قǂP���ȏ�̍����ɂȂ��Ă����I�I�u�^�N�T�����������B
�@�@�@�I�I�u�^�N�T�����O�̗l�q
�@�@�@�I�I�u�^�N�T������̗l�q
�@�@�@�@�I�I�u�^�N�T�̏�������
��T�ԂԂ�ɁA�����ŁA�V�H�̃J���K���̃q�i�������B�V�H�Ƃ����C�ł������B
�@�@�@�J���K���̃q�i�V�H�Ɛe��
|
|
|
|
| 2011�N6��12���i���j |
| �J���K���̃q�i����� |
�@�ߌ�A���ŁA�V���ɃJ���K���̃q�i�S�H�����������B�܂����܂ꂽ����̂悤�Ɍ������B
�@�@�@�J���K���̃q�i�S�H
�@�@�@�J���K���̃q�i�S�H
|
|
|
|
| 2011�N6��12���i���j |
| �j�R�j�R����́u���R�G�l���M�[�v�L���ҍ��k�� |
�@�ߌ�Q�������Q���ԁA�j�R�j�R����̐����p�ŁA�u���R�G�l���M�[�v�Ɋւ���̗L���ҍ��k��̗l�q���݂��B���߂Ă̊��Ƃ̂��ƂŁA�j�R�j�R���悾�����A�C���^�[�l�b�g����Ő����p�����B
�@�L���҂Ƃ��ď����ꂽ�̂́A�}�A�~�q����i���R���T���^���g�j�A���c���j����i���T�b�J�[���{��\�ēj�A���ѕ��j����iap bank ��\�����j�A��{���ꂳ��i�~���[�W�b�V�����j�A�����`����i�\�t�g�o���N�В��j�ł������B
�@�S�ʓI�ɂ́A���R�i���z���A���́A�n�M�Ȃǁj�G�l���M�[�̔䗦��啝�Ɋg�債�A���q�̓G�l���M�[�≻�i�Ζ��A�ΒY�Ȃǁj�G�l���M�[�̈ˑ��x��������ׂ��ł���Ƃ̗���ł��������A���́A���d�ł��錠���A���d�����d�͂錠����^���鐧�x��������邱�Ƃ����߂Ă����B
�@���c����́A�u���R�͎q������̗a���蕨�A��������A�j���肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƁB���т���́u����^�̎Љ��A�z�I�ȎЉ�ɕς�邱�Ɓv��b���ꂽ�B���A���@���ŁA�R�O�N�O�̃t�[�g�s�A�v����܂̏Љ��n�܂�A�����Ƃ̎�g�̒������Ƃ�b���Ă���ꂽ�B�u�n�����~���̂͐A���v�Ƃ����̂��A���_�̂悤�ŁA�b���o���ƂƂ܂�Ȃ��悤�������B |
|
| 2011�N6��11���i�y�j |
| ���������R�ώ@���z�^���ώ@�� |
�@���i�P�O����j�A���������R�ώ@���Ńz�^���ώ@��������B�������{�����e�B�A���ē����ŁA�T�|�[�g�����B�����A���]�Ԃ̒��֏�̐����̒S���Ƃ��āA�����������ЂƎ������������B��t�͂U��������n�܂�A�ŏI�͂V��������ŁA�ꏊ�́A���R�ώ@�Z���^�[�O�ł������B���ۂɃz�^��������̂́A�Â��Ȃ��ăz�^�����o��܂ő҂��Ƃ��K�v�ŁA�V����������A�����A�ē������āA�A���Ă����������B
�@�z�^���ώ@��ɂ���ꂽ���͂S�O�O�����܂�ł������B�z�^���͂��Ȃ�̐������ł���āA���q�l���A�������ɋA���Ă�����āA�ق��Ƃ����B
�@����i�P�P����j���J�łȂ���A�z�^���ώ@��́A���{�����\��ł���B |
|
|
|
| 2011�N6��10���i���j |
| �s����w�F�Z�p�Ɛl�Ԃ̊W��₢���� |
�@�����́A�O��s�Љ���َ�Â̎s����w�����R�[�X�u���R�Ɛl�Ԃ̋����v�̑�T��ڂ̍u���ɏo�Ȃ����B�����́A�u�����ЊQ���i�s���邢�܁A���{����A�Z�p�Ɛl�Ԃ�₢�����v�Ƃ̃e�[�}�ŗ��J��w�����̖x�����x�搶�̍u�����������B
�@�Z�p�̖{�����ǂ��Ƃ炦�邩�H����n�܂��āA�Љ�I�K�͂̋Z�p�V�X�e���ɂȂ������A�Z�p�̎�́i�s���j�͂ǂ������l���A�s�����A�ӎv������\������傫�Șg�g�݂������I�ɍ\�z���邱�Ƃ���ł���Ƃ������ƂŁA���b���I������B
�@�ł́A���ۂɁA�s���͂ǂ���������̂��ɂ��Ă܂ł́A�悭�������ł��Ȃ������B |
|
|
|
| 2011�N6��9���i�j |
| �������{�����e�B�A�̎��劈�� |
�@�ߑO���A����̖쒹�ώ@���s�Ȃ����B�{�����e�B�A�P�R�����Q�����āA�Q���Ԕ������āA����������쒹��T���ĕ������B�g�����킹�ł́A�P�W����m�F�����B�Ȃ��������ŁA�p�͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�z�g�g�M�X���m�F�ł����B�J���Z�~���p�������Ă��ꂽ�B
�@�@�@�J���Z�~
�@�@�@�@�J���K���ƂT�H�̃q�i����
�@�@�@���̎q������
�@�@�@�@�������̎q������
�@�P�P���T�T������A�쒹�O���[�v�̃~�[�e�B���O���s�Ȃ����B�ߌ�́A�L�u�ŁA���o�[�h�T���N�`���A���̃A�V���̃J�i���O���̏�����Ƃ��s�Ȃ����B
|
|
|
|
| 2011�N6��8���i���j |
| �쒹�ώ@�̃y�[�W�̎ʐ^��lj� |
|
|
|
| 2011�N6��8���i���j |
| �������Ă悩�����I |
�@���O�A���]�ԂŖ��ɂł��B�����s�̋Ǝ҂ɂ�鑐�����s�Ȃ��Ă����B��̋Ǝ҂́A���̍��݂��A�䓃�⋴������V���܂ł����߂Ă����B���݂́A���܂�i��ł��Ȃ������B�H�̏����㗬�܂łł������B�ʂ̋Ǝ҂́A���̔���X�^�[�g���āA�x�m���勴�܂ł̗��݂������߂Ă����B
�@�@�@�Ǝ҂ɂ�鑐����
�r���A�J���Z�~�̎p�����������̂ŁA�����~�ɍ~��āA�ʐ^���Ƃ����B
�@�@�@�J���Z�~
�@�@�@�J���Z�~
�ƃ��I����āA�ړ����͂��߂���A�����Y�L���b�v���Ȃ����ƂɋC�������B��قǂ܂Ŋm���ɂ������̂ŁA��������T���Ȃ���A�߂��ĉ�������ƁA�����Ƀ����Y�L���b�v�����������B�����ł������B
�@�@�@�����Y�L���b�v�͂����Ɍ��������B
|
|
|
|
| 2011�N6��7���i�j |
| �u�͐���}�v�쐬�ɂƂ��Ȃ��t�B�[���h���[�N�@ |
�@�����́A�ߌ�P������A��여��A����Ȃ��Ƃ�����́u�͐���}�v�쐬�ɔ����t�B�[���h���[�N�ɎQ�������B����͓ڑ�P��ŁA���̕��ɋ�����_�����܂ł���邢���B�Ō�́A���c�J�g���X�g�ŁA�͐���}�ɋL�ڂ������Z�߂��B
�@��q�ʐ�E�G�́A�ĊJ���ŁA��������ς�����B���w�r���������A�V���b�s���O�Z���^�[�̂悤�Ȃ��̂��������B���̉�����̍H������i���̗l�q�ł���B
�@�@�@�@���̍ʼn�����A���̐�ő�����ɍ�������B
�@�@�@�@�g�����q�ʐ�߂�B
�@�@�@�@�A�I�T�M
|
|
|
|
| 2011�N6��6���i���j |
| ������ƈꕞ |
�@���A�v���Ԃ�ɒ�̎G�����Ƃ�B���A�J���p�j�������₩�ɍ炢�Ă���B������Ƃ����Ղ����āA�Ԃ߂�B�ׂɂ́A�o���F�o�����[�i���炢�Ă���B�́A�F�l�ɂ����������c���̏Ă���������B
�@�@�@�J���p�j����
�@�@�@�J���p�j����
�ߌ�A��w�̃N���X�����̂ŁA�|���܂ŏo������\��ł��B
�@������A�g�o�u�V�j�A����v�̌f����
�@http://8926.teacup.com/adam/bbs
�ɃT���R�E�`���E�̎ʐ^�̌f��������܂����B
�݂Ă��������B
|
|
|
|
| 2011�N6��5���i���j |
| ��쎩�]�ԎU���F�쒹�̃q�i���� |
�@�����A�U������ɉƂ��o�āA���������̌䓃�⋴����A�㗬�̂�܂��܂ōs���A�����Ԃ��ĕ�����̐X�����̒r���݂āA����ɂX������A�����B
�@���ŁA���N���߂ăJ���K���̃q�i�����邱�Ƃ��ł����B�V�H�̃q�i����Ă����B�߂��ł݂Ă������ɕ����ƁA�W�H�������A�����Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł������B
�@�@�@�J���K���Ƀq�i�V�H
��܂�����݂�ƁA�q���Â�̉Ƒ����A���̒��ɓ����Ă����B
�@�@�@���̐l�X
������̐X�����̒r�ł́A�J�C�c�u���̃q�i���R�H�����A���N�́A���̒r�śz�����悤���B�����傫���Ȃ��Ă������A�c�̔����V�}���܂������c���Ă����B�o���̃��J���S�H�����B
�@�@�@�@�J�C�c�u���̐e�q
�@�@�@�o���̃��J
�����̃g�C���Ƀc�o����������A�o����A�������肵�Ă����B������������Ǝv�����A�����p�ł������̂ŁA�m�F�͂ł��Ȃ������B�d���ł́A�X�Y���̎p�����������B
�@�@�@�X�Y��
|
|
 �@�@��i�W���̗l�q
�@�@��i�W���̗l�q  �@�㗬�ł̑���̗l�q�B
�@�㗬�ł̑���̗l�q�B  �@�Ǝ҂ɂ�鏜���̗l�q�������B
�@�Ǝ҂ɂ�鏜���̗l�q�������B  �@���̕��i���㗬�B
�@���̕��i���㗬�B  �@�x�m���勴�̑���̗l�q
�@�x�m���勴�̑���̗l�q  �@�W���Y�_�}
�@�W���Y�_�}  �@�W���Y�_�}
�@�W���Y�_�} 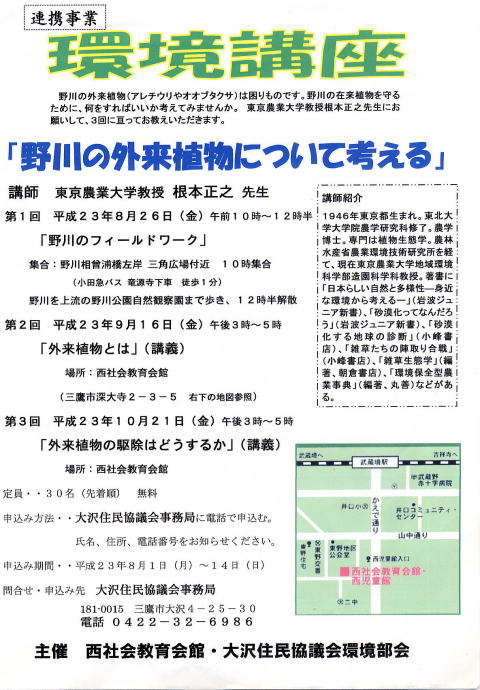 ���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v
���u���u���̊O���A���ɂ��čl����v �@�@�J���Z�~
�@�@�J���Z�~