| �����L>>�@ |
| 2013�N6��18���i�j |
| ���Ȃ̒���f�f |
| �@�䒃�m���̕a�@�܂ŁA�R�����ɂP�x�̓��Ȃ̒���f�f�ɍs���Ă��܂����B���ʂ́A���ɖ��Ȃ��B�@�R���X�e���[���̊֘A�́A������ݑ����Ă���̂ŁA��l���Ɏ��܂��Ă���B�ł��ˑR�A�A�̒��q���������肵�Ȃ����Ƃ���A�O�̂��߃A�����M�[�̌����i���t�j�����Ă�������B���ʂ́A����̐f�f���ɒ�����B
|
|
|
|
| 2013�N6��17���i���j |
| �V���^�G�M�N�i�����e�j |
�@�߂��̓V����ʂ�ŃV���^�G�M�N�i�����e�j�����������B�새�[���b�p�i�n���C�j�C�ݒn�挴�Y�̑��N���B�L�N�ȃL�I�����B�����ɂ͋����Ƃ����Ă���B�ʖ��̓_�X�e�B�[�~���[�iDusty
miller�j�B�t���y���ސA���̂悤���B
�@�@ �@�V���^�G�M�N �@�V���^�G�M�N
�@�@ �@�V���^�G�M�N �@�V���^�G�M�N
�@�@ �@�V���^�G�M�N �@�V���^�G�M�N
|
|
|
|
| 2013�N6��16���i���j |
| �M�{�E�V |
�@�䂪�Ƃł́A���A���̃M�{�E�V�i�[���j�ɍ����Ԃ��炢���B�M�{�E�V�́A���Ƃ��Ɠ��{�i�Ⓦ�A�W�A�j�̌×��̐A���ł��邪�A��x���[���b�p�ɓn��A��ςȐl�C���o�āA���{�ɋA���Ă��܂����B�����e���D�݂܂��B������W���F�̉Ԃ��R���܂��B�Ԋ��͕��ʂV������W���B�����ȃM�{�E�V���B�M�{�V�Ƃ������B���O�́A�ڂ݂��A���⎛�Ђ̗����Ɏ��t����ꂽ�l�M�V��Ɏ�������Ɍ����Ă�ꂽ���Ƃ��炫�Ă���B
�@�@ �M�{�E�V �M�{�E�V
�@�@ �@�M�{�E�V �@�M�{�E�V
|
|
|
|
| 2013�N6��15���i�y�j |
| �l�W�o�i�i���ԁj |
�@�J��̒�ŁA�l�W�o�i�i���ԁj���������B�����ȃl�W�o�i���̑��N���B�ʖ��́u���a�Y���v�B�ג����Ԍs�ɏ����ȃs���N�̉Ԃ�������ɑ�R���Ă���B�������ƉE����������B�S�l���̉͌�����b�̘a�́u������
���̂Ԃ������� �N���� ���ꂻ�߂ɂ� ��Ȃ�Ȃ��Ɂv�i�Í��W�j�ɂ��̂��Ă���B
�Ԃ͍炢�Ă��P�O���قǂ������ł���B
�@�@ �l�W�o�i �l�W�o�i
|
|
|
|
| 2013�N6��15���i�y�j |
| �A�x���i |
�@�A�i�x���́A�k�A�����J���Y�̃A�W�T�C�B�����Ԃ���{��ɂ��B�䂪�Ƃ͔��A���ł��邪�A���̏ꍇ�ɂ͐��ꂵ�₷���B�Ԋ��́A�U���`�V���B
�@�@ �@�A�i�x�� �@�A�i�x��
�@�@ �@�A�i�x�� �@�A�i�x��
|
|
|
|
| 2013�N6��14���i���j |
| ���̐������̊ώ@�� |
�@��여��A��������̕��ȉ��Â̖��̐������̊ώ@��A�W���S��(��)�ߑO�P�O������P�Q���i���J���s�j�ɊJ�Â����B
�@�Ώێ҂͂R�O�l�i���w�R�N���ȉ��͕ی�ғ����j�A�W���͓s�����������R�ώ@�Z���^�[�O�ł��B
�@�\������́A�����s�k�����암���ݎ������ŁA�V���P��(��)�`�P�O��(��)�̕����ߑO�P�O���`�ߌ�T���̊ԂɁA�d�b�O�S�Q�|�R�R�O�|�P�W�S�T�ɐ\�����ނ��ƁB
|
|
|
|
| 2013�N6��14���i���j |
| �a�@�ʂ� |
| �@�ߑO���A���炩���ߗ\������Ă����āA�O��w�k���̎��@��A�Ȃ̃N���j�b�N�ɏo�������B�����́A�r���̂T�K�ɂ���A���ȁA���`�O�ȁA���@��A�ȁA��ȁA��ǂ���������N���j�b�N���[����ڎw���Ă��邻�����B
�@�\����P�T���P�ʂŎĂ����B�ł����ۂ̐f�@�́A�\����Q�O�����������A��f�[�ɋL���A�Ō�t�̖�f���āA�\��̎��ԑт��S�O���x��Ă̐f�@�ƂȂ����B
�@�̂ǂ��܂��Ԃ��̂ŁA�̂ǂ���Â�������T�ԕ��������Ă��ꂽ�B�Ƃɂ����債�����Ƃł͂Ȃ������Ȃ̂ŁA����S�B
|
|
|
|
| 2013�N6��13���i�j |
| ���ׂ̋C�z |
| �@���̓~�͕��ׂ��Ђ��Ȃ��������A�~�J�ɓ���A��邩��A���M������A�ǂ������ׂ̋C�z�ł���B�����́A�\������ׂăL�����Z�����āA�{���ɓw�߂��B�����ԗǂ��Ȃ��Ă����悤�Ɏv���̂ŁA�����A����������d���邱�Ƃɂ������B |
|
|
|
| 2013�N6��12���i���j |
| �W�O�Q�O�^�� |
�@���U��ʂ��ĐH���̎�ނ��킸�ɁA�����̎��Ŋ��߂�ɂ́A�Œ�Q�O�{�̎����K�v�������ł��B�W�O�ɂȂ��Ă������̎����Q�O�{�ȏ�ۂ��܂��傤�Ƃ����^�����A�W�O�Q�O�i�͂��܂�ɂ��܂�j�^���������ł��B
�@���{�́A�������ł͂��邪�A�W�O�Έȏ�̐l�̎��̐��͈ĊO���Ȃ��A���������V�`�W�{���x�������ł��B
�@��������҂ł��邪�A���݂Q�S�{�����̎��������Ă���B�������ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���B�����Q�x�̎������͓��R�ł����A�R�������甼�N�Ɉ�x�A�a�@�̎��ȂŎ��̃N���[�j���O���s���Ă�����Ă���B�������ϗL�����ƍl���Ă���B
�@�����̌ߑO���A�J�̒����A�䒃�m���ɂ��錳�̉�Ђ̓����a�@�ɏo�����āA�R�O���قǂ����āA���̃N���[�j���O���s���Ă����������B��d���ł͂��邪�A������厖�ɂ��Ă��������B
|
|
|
|
| 2013�N6��11���i�j |
| ������� |
�@�ŋߍ��ɋC���ŁA�̗͋��������˂āA����A���̔���n���Ԃ����邢���B�A��́A�������č�w���璲�z�w�ɂłāA�o�X�ŋA���Ă��܂����B
�@���̂Ƃ���̋�~�J�ŁA���̐��͏��Ȃ��A����ł��āA������Ƃ���ŗ̑�����R�������Ă����B�ł����ӂɂ́A�~�N���A�T���J�N�C�A�t�g�C�A���V�A�q���K�}���������萬�����Ă����B�I�I�u�^�N�T�����X�P���ȏ�̍����ɂȂ��Ă���p�����������B���ӂł́A�n�N�Z�L���C�A�R�T�M�̎p���������B
�@�@ �@�T���J�N�C �@�T���J�N�C
�@�@ �@�t�g�C �@�t�g�C
�@�@ �I�I�u�^�N�T �I�I�u�^�N�T
�@�@ �@�n�N�Z�L���C �@�n�N�Z�L���C
�@�@ �@�R�T�M �@�R�T�M
|
|
|
|
| 2013�N6��10���i���j |
| �~�N���i���I�j |
�@���ł́A���ꂪ�ɂ₩�ȂƂ���ŁA�~�N�������炵�Ă��邱�Ƃ�����B�n���s��L���Ċ��𑝂₷�Ƃ����Ă���B�ʎ��i�W���ʁj���A�I�̃C�K�Ɏ��Ă���̂ŁA�~�N���i���I�j�̖�������B�t�́A�����ɋ߂����̒f�ʂ��O�p�`�ŁA�_�炩���X�|���W������Ă���B
�@���N�͓��ɂ悭�ԁi���ԂƗY�ԁj�����Ă���B���ʁA�Ԋ��͂U������W���Ƃ����Ă���B
���A�~�N���́A���Ȃ̏���Ŋ뜜��Ɏw�肳��Ă���B
�@�@ �@�~�N�� �@�~�N��
�@�@ �@�~�N���̎��� �@�~�N���̎���
�@�@ �@�~�N���̗Y�� �@�~�N���̗Y��
�@�@ �@�~�N���̉ʎ� �@�~�N���̉ʎ� |
|
|
|
| 2013�N6��9���i���j |
| �K�E���i�������j |
�@���̓��[�̖h�����ɃK�E���̉Ԃ������Ă��܂����B���ɍ炭�s���N�������������Ԃ��A���ɗh��Ē��������悤�Ɍ����邱�Ƃ��甒�����ƌĂ��B���{�ɂ͖��������ɓ����Ă����k�A�����J���Y�̑��N���B�O����ł��邪�A�������B
�@�@ �@�K�E�� �@�K�E��
�@�@ �@�K�E�� �@�K�E��
|
|
|
|
| 2013�N6��8���i�y�j |
| ���ɂ� |
�@���A���]�ԂŖ��̗l�q�����ɍs�����B
�@�܂��́A�����s�ɂ�鍡�N��P��ڂ̑�����̐i�s�ł��邪�A���`�䓃�⋴�Ԃł́A��`�������Ԃ������āA���ׂĊ������Ă����B
�@��~�J�Ȃ̂ŁA���̐������Ȃ��B���ɂ��ʂ����̏㗬�����A���͂�����Ă����B����ȂɂЂǂ��͎̂��N�Ԃ�ł���B
�@�@ �@���͂�̖�� �@���͂�̖��
�@���ʂ����̂����Ƃɂ���N�}�m�~�Y�L�ɂ́A�Ԃ��炫�n�߂Ă����B�����㗬�ł́A�J���K�����q�i�T�H�����������B�R���قǑO�ɐ��܂ꂽ�q�i���������B
�@�@ �@�N�}�m�~�Y�L�̉� �@�N�}�m�~�Y�L�̉�
�@�@ �@�J���K���̃q�i�T�H �@�J���K���̃q�i�T�H
�@���̔������t�߂ŁA�J���Z�~�ƃA�I�_�C�V���E�����������B�J�����q�����������݂ɉ͌��ɍ~��Ă����B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�@�@ �@�A�I�_�C�V���E �@�A�I�_�C�V���E |
|
|
|
| 2013�N6��8���i�y�j |
| �s����w�ŗ�ؗC�i�搶�̍u�`����u |
�@�O��s�Љ��َ�Â̎s����w�����R�[�X�u���E�ɐ�������{�̏���ⳁv�ł́A�����R��ڂ̍u�`������A�@����w������ؗC�i�搶�́u�A�W�A�S�̂̊O���E���S�ۏ�v�Ƒ肷��u�`����u�����B
�ȉ��������������_�́A�A�W�A�������Ȏ��_�Ƃ��āA�@�A�����J���A�W�A�������Ă��Ă���u�A�W�A�E�����m�v�̎��_�A�A��������u�A�W�A�̎���v�̎��_�A�B�A�W�A�̐����Љ�́A�s���Љ�E���剻�E���q����̎��_�A�C�o�ς̑��݈ˑ����i��ł���̂ŁA�n���`�̎��_�Ō��邱�Ƃ���Ƃ������Ƃł������B
�@
�@�u�A�����J�͑ޒ����A�����͂���ӂ��B�ł��V�����������ł��Ȃ��B�������̎Љ�ɓ˓����Ă��Ă���B�����Ȃ�����ł���iG0�j�B�s���Ǝs��������Ȃ��A�s���O�������߂邵�����@���Ȃ��v�Ƃ����̂��A�搶�̎咣�Ǝ�����B
�@�b��Ƃ��āA�@�u�����V����@�v�������₩��Ă���A�A�������߂̖{�ɁA�������I�q���u�����ƕ����O���v������̂Q�����������B |
|
|
|
| 2013�N6��7���i���j |
| �s���b�ԍP�t�� |
�@����̌ߌ�A�N���X��̋A��ɁA�s���b�ԍP�t�������w�����B�ړI�́A�m�l���́A�����̒|�т̊Ǘ������Ă��đ�ς������ƕ����Ă����̂ŁA���̒|�т��݂邽�߂ł������B�ē��ɂ́A���x�b�Ԃ��A�����S�O�N�ɂS�O�̂���ɂ��̒n�ɏZ�݁A�G�ؗтɈ͂܂�A���R�̒��œc���������y���݁A�������c�����B���a�P�Q�N�Ɉ��q�v�l���瓖���̓����s�Ɍ����Ƃ��Ċ���A���a�U�P�N�Ɂu�����s�w��j�Ձv�ɂȂ����|�L�ڂ���Ă����B
�@�|�т́A�l�肪�����邽�߁A�ŋ߂́A�ꕔ�A�[���Ɏ肪����Ă��Ȃ��ꏊ������ꂽ�B
�@�@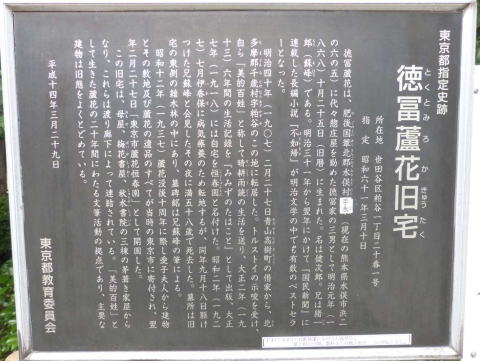 �@�ē��� �@�ē���
�@�@ �@�ꉮ �@�ꉮ
�@�@ �@�~�ԏ��� �@�~�ԏ���
�@�@ �@�A�������}�i���a�U�O�N�j �@�A�������}�i���a�U�O�N�j
�@�@ �@�|�� �@�|��
�@�@ �@�|�� �@�|��
|
|
|
|
| 2013�N6��6���i�j |
| �_�c�w�m��ٖ{�قɂ� |
�@�́A��w�̂P�C�Q�̎��A�p��̎��Ƃœ������������̂̔N�P��̃N���X��������B�����t�߂ɂ���P�S�����o�Ȃ����B���̃N���X��͑�ϒ��������Ă��邪�A���݂������N�ɂȂ����̂ŁA���̉�������߂邩���b��ɂȂ����B���_�́A���͂����̉�ɂȂ��Ă���̂ŁA�������炭�͑����邪�A�A���R�[���Ɨ����̗ʂ����炷���ƂɂȂ����B��l�Âߋ����������A�b��́A�@��i�G�A�Ǐ��A���s�Ȃǁj�V�l�A�A���N�T�l�A�B���̑��i�d���A�o�ϓI�Ȃ��ƂȂǁj�Q�l�̊����ł������B�悭���N�̘b�������Ȃ肪�������A���낢��Șb�肪�o�āA�y�����ЂƎ��ł������B
|
|
|
|
| 2013�N6��5���i���j |
| ���������ԉ��ɂ� |
�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n������E�̃{�����e�B�A����̌��C��ŁA���������̔��������ԉ��̌��w�ɏo�����܂����B�Q���҂͋���̃X�^�b�t�R�����܂߂āA�����R�O�����A�݂���o�X�Ō��C�ɏo�����܂����B
�@�悭�������ꂽ�����ԉ��ɂ́A�����̐��Ώ��Ȃǂ̐����n�ɐ��炵�Ă���A�����W�߂��Ă��܂��B���n�т̐A���Q�O�O��̑��A������сA���R�A���P�P�O�O�킪�W�߂��A���̑����܂߂�ƑS���łP�V�O�O��ƂȂ邻���ł��B�����͇@���t�L�t���ы�A�A�X�X�L������A�B��w������A�C�k�}�K��������A�D���R�̂��Ԕ���A�E���w������A�F��Ό�������A�G�����ы悪����A���w�ł́A�K�C�h����Ɉē��ł͂Q���Ԃ��K�v�Ƃ̂��Ƃł������B
�@���炢�Ă���Ԃ̎ʐ^���B���Ă��܂����̂ŁA�ꕔ���������܂��B
�@�@ �@�����ԉ��̕��i �@�����ԉ��̕��i
�@�@ �@�u���[�|�s�[ �@�u���[�|�s�[
�@�@ �@�H���A���A�V���w�C�V���\�E �@�H���A���A�V���w�C�V���\�E
�@�@ �@�q�I�E�M�A���� �@�q�I�E�M�A����
�@�@ �@�C�u�L�g���m�I �@�C�u�L�g���m�I
�@�@ �@�n�}�i�X �@�n�}�i�X
�@�@ �@�T�C�n�C���� �@�T�C�n�C����
�@�@ �@�q���T���� �@�q���T����
�@�@ �@�R�}�N�T �@�R�}�N�T
�@�@ �@�T���W���E�R�E�z�l �@�T���W���E�R�E�z�l
�@�@ �@���V���q�i�Q�V �@���V���q�i�Q�V
�@�@ �@�G�]�m���G���\�E �@�G�]�m���G���\�E
�@�@ �@�I�J�^�c�i�~�\�E �@�I�J�^�c�i�~�\�E |
|
|
|
| 2013�N6��4���i�j |
| ���͐������Ȃ��A�ׂ̌����̒r�ɂ̓J���K���̃q�i�V�H |
�@�~�J�ɓ��������A���T�͉J���~��Ȃ������ł���B���A���̐�����Ϗ��Ȃ��ȂĂ���B��삭�ʂ����㗬�ł͐��ꂪ�������Ă�����B�N���L�ꂩ��͗N�������ɒ����ł���̂ŁA�����艺���͑��v�ł���B���T�̉J���҂��ǂ������B
�@�@ �@�@���ʂ����㗬���́A���� �@�@���ʂ����㗬���́A����
�@�@ �@�@���ʂ��������́A�N���L��̗N�������� �@�@���ʂ��������́A�N���L��̗N��������
�@�߂��̌����̏C�i�r�ɂ��J���K���̃q�i���a���������Ƃ�m�����̂ŁA���A���ɍs�����B�܂����܂�Ă���Ȃɓ��ɂ����o���Ă��Ȃ��q�i�V�H���A�e�Ɏ���Ēr�ɂ����B�J���X���߂Â������ɂȂ����̂ŁA�e�́A�J���X���߂Â��Ȃ��悤�ɈЊd�����B�����J���X�̌��ނɋ��͂����B
�@�@ �@ �J���K����Ɓ@�i�e�ƃq�i���H�j �@ �J���K����Ɓ@�i�e�ƃq�i���H�j
�@�@ �@ �J���K����� �@ �J���K�����
�@�@ �@ �J���K����� �@ �J���K�����
|
|
|
|
| 2013�N6��3���i���j |
| ���ɁA�J���K���̃q�i�R�H |
�@���N�́A�Ȃ��Ȃ��J���K���̐������Ȃ��Ǝv���Ă������A�����A�W���S�T������A����Ɩ��ŃJ���K���̐e���R�H�̃q�i��A��Ă���̂��݂��B�q�i�͐��܂�Ă���A�P�T�Ԉȏ�͌o���Ă���悤�Ɋ����邪�A���ʂ����Ȃ����������ɂ������ƈړ����Ă����B�߂��ɂ����l�̘b�ł́A�ŏ��͂U�H�������A�R�H�Ɍ����Ă��܂����悤���B�B���Ƃ��낪���Ȃ����ł��A���Ƃ������Ɉ���Ă���邱�Ƃ����҂������B
�@�@ �@�J���K���P�Ɓi�e�ƃq�i�R�H�j �@�J���K���P�Ɓi�e�ƃq�i�R�H�j |
|
|
|
| 2013�N6��2���i���j |
| ���ɍ炭�A�������A���E�I�I�L���P�C�M�N |
�@�����A�������]�ԂŁA���\�Y������䓃�⋴�Ԃ����ĉ�����B
�@�����s�̋Ǝ҂ɂ�鑐���肪�A�s���Ă��āA�����Ԃ̉E�݂ł͑�����́A���łɏI����Ă����B�@�H�ƌ䓃�⋴�Ԃł͍��݂̑����肪�I����Ă����B
�@���T�́A�S���I�ȁu�g�߂Ȑ��̈�Ē����v���s���Ă��āA��㗬�ł��A���������������Ȃ��Ă����B
�@���ł́A�c�o���̎p�����������B�J�����q���̎p���������B���N�̓J���K���̐��̎p�́A���ł́A�܂����Ă��Ȃ��B
�@��������݂ŁA�I�I�L���P�C�M�N���炢�Ă����B�����~�ɍ~��āA���������Ă������B
�@�I�I�L���P�C�M�N�i����{�e�j�́A�A�����J���Y�̑��N���ŁA��������ɓ��{�ɂ����O���A���B�ɐB�͂������A�Ή��Ȃǂɗ��p���ꂽ���Ƃ�����B�悭�͐�~�⓹�H�����ɑ�Q��������B�ȑO�ɂ́A���������F�̉Ԃ�����̂ŁA�Ή��A���Ƃ��Ă��ϏܐA���Ƃ��Ă��D�܂ꂽ���Ƃ��������B�������A�ݗ���Ɉ��e����^���鋰�ꂪ�w�E����A2006�N�ɊO�������@�̓���O�������Ɏw�肳��A�͔|�E���n�E�̔��E�A�o���Ȃǂ��֎~���ꂽ�B������Ƒ�ύ���A���ł���B
�@�@ �@�I�I�L���P�C�M�N �@�I�I�L���P�C�M�N |
|
|
|
| 2013�N6��1���i�y�j |
| �����͈�������V����\���Ŋ������܂����B |
�@�ŏ��ɍ����V����\���̎O��s���ƐX�ƊG�{�̉Ƃ̑��d�ɈڐA�����t�W�o�J�}�U���́A���炪�͂��������Ȃ��A����v�����āA�V���ɒlj��ڐA���邱�Ƃɂ��܂����B����̗[���A����̒납�琶�炪�����t�W�o�J�}�R����lj��ڐA���A���̍ہA�u�ԂƖ�̔|�{�y�v�T�OL���lj����܂����B�����X���߂��A�G�{�̉Ƃ̑��d�̃t�W�o�J�}�ɐ����ɂ����܂����B����Ƃ���ڂ�Ƃ��Ă����̂ŁA���s���Ɣ��f���A������t���l�q���݂邱�Ƃɂ��܂����B�ߌ�R��������A�ēx���ɍs�Ă݂�ƁA�����z���グ�A�������肵�Ă��܂����B����ň���S�B
�@�@ �@�ڐA�����t�W�o�J�} �@�ڐA�����t�W�o�J�}
�@�ߑO�P�O������Q���ԂقǁA���ׂ̃R�X���X��قŁA���[�N�V���b�v�u �ǂ�Ȓ|�тɂȂ����炢���̂��H�v�����{�A�Q���҂͂P�T���B�R�ǂɕς�āA���[�N�V���b�v�̌��ʂ��܂Ƃ߁A�ǂ��Ƃɕ��Ă��炢�܂����B
�@�ߌ�P������Q���ԁB�����Q�P�����Q�����A�V����\���̒|�тŁA�|�і��x�Ǘ����������{���܂����B�����́A�ۑS�������傫�Ȗ̋߂��ɂ���|�̔��̂���ɍs���܂����B
�@�@ �@�|�т̃z�I�m�L�̎���̒|�̔��� �@�|�т̃z�I�m�L�̎���̒|�̔��� |
|
|
|
| 2013�N5��31���i���j |
| �s����w�����R�[�X�u���E�ɐ�������{�̏���ⳁv��Q�u |
�@�����́A�s����w�ŁA������w��w�@�������������ȋ����Ï���q�搶�́w�u�o�ψ��S�ەۏ�v���u�o�ςƈ��S�ۏ�v���x�Ƒ肷��u�`�����B�搶����́A����R��̍u�`���邪�A�����͂��̑�P��ڂ̍u�`�ł���A�@���S�ۏ�̊T�O�A�A���{�ɂ��Ă̗��j�I�l�@�A�B�u�o�ϓI�ȋ��Ђ���̈��S�ۏ�v�Ɓu�o�ϓI��i�ɂ����S�ۏ�v�A�C����̉ۑ�ɂ��Ă̍u�`���������B
�@�搶�̘b�ł́A�����W�ł́A����܂Łu���o�����v�ŁA���{�͌o�ς𒆐S�ɋ����W��i�߂Ă������A����͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ̂��Ƃł������B |
|
|
|
| 2013�N5��30���i�j |
| ���̑�����i�����s�j�Ǝ����� |
�@���ł́A�N�ɂR��A��ɍ����~�̑����肪�s����B���̍ہA�������̂̂��߂ɐ��ӂP�D�T���͈̔͂́A�����c���Ă���B�S�N�قǑO����A���͈̔͂��܂���������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�R���̈�Âɕ����āA�N�ɂP�x�����͕K������悤�ɂȂ��Ă���B���N�́A���̌䓃�⋴����Ԃ̑�����́A�P��ڂ͂T�����{����U�����{�A�Q��ڂ͂V�����{����W�����{�A�R��ڂ͂P�O�����{����P�P����{�ƌf������Ă���B
�@���̑�����̉Ǝ����̐ݒ�ɂ���ẮA���̐A�����傫�����E�����B���ۂɂǂ̂悤�ɂȂ�̂��́A����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��Ƃ����ŁA��여��A��������̕��ȉ�ł́A���̐��ӂŎ��ۂ̑�����������n�߂��B
�@�ł��A��...�����肵�Ă���̂́A�Ԃ��炫�A�킪���O�ɑ����������ƁA����ꂽ�쑐�́A�Ԃ��炩�Ȃ����A�킪�ł��Ȃ��̂ŁA�ɖ���͍̂���ɂȂ�B�Ӑ}�I�ɑ��₵�����쑐�́A����������Ȃ����A������̎��������炷���Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B
�@���̑��₵�����쑐�̈�Ɏ����̃t�W�o�J�}������B�����s�ɂ��肢���āA�����~�̈ꕔ�͈̔͂𑐊��肩�珜�O���Ă��������Ă���B���̑��A�����̃t�W�o�J�}�ȊO�͎��������ő���������邱�Ƃ��K�v�ł���A��ςł���B���N�łR�N�ڂł��邪�A���N����P��ڂ̑�����́A����I���A�����ɏ����͈͂��珜�O����Ă��邱�Ƃ������m�F�����B���N���t�W�o�J�}���A�Ԃ��炩���A��N�Ɠ��l�A�T�M�}�_�������̉Ԃ�K�₵�Ă���邱�Ƃ����҂������B�N�X�������ł͂��邪�A���������Ă��Ă���̂͂��ꂵ�����Ƃł���B�����ƌ���B
�@�@ �@�������̖�� �@�������̖��
�@�@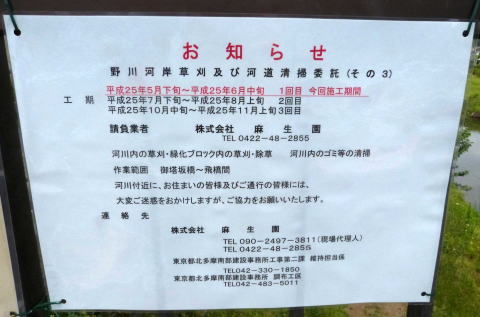 �@������̌f�� �@������̌f��
�@�@ �@��쎩���̃t�W�o�J�} �@��쎩���̃t�W�o�J�}
�@�@ �@�����̖�쎩���̃t�W�o�J�}�@�i���N�̏H�ɉԂ����҂ł���j �@�����̖�쎩���̃t�W�o�J�}�@�i���N�̏H�ɉԂ����҂ł���j
�@�@ �@�����̑����쎩���̃J�����i�f�V�R�i��N�ĂɉԂ��炢���j �@�����̑����쎩���̃J�����i�f�V�R�i��N�ĂɉԂ��炢���j |
|
|
|
| 2013�N5��29���i���j |
| ���l�̃z�e���ŁA��w�̃[�~�̓����� |
�@�����̒��A���l�R�������߂��̃z�e���j���[�O�����h�^���[�T�e�́u���E�m���}���f�B�v�ŁA��w�̃[�~�̓�������s�����B�[�~���w�����ꂽ�o���E���搶�́A���łɑ��E����Ă�������P�O�N�قnjo���A����������𑱂��A����o�ł̕��W�u�@�Ӂv���P�T������N�̂P�O���ɔ��s���Ă��邱�ƂɁA�搶�̉e���̑傫����������B
�@�����������l�ɏo������̂ŁA�������߂ɉƂ��o�āA��̑O�ɁA���߂ĉ��l���؊X�ƎR�����������w���Ă����B���{�X�D�X��ۂ̑D�������w�����B
�@�@ ���؊X�̑P�ז�
�@�@�@���{�X�D�X���
|
|
|
|
| 2013�N5��28���i�j |
| �Z���_���̉� |
�@���������R�ώ@���̃Z���_���̖ɁA���������F�̏����ȉԂ��[��ɂ���������Ă��܂����B
�@�@ �@�Z���_���̉� �@�Z���_���̉�
|
|
|
|
| 2013�N5��28���i�j |
| �_��A�������ɂ� |
�@������_��A�������ɗ���������B�����́A�Ԃ����̒c�̂̕��̎p�����������B���炢�Ă���̂́A�o���ƃT�c�L�ł���B�A�W�T�C���������炫�n�߂Ă����B
�@�@ �@�o���i�v�����Z�X�E�`�`�u�j �@�o���i�v�����Z�X�E�`�`�u�j
�@�@ �@�o���i�m�b�N�A�E�g�j �@�o���i�m�b�N�A�E�g�j
�@�@ �@�o���i�S�[���h�}���[�j �@�o���i�S�[���h�}���[�j
�@�@ �@�T�c�L �@�T�c�L
�@�@ �@�A�W�T�C �@�A�W�T�C
�@�@ �@�A�W�T�C �@�A�W�T�C
|
|
|
|
| 2013�N5��27���i���j |
| ���c�w�r���ŁA�F�Ƃ����̉�H |
| �@�����́A���c�܂ŏo�����āA�F�Ƃ����̉�H�����܂����B����������茳�C�ŁA�悩�����B�ߓ������́u��҂Ɂ@�E����Ȃ��@�S�V�̐S���@�`��ÂƖ���@�������āA���C�ɁA������������@�`�v��E�߂��A�A��ɏ��X�ő����w�����āA�ǂ�ł��܂��B�܂��r���ł����A�������̃q���g����R������Ă���悤���B
|
|
|
|
| 2013�N5��26���i���j |
| ���ɒ����N���ʂ̑���i�T���j |
�@����ƍ����̌ߑO���ɁA���ɒ����N���ʂ𑪒肵���B����_�́A�O��n��̂P�R�����ł���B�ꏊ�ɂ�胁�X�V�����_�[�Ȃǂ̗e��ɏW�߂āA���̎��Ԃ𑪒肵�āA�N���ʂ��v�Z����B�ꏊ�ɂ���āA���̗t�̕����𗬂��ė����𑪂�A����̕��Ɛ[���𑪂��ėN���ʂ��v�Z����B�ꏊ�ꏊ�ŁA����₷�����@�����߂đ��肵�Ă���B
�@���́A���������������̗N���̑�r������Ƃ��āA�������s�A������s�A�O��s�A���z�s�A���]�s�A���c�J��Ƃ���ɗN�����W�߂ė���A��q�ʐ�t�߂ő�����ƍ������钷����Q�O�����̂P���͐�ł���B�O��n��ł��A��ɍ��ۊ����w�\���⍑���V����\���̗{��Ƃ���N�����A���ɒ����ł���B���̗N���ʂ��������Ȃ��悤�ɂƊ肢�Ȃ���A����܂łR�N�]��̊ԁA�����P��̑���𑱂��Ă���B�N�Ԃł͂R������T�������A��ԗN���ʂ����Ȃ������ł���B
�@�@ �@�ق����i�����t�߁j�ł̑���̗l�q �@�ق����i�����t�߁j�ł̑���̗l�q
�@�@ �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q
�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q �@�㗬�ł̑���̗l�q
�@�@ �Y�㗬�ł̑���̗l�q �Y�㗬�ł̑���̗l�q
|
|
|
|
| 2013�N5��26���i���j |
| ����̖��̌��w�� |
�@����ߌ�A��여��A��������_�J������̈ē��ŁA�P������Ŋ��������X��R�O�����������w���ꂽ�B�R�[�X�́A�ߌ�P���ɖ������Ǘ����ɏW�����A����������N���L��A���R�ώ@���A�����ŕ�����������̒����r�A�r�I�g�[�v�r�A���R�Đ��n�A�N�W���R�A���̌�n�P�̐X���p�ّO��ʂ�A������s�����ʼnJ���Z���܂������w���A�Ō�Ɉӌ��������s�����B�ߌ�T���߂��Ɍ��w�I�������B������s�̑q����ƂƂ��ɁA�����A�_�J����̈ē��̃T�|�[�g���������Ă����������B
�@���ł́A�Ƒ�����̎q���������A��ɓ��菬���ȖԂ������ē�������Ă����B���ӂɗe�Ղɋߊ�����̂������i�ł������B���w�ɂ���炽���X���Ⴂ�l�����������悤�Ɋ������B
�@�@ �@�������t�߂� �@�������t�߂�
|
|
|
|
| 2013�N5��25���i�y�j |
| ���̓����� |
| �@���A�s���J�w�߂��̃��X�g�����ŁA��Q�̂��ߐ�iISO�i���E���V�X�e���̐R���@�ցj�̔N�P��̓�������s�����B�����͂P�O���B�����P�V�N�قǂ��������A�ސE���Ă�����A�݂�Ȃłł��邾���W�܂��Ă���B����̎Q���͂T�������B�����͂V���͏W�܂�B�����Ŏd���𑱂��Ă���l������A���̂悤�ɂ������藣��Ă��܂��Ă���l������B�K���A�e�l���A���̂P�N�ԁA�ǂ����Ă�������b������B |
|
|
|
| 2013�N5��24���i���j |
| �s����w�ŁA���u�Б�w��w�@�l��q�����̍u�`�����B |
�@�O��s�Љ���َ�Â̎s����w�����R�[�X�́u���E�ɐ�������{�̏���ⳁv�R�[�X�̑�P��̍u�`���n�܂����B�����́A���u�Б�w��w�@�r�W�l�X�����ȋ����̕l��q�搶�̍u�`�ł������B��ڂ́u�O���[�o���o�ςƓ��{�P�v�ł������B�{�N�x�͕l�搶����T��̍u�`���邱�ƂɂȂ�A���̑������̐搶��������e�_�̍u�`������B
�@�����̕l�搶�̍u�`�́A�ꖡ���s���A��ǂ݂Ȃ��b�������ށB�u�`�̑O���A����̓��{�̊����̖\���ɐG��A�A�x�m�~�b�N�X�͑��������_�𔘂��o���Ă���B���̂��Ƃ��A���̂T�̖��_�������Đ��������ꂽ�B�A
�@�Y�����Y�^���������`�ւ̎���
�A�~���_���^�A�o�����ւ̉�A
�B���_�Ԃ��^���Z�Ǘ��i����͒ʉ݂̔Ԑl�ŁA���{�ƓƗ�����������ێ����Ȃ���A����܂ŋ��Z�Ǘ������Ă������A���₻�̗��ꂪ�ێ�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���_�Ƃ͐��{�Ɠ���̊W�������Ă���j
�C�s���߂����s��Ƃ̑Θb
�D���O�����o�u���o�ω��̐i�s
�@�܂��A�u�`�̌㔼�ł́A���ʂ̐S�z�_�Ƃ���
�@������s����������邱�Ƃŋ��Q��������\��
�A�ʉݐ푈�i�בֈ����������j�̉\��
��������ꂽ�B
�@�搶�̂��l�������Ȃ�ɗ��������Ƃ���ł́A�l�搶�̗���́A�u���{�̂悤�Ȑ��n�����o�ςł́A�����̕K�v�Ȏ���͑��Ƃ��Ă���A���̖L�������O���[�o���ɕ��z���邱�Ƃ��l����ׂ������ɂ��Ă���A�ނ���~���ŁA�h�����[�g�T�O�~���炢�ɂ����ꗎ�������̂������v�Ƃ��l���̂悤�Ɏ~�߂��B���������āu�A�x�m�~�N�X�́A�ߋ��̖������Ă��āA�����̖��̂��߂ɂ͂������Ďז��ɂȂ�v�Ƃ̂��l���Ǝ~�߂��B�Ō�ɁA���₵�Ă݂܂����B�u�搶�́A�ʉݐ푈������A�����I�ɂ͑h�����[�g�����ǂT�O�~���炢�̉~���ɗ��������ƍl���Ă�����̂ł����H�v�ƁB�Ԏ��́u�C�G�X�B���������Ȃɒ����ł͂Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��ł����B
���ꂩ��A��R�����邱�Ƃ����肻�����B |
|
|
|
| 2013�N5��23���i�j |
| �����V����\���̒|�т����� |
�@�@�����́A�ߑO�P�O������R���Ԕ��قǁA���ʂɋ������������āA�����V����\���̒|�сi�V���O�j�̌���̉������s�����B�������̑O�ɁA�K�����������āA���S�̊m�ۂƍ�Ƃ̗\��𗧂ĂĂ���B
�i�P�j�܂��́A���̎����A⡂̐������C�ɂȂ�Ƃ���B��N�́A�T������U���ɂ́A⡂��悭�������āA�ق��Ă����Ƒ傫���Ȃ��Ŕ��̂���̂ɑ�ώ�Ԃ����������B�Ȃ�ׂ����������ɁA���u�����Ēu�������Ƃ���ł���B�Ƃ��낪���N�́A�v�����قǂ�⡂́A�����Ă��Ȃ������B�S�̓I�ɒ|�̐����������̂ŁA�n���s�ɉh�{���~�ς����ʂ��������Ă��邽�߂Ɛ��肵�Ă���B����ł��������Ă��Ă���⡂́A�����������B
�i�Q�j���̂����|�̒u����Ƃ��āA�P�ӂQ���̐����`�̂S���ɂS�{�̍Y��ł��A�����ɔ��̂����|���R���̒����ɓ������āA���R�Ɛςݏグ�Ă���B�����́A�`�]�[���ɂ��̍Y���S�{�ł��Ēu���������₵�āA���u���̒|��u���Ȃ������B
�i�R�j�o�Ă���T�T���A�ڗ����̂��������Ă������B
�@�̂���A�u�|�M�Ƃ������̂͂P�ɂP�{���悤�ɂ��Ă����ƁA�������肪�ǂ��A�����ڂ����ꂢ�ł���v�ƌ����Ă���B���̒|�т́A�܂��|�̖��x�̍����Ƃ���Ƃ����Ȃ肠�邪�A����ł��ȑO���́A�S�̓I�ɂ͂���Ɩ��邭�Ȃ��āA���ꂢ�ɂȂ��Ă������B���ꂵ�����Ƃł���B
�@�@ �@�`�]�[���̒|�̒u����� �@�`�]�[���̒|�̒u�����
|
|
|
|
| 2013�N5��22���i���j |
| ���������E���Ζ쒹�̐X�T���� |
�@�����́A�݂���o�X�ŁA���������E���Ζ쒹�̐X�T����ɏo�����Ă��܂����B�����̂�����C�������ς��z������ł��܂����B�����������猩��x�m�R�ɂ͏����_���������Ă��܂����B�����̉����̖Ƀz�I�A�J���Ƃ܂��Ă��܂����B���}�c�c�W�炢�Ă��܂����B�n���T�L���}�K���V�̉ԂɃE�X�o�V���`���E���Ƃ܂��Ă��܂����B���Ζ쒹�̐X�ł́A�J�����q���̎p�����܂����B
�@��������ŁA�F�ŁA�m�F�ł����g���̎�ނ͂R�R��ł����B���ɂ͎p�͌������A�������Ŋm�F�������̂�����܂����B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
�@�@ �@�z�I�A�J �@�z�I�A�J
�@�@ �@���}�c�c�W �@���}�c�c�W
�@�@ �@�E�X�o�V���`���E �@�E�X�o�V���`���E
�@�@ �@�J�����q�� �@�J�����q��
|
|
|
|
| 2013�N5��21���i�j |
| �����A�V�W���E�J�����A�����T�H�������܂����B |
�@�������A�S��������V�W���E�J���������ɉa���^��ł����B�W���߂��q�i�����߂đ����̌��������̂��������B���C�ȃq�i���ŏ��ɔ�ї����A�����Ɏ����������B���̌サ�炭���āA�c��̂R�H��������ї����A�S���Ńq�i�T�H�������ɔ�ї������B
�@�@ �@�V�W���E�J���̑����� �@�V�W���E�J���̑�����
�V�W���E�J���̑������̓���́A���L�ł݂邱�Ƃ��ł��܂��B
�ŏ��̂Q�H�@�@http://www.youtube.com/watch?v=sVXsr22LOOQ&feature=youtu.be
��̂R�H�@�@�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2A4lLky9Gow
|
|
|
|
| 2013�N5��20���i���j |
| �@�J�̓����A�V�W���E�J���͉a�𑃂ɉ^��ł���B |
�@�����́A�J�̓��ɂȂ��Ă��܂����B����ł��V�W���E�J���́A����ɉa�𑃔��ɉ^��ł���B�������́A���Ȃ�߂��Ȃ��Ă����悤���B
�@������o�Ă���Ƃ��ɂ́A�������́i�t���j�����킦�Ă���B���̒������ꂢ�ɂ��Ă���悤���B
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J�� |
|
|
|
| 2013�N5��19���i���j |
| ��ŁA�o���u�o�����[�i�v���炫�n�߂܂����B |
�@���A�䂪�Ƃ̒�ŁA�u�o�����[�i�v�Ƃ������̃o�����炫�͂��߂܂����B���|��ŁA��d�炫�̏��ւ̃o���ł����A�s���N�F�̒��S�ɔ�������A�F�������ƂĂ��������B
�@�@ �@�o���u�o�����[�i�v �@�o���u�o�����[�i�v
�@�@ �@�o���u�o�����[�i�v �@�o���u�o�����[�i�v
�@�@ �@�o���u�o�����[�i�v �@�o���u�o�����[�i�v
|
|
|
|
| 2013�N5��18���i�y�j |
| �@�����V����\���ł́A�{�����e�B�A���� |
�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̒�ኈ�����ł������B�ߌ�P������Q���ԁA�����V����\���i��V���w�Z�O�̒|�тŁj�Œ|�т̖��x�Ǘ��������s�����B�Q���҂͂P�U���B�����̓��e�́A�����^���A�Ǖ����A�O���S�O���̍�ƂƂP�T���̋x�e�A�㔼�S�O���̍�ƁA�Ō�ɂӂ肩����Ǝʐ^�B�e���s�����B�|�̂��A�ʐ肵�A�}���A��߂��ꏊ�ɐ��R�ƒu���B�����́A��T�O�{�̒|�̂��A�����������B
�@���P��A�Q�N�Ԃ̊����ŁA�|�т́A���������邭�Ȃ�A�������肵���|�тɕς��Ă������Ƃ������ł���悤�ɂȂ����B���ꂵ�����Ƃł��B
|
|
|
|
| 2013�N5��18���i�y�j |
| �A�}�����X�̉� |
�@����A���A���̃A�}�����X�̉Ԃ��炫�܂����B���N�łP�O�N�ڂł��B�Q�O�O�S�N����Q�O�P�O�N�܂ł́A���N�S�ւ̉Ԃ����܂����B�Q�O�P�P�N�́A�������������߂��Ԃ͍炫�܂���ł����B���Q�O�P�Q�N����́A�Q�ւ̉Ԃ������܂����B���N���Q�ւɂȂ肻���ł��B
�@�A�}�����X�́A��A�����J���Y�ł��B�U�ق̑傫�ȉԂ������ł��B���|��Ƃ��āA�Ԃ̐F�͂��낢��Ȃ��̂�����悤�ł��B
�@�@ �A�}�����X�̉� �A�}�����X�̉� |
|
|
|
| 2013�N5��17���i���j |
| ��������A�s����w�����R�[�X���J�u |
�@��������A�O��s�Љ���َ�Â̎s����w�����R�[�X���J�u�����B�R�[�X�́A���N�łS�U�N�ڂƂȂ�A��������u�w�K�̎�͎̂s���ɂ���v�Ƃ̖�����f���A�s�����g���A���E�^�c���Ă����`��������B�e�R�[�X�ɂ́A��N�ԂɂR�O��̌p���w�K���Ԃ�����A�[�~�i�[���`���Ői�߂���B
�@���́A��C�u�t�l��q����i���u�Б�w��w�@�r�W�l�X�����ȋ����j�A�R�[�X���F�u���E�ɐ�������{�̏���ⳁ`�����o�ς̎��_�Ł`�v����u����B���̍u���͓��Ɋ�]�҂������A���I�Ŏ�u�҂����܂����B���I���͖�R�O�����x�ƘR�ꕷ���Ă���B�K���ɂ����͒��I�ɓ�����A��u���邱�Ƃ��ł���B�����́A�J�Z���ƁA�I���G���e�[�V�����A��u�҂̎��ȏЉ�ƁA�^�c�ψ��̑I�o�Ȃǂ��s�����B���T�̋��j������A���悢��u�`���n�܂�B
�@�@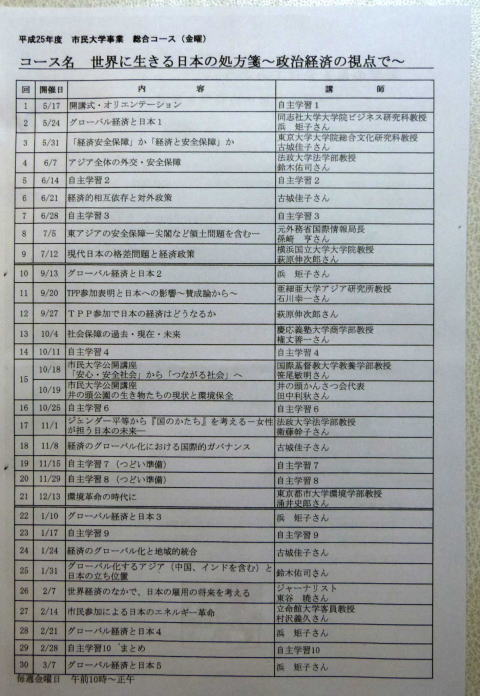 �@�R�[�X�̃v���O���� �@�R�[�X�̃v���O���� |
|
|
|
| 2013�N5��16���i�j |
| ���̎��R�ώ@�� |
�@�ߑO���A�u���̎��R�ώ@��v���s�����B���̕x�m���勴�`���\���ԂŁA���̐A���A���������ώ@���A���R�Ƃ̋����̂��߂ɉ�����������̂��ƁA�����l���邫�������Ƃ������Ƃ̎v������ł���B�u�݂������̉�v�̉���U���ƁA��ʎQ���҂V���̑����P�R�������̏����Ȋώ@��ł���B
�@�A���ɂ��ẮA�ڂɂ����̂͂قƂ�ǂ��O���A���ł��邱�Ƃ�m�炳�ꂽ�B�L�V���E�u�A�i�K�~�q�i�Q�V�A�C���J�^�o�~�A�A�����J�t�[���A�I�I�J���a�V���A�j�Z�A�J�V�A�ȂǁB��R�̍��������������Ă������A�������Ď��ɂ͖��O�͂悭�킩��Ȃ��B���̐��ӂɂ̓V�I�J���g���{�̎p���������B
�I����A�L�u�ŁA�����`�����ꏏ�����B������y�����ЂƂƂ��ł������B
�@�@ �@�L�V���E�u �@�L�V���E�u
|
|
|
|
| 2013�N5��15���i���j |
| �V�W���E�J���̎q��� |
�@������A�V�W���E�J���̗Y�A���Ƃ����݂ɉa�𑃔��ɉ^��ł���B���̋߂��ɗ��Ă���A���ɒ��ɓ��鎞�ɂ͂Ȃ��Ȃ��T�d�ł��B���肩���āA�����Ԃ����Ƃ�����܂��B�ł��m���ɉa���^��ł���B����ɂƂ�܂����̂Ō��Ă��������B
���L�̂t�q�k�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZgjaWQNaleQ
|
|
|
|
| 2013�N5��14���i�j |
| ���̗��ʑ���i�T���j |
�@�ߑO���A���̗��ʑ�����O��s���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ōs�����B������l�Ŏ��{���Ă���B�R���̑���l�����N�̍Œ�l�ł��������A�S���A�T���Ǝ�����Ă��Ă���B�ł��A�܂��܂��������x���A���͗���ł���B
�����Q�Q�N�P������A�����P������Ă��Ă���A��N���܂ł̂R�N�Ԃ̃f�[�^�\�́A���̂g�o�u�V�j�A����v�̊ώ@�i���̗N���ʁA���ʁj�̃y�[�Whttp://homepage2.nifty.com/adam-san/report/report1.html�ł݂邱�Ƃ��ł���B��여��A����́u�Ȃ��Ƃ����ʁv���ȉ�ŕ��Ă���B����́A�ȕւȕ��q�𗬂������𑪂���@�ł��邪�A���̗��ʂ̔N�Ԃ̕ω����ώ@���邱�Ƃ��ł���B
�@�@ �ł̑���̗l�q �ł̑���̗l�q
|
|
|
|
| 2013�N5��13���i���j |
| ���̑�����̎��� |
�@�������Ă����여��A����������ȉ�ł́A������̎����A��ς���Ɛ�ӂ̐A���ɂǂ̂悤�ȈႢ���ł邩���A�f�l�ł����邪�A�Ƃɂ����ψ����g�Ŏ������Ă݂邱�ƂɂȂ�A�܂��挎����������ꏊ�̑I����s���A��������������J�n���邱�ƂɂȂ����B�����ߌ�ɁA��P��ڂ̊ώ@�Ƒ�������s�����B��ׂ�ɂT�����T���̕��`�̃G���A���W�����ݒ肵�āA���̑S�͈͂̊ώ@�ƂQ�����̃G���A�̑�������s�����B���̂悤�Ȋ������s�����ƂŁA�������ɂ��Ẳ�X�̗����������͐[�܂邱�Ƃ����҂��Ă���B���ʂ��o����A���Ƃ�����b�����ƂɂȂ�Ǝv���B
�@ �@�@������̗l�q �@�@������̗l�q
�@ |
|
|
|
| 2013�N5��13���i���j |
| �A�����Z�E�c�{ |
�@�J���⡂ɗႦ��Ƃ����߂���������Ȃ����A�ŋߖ��ł悭���Z�E�c�{����������B�k�A�t���J���Y�̊A���ł���B�}���Ȃ�A�L�N�Ȃ�Z���Ȃ̐A���Ɋ���B���ł́A�}���Ȃ̃V���c���N�T�Ɋ��Ă���Ƃ������������B�ł��v���ӊO���A���Ɏw�肳��Ă���A���ł���B���Z�E�c�{�́A�h�{�̂��ׂĂ������A���Ɉˑ����Ă��邽�߁A���g�͗t�Αf�������Ă��Ȃ��B���̂��߂��A�S�̓I�Ɋ��F�ł���B�Ԋ��͂T���`�U���ŁA�O�`�̉Ԃ��炩����B�������̂ɃX�X�L�ȂǂɊ���i���o���M�[�������邪�A������͂��ꂢ�ł���B���̉Ԋ��͂V���`�X���ł���B
�@�@ �@���Z�E�c�{ �@���Z�E�c�{
�@�@ �@���Z�E�c�{ �@���Z�E�c�{ |
|
|
|
| 2013�N5��12���i���j |
| �G�S�m�L�̉� |
�@�����ɁA���������R�ώ@���̒���������B�����̃G�S�m�L�ɂ͉Ԃ����n�߂��B�Ԃ́A�������^�ȉԂŁA�}�����ς��ɉ������ɂ��B�炫���낤�����ɂ́A�ꎞ�����͂����邭������B���̖̎��i�ʔ�j�ɂ́A�L�łȕ������܂܂�Ă��āA�́A���̕ߊl�Ɏg��ꂽ���Ƃ��������B�L�łł͂��邪�A�Ȃ������}�K���́A���̎����D�݁A����������ɂ́A�G�S�m�L�ŁA���}�K�����悭��������B
�@�@ �@�G�S�m�L�̉� �@�G�S�m�L�̉�
�@�@ �@�G�S�m�L�̉� �@�G�S�m�L�̉�
�@�@ �@�G�S�̖̉� �@�G�S�̖̉�
�@�ߑO���A�������̈���{�����e�B�A�̉�̑���������B�o�^���Ă���{�����e�B�A�͂P�O�O����ł��邪�A�����͖�S�O�����o�Ȃ����B��Ȋ����́A���R�ώ@���̈ێ��Ǘ������ł���B���R�ώ@���ɂ́A���{�͂S�U�S��A�ؖ{�͂P�R�P�킪����B�ߌ�́A���S�Ǘ��u�K�����A����ɂ��o�Ȃ����B
|
|
|
|
| 2013�N5��11���i�y�j |
| �V�W���E�J���̑��� |
�@������A��̃V�W���E�J���̑������ώ@���Ă���B�����́A���A�Ԃ��炩���Ă���}���~�̖ɂ��Ă���B�V�W���E�J���̗Y����ɉa���^��ł���B���ł���B���Ȃ�傫���̂ŁA���͛z�����Ă���A���Ȃ肽���Ă���悤�Ɋ�����B�p�x�ł����A���͓��ɕp�ɂ̂悤�Ɋ�����B�V������W�����܂łɁA�P�S��^��ł����B���̂������X�͂Q���B�����ɂ��ƁA�������Ԃ́A�P�Q���`�P�S���ŁA���͛z�����Ă���P�U���`�P�X���ő��������ł���B�䂪�Ƃ��������́A�����߂��̂ł͂Ȃ��Ɗ�����B
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@���������o���V�W���E�J�� �@���������o���V�W���E�J��
�@�@ �@�}���~�̖ɂ������� �@�}���~�̖ɂ�������
�@�@ �@�}���~�̉� �@�}���~�̉�
|
|
|
|
| 2013�N5��10���i���j |
| ���̉ԁ������� |
�@����A�������Ō���쒹�ώ@���s�����B�~���͋���A�Ē��̓L�r�^�L�A�c�o�����炢�ŁA�쒹�̎p�͏��Ȃ������B�����̒��ł́A�����Ԃ����Ă���B�^�j�E�c�M�A�g�`�m�L�A�~�Y�L�A�T���t�^�M�Ȃǂł���B
�@�@ �@�^�j�E�c�M �@�^�j�E�c�M
�@�@ �@�g�`�m�L �@�g�`�m�L
�@�@ �@�~�Y�L �@�~�Y�L
�@�@ �@�T���t�^�M �@�T���t�^�M
�@�@ |
|
|
|
| 2013�N5��9���i�j |
| ���������J���E�̌̂����������B |
�@���N�̂S���Q�X���ɁA���̔��ŗ����ɑ��������J���E�ɋC���t�����̂ŁA�����̏����ʐ^��t���āA�A����̈�ł���R�K���ތ������ɕ��܂����B�����A����������ʐ^�����������P�݂̂̂��Y������Ƃ̘A���������܂����B����ɂ��ƁA�Q�O�O�V�N�R���P�V���ɓ����s�`���U���i���̓��j�ŕ��������J���E�̃q�i���Y�����邻���ł��B�u�̂����肳��܂����̂ŁA�u�W��������L�^�v�Ƃ��Đ����ɓo�^�v���܂��B�v�Ƃ̂��Ƃł��B
�@�@ �@�S���Q�X���ɎB�e�����J���E�̎ʐ^ �@�S���Q�X���ɎB�e�����J���E�̎ʐ^
|
|
|
|
| 2013�N5��8���i���j |
| �u�^�i |
�@�u�^�i�́A���[���b�p���Y�̑��N���A�O���A���B�L�N�ȃG�]�R�E�]���i���B��������̂悢���[�Ȃǂɐ�����B�n�ۂŗt���L���A�^�Ȃ�Ԃ̌s���̂��B�t�����X���́u�u�^�̃T���_�v�B
�ʐ^�́A�����V����\���ŎB�e�����B
�@�@ �@�u�^�i�̉� �@�u�^�i�̉�
�@�@ �@�u�^�i�̗t �@�u�^�i�̗t
�@���́A���������C��Ȃ̂ŁA�A���������s�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B����A�G�{�̉Ƃ̒�ɈڐA�����t�W�o�J�}�ƃJ�����i�f�V�R���C�ɂȂ��Ă���B�����́A�|�т̉����ɍs���ۂɁA�������A�����������Ă����������B�����Ɉ���āA�ǂ�ǂ����Ăق����B
|
|
|
|
| 2013�N5��7���i�j |
| �I�L�i�O�T�̉ʎ� |
�@���������R�ώ@���ɂ́A�I�L�i�O�T�������Ă���B�L���|�E�Q�ȃI�L�i�O�T���̑��N���ł���B�Ԋ��͂R������ŁA���́A�H�я�ɂ̂т��ʎ������Ă���B�����V�l�̔����Ɍ����ĂāA�I�L�i�O�T�̖��O�ƂȂ����悤�ł���B
�@�@ �@�I�L�i�O�T�̎Ⴂ�ʎ� �@�I�L�i�O�T�̎Ⴂ�ʎ�
�@�@ �@���ɔ����Ղ��Ȃ����I�L�i�O�T�̉ʎ��̏W�܂� �@���ɔ����Ղ��Ȃ����I�L�i�O�T�̉ʎ��̏W�܂�
�@�@ �@�Q�l�F�R���Q�R���ɎB�e�����I�L�i�O�T�̉� �@�Q�l�F�R���Q�R���ɎB�e�����I�L�i�O�T�̉� |
|
|
|
| 2013�N5��6���i���j |
| ��앗�i |
�@�����́A�A�x�̍ŏI���A���̗��ł́A�Q���Q���̏�Ɍ�̂ڂ肪�A���ɂȂт��Ă����B
�@�@ �@ ��̂ڂ� �@ ��̂ڂ�
�N���L��t�߂̖��ł́A�q���������Ԃ������āA���̐������̂�ǂ������Ă����B
�@�@ �@���ŗV�Ԏq������ �@���ŗV�Ԏq������
���R�ώ@���̒��ł́A�g�E�_�C�O�T���Ђ�����炢�Ă����B
�@�@ �@�g�E�_�C�O�T �@�g�E�_�C�O�T
|
|
|
|
| 2013�N5��5���i���j |
| ���������R�ώ@���̖쑐 |
�@�����A�����ɖ��������R�ώ@���ɍs�����B�P���Ԃقlj������݂��B
�n���V���E�Y���i�������j���炢�Ă����B�ȑO�͂Ȃ������̂ŁA���߂Ă݂��B
�L���|�E�Q�ȃZ���j���\�E���̂�A���@�Ԃ̌`�������Ɏ��Ă��邱�Ƃ��炱�̖��������B�w��clematis japonica
�@�@ �@�n���V���E�Y�� �@�n���V���E�Y��
�@�@ �@�n���V���E�Y�� �@�n���V���E�Y��
�J�����i�f�V�R���Q�֍炢�Ă����̂ŋ������B�Ԋ��́A�ʏ�͂V������P�O���ł���B�����炫���H�@������������B
�@�@ �@�J�����i�f�V�R �@�J�����i�f�V�R
�z�^���J�Y�����A�Q���������B
�@�@ �@�z�^���J�Y�� �@�z�^���J�Y��
���̑��A�`���E�W�\�E�A�E�}�m�A�V�K�^�A�L���������炢�Ă����B
�@�@ �@�`���E�W�\�E �@�`���E�W�\�E
�@ �@�L������ �@�L������
|
|
|
|
| 2013�@�N5��5���i���j |
| �V�W���E�J���̑��Â��� |
�@��̃}���~�̖ɂ����V�W���E�J���̑��ɁA�������T���߂�����V�W���E�J��������ɉa���^��ł���B�^�Ԃ̂̓I�X�ŁA���X�͑��̒��ɂ��āA���X�O�ɏo�Ă����悤���B��N���߂ăV�W���E�J�������������āA�����W�H���T���Q�R���ɑ������Ă����܂����B���N���A�����������Ƃ�����Ă��܂��B
�@�@ �@�V�W���E�J�����a���^��ł��܂����B �@�V�W���E�J�����a���^��ł��܂����B
�@�@ �@�V�W���E�J�������ɓ��낤�Ƃ��Ă܂��B �@�V�W���E�J�������ɓ��낤�Ƃ��Ă܂��B
�@�@ �@�V�W���E�J���̔��������܂��B �@�V�W���E�J���̔��������܂��B
�@�@ �@�V�W���E�J�����o�Ă��܂����B�������킦�Ă��܂���B �@�V�W���E�J�����o�Ă��܂����B�������킦�Ă��܂���B
�@�@ �@�V�W���E�J���������痣��܂����B �@�V�W���E�J���������痣��܂����B
�@��N�̓���́Atou-tube�ɂ���܂��B���L��URL�ł݂邱�Ƃ��ł��܂��B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gc8wHMRXIhc
|
|
|
|
| 2013�N5��4���i�y�j |
| �������{�@�����e�B�A��ኈ�����i�T/�S�j |
�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ�����ł���B�{�����e�B�A�́A���g�̃O���[�v�ɕʂ�Ċ������s�����B���́A�Z���o�q�G���\�E�̏������s���O���[�v�ɉ�����āA�Q���Ԏ�̊����������B����ȉԂ����邪�A���������č����Ă���쑐�ł���B���N�͓��ɍL���ɐB���Ă��܂����悤���B���A�Ԃ̎����ɏ��������Ă��܂�Ȃ��ƁA�����Ȃ��Ă͗��N�͑����č���B���R�ώ@���ł̃{�����e�B�A�̊����̑唼�́A�����ł���Ɗ����Ă���B��Ȃ��̂��c���ɂ́A��ȍ�Ƃł���B
�@���������R�ώ@���ł́A���N�����\�E���炢�Ă����B�N�����\�E�́A�T�N���\�E�̒��Ԃł��邪�A��r�I�����ȏꏊ�ɐ��炷��B�����́A�߂��ɃJ���K���̃y�A�������B
�@�@ �N�����\�E�ƃJ���K���y�A �N�����\�E�ƃJ���K���y�A
�@�@ �@�N�����\�E �@�N�����\�E
�@�@ �@�N�����\�E �@�N�����\�E
�@�@ �@�N�����\�E�i���j �@�N�����\�E�i���j
|
|
|
|
| 2013�N5��3���i���j |
| ���n��W�����ɁA�r�܂� |
�@ �ߌ�A�r�܂̌|�p����T�K�̉��ɁA���n�W�����ɏo�����Ă��܂����B��w�̗F�B���ސE��Ɏn�߂����n��̎t�̌W���Ƃ������ƂŁA�ē������������܂����B��i�́A�x�m�R�A�ܓc�̑�A�k�J�Ȃǂ�����̂����������B�F�B���ꏏ�ɉ���āA���������Ă��ꂽ�B
�@�@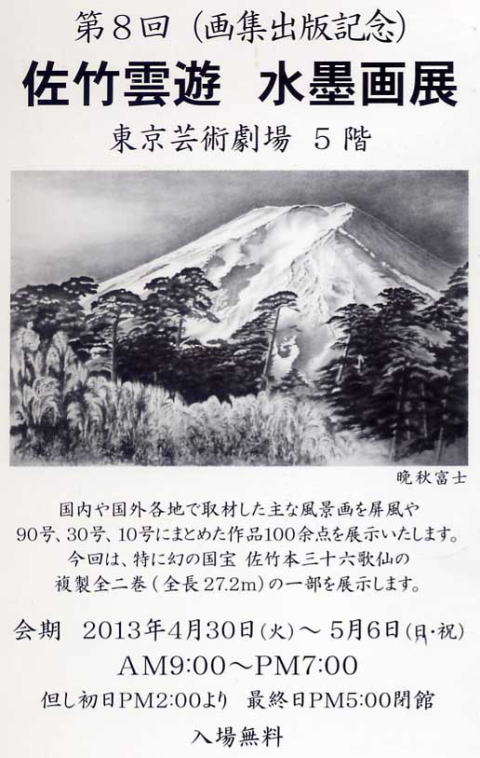 ���n��W�̈ē� ���n��W�̈ē�
|
|
|
|
| 2013�N5��2���i�j |
| ����O�������i�A���j�I�I�J���a�V���̏��� |
�@�ߌ�A����ė����̂ŁA���̑��\�Y������쐅���܂ł̊ԂŁA���ӂ̓���O�������i�A���j�I�I�J���a�V���̏������Q���ԂقǍs�����B�����x�I�I�C�k�m�t�O���̂悤�ȉԂ����Ă��āA�Q�����ڗ��B
�@�@ �I�I�J���a�V�� �I�I�J���a�V��
�@ �����悤�Ȑ��ӂɃI�����_�K���V�i�ʖ��N���\���j�������Ă���B�������̕t��������T���_�Ȃǂɂ��g���Ă���A���ł���B�H�p�ɂ͍͔|�������Ȃ��邪�A�쐶�����Ă��Ė��ł��悭��������B���Ԃ̎����ł���B
�@�@ �N���\�� �N���\��
�@�@ �N���\���̉� �N���\���̉�
|
|
|
|
| 2013�N5��1���i���j |
| �~�̉ԋg�ˎ��X�ŁA�����̉�H |
�@�����́A���}�f�p�[�g�̂X�K�ɂ���~�̉ԋg�ˎ��X�ŁA��ڂ̂��߂ňꏏ���������Ƃ����̉�H�������B���̓X�͗\�������ƌ������p�ł��A�����������͋C�ŁA��b���y���߂�̂ŋC�ɓ����Ă���B���݂������N�Ȃ̂ŁA�a�C�̘b�A�o�ς̘b�A�A���H���̘b�Ȃǎ��Ԃ�����Ȃ������B
�s�������ɂ́A��̓���������ʂ蔲���Ă����B��a�R�ł́A�L���������炢�Ă����B�䒃�m�����璭�߂鎵�䋴�ɂ́A�l�̎p�͂��܂葽���͂Ȃ������B
�@�@ �L������ �L������
�@�@ �@���䋴���] �@���䋴���]
|
|
|
|
| 2013�N4��30���i�j |
| �����V������� |
�@�������܂��Ă����̂ŁA�ߌ�R�����납��A�V����̎������܂�肵�܂����B
�@�@ �@ �@
�{�����e�B�A�����Ă��鍑���V����\���i�V���O�j�̒|�т̊O����`���Ă݂܂����B
�@�@ �@ �@
���̗��ɂ́A��̂ڂ肪���C�悭�̂ڂ��Ă��܂����B
�@�@ �@ �@
�����̖��Ńo���̎p���������܂����B���x����n�p���̑O�ł��B
�o���̓�����Ƃ�܂����B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oiEFZKdw7gY
�@�@ �@�@�@ �@�@�@
�����V���䐳��t�߂ŁA�W���E�j�q�g�G���c���Ă��܂����B
|
|
|
|
| 2013�N4��29���i���j |
| ���U�� |
�@��^�A�x�R���ځA�����ӂ��U�܂����B������̏㗬������A���̗��A�����ԉ��A���R�ώ@�������Ă���A���̍�����������Ԃ��āA�����̑�܂ł����������܂����B
�@�ł̓J���E�̎p�����܂����B���̗��ɂ́A��̂ڂ肪�g����A�J�����}�����A���������̂�҂��Ă��܂����B�����ԉ��ŁA�A�I�W�ɂ����܂����B���ʂ����㗬�ł́A�����I�I�u�^�N�T�̉�����݂����܂����B���R�ώ@���ł́A���I�h���R�\�E�̌Q�����A���J�ł����B�L���������炢�Ă��܂����B���r�ɂ́A�܂���������܂����B���̃z�^����t�߂ɂ́A�q����������R�V��ł��܂����B�N���L��ł������ł����B��쉈��������Ƒ����ꂪ�A��R���܂����B
�@�����͉J���~��悤�Ȃ̂ŁA�����A�O�ɏo��̂������ł��傤�B�@�i�P�T�T�O�O���j
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
�@�@ �@�I�h���R�\�E �@�I�h���R�\�E
�@�@ �@�L������ �@�L������
�@�@ �@�Z�O���Z�L���C �@�Z�O���Z�L���C
|
|
|
|
| 2013�N4��28���i���j |
| �X�Y�������� |
�@�����ŁA�X�Y�������炢�Ă���B
�@���������������Ă����B�����Ƒ����Ăق����B
�@�@ �@�X�Y���� �@�X�Y����
�@�@ �@�X�Y���� �@�X�Y����
|
|
|
|
| 2013�N4��27���i�y�j |
| �̃{�����e�B�A�A���� |
�@�ߑO���A��������̃{�����e�B�A�O���[�v�̘A����������B�A����́A�X�N�ԁA���N�����Ȃ�ꂽ�̃{�����e�B�A�u���i�S�U��̘A���u���j�̏C������P�Q�O����ΏۂɁA�o�Ȃ����肢���Ă���B�����̘A����ɂ͂��̂����̖�P�V���̂Q�O���قǂ̏o�ȂɂƂǂ܂����B�ߌ�́A�Q���ԂقǓV����|�тł̖��x�Ǘ��̒�ኈ�����s�����B�O���́A�ۑ����̎���̒|�̔��́A�㔼�́A�̂юn�߂�⡂̖��x�Ǘ������ł������B
�@�@ �@�^�P�m�R �@�^�P�m�R
�@��Ƃ��I����āA�߂�������ƁA��ɗ��t�W�����h�ȉԂ����Ă����B
�@�@ �@�t�W �@�t�W
�@�@ �@�t�W �@�t�W
|
|
|
|
| 2013�N4��26���i���j |
| �O��s�̐��ƐX�ƊG�{�̉Ƃ̖쑐�i�J�����i�f�V�R�ƃt�W�o�J�}�j |
�@�����V����̍\���ɁA�O��s�̐��ƐX�ƊG�{�̉Ƃ�����B�ߑO���A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�S�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�U���̈ڐA�i�n�A���j�̂���`���ɏo�������B�{�����e�B�A�̂m����ƐE���̂s����Ǝ��̂R�l�ŁA�Q���Ԃقǂ����ă|�b�g�c�̈ڐA���s�����B
�J�����i�f�V�R�́A�G�{�̉Ƃ̖�����������̃J�c���̖̎���ɂQ�Q���ƁA�������ĉE���̉Ԓd�ɂP�W�����ڐA�A�t�W�o�J�}�́A���̑��d�̈ꕔ�ɂU�����ڐA�����B���ꂼ�ꂪ�����ꏊ�Ɏ��܂����̂ŁA�喞���I
�@�Ԃ̍炭�G�߂��y���݂ł���B
�@�@ �J�c���̖̎���̃J�����i�f�V�R�̕c�i�����̔����قǁj �J�c���̖̎���̃J�����i�f�V�R�̕c�i�����̔����قǁj
�@�@ �@�E���̉Ԓd�̒��̃J�����i�f�V�R�̕c �@�E���̉Ԓd�̒��̃J�����i�f�V�R�̕c
�@�@ �@���d�̒[�̃t�W�o�J�}�̕c �@���d�̒[�̃t�W�o�J�}�̕c |
|
|
|
| 2013�N4��25���i�j |
| �s����ԎR�����̃��T�V�m�L�X�Q |
�@�ߌ�A�����쉀�ׂ̗ɂ���s����ԎR�i�����܁j�����̃��T�V�m�L�X�Q�̗l�q�����ɂ����Ă��܂����B�����͍炫�n�߂Ă�����̂�����܂������A��͂�T���̘A�x���炪������ɂȂ�悤�ł��B�L�������A�M�������͂����A���Ȃ�炢�Ă��܂����B
�@�@ �@���T�V�m�L�X�Q�̈ē��� �@���T�V�m�L�X�Q�̈ē���
�@�@ �@���T�V�m�L�X�Q �@���T�V�m�L�X�Q
�@�@ �@�L������ �@�L������
�@�@ �@�M������ �@�M������
�@�A��́A����������A���������̖��ɉ����ē���ʂ��ċA���ė��܂����B�r���́A�㗬�Ƒ��\�Y�������ŁA�C�ɂȂ��Ă����I�I�J���a�V���̏������s���܂����B�߂��ɃJ���Z�~�����܂����B���ł����B
�@�@ �@�I�I�J���a�V�� �@�I�I�J���a�V��
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
|
|
|
|
| 2013�N4��24���i���j |
| ���c�ЕF���������和�̕��� |
�@�����V����\���̒|�т̖��x�Ǘ��������{�����e�B�A�ōs���Ă��邪�A���̒|�тׂ̗Ɂu�O�鍑�ە��v�Ղ�����B���a�̎����A�U�O���̍����ɃA���e�i��t����S�����������B���݂́A���łɌ����͂Ȃ��A������̖和�Q�{�������c���Ă���B���̉E���̖和�ɂ́u�O�鍑�ە��v�̕�����������Ă���B�������悭�ǂ�ł݂���A���̕����͎��c�ЕF�i�����w�ҁA���M�Ɓj�������Ă��̂ł������B�M�d�Ȃ��̂��I
�@�@ �@ �和�̕��� �@ �和�̕���
|
|
|
|
| 2013�N4��23���i�j |
| �I�[�v���K�[�f�� |
�@�߂��̂����I�[�v���K�[�f���̈ē��������������̂ŁA�q�������Ă�������B�ē��ɂ́A�u�I�[�v���K�[�f���Ƃ́A�l�̒�����Ԍ���ŊJ�����A�n��̔����Ɋ�^����{�����e�B�A�����ł��v�Ə�����Ă����B�E�b�h�f�b�L�̏�ɂ͂́A�P�O�N�]�肩���Ĉ�Ă����h�ȓ��I���������B
�@�@ �@���I �@���I
�A��̓��A�ʂ̉Ƃ̒�Ńc�c�W�����ꂢ�ɍ炢�Ă����B
�@�@ �c�c�W �c�c�W
|
|
|
|
| 2013�N4��22���i���j |
| �I�i�K�A�J���Z�~�A�R�K���������� |
�@�ߌ�A������s�̓V�_���܂ŏo�����܂����B�ړI�́A��여��A��������̕��ȉ�̃����o�[�ŁA������̎����̈Ⴂ���A�A���̐���ɗ^����e���̒������s���ꏊ�̑I��̂��߂ł���B
�@�r���̖��ŁA�I�i�K�A�J���Z�~�A�R�K�����������܂����B
�@�@ �@�I�i�K �@�I�i�K
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�@�@ �@�R�K�� �@�R�K��
|
|
|
|
| 2013�N4��21���i���j |
| �_��A�������̍��炢�Ă���ԁF�V���N�i�Q�A�t�W�A�n���J�`�m�L�Ȃ� |
�@�ߌ�J���~�̂ŁA�_��A�������ƐA�����l���Z���^�[�ɍs�����B�_��A�������ł́A�V���N�i�Q�A�t�W�A�n���J�`�m�L���A����t�߂ŁA���炢�Ă���ԂƂ��Ĉē�����Ă����B
�@
�@�@ �@�V���N�i�Q �@�V���N�i�Q
�@�@ �@�t�W �@�t�W
�@�@ �@�n���J�`�m�L �@�n���J�`�m�L
�@�@ �@�V���E�u �@�V���E�u
�@�@ �@�`�S���� �@�`�S����
|
|
|
|
| 2013�N4��20���i�y�j |
| �O�������i�A���j�I�I�J���a�V�� |
�@�����́A������ʼn������Ă�����ł̗��ʑ�����s�����B�����Ȃ������I�������B
���̕t�߂̍��݂̐��ӂɂ͓���O�������i�A���j�I�I�J���a�V���̌Q�����ڗ��B�����x�Ԃ����Ă���B�I�I�C�k�m�t�O���̂悤�ȉԂł���B���ʑ��肪�I����Ă���P���ԂقǏ����������B
�@�@ �@ �I�I�J���a�V�� �@ �I�I�J���a�V��
|
|
|
|
| 2013�N4��19���i���j |
| �����쎩���̃J�����i�f�V�R�Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�̈ڐA�i��Q�e�j |
�@�O��s�̐��ƐX�ƊG�{�̉Ɓi�����V����\���j�̂s������A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c���A���A��ĂĂ���������Ƃ̘A���������������̂ŁA���������Ă������쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�S�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�U�����A�ߌ�A���͂������B��ς��ꂵ�������Ă���B�����Ɉ炿�A��������̉Ԃ����A�����ۑS����邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�@�@ �@�J�����i�f�V�R�̕c �@�J�����i�f�V�R�̕c
�@�@ �@�t�W�o�J�}�̕c �@�t�W�o�J�}�̕c
|
|
|
|
| 2013�N4��19���i���j |
| ���F��여�您�����߃X�|�b�g |
�@��여����ۑS���c��A���i�n�}�j�F��여�您�����߃X�|�b�g���A�挎�̕����Q�T�N�R���ɔ��s�����B�\�́A��여��̒n�}�ŁA�S���̋��̖��O���ڂ��Ă��āA�������߃X�|�b�g�Q�O�������Љ��Ă���B���ʂ́A���̐��ӂ̐����m�[�g�ɂȂ��Ă��āA���̎�Ȗ쒹�A�����A���������A�쑐�A�̎��A���ށA�b�k�ނ��Љ��Ă���B��ϗL�p�Ȓn�}�ł��B����̎s��̒S���ہi�O��s�ł͓s�s�������ƌ����ہj�Ŗ����œ���ł���B���Ɍ��肪����̂ŁA�v���ӂł���B
�@�@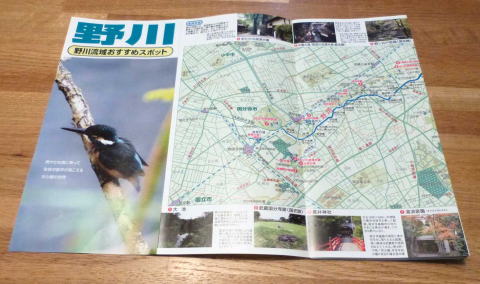 �@ ���n�} �@ ���n�}
|
|
|
|
| 2013�N4��18���i�j |
| ���̃N���X��_�c�w�m��� |
�@���A�������ӂɍݏZ����A��w�̓d�C�H�w�Ȃ̃N���X���_�c�w�m��قōs�����B����łP�Q��ڂƂȂ�A�l���������������Ă������A�X�����Q�����āA�Q���ԗ]��A�y�����ЂƎ������������Ƃ��ł����B
�@���N�A���������A�������A���������ōs�����ƂŁA�N���X����p�����₷���悤�ɓw�߂Ă���B�����G�k������̂ł͂Ȃ��A�S������ꌾ�A�A�K���ߋ���b���Ă��炤�悤�ɂ��Ă���B���������N�Ȃ̂ŁA�P�N�̊Ԃł͑傫�ȕω����Ȃ����A����Ȃ�ɓ��X���Ă�����ł́A�����ȕω���������̂ł���B��������̗F�B�̂��̌o���́A��ώQ�l�ɂȂ�Ƃ��������Ă���B
�@�w�m��ق́A�����オ�K�v�ł��邪�A���͂P�Q�N�Ԓl�グ�����Ȃ��ł����̂ŁA������A�H�v�����Ēl�グ�����Ȃ��ŁA���Ƃ���肭������Ă��������B |
|
|
|
| 2013�N4��18���i�j |
| �L�����������������R�ώ@�� |
�@������A���������R�ώ@���ɂ��܂����B�L�����������łɂR�ւقǍ炫�͂��߂Ă��܂����B�@���������悤�Ɋ����܂��B
�@�@ �@�L������ �@�L������
�@�W���E�j�q�g�G�A�z�^���J�Y���A�V�������炢�Ă��܂����B
�@�@ �@�W���E�j�q�g�G �@�W���E�j�q�g�G
�@�@ �@�z�^���J�Y�� �@�z�^���J�Y��
�@�@ �@�V���� �@�V����
|
|
|
|
| 2013�N4��17���i���j |
| � |
�@�����́A�߂��̓V����̒|�т̉����ɂɏo�������B�r���O��s�̊G�{�̉Ƃɗ������A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�Q�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�T����������|�A�\���o���B����Ă���������悤�Ȋ��G���B���������ł�����ꂵ�����Ƃł���B
�@�|�тł́A⡂������o�Ă��Ă����B�����́A�߂��̏��w�Z�̍��w�N�̐��k���A⡂ق�ɂɗ��Ă����B���n�������̂͂܂����������悤�������B
�@�@ �@���w������ �@���w������
�@�@ �@� �@�
|
|
|
|
| 2013�N4��16���i�j |
| ���̗��ʑ���i�S���j |
�@�����́A�P�O������A���̂Q�����i�x�m���勴�A�j�ŗ��ʑ�����s�����B������肷��\��ł��������A�����i�\��ł͂T���قǁj���邽�ߓr���Œ��~�����B�����𗬂��ė��ʂ𑪒肷�邽�߁A��������Ƒ��萸�x�������Ȃ�̂ŁA���������Ȃ����ɍēx��������邱�Ƃɂ����B
�@�����̂Q�����̎b��I�ȑ��茋�ʂł́A�P�T�ԂقǑO�̉J�ŁA�挎��藬�ʂ͑����������A�܂��A�ŋ߂̃s�[�N���i�����Q�S�N�T���j�̂P�T�����x�����߂��Ă��Ȃ��B�������܂萅�[�������Ă��A����͂���قǑ����Ȃ��B���ꂩ��T�����S�z�ł���B�@
�@����ɍۂ��āA��̗���ɒ��������^�R�����Q�{�����Ă���B�Ԋu�͂Q���B���̊Ԃ��A�㗬���畂���𗬂��āA�����𑪂�B�앝�A���[�������āA���ʂ��v�Z����B
�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q �@�㗬�ł̑���̗l�q
�@���肵�Ă���t�߂ɂ́A�~�N�������炵�Ă���B�~�̊Ԃ͌͂�Ă����t���A�܂��V�����̗t���o�Ă��Ă����B
�@�@ �@�~�N�� �@�~�N��
|
|
|
|
| 2013�N4��15���i���j |
| ���ɒ����N���ʂ̑���i�S���j |
�@�����͌ߑO���A�����s���Ă�����ɒ����N���ʂ̑�����O��n��̂P�R�����i�����`�Y�ԁj�ōs�����B���v�̗N���ʂ́A�挎�̑���l����T�O�����܂葝���������A�܂����������̂R�O�����x�ł���B
�P�T�ԂقǑO�̉J�ŁA���ɂ͈�U�͐����߂��Ă������A���̌�́A�܂��������������Ă���悤�Ɍ�����B
�@�@ �@�N���L��ł̑���̗l�q �@�N���L��ł̑���̗l�q
�@�@ �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q �@�����̂����t�߂ł̑���̗l�q
��N�̑���̌��ʂ́A���̂g�o�u�V�j�A����v�̒��̊ώ@�i���̗N���ʁA���ʁj�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B
�@���L�̂t�q�k�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
http://homepage2.nifty.com/adam-san/report/report1.html
���ɂȂƂ��ɂł��A���Ă��������B
�@��������Ă���ƁA�ǂ����炩�A�T���K�j���p���݂����B
�@�@ �@�T���K�j �@�T���K�j
|
|
|
|
| 2013�N4��14���i���j |
| �������{�����e�B�A�̒�ኈ�����i�S���P�S���j |
�@�����́A��Q���j���ŁA�������{�����e�B�A��ኈ�����ł���B�X�����A���R�ώ@�Z���^�[�ɁA�{�����e�B�A�B���W�܂�A�����͂R�̃O���[�v�ɕʂ�āA�Q���Ԃقǂ̒�ኈ�����s�����B���́A�A���O���[�v�̒�ẴZ���o�q�G���\�E�̏�����Ƃɉ�������B
�@�Z���o�q�G���\�E�́A���ȉԂ��炩����O���A���ł��邪�A���R�ώ@�����ł͑����Ă��܂��Ă���B�Ԋ��ł���A���N���̎����ɂ́A��R�̃{�����e�B�A�����o�ŁA�P�{�P�{�������B�l��̂������Ƃł���B
�@�A�蓹�A���̂��ʂ��������ł́A�q�����������ɓ����ėV��ł���p�����������B�܂����\�Y���������݂̑��̗��ɂ́A��������̂ڂ肪�g�����Ă����B�J���Z�~���p�������Ă��ꂽ�B
�@�@ �@�Z���o�q�G���\�E �@�Z���o�q�G���\�E
�@�@ �@���ŗV�Ԏq������ �@���ŗV�Ԏq������
�@�@ �@��̂ڂ� �@��̂ڂ�
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
|
|
|
|
| 2013�N4��13���i�y�j |
| �������쒹�ώ@��i�S���j |
�@�ߑO���A���̓~���̃V�[�Y���̍Ō�̖쒹�ώ@��������ŊJ�Â��ꂽ�B��Â͖������̈���{�����e�B�A�̉�쒹�O���[�v�ł���B�g���̏��Ȃ��A���ꂩ��́A���炭���x�݂��āA�ĊJ�͏H�̂P�O���P�Q���i�y�j�ł���B
�@��ʂ̎Q���҂͖�T�O������A���q���͂T���ł������B�����͋ߗׂ̏�����s�A�{���s�A�O��s�A���z�s�A������s�ł��邪�A��c��A�L����Ȃǂ�����Q������Ă����B�{�����e�B�A�X�^�b�t�͂X�����Q�����A�ē����߂��B
�@�c�O�Ȃ���A�g���̉e�͏��Ȃ��A�m�F�ł����g���͂P�W��ɂƂǂ܂����B�����̃n�C���C�g�́A�J���Z�~���S����p���݂��Ă��ꂽ���Ƃł������B�ɐB�̎����ɂȂ邽�߂��A�m�F�ł����R�H�݂͂ȃI�X�ł������B
�@�����̉��₩�ȓ��a�̂Ȃ��A�V�̌������������������A���t���b�V�ł������Ƃ͂悩�����Ǝv���Ă���B
�@�쒹�ώ@��I����A�V�����|�X�^�[�ւ����B���́A�|�X�^�[�̍쐻�E�f����S�����Ă���B
�@�@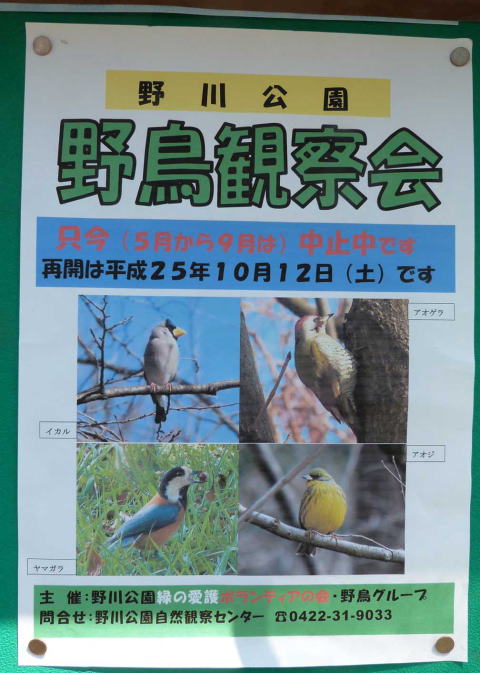 �@�쒹�ώ@��̃|�X�^�[ �@�쒹�ώ@��̃|�X�^�[
|
|
|
|
| 2013�N4��12���i���j |
| �������ƕ�����̐X����������Ă��܂����B |
�@�P�P���O�Ɏ�����o�āA���]�ԂŁA�������ƕ��������������Ă��܂����B
���������R�ώ@���ł́A�G�r�l�A�`�S�����A�I�h���R�\�E�A�T�N���\�E�A�T�M�S�P���炢�Ă��܂����B
�@�@ �G�r�l �G�r�l
�@�@ �@�`�S���� �@�`�S����
�@�@ �@�I�h���R�\�E �@�I�h���R�\�E
���z��s��ׂ̗̕�����̐X�����̒r�ɂ́A�q�h���K������Q�O�H�A�o���P�H�����܂����B�q�h���K���́A�r����o�āA�Ő��ʼn����H�ׂĂ��܂����B
�@�@ �@�q�h���K�� �@�q�h���K��
|
|
|
|
| 2013�N4��11���i�j |
| �S������쒹�ώ@�������� |
�@�ߑO���X������Q���Ԕ��قǖ������Ń{�����e�B�A���ԂP�P���ƁA�S���̒��쒹�ώ@���s�����B
�@�ώ@�����̂͂Q�R��ŁA�~���͂����c�O�~�ƃV�����������邮�炢�ŁA�W���E�r�^�L��r���Y�C�̎p�͂����Ȃ��B����ĉĒ��̃c�o���̎p����������悤�ɂȂ��Ă����B���ۊ���\���̍������R�������̎G�ؗт���̓I�I�^�J�́u�M�b�M�b�v�Ƃ����������������Ă����B
�@���R�ώ@���̒��ł́A�~�c�o�c�c�W�A���V���E�����J�Y���A�`���E�W�\�E�A�T�M�S�P�A�C�J���\�E�A�C�`�����\�E�A�z�E�`���N�\�E�Ȃǂ̉Ԃ��炢�Ă����B
�@�V�C�\��ʂ�A���߂��납�班���J���~���Ă������A�P���ԂقǂŐ��ƂȂ����B
�@�@ �@�~�c�o�c�c�W �@�~�c�o�c�c�W
�@�@ �@�`���E�W�\�E �@�`���E�W�\�E
�@�@ �@���V���E�����J�Y�� �@���V���E�����J�Y��
�@�@ �@�T�M�S�P �@�T�M�S�P
|
|
|
|
| 2013�N4��10���i���j |
| �����̃J�����i�f�V�R�ƃt�W�o�J�}�̈ڐA |
�@�ߌ�A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c���ڐA���s�����B�ڐA��́A�O��s�̎��R���ۑS�n��ŁA�Ǘ�������Ă���g����̂����ӂŁA���������Ă������쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c�Q�O���Ɩ�쎩���̃t�W�o�J�}�̕c�P�O�����������A��ĂĂ��������邱�ƂɂȂ�A�c�����n�����A�ڐA���I�������B���ӂ��Ă���B�����Ɉ炿�A��������̉Ԃ����A�����ۑS��������Ƃ����҂���B
�@���̕c�̂��������͉��L�̒ʂ�ł��B
�@�J�����i�f�V�R�F�P��N�H�A���������_�Ƒ�w�����̍��{���V�������璸���������쎩���̃J�����i�f�V�R�̃Z���|�b�g�c���A�����̒�ň�ĂāA��R�̉Ԃ��炩���A������n���܂����B���̎�����N�̏H�Ɏ����A�c����Ă܂����B
�@�t�W�o�J�}�F���ɂ킸���Ɏ������Ă���t�W�o�J�}�̎����N�̎悵�A�H�ɃZ���|�b�g�Ɏ���܂��A�|�b�g�ɈڐA���ĕc����Ă܂����B���t�W�o�J�}�͊��Ȃ̐�Ŋ뜜�뜜�U�ށiVU�j�ɕ��ނ���Ă��܂��B
�@�@ �@�J�����i�f�V�R�̕c �@�J�����i�f�V�R�̕c
�@�@ �@�J�����v�i�f�V�R�ڐA�� �@�J�����v�i�f�V�R�ڐA��
�@�@ �@�t�W�o�J�}�̕c �@�t�W�o�J�}�̕c
�@�@ �@�t�W�o�J�}�ڐA�� �@�t�W�o�J�}�ڐA��
|
|
|
|
| 2013�N4��9���i�j |
| �������E�������������� |
�@�X�����ɉƂ��o�āA���̔���㗬�̏�����V���܂ŕ����A�A��͖��ƕʂ�āA����������E��������������Ă��܂����B��P�S�O�O�O���ł����B
�@�����́A���w�Z�̓��w���ł��B���ł́A�����J���Z�~�̎p���������܂��B�܂��~���̃c�O�~�̎p���悭�������܂��B�V�����������܂����B�ȑO�I�I�u�^�N�T���������Ă����ՂɃL�����\�E�̉Ԃ��݂��܂����B�߂��ɂ��݂���炢�Ă��܂����B�c���{��t�W�o�J�}���V�肪�萶���Ă��Ă��܂��B�J���g�E�^���|�|���A�炢�Ă��܂����B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�@�@ �@�L�����\�E �@�L�����\�E
�@�@ �@�t�W�o�J�} �@�t�W�o�J�}
�@����������̃N�W���R�t�߂ł́A�q�����������C�ɗV��ł��܂����B�t�f�����h�E��j�����\�E���炢�Ă��܂����B�������ł́A�V���N�i�Q���炢�Ă��܂����B
�@�@ �@�q������ �@�q������
�@�@ �@�t�f�����h�E �@�t�f�����h�E
|
|
|
|
| 2013�N4��8���i���j |
| �̂�L�̎q�S�C�������� |
�@�R���O�i�S���T���j�̒��A���������ƔG�ꉏ�ɒu����Ă����i�{�[�����̒�����A�e�L�P�C����яo�����B��������Ǝq�L���S�C�����̂ŋ������B�܂����܂�Ă���Ȃɂ����Ă��Ȃ��悤�������B�Ƃ肠�����A�i�{�[�������A�G�ꉏ�̉��Ɉڂ����B�s�����ɓd�b�����āA�ǂ���������������Ă݂����A�u�s�����Ƃ��Ă͉����ł��Ȃ��v�Ƃ̕Ԏ��ł������B���́A�����s��������Z���^�[�ɓd�b�����邵���Ȃ��悤�������B�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂Ă��A��������Ă��ꂻ���ɂȂ����Ƃ����͂킩�����B
�@���̂U���ƂV���͕��ƉJ�̓��ƂȂ����B�i�{�[�����̒����J�ɔG��Ȃ��悤�ɂƁA�G�ꉏ�ɂ́A��������ɑ傫�Ȓi�{�[�����������B����Œ��ɂ͉J�͓���Ȃ����悤�������B�q�L���J�ɂʂ��Ɨ₦�邱�Ƃ�S�z�������A���Ƃ����߂������悤�������B
�@�����i�W���j�A�����̒��A�i�{�[�����̒�������ƁA�q�L�͂������Ȃ������B�e���ǂ����ɂ�Ă������悤���B�����d�{�[���A���������B�����䂪�Ƃɂ͖߂��Ă��Ȃ����A�ǂ����߂��Ɉړ����������ŁA���̉Ƃ́A�����Ă��邩������Ȃ��Ǝv���Ă���B
�@�@ �@�q�L�S�C �@�q�L�S�C
|
|
|
|
| 2013�N4��8���i���j |
| ��������A�b�B�X���̔n���܂ŕ��� |
�@�����́A�������V�C�������̂ŁA�������牺���̔n���i�b�B�X���j�܂ŕ������B�X�H���̃n�i�~�Y�L�̉ԁi���͉ԂłȂ���䚁j���ڗ��悤�ɂȂ��Ă����B�A��́A�������̎č�w����d�ԂŒ��z�w�ɏo�āA�o�X�ŋA���Ă��܂����B��P�Q�T�O�O���ł����B
�@�@ �@�n�i�~�Y�L �@�n�i�~�Y�L
�@�@ �@�n��������̉����߂� �@�n��������̉����߂�
�@���̂Ƃ���̉J�ŁA���ɂ͐����߂��Ă����B�i�m�n�i�̉��F�����ꂢ�ł����B��̔ɐB���̂悤�ŁA��̌Q�ꂪ�ڗ������B�ɏW�܂�A�p�V���p�V���Ɛ����𗧂ĂĂ����B�܂��~���̃R�K���A�}�K���A�c�O�~�̎p�����������B
�@�@ �@��̌Q�� �@��̌Q��
�@�@ �@�i�m�n�i �@�i�m�n�i
|
|
|
|
| 2013�N4��7���i���j |
| Facebook�ɎQ�����܂����B |
�@�������AFacebook�ɎQ�����܂����B
�����g������������Ă݂����ł��B
���L�̂t�q�k���猩�邱�Ƃ��ł��܂��B�ɂȂƂ��ɂĂ݂Ă��������B
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100005638663147
|
|
|
|
| 2013�N4��6���i�y�j |
| �V�W���E�J���̑��Â��� |
�@��̃}���~�̖ɂ̓V�W���E�J���̑����������Ă���B��N�U���ɂ́A�V�W���E�J���̐������������B���N�͂ǂ����ƁA���ӂ��Ă��邪�A�����A�����ɁA�R�P�̂悤�Ȃ��̂��^��ł����B
�@�@ �@�V�W���E�J�������̍ޗ����^��ł��� �@�V�W���E�J�������̍ޗ����^��ł���
|
|
|
|
| 2013�N4��5���i���j |
| �����A����̉J�ŁA���ɍĂѐ����I |
�@�ߑO���A���]�ԂŖ���������B�P����A����̉J�ŁA���ɂ܂������߂������Ƃ͂悩�����B���������ł́A�����ݒr�ɐ�������A���̂��ʂ����㗬�ł������������B�����O�܂ł́A���͂�ł������̂��R�݂����B����������̂�܂��t�߂̖��ɂ������������B
�@�@ �@��삭�ʂ����㗬 �@��삭�ʂ����㗬
�@�������̒��Ńg�E�_�C�O�T���������B���R�ώ@�����ł́A�C�J���\�E�A�T�N���\�E�A�C�`�����\�E�A�j�����\�E�A���}�u�L�\�E�A�J���g�E�^���|�|�Ȃǂ��炢�Ă����B���͗t���ƂȂ��Ă��āA�I�I�V�}�U�N�������J�ł������B
�@�@ �@�g�E�_�C�O�T �@�g�E�_�C�O�T
�@�@ �@�A�P�r �@�A�P�r
�@�@ �@�C�J���\�E �@�C�J���\�E
|
|
|
|
| 2013�N4��4���i�j |
| �K�r�`���E�̐����с������V����\�� |
�@�ߑO���A�̃{�����e�B�A�����Ă��鍑���V����|�т̉����ɏo�������B���傩���V���w�Z�O�̒|�тɍs���r���̍����ŁA�K�r�`���E�������т����Ă����B
�@�@ �@�K�r�`���E �@�K�r�`���E
�@�@ �@�K�r�`���E �@�K�r�`���E
�@��V���w�Z�O�̒|�тł́A��X�̃{�����e�B�A�����ŏo�����̒|�̔p�ނ��A�����V����̎{�݉ۂ��A�N�x���ɏ��������Ă��ꂽ�����ŁA�|�т���ς������肵���B�����̐��ʂ��ڂɌ�����悤�ɂȂ��������ŁA��ϊ��ł���B
�@�@ �@�������肵���|�� �@�������肵���|�� |
|
|
|
| 2013�N4��3���i���j |
| ���s�ɂćD�@�S���R���@�㑺�~�V�W |
�@�S���R���@�������ŏ㑺�~�V�W���A��������J�Â���邱�Ƃ�m�����̂ŁA�P�O���ɍ������ɓ���A���w���Ă����B����Ԓ���̑�P�l�ҁA���{��Ƃ̏㑺�~�V���́A����ɂQ�U�O��A�P�U�O�O�H�̒������炵�A�ώ@���Ă�����Ƃ̂��Ƃł������B�p��̃��b�g�ɂ́A�u���R�Ƃ̋��������ɂȂ����Ȃ��ŁA���R�̔����J���Ă���邩�Ǝv���܂��v�Ə�����Ă����B�܂��u�Ώۂ̍Č��ł͂Ȃ��A���R�Ƃ̑Θb�̒��Ŗ��z�����A�^��P����̐��E�����R�̎p����āA���������́v�Ƃ�������Ă����B���w��A�O����C�ɂȂ��Ă������m���ŁA������H�ׂ邱�Ƃ��ł����B
|
|
|
|
| 2013�N4��3���i���j |
| ���s�ɂćC�@�S���Q���@�{���A�����̍� |
�@�S���Q���@�����́A����������J�̓V�C�\��B�ߑO�P�O�����ɕ{���A�����̖k�R��������ɐ̂̒��Ԃ��U���W�܂�A�A�����̍����y���݁A���Q�̂��ٓ����B���̋߂��ɂ͍���Ƃ��낪�Ȃ������̂ŁA�����͂Ȃꂽ�Ƃ���Ƀx���`���m�ۂ��āA�����ɍ��̉Ԃ����Ȃ���A���k����B�݂ȏ����ÂN���Ƃ��Ă������Ƃ́A�������Ȃ����A���̂悤�ɍĉ�ł����т𖡂키�B�A��ɂ́A����ɏo�āA����ׂ�̔��̓��i���ΐ썶�݁j�̂�����������łȂ���A�������ƁA�Â��Ȏ��Ԃ𖡂키�B�i���X�ŁA������肨�������Ă���A���U�����B
�@�@ �@���̓��̍� �@���̓��̍�
�@�@ �@���̓��̍� �@���̓��̍�
|
|
|
|
| 2013�N4��3���i���j |
| �@���s�ɂćB�@�S���P���@�N�w�̓��̍� |
�@�S���P���B�����́A�R��̂����ɐe�A�Z��̂���Q��������B�A��́A�����ɂ悤�ɁA�C���N���C���Ղ���a���ׂ�̘H���T���ɏo���B��T������͓N�w�̓��Ɍ����B�ቤ���Ȃ�R�����Q�O���قǕ����A�V�����Ɣ��d�̕�ɎQ��B�߂��ēN�w�̓�����t���̕��ɕ����B�a���ׂ�ɂ͍������J�ł������B�O���l�ό��q�������B
�@�@ �@�N�w�̓��̍� �@�N�w�̓��̍�
�@�@ �@�V�����̂��� �@�V�����̂���
�@�@ �@�V�����d�̂��� �@�V�����d�̂���
|
|
|
|
| 2013�N4��3���i���j |
| ���s�ɂćA�@�R���R�P���@�䏊�̍� |
�@�R���R�P���B�ߑO���A�䏊�̋��߉q�@�Ղ̖��J�̍������ɍs���B�P�P��������䏊�̋߂��ő�w�̃[�~�u�@�Ӌ�y���v�̉������A�o�Ȃ���B�Q�S�����Q���A����ł������B�o���E���搶�͂P�O�N�قǑO�ɑ��E���ꂽ���A�[�~�̊w�����A���ł��u�@�Ӌ�y���v���p�����Ă���B�搶�̐l�����傫���������߂ł���Ɗ����Ă���B�M�d�ȏW�܂�ł���A�N���Ƃ�Ƌ��ɋM�d�ȉ�ɂȂ��Ă����B
�@�@ �@�䏊�̍� �@�䏊�̍�
�@�@ �@�䏊�̍� �@�䏊�̍�
|
|
|
|
| 2013�N4��3���i���j |
| ���s�ɂć@�@�R���R�O���@�~�R�����̍� |
�@3��30���@���߂��ɐV�����ŋ��s�Ɍ��������B�S��5���̗��ł���B
�����́A�z�e���ɂ��Ă���~�R�����̂�����������ɍs�����B�A��ɁA�_���̈�͂̑O��ʂ�A�̕�����ցB�c�O�Ȃ���s�x��́A4��1������ł������B���m�������w���āA����̂Q�K�̏��t�łɂ���H�ׂ��B�̂��炠��i���X�u�z�n�v�ɂăR�[�q�[�������ς��ň�x�݂����B
�@�@ �@�~�R�����̍� �@�~�R�����̍�
�@�@ �@���t�̂ɂ��� �@���t�̂ɂ���
|
|
|
|
| 2013�N3��30���i�y�j |
| �V����̍��̑�� |
�@�W�҂�������Ȃ����A�V����̉��ɂ́A���R���`�̍��̑������A�����J�Ō�����ł���B��X�{�����e�B�A���������Ă���|�тɋ߂��A���N���邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���B
�@�@ �@�� �@��
�@�@ �@�|�т̌������ɂ͒��w�Z�̍Z�� �@�|�т̌������ɂ͒��w�Z�̍Z��
�s���ŁA�S���قǓ��L�̍X�V���ł��܂���B�܂��ĊJ�������낵�����肢�������܂�
|
|
|
|
| 2013�N3��29���i���j |
| ���̂U�R�� |
�@��������Ђ̓����U�R�������Ŏd�������Ă������Ԃ̂n�a���邠��A�P�S�����o�Ȃ����B�̂̌����̘b�A�ŋ߂̌��N�̘b�A���q�̎����b�Ȃǂ��낢��̘b���łāA�y�����ЂƎ����߂������Ƃ��ł����B
�@��n�܂�O�ɁA�P���ԂقǑ����s���āA�������ƒ뉀�����w�����Ă����������B�����ɂ͖��̌���Ƃ�����r������A�����ɂ͐��{�̗N���������ꍞ��ł��邻���ł���B�ē��ɂ��Ƒ�r�̍ŏI�����ʂ͖L�����ɂ͂P�O�O�O�O���b�g��/���A�������ɂ͂S�O�O���b�g��/���ƂȂ��Ă����B�b�ɒ����ƖL�����ɂ͂P�U�V���b�g��/�b�A�������ɂ͂U�D�V���b�g��/�b�ƂȂ�B�������̕����ʂ���Ϗ��Ȃ��̂ɂ͋������B
�@�@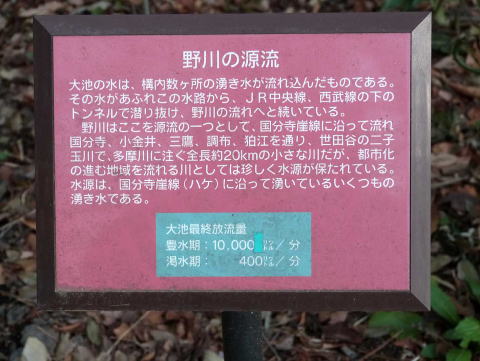 �@�ē��� �@�ē���
�@�@ �@ ��r �@ ��r
|
|
|
|
| 2013�N3��28���i�j |
| ��V���w�Z�Z���ɁA�w�Z�̑O�̍����V����|�т̂Q�N�Ԃ̃{�����e�B�A������� |
�@�ߑO���A�A�|�B���g���Ƃ��Ă������O��s����V���w�Z�Z����K�₵�A�w�Z�̑O�̍����V����|�тł̂Q�N�Ԃ̃{�����e�B�A����������B�ԂƗ̂܂��O��n������̐E���Q�������Ȃ����B
�@�w�Z�̑O�̒|�т́A��������w���w���̂ɂ́A�u���ԂƂƂ��ɐ����Ă����@�̂т䂭��|�̂悤�Ɂv�Ƃ������Ă���B�w�Z�ƍ����V����Ƃ̌𗬂�����Ƃ̂��ƁB���k�����́A�|�̃h�[������A���������߂�A⡂ق�Ȃǒʂ��A�|�тɐe���݂������Ă���Ƃ̂��Ƃł������B
�@�w�Z�̂R�K�A�S�K����A�����V����̒|�т̗l�q�������Ă����������B�ォ�猩��|�т́A���i����|�тƂ͂܂�����������ł������B
�@
�@�����́A�|�тł́A�Ǝ҂��|�̔p�ނ̉����Ƃ����Ă����B�V����{�݉ۂ̂����ӂɂ����̂ŁA���ӂ������B����ŁA�|�т��܂��܂��������肷�邱�ƂɂȂ�A��ς��ꂵ�����Ƃł���B
�@�A��ɁA���ƒ��z��s��t�߂̍��̗l�q�����ɂ������B���܂��ɖ��J�ł���B
�@�@ �@���t�߂̍� �@���t�߂̍�
�@�@ �@���z��s��t�߂̍����� �@���z��s��t�߂̍�����
�@�@ �@���z��s��t�߂̍��̑�� �@���z��s��t�߂̍��̑��
|
|
|
|
| 2013�N3��27���i���j |
| ���\�h��{�`�G�b�N���X�g���� |
|
�@�����́A���J�ŁA�܂��~�ɋt�߂肵���悤�Ɋ����B�������g�̍����傫���ƁA���N�Ǘ�����ς��B
�Ƃ���ŁA�啪�O�ɁA���\�h��{�`�G�b�N���X�g�������s���A�A���P�[�g�̕Ԏ����o���Ă��������A���̌��ʂ����̂قǑ����Ă����B
�u�U�T�Έȏ�ʼn��ی��̗v�x���E�v�����Ă��Ȃ�������ΏۂɁA���튈���A�^���@�\�A�h�{�A���o�A�O�o�A�C���A���̖Y��̂V�̊ϓ_����A�����@�\�̏�Ԃ��m�F�����Ă��������܂����B���̌��ʁw���̂Ƃ���A�����@�\�ɂ��Ă͐S�z����܂���x�v�Ƃ̑�������ł������B
�@�{�����e�B�A�����ŁA�̂Ɠ����g���Ă��邱�Ƃ��A��Ԍ��N�ێ��ɖ𗧂��Ă���悤�ł���B�L����Ƃł���B
|
|
|
|
| 2013�N3��26���i�j |
| �߂��̍��͖��J�A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�c�̉œ���� |
�@�ߑO���A�i�q�V�����̐ؕ����ɕ������w�܂ŏo�������B�������w�O�ʂ�̍��������J�ł������B�߂��̂����̍������J�ł������B�A��̃o�X�́A�h�b�t�����œr�����Ԃ����āA�h�b�t���傩��A���������Ă����B�w�Z�̊W�҈ȊO�́i��q�̂Ƃ�����j�����ɂ͂��邱�Ƃ͉������Ă��������Ƃ̊Ŕ��������B�������܂��ɖ��J�ł������B
�@�@ �@���i�������w�߂��j �@���i�������w�߂��j
�@�@ �@���i�h�b�t����j �@���i�h�b�t����j
�@���A�l�ŁA�|�b�g�ň�ĂĂ��鑽���쎩���̃J�����i�f�V�R�̑�Q�̉œ���悪�A�_��A�������A�����l�Z���^�[�̂����͂ŁA�قٌ��܂����B��P�́A�������R���ɂ��鎩�R���ۑS�n��i�Q�O���j�ŁA��Q�͏��w�Z�̉Ԓd�i�Q�O���j�ł���B��R�͌��ݐՒ��ł���B�S���ɂȂ�ƒn�A���ɂ���̂������̂ŁA���낻�댈�܂��Ăق����B
�@�@ �@����Ԓd�̃J�����i�f�V�R�̃|�b�g�c �@����Ԓd�̃J�����i�f�V�R�̃|�b�g�c
|
|
|
|
| 2013�N3��25���i���j |
| �A���ώ@����������e����� |
�@�����́A���V�C���悭�Ȃ��������A�{�����e�B�A���Ԃ̐A���ώ@��ɎQ�����āA���������e����ʂ̐A���ώ@�ɏo�������B�X���ɂi�q�����w�k���ɏW�����A�㞭�c�����珬����ɉ����Ďn�܂�~���R�[�X������A���e��L�����v��Ɏ��铹�����邢�āA�ώ@�����B�r���ʼnJ�ƂȂ��Ă����̂ŁA�L�����v��Œ��H���Ƃ�A���e�o�X�₩��o�X�ō����w�܂ŋA���Ă����B
�@
�@�L�o�i�A�}�i�A�A�Y�}�C�`�Q�A�J���g�E�~���}�J�^�o�~�A���}�G���S�T�N�A�i�c�g�E�_�C�A�I�L�i�O�T�A���S���l�R�m���A�}���V�O�T�Ȃǂ��ώ@�ł����B
�@�@ �L�o�i�A�}�i �L�o�i�A�}�i
�@�@ �@�J���g�E�~���}�J�^�o�~ �@�J���g�E�~���}�J�^�o�~
�@�@ �@���}�G���S�T�N �@���}�G���S�T�N
�@�@ �@�i�c�g�E�_�C �@�i�c�g�E�_�C
�@�@ �@���S���l�R�m�� �@���S���l�R�m��
|
|
|
|
| 2013�N3��24���i���j |
| �A�����l���Z���^�[�u����u�g�߂ȐA���Љ�̑��l���v |
�@�����ߌ�P������A�_��A�������A�����l���Z���^�[�ŁA���{���V�搶�̍u����u�g�߂ȐA���Љ�̑��l���v������A���u���܂����B
�@ ���{�搶�́A��N�����_�Ƒ�w������ފ�����A���݂́A������w��w�@�_�w�����Ȋw�Ȃɂ�����B�@�_��A�������̍u����̈ē��ɂ́A�u�N��������I�ɖڂɂ���A�����ނɁA�A���Љ�ŌJ��L�����鋣����A�������������Ƃ̐킢�Ȃǂɂ��Ă��Љ�܂��B�g�߂ɂ���A���̐�����
�����߂Ď������Ă݂܂��H�v�Ə�����Ă��āA��ϋ���������u����ł����B
�@
�@�ȑO����A���{���V�搶���玄�ɂ́A�u�O���A�����������āA�]������̃`�K���i�X�X�L�j�����āA�����ɃJ�����i�f�V�R�A�t�W�o�J�}�A�m�A�U�~�A�c���K�l�j���W���A�Ȃǂ����݂�����炵�����R���Ƃ���ǂ��Ă��������v�Ƃ̂����������������Ă���܂��B
�@�����́A�l�Ԃ̎肪���������A�����R�̐A���Q���̑��l���ɂ��Ă킩��₷�����b�����������ė����������Ɗ����Ă��܂��B
�@�@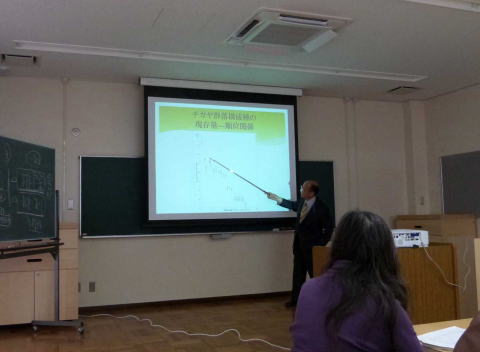 �u����̗l�q �u����̗l�q
�@�@ �@��O�ł̐A���̐��� �@��O�ł̐A���̐���
|
|
|
|
| 2013�N3��24���i���j |
| ���̗N���ʁA���ʂ̊ώ@���ʂ̃��|�[�g |
�@���̂R�N�C�S�N�ԁA���Ŋώ@���Ă����N���ʁA���ʂ̊ώ@���ʂ��Ȍ��ɂ܂Ƃ߂�����ł̃��|�[�g�̃y�[�W���g�o�u�V�j�A����v�̒��ɍ쐬���܂����B
���e�́A
�@�O��n��ɂ�������ɒ����N���ʂ̔N�ԕω��i�R�N�ԁj
�A�O��n��ɂ�������̗��ʂ̔N�ԕω��i�S�N�ԁj
�ł��B
�@���������여��A����Ȃ��Ƃ�����ŕ������e�ł��B
�t�q�k�F�@http://homepage2.nifty.com/adam-san/report/report1.html�@�ł݂��܂��B
�܂��A�{�g�o�̃g�b�v�y�[�W����A�@���ώ@�i���̗N���ʁA���ʁj�@���N���b�N����ƁA�݂��܂��B
�S�̂�����͌��Ă��������B
|
|
|
|
| 2013�N3��23���i�y�j |
| �h�b�t�̍��A�������̍� |
�@�ߑO���A�h�b�t�i���ۊ����w�j�Ɩ������̍��̗l�q�����ɍs�����B����ɂ́A�ύ��ɂ��ĂƂ̊Ŕ��o�Ă����B�����͂��������������B�y�E���͂P�O������P�V���܂ŁA�͈͂́A���傩��V���[�^���[�܂łƏ�����Ă����B�ł��܂����ɗ���ЂƂ͂���Ȃ������Ȃ��B�������ƍ��̕��ؓ��̍����A���łɌ�����ƂȂ��Ă����B
�@�@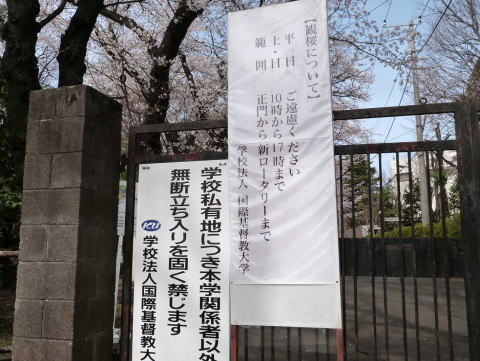 �@�Ŕ@�i����ɂ������Ŕ��E�E�j �@�Ŕ@�i����ɂ������Ŕ��E�E�j
�@�@ �@�h�b�t�̍� �@�h�b�t�̍�
�������ł́A�����̂a�n��̍��̕����A�悭�炢�Ă��āA���̉��ɂ́A�Ԍ��̉Ƒ����ꂪ�����B
�@�@ �@�������̍� �@�������̍�
�@�@ �@�������̍� �@�������̍�
|
|
|
|
| 2013�N3��23���i�y�j |
| ���������R�ώ@�� |
�@�ߑO���A���������R�ώ@�����ώ@�����B��������Ԃ́A�J�^�N���A�I�L�i�O�T�A�V���������A�q�g���V�Y�J�A�E�O�C�X�J�O���Ȃǂł������B
�@�@ �@�J�^�N�� �@�J�^�N��
�@�@ �@�I�L�i�O�T �@�I�L�i�O�T
�@�@ �@�V�������� �@�V��������
�@�@ �@�E�O�C�X�J�O�� �@�E�O�C�X�J�O��
�@�@ �@�q�g���V�Y�J �@�q�g���V�Y�J |
|
|
|
| 2013�N3��22���i���j |
| ���Ɛ_��A�������̍��̊J�ԏ� |
�@�ߑO���A���̔��狴�ꋴ�܂ŕ����A�����Ŗ��ƕ�����Đ_��A�������̍����݂��B
���ł́A�����̉E�݂ƌ䓃�⋴�����̗��݂ɍ��̖�����A���J�Ƃ͂����Ȃ������\�����Ă���B�䓃�⋴�����ł́A���̉��̏W�܂��Ă���O���[�v�����������B
�@�@ �����̃T�N�� �����̃T�N��
�@�@ �@�䓃�⋴�����̃T�N�� �@�䓃�⋴�����̃T�N��
�@�_��A�������ł́A�����ɍ��̊J�ԏ̕\��������A����ɂ��ƁA�����̃J���q�U�N���A�J���Y�U�N���A�V�_���U�N���A�_�㏌�����łɖ��J�ŁA�\���C���V�m�͂R���炫�ƕ\������Ă����B
�@�@ �@���̊J�ԏ̕\�� �@���̊J�ԏ̕\��
�@�@ �@�J���q�U�N�� �@�J���q�U�N��
�@�@ �@�V�_���U�N�� �@�V�_���U�N��
�@�@ �@�_�㏌ �@�_�㏌
|
|
|
|
| 2013�N3��21���i�j |
| ���̕��i |
�@���������̖��̐�ׂ�ŁA�^���|�|�������Ă��܂����B�`�G�b�N���Ă݂�ƃJ���g�E�^���|�|�ł����B
�@�@ �@�J���g�E�^���|�| �@�J���g�E�^���|�|
���̑������T�L�n�i�i���炢�Ă��܂����B
�@ �@�@�����T�L�n�i�i �@�@�����T�L�n�i�i
������ł́A�i�m�n�i�������ς��炢�Ă��܂����B
�@�@ �@�i�m�n�i �@�i�m�n�i
���͏��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�~���̃V���͂܂����܂��B
�@�@ �@�V�� �@�V��
�����̃J���Z�~�̎p������܂��B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�����A�������炫�n�߂Ă��܂��B
�@�@ �@�����̃T�N���̗l�q �@�����̃T�N���̗l�q
|
|
|
|
| 2013�N3��21���i�j�@ |
| ���̐��͂ꂪ�����i���ʂ����t�߁A��܂��t�߁j |
�@���̎����A��ʂ̉J�ʂ����҂ł��Ȃ����߁A�������R������̗N�������܂��܂��������A���̐��͂�͈̔͂��L�����Ă���B���������R�ώ@���ł́A�N�������Ȃ��z�^���̔ɐB�ւ̉e�����S�z����Ă���B�N���L��̗N�����������ʂ������牺���́A�������邪�A���ʂ����㗬�ł́A�N�����قƂ�ǒ����ł��Ȃ��̂ŁA���͂�͈̔͂��L�����Ă���B����������ɓ���ƁA�������܂��Ԃł́A���͂�̏ł��B
�@�@ ��삭�ʂ����㗬�̗l�q ��삭�ʂ����㗬�̗l�q
�@�@ �@��쏬����V���㗬�̗l�q �@��쏬����V���㗬�̗l�q
�@�U�����ɁA�Ȃ�Ȃ��Ƒ����̉J�����҂ł��Ȃ��̂ŁA���̂܂܂ł́A�X�Ɉ����ƂȂ邱�Ƃ��S�z�ł��B
|
|
|
|
| 2013�N3��20���i���j |
| �����V����|�т̉��� |
�@�ߑO���A�{�����e�B�A�Ŗ��x�Ǘ������Ă��鍑���V����̒|�т̉����ɂ��� ���B���̒�ኈ�����̑O�ɁA���O�ɉ��������č�Ƃ̊댯�h�~�Ɨ\��𗧂Ă�B���[�_�[������̂̋`���ł���B���łɁA�Ǘ����Ă���|�т̏J�Ɋώ@����B�ւ̖����{����A���ꂼ��Ɉ�����Ԃ��炩���Ă���B
�@�@ �@�� �@��
�@�@ �@�� �@��
�@�@ �@�� �@��
�@�R�u�V���炫�������B���̊ԍ炢�Ă����~�͂����Ԋ����߂����B
�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V
�@���x�Ǘ������Ă���|�т̋߂��ɁA���̂U�O���S���̐Ղ��c���Ă���B���̋߂��ɑ傫�ȍ��̖�����B���`���̂т̂тƂ������R�Ȏ��`�����Ă���B���̍��ɂ�����ق�Ԃ��炫�������B
�@�@ �@�� �@��
|
|
|
|
| 2013�N3��19���i�j |
| �{�����e�B�A�𗬉� |
�@�ԂƗ̂܂��O��n�������Ẫ{�����e�B�A�𗬉�A�ߌ�Q������J�Â��ꂽ�B
�؎R�����ǒ��̈��A�ł́A�ԂƗ̂܂��O��n������ɌW���{�����e�B�A�O���[�v�͂Q�T����A���悻�T�O�O�����������Ă���B�ł��A�ԂƗ̂܂��O��n������̉�����͌����_�ŁA�P�T�O���Ƃ܂��܂��ŁA�������̓o�^�����Ă��������Ƃ̂��Ƃł����B
�O���[�v�ɂ́A���̗��A����̗��A�ےr�̗��A�R�~�Z���i���A����A����A��̓��A�V�쒆���A�A���A�w�O�j�̉Ԓd�f�A�Ԓd�{�����e�B�A�̊Ǘ����Ă���Ԓd�̂f�A�����Ȍ����̉Ԓd�i�k�K�[�f���A�X�|�b�g�K�[�f���A������K�[�f���Ȃǁj�̂f�A�̃{�����e�B�A�̂f�Ȃǂł���B
�@���ꂼ��̃O���[�v�̊����̏Љ�A�p���[�|�C���g�Ő�������A���̍ہA�e�f�̏o�Ȏ҂���̐������������B
�@�Ō�́A�R�O���قǎ��R�Șb�������̏ꂪ�ݒ肳�ꂽ�B�S���ɖ����ɏI�������B |
|
|
|
| 2013�N3��19���i�j |
| �t�W�o�J�}�̈ڐA |
�@�@�啪�g�����Ȃ��Ă����̂ŁA�|�b�g�ň�ĂĂ����t�W�o�J�}�X�����A�����A�Ԓd�ɈڐA�����B�Ԓd�ɂ́A�����i���j�����́A�����ڐA�����t�W�o�J�}�ŁA�����i�E�j�����͍�N�A�����J�����i�f�V�R�Ƃ����z�u�ɂȂ��Ă���B�����Ɉ���Ăق����B
�@�@ �ڐA��̉Ԓd �ڐA��̉Ԓd
�@�@ �@�ڐA��̃t�W�o�J�} �@�ڐA��̃t�W�o�J�}
|
|
|
|
| 2013�N3��18���i���j |
| �{�����e�B�A�c�̂̑��� |
�@�����́A�O��s�s�������Z���^�[�ŁA���ŊO���A���̋쏜�ƐA���������s���Ă���u�݂������̉�v�̑�����s�����B���݂́A����U���ł��邪�A�����A�����v��A��v�Ȃǂ��c�_���āA�����Q�T�N�x�̊��������߂��B�����ł��s���b�ƌ��銈�����s���������̂ł���Ǝv���Ă���B
�@����܂ł̂T�N�Ԃ̊����ŁA�O��s�𗬂����́A�x�m���勴�`��Ԃ̉͐�~�ł́A�O���A���̃A���`�E���ƃI�I�u�^�N�T�͑啝�Ɍ��������B��N����A�V���Ɋ����͈͂ɒlj�������`�䓃�⋴�Ԃł́A�����P�C�Q�N�撣��Γ��l�Ɍ�������ƍl���Ă���B�����܂ł́A��萋����K�v������B
�@���́A���a�S�O�N���ɑ啝�ȉ͐���C���s���A����ɂ��N�����Ă����A���������A���Ƃ��Ƃ̖��ɂ������A���͉����Ƃ������Ƃɂ��ẮA��X�ɂ��悭�킩���Ă��Ȃ��̂ŁA������Â��������Œ��ׁA���݂̖��̐A�����ǂꂾ���قȂ��Ă��邩�A�ۑS���ׂ��A���͉����H���͂����肵�Ă����K�v���������B
|
|
|
|
| 2013�N3��17���i���j |
| ���̒g�����ŁA��̃`���[���b�v���炫�n�߂܂��� |
�@�`���[���b�v�́A���炫�̂��̂ł��A�Ԋ��͂S����{�Ǝv���Ă��܂������A�����A��̉Ԓd�Ɣ��A���̃`���[���b�v���A�Q�֍炫�n�߂܂����B�܂��܂��t�ƂȂ��Ă��܂����B
�@�@ �@�`���[���b�v �@�`���[���b�v
�@�@ �@�`���[���b�v �@�`���[���b�v
|
|
|
|
| 2013�N3��17���i���j |
| ���̂Ȃ��Ƃ����ʑ��� |
�@�����̌ߑO���A��여��A����Ȃ��Ƃ������ẤA���̗��ʑ�����A�S������O��s�̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ōs�����B
�@���̔[�����ʑ���́A���̑S����Ŗ�여��A����̓s���ψ��A�s���ψ��Ǝ����ǂ̐l�X�����͂��āA�N�ɂR������Ă���B���́A�����s�̐E���ƃ`�[����g��œ�l�ő���������B
�@�Q���O�Ɉ�l�ő��肵�����Ɠ������A���������̗����͑�ϒx���āA�����̗��ꂪ���̉e������̂ŁA����ɂ͎��Ԃ�������A��J�����B
�@���̗��ʑ���́A�Q�O�O�U�N����n�܂��Ă���A����łQ�T��ڂƂȂ� |
|
|
|
| 2013�N3��16���i�y�j |
| �������̈���{�����e�B�A�̉�̒�ኈ�� |
�@�����́A��R�y�j���ŁA�������̈���{�����e�B�A�̉��ኈ�����ł���B���V�C�������̂ŁA�T�O���߂��̃{�����e�B�A�������ɎQ�������B��ኈ�����́A�������R��ŁA��P�y�j���A��Q���j���A��R�y�j���ƂȂ��Ă���B�����́A�X��������P�P�����̂Q���ԁA�T�قǂ̃O���[�v�ɕ�����A���R�ώ@�����̂��낢��ȕۑS�������s�����B���́A���o�[�h�T���N�`���A���̒��̃A�Y�}�l�U�T�̊�������s���O���[�v�ɓ���A�����������B
�������ł��A���̐������Ȃ����Ƃ��Ƃ����b��ɂȂ�B���ꂩ��S���A�T���Ɍ����āA���܂�J�����҂ł��Ȃ����Ƃ���A��ϐS�z�ȏł���B
���̑��\�Y���t�߂ł́A�R�u�V���炫�n�߂Ă����B
�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V
�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V
|
|
|
|
| 2013�N3��15���i���j |
| ���̗��ʑ���i�R���j |
�@�����́A�X��������A���̂R�����i�x�m���勴�A�A��j�ŗ��ʑ�����s�����B���ʂ́A�挎��蔼���ȉ��ƂȂ�A�ŋ߂̃s�[�N���i�����Q�S�N�T���j�̂S�����x�ɂ܂Ō������Ă���B�������܂萅�[�������Ă��A����͑�ϒx���B���ꂩ��S���A�T�����S�z�ł���B����́A��Ԏ�������A�P�Q�����ɂ͉��Ƃ��I�������B
�@���ō��͂P�{�������炢�Ă����B�V����ʂ�ł́A���i�J���q�U�N���j��R�u�V���炢�Ă����B�t�̕��͋C���o�Ă����B���ɂ́A�����́A�~���̃I�i�K�K���̎p�͂����Ȃ������B
�@�@ �@���̍� �@���̍�
�@�@ �@�V����ʂ�̃T�N���i�J���q�U�N���j �@�V����ʂ�̃T�N���i�J���q�U�N���j
�@�@ �@�R�u�V �@�R�u�V
|
|
|
|
| 2013�N3��14���i�j |
| ��̔~�́A�x�炫�̖L��~�H |
�@�~�́A���ɐ�삯�Ă��ꂢ�ȉԂ�����Ƃ��낪�����Ǝv���Ă����̂ŁA��̔~���x�炫�Ȃ̂�s���Ɋ����Ă����B�~����Ȃ��̂��Ƃ��v�������Ƃ��������B���A���J�ŁA������d�̉Ԃ��R���Ă���B
�@�@ �@�~ �@�~
�@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA��d�炫�̑�ւ̉Ԃ�����A�x�炫�̖L��~�̕i��Ɂu�J�̐�v������B�ʐ^������ƉԂ̊����͂悭���Ă��āA��������ł���B�ł��A��̔~�̉Ԃ͑�ւłȂ��B���̓_�����قȂ�B���ǁA���f�ł����ɂ��邪�A�x�炫�̔~�ł��邱�Ƃ́A�[�����ł��Ă���B�q���h�������āA����ɉԂ̖����z���Ă���悤���B
�@�@ �@�q���h�� �@�q���h��
�����M�����Ԃ����Ă���B
�@�@ �@�����M�� �@�����M��
�n�i�J�C�h�E�ɂ͂ڂ݂����Ă���B
�@�@ �@�n�i�J�C�h�E�@ �@�n�i�J�C�h�E�@
|
|
|
|
| 2013�N3��13���i���j |
| ��V���w�Z�O�̍����V����̒|�тŁA���N�͒ւ������Ă��܂� |
�@ ��V���w�Z�O�̍����V����̒|�тŁA����܂Œ|�тɈ͂܂�Ă��܂��Ă����ւ��A�̃{�����e�B�A�̖��x�Ǘ������ōĂі��邳���Ƃ���ǂ��A���N�͋v���Ԃ�ɂ��ꂢ�ȉԂ����Ă���B
�@�@ �@�ւ̉� �@�ւ̉�
�@�@ �@�ւ̉� �@�ւ̉�
�@���̑�V���w�Z�O�̍����V����̒|�сi��S�U�O�O���Q�j�ł́A�V����̋��āA�ԂƗ̂܂��O��n������ �̃{�����e�B�A�ɂ��|�т̖��x�Ǘ��������n�܂��Ă���A�����Q�N�Ԃ��������B
�@����܂ŁA���̊����́A�����Q�R�N�x�ɂ͂Q�����ɂP��A�����Q�S�N�x�ɂ͌��P��̕p�x�Ŏ��{����A�S��͉J�Ȃǂ̂��߂ɒ��~�ƂȂ������A�P�S�����s�����B����P�O���`�Q�O���̎Q���҂�����A��x�ȏ�Q�������l�͂T�O���߂��ɂȂ�B
�@�Q���҂����́A�قƂ�ǂ��A���N�s���Ă���ԂƗ̂܂��O��n�������Ấu�̃{�����e�B�A�u���v�i�S�U��j�̏I�����ł���B���́u�̃{�����e�B�A�u���v�́A����܂ŔN�P��A�X��J�Â��ꂽ�B���C���u�t�́A�����_�Ƒ�w�����ŁA�ԂƗ̂܂��O��n����������_����א搶�����疱�߂�ꂽ�B�C���҂͂��łɖ�P�O�O���ƂȂ��Ă���B
�@
�@���̊����ɁA�S�����������́A����ԂƗ̂܂��O��n������̉���ƂȂ�A���N�P�O���`���N�̂P���̊ԂɊJ�Â����u�̃{�����e�B�A�u���v����u���Ă����������Ƃ��������߂���B���݁A��V���w�Z�O�̍����V����̒|�т́A���̍u���C���҂����̎��H�̏�i���C���t�C�[���h�j�ƂȂ��Ă���B�u�y�������S�Ȋ����v��ڎw���āA�����������A�C���Ɋ������Ă���B
�ԂƗ̂܂��O��n������̂g�o��
http://hanakyokai.or.jp
�ł��B
|
|
|
|
| 2013�N3��12���i�j |
| ���ɒ����N���ʂ̑���i�R���j |
�@�����͌ߑO���A�����s���Ă�����ɒ����N���ʑ�����P�R�����i�����`�Y�ԁj�ōs�����B���v�̗N���ʂ́A�挎�̑���l����R�T�����܂茸�����Ă����B
�@�@ �@����̗l�q�i�㗬�j �@����̗l�q�i�㗬�j
�@�@ �@����̗l�q�i�쐅���`�Y�ԁj �@����̗l�q�i�쐅���`�Y�ԁj
�@�����́A���₩�ȓ��ŁA����͂X���O����X�^�[�g���A�P�Q�����ɖ����I�������B
�@�挎�̑��莞�A���������̍����`���ʂ����ԂŁA���̗ʂ����ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ��낪�������B�����͗\�z�ʂ萅�͂�ɂȂ��Ă����B
�@�@ �@���͂�̖��i��삭�ʂ����㗬�j �@���͂�̖��i��삭�ʂ����㗬�j
�@�@ �@�Z�O���Z�L���C �@�Z�O���Z�L���C
|
|
|
|
| 2013�N3��11���i���j |
| �_��A���������E���������A������ |
�@�_��A���������E�������ł́A���{�̖��ԂQ�U�O�i�킪������B���͊����ł͒ցi�t�Ɩj�Ə����B�Q���A�R����������ł���B������j���̌ߌ�ɂ͉����ɂ��K�C�h�c�A�[���������B
�u���̏��v�A�u���v�A�u�_��s���v�Ȃǂ̂��̖��Ԃ̏Љ�������B�����Ƃ����ԂɎ��Ԃ������̂ŁA���Ƃ͂�����茩�Ă��������Ƃ̂��Ƃł����B�u���̏��v�A�u���v�͍��炢�Ă���A�����ł́A���Ɂu���Ȃ̉ԁv�Ƃ��đ��d����Ă���悤���B�_��A�������Ō��������ꂽ�u�_��s���v�́A���͍炢�Ă��Ȃ��āA�����P�T�Ԃقǂ���ƉԂ��炫�����ł������B
�@�@ �@�����ɂ��K�C�h�c�A�[ �@�����ɂ��K�C�h�c�A�[
�@�@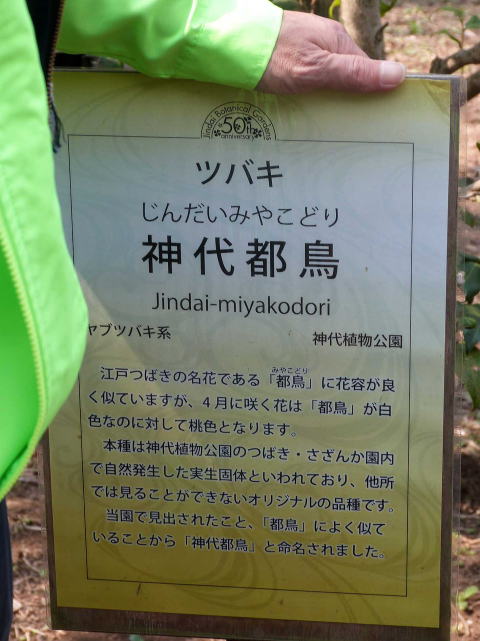 �@�_��s���̐����� �@�_��s���̐�����
�@�@ �@��� �@���
�@�@ �@�� �@��
�@�@ �@�g�̏� �@�g�̏�
�@�@ �@���� �@����
�@�@ ��ȍi ��ȍi
�R���P�V���i���j�ߌ�Q������A���x�͉��|�S���E���ɂ����E�T�U���J���K�C�h�c�A�[���J�Â����Ƃ̂��Ƃł���B����������Ƃ���ɁA�ē����f������Ă����B
�@�@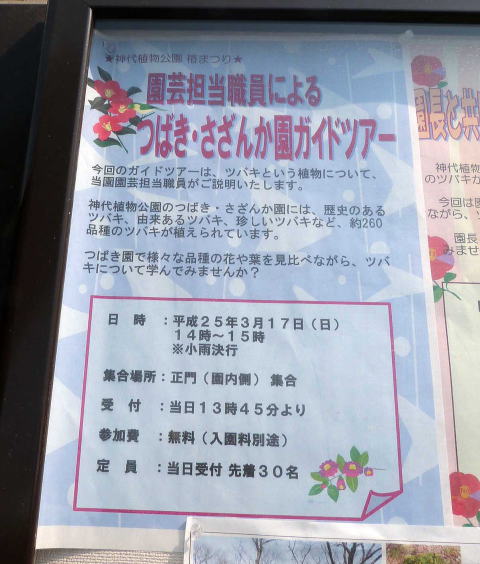 �@�K�C�h�c�A�[�̌f�� �@�K�C�h�c�A�[�̌f��
�܂��A�R���Q�O���ɂ́A�ߌ�P��������{�c�o�L�����؏�v���ɂ��u����u���S�҂̂��߂̃c�o�L�̖����ݕ��v���J�Â����B
�@�@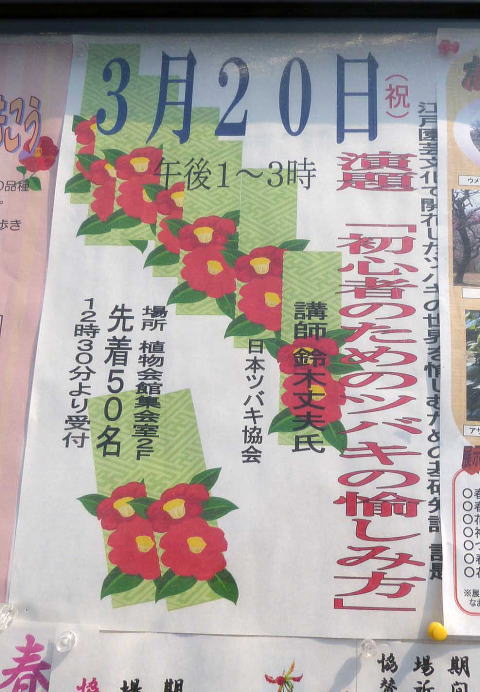 �@�u����̈ē� �@�u����̈ē�
|
|
|
|
| 2013�N3��10���i���j |
| ���N�̍��̊J�ԗ\�z�́H |
�@�����A�m�g�j�̂s�u�����Ă���ƁA���N�̍��̊J�ԗ\�z������Ă����B����ɂ��ƍ��N�́A���m�͂R���P�V���A���͂R���Q�U���A�����i�s�S�j�͂R���Q�R�����������B����͌��߂�ꂽ�W���̊J�Ԏ����̗\�z�ł���B�W���́A���m�ł͍��m��ɁA�����ł͖����_�Ђɂ�����̖ł���B�����Ɋւ��ẮA���N�̊J�ԗ\�z���́A�R���Q�U���ł���̂ŁA�J�ԗ\�z�Q�R���́A��N���R�������B�m�g�j�̋C�ۗ\��m�̓삳��̗\�z�ł́A�X�ɂQ�������A�R���Q�P�����������B
�@���̑f�l�̗\�z�ł����A�J�Ԃ���W���قǒx��Ė��J�ƂȂ�̂ŁA�����ł͍��N�́A���J�͂R���Q�W������R�O�����ŁA�R��������S���V�������Ԍ��̂���Ɨ\�z�����B
�@���z�s���̖��̃��C�g�A�b�v�́A��N�͂S���P�O���ł������B���N�́A���������Ȃ�̂��ȁH�Ə���ɗ\�z���Ă���B
�@���ׂĂ݂Ēm�����̂ł����A���̉ԉ�́A���������ɂł��Ă��āA�x�����Ă��邪�A�����ł��̋x������ڊo�߁A�R���ɓ����ċC�����㏸���Ă����ɂ�ԉ�͐������Ă����B���N�́A�������������̂ŁA���̉ԉ�́A�����ɋx������o�߁A���̎����̋C�������N��荂�������������Ƃ���A���̊J�Ԃ͕��N��菭�������Ȃ�Ƃ̗\�z�ƂȂ�悤���B
�@�Ƃ̒�ł́A������Ɣ~���J�Ԃ����B�~�̖Ƃ������ƂŁA�R�O�N�ȏ�O�ɍw�������ł��邪�A��N�J�Ԃ��x���̂ŁA�ق�Ƃɔ~���ǂ����l���Ă���Ƃ���ł���B
�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�
|
|
|
|
| 2013�N3��9���i�y�j |
| �R���������쒹�ώ@�� |
�@�������ł́A���N�P�O�����痂�N�̂S���܂ŁA������Q�y�j���ߑO���ɁA��ʌ����ɖ쒹�ώ@��s���Ă���B�ē�������̂́A�������̃{�����e�B�A�ł���B�Q���҂́A�ߑO�X���ɖ��������R�ώ@�Z���^�[�O�ɏW���ƂȂ��Ă���B���O�\�����݂͕s�v�ŁA���߂Ă̕����劽�}�ł���B
�@�������A���̖쒹�ώ@��̊J�Ó��ł������B�K�����V�C���悭�A��ϑ����̈�ʎs�����Q�����ꂽ�B���̐��͖�T�T���ł���B�X�^�b�t���P�O�������Q�����A�����S���Ă��q�l���ē������B�R�[�X�́A�X���Ɏ��R�ώ@�Z���^�[���X�^�[�g���āA���R�ώ@�����A�N���L��A����܂ŁA�������a�n��A�`�n��Ɖ���āA���R�ώ@�Z���^�[�ɂP�P�����ɖ߂��Ă���B�Ō�Ƀ��N�`���A���[���ŁA���������g���̊m�F�i�g�����킹�j���s�����B
�@�m�F�ł����g���̎�ނ͂Q�W��ł������B�ҋׂł́A�I�I�^�J�A�g�r�A�m�X���A�c�~���A�Z�L���C�ł́A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�̂R����A���ƃJ���Z�~�A�A�I�Q���A�J�V���_�J���m�F�ł����B
�@�@ �@�����Ƀm�X�� �@�����Ƀm�X��
�@�ߌ�A���]�ԂŌ����������A�S���P�R���J�×\��̂S���̖쒹�ώ@��̃|�X�^�[���A���������V�����Ɍf�����s�����B���́A���̂S�N�Ԗ쒹�ώ@��̃|�X�^�[�̍쐬�ƌf����S�����Ă���B����́A���̃V�[�Y���̍Ō�̖쒹�ώ@��ƂȂ�̂ŁA�����̎s���̎Q�������҂��܂��B
�@�@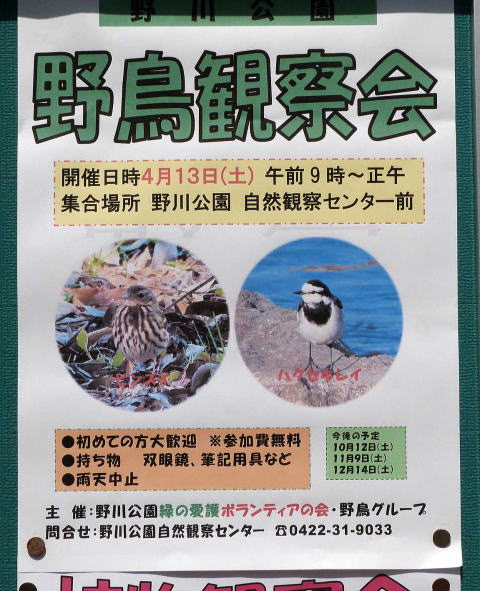 �@�S���쒹�ώ@��{�X�^�[ �@�S���쒹�ώ@��{�X�^�[
|
|
|
|
| 2013�N3��8���i���j |
| ����������̏������m�F |
�@����̌ߑO���A����������{�����e�B�A�̉�쒹�O���[�v�̌���쒹�ώ@���������B�{�����e�B�A�P�R�����Q�����A���������R�ώ@�����A�������a�n��A�`�n����Q���Ԕ������ĉ��A�쒹���ώ@�����B�ώ@�ł����̂͂R�P��̖쒹�ŁA�g�s�b�N�X�Ƃ��āA�u�E�O�C�X�̏����v���m�F�����B
�@�������̔~���ł́A�g�~�A���~�Ƃ��悭�炢�Ă����B���x�A���Y�����āA�~�̎}�ɂƂ܂��Ă��ꂽ�B�~�̉Ԃɂ̓��W���̌Q������Ă����B
�@�V���̌Q��́A���̎����n��ɍ~��āA�a��T���Ă����B
�@�@ �@�������~���̔~ �@�������~���̔~
�@�@ �@�������~���̔~ �@�������~���̔~
�@�@ �@�~�ƃ��Y �@�~�ƃ��Y
�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��
�@�Ƃ���ŁA��̏����Ƃ́A��̂��̔N�ŏ��̖����̂��Ƃ������B�~���I���A�t�̖K�����������̖����́A��̏����Ƃ��āA�Â�����l�X�ɐe���܂�Ă����悤���B�܂��A�g�@�،o�h�Ɩ����Ƃ���A��͂Ƃ��ɒ��d���ꂽ�B
�@�C�ے��̔��\���Ă��鐶���G�ߊϑ�����̏������̓��������}�ɂ��ƁA�P�X�W�P�N�`�Q�O�P�O�N�̕��N�l�́A�����ł͂R���P�O��������̏������������Ɠǂ߂�B
|
|
|
|
| 2013�N3��7���i�j |
| ���͂�̖�� |
�@�����Ȃ���́A��ł͂Ȃ��B�ł����A���̏㗬�̈ꕔ�ł͐��͂ꂪ�������Ă���B���̏ꏊ�́A�@����������̒��́A��܂��̏����㗬����Q�����ԁA�A�������̂��ʂ����t�߂ł���B�����P�W�N�R���ɂ������͂ꂽ���A����ȗ��̃s���`�ł���B���������R�ώ@���̋��r���������花�オ���Ă��܂��Ă���B������ʂ̉J�͊��҂ł��Ȃ��̂ŁA�T������܂ł́A���̐��͌������Ă������Ƃ��\�z����A�[���ȏł���B
�@�@ �@��삭�ʂ����㗬�̐��͂� �@��삭�ʂ����㗬�̐��͂�
�@�@ �@���R�ώ@�����̋��r�̐��͂� �@���R�ώ@�����̋��r�̐��͂�
�@������s�s���̉e���ŁA���̗���t�߂̟��{��ł̉J���Z�����A�������Ă��邱�Ƃ����{�I�Ȍ����ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł���B������n���́u���݂��v�́A�����Ȃ��̂ŁA���͕̂����肸�炢�B�J���Z�����A�Z�����ܑ��A�J���^���N�ȂǑi�߂��Ă��邪�A�܂��܂��ł��Ă��Ȃ����߂Ǝv�킴������Ȃ��B
|
|
|
|
| 2013�N3��7���i�j |
| ���̖�여��A��������ȉ� |
�@���A���z�s�̕�����ق�������ŁA��여��A��������ȉ�J�Â��ꂽ�B
��ȋc���
�@���̋����W�ɂ���
�A��여��͐쐮���v��̌������ɂ���
�B���c�J�_���̗���W�J�ɂ���
�ł������B
�@�@�́A���̋����W�ɂ��āA�����Q�T�N�x���ɂ��Q��قǃ��[�N�V���b�v���J�Â��A�A�C�f�A�����Ă������ƂɂȂ�B����̎s���ɂƂ��Ă������̂��ł���Ƃ��ꂵ�����ƂɂȂ肻�����B
�@�B�͖��̍��J��ɂ��߁A����Ɂu�s���J�������v�̍l���y�����A����S�̂ʼnJ���̈ꎞ���������邱�ƂŁA���J���̖��̗��ʂ̃s�[�N�J�b�g�����Ă������Ƃ������Ƃł���B
|
|
|
|
| 2013�N3��6���i���j |
| ���Ȃ̒���f�f |
�@����́A�䒃�m���̕a�@�܂ŁA���Ȃ̒���f�f�ɏo�������B�_�C�G�b�g�̌��ʂ́A�U�������炢���Ȃ��Ƃ͂�����o�Ă��Ȃ��Ƃ̈�t�̐�����M���āA�_�C�G�b�g��́A���̑̏d���ێ����邱�Ƃɂ����B
�@�A��ɁA�����ē����V�_�A�s�����@�뉀�A���̕s�E�r�Ɖ�����B
�����V�_�ł́A�Ԃ����̃O���[�v���A�~�����ɂ��Ă����B
�@�@ �@�����V�_ �@�����V�_
�s�����@�����ɂ͏��߂Ă������B�m�ق̓��������w�����B
�@�@ �@�s�����@�����m�� �@�s�����@�����m��
�@�@ �@�c�o�L�Ɛԃ����K�̕� �@�c�o�L�Ɛԃ����K�̕�
�������s�E�r�ł́A�a���֎~�̊Ŕ��o�Ă����B
�@�@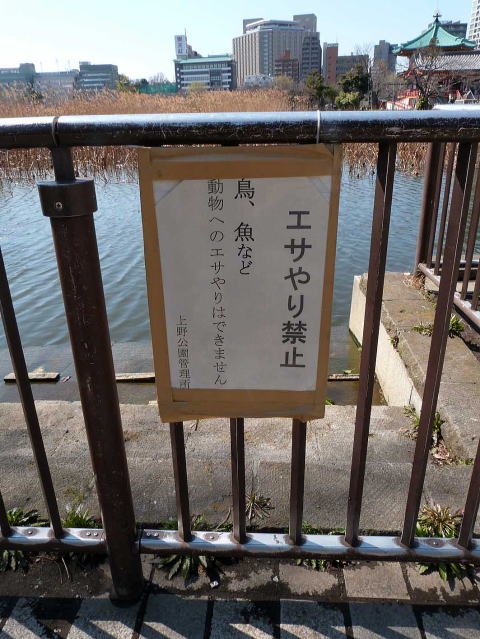 �@�a���֎~�̊Ŕ� �@�a���֎~�̊Ŕ� |
|
|
|
| 2013�N3��5���i�j |
| ���̖�여��A��������̕��ȉ� |
�@���A���z�̕�����ق�������ŁA��여��A��������̕��ȉ�J�Â��ꂽ�B
�c��́A�u���̑�����ɂ��āv�ł������B�c�_�̌��ʁA�����莞����ς������������邱�ƂɂȂ����B�ψ��������W�܂��āA�W�̎�����ɂ��Ď�����ς�����������s���A���̌��ʂ����Ă������Ƃɂ����B
���ʂ͂Ƃ������A�Ƃɂ�������Ă݂邱�ƂɈӖ�������Ɗ������B |
|
|
|
| 2013�N3��4���i���j |
| ����ҁF��̐���Ƀ��W�����E�E |
�@�������A��̐���ɁA���W�������Ă���B�J�����ɂ��Ă��铮��@�\�ŁA����łƂ��Ă݂��Byoutube�ɓ��e�����B���Ă��������B
�@http://www.youtube.com/watch?v=n-EguFdLTqE&feature=player_detailpage
�@���́Ayoutube�̓o�^����́A��ɖ쒹�����ɂ��Ă��邪�A���v�łT�U�{�ɂȂ����B���̂����������߂T�{�́@�@
�@�@���̉́E�E�H�w�Z�̐��k���쎌�A��Ȃ��A�̂��Ă��܂��B
�@�A�V�W���E�J���̑������E�E��̑������琗���炿�܂����B
�@�B�W���E�r�^�L�̖����E�E�����ԉ��ŃW���E�r�^�L�̖�����^��
�@�C�K�r�`���E�̖����E�E������ŎB�e
�@�D�A�I�W�������ԉ�
�@
�ł��B�@okinatokyo �Ō�������ƁA�o�Ă��܂��B
http://www.youtube.com/user/okinatokyo?feature=watch
�����������B
|
|
|
|
| 2013�N3��3���i���j |
| ��̐���Ƀ��W���̌Q�ꂪ�E�E |
�@��̐���ɂ́A�����V����������t����Ă���B��Ԃ悭���āA�В����Ă���̂̓q���h���ł���B�������ނ��A�~�ł��悭�����т�����B���̎��́A�V�W���E�J���ƃ��W���ł���B
�@�����́A���W���̌Q�����āA����́A�ɂ��₩�Ȃ��Ƃł����B
�@�@ �@���W���W�H �@���W���W�H
|
|
|
|
| 2013�N3��3���i���j |
| �@�����v�V����|�т̔~�ƃc�o�L�̊J�� |
�@�@����́A�����V����|�т̃{�����e�e�B�A�����i���x�Ǘ������j�̒�ኈ�����ł������B���v�P�V�����Q�����A�|�̔��̍�Ƃ������Ȃ����B���������������A���ӂ����Ȃ��犈���������B
�@���̂Q�N�Ԃ̊����ŁA�ꕔ�ł͒|�̖��x���������A�|�т͂����Ԗ��邳���Ƃ���ǂ��Ă����B���Ƃ��Ƃ����āA�����Ă����|�ɂ���������͂܂�Ă��܂������ɂ��A���͂̒|����蕥���āA�������������悤�ɂȂ��Ă����B���̒|�тɂ���~�ƃc�o�L�́A�������n�߂Ă���͂܂��Ԃ��݂Ă��Ȃ��������A���N���߂ĉԂ����邱�Ƃ��ł����B�����̐��ʂ��A�~�ƃc�o�L�̊J�ԂŌ��ĂƂ邱�Ƃ��ł��A�݂�Ȃł�낱�B
���N�ɂ́A�����Ƃ�������̉Ԃ����Ă����悤�ɁA���������A�撣�肽���B
�@�@ �@�c�o�L�̉� �@�c�o�L�̉�
�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�
|
|
|
|
| 2013�N3��2���i�y�j |
| �������肨�Ȃ��݂ɂȂ����W���E�r�^�L |
�@�����́A���V�C�͂������A���̋������ł���B�������肨�Ȃ��݂ɂȂ����W���E�r�^�L�i�Y�j�́A�������o�Ă��Ă��ꂽ�B���ꂵ���ЂƎ��ł���B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�Y�j �@�W���E�r�^�L�i�Y�j
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�Y�j �@�W���E�r�^�L�i�Y�j
�@���̐��ԏ����t�߂ł͔~�̉Ԃ��悭�炢�Ă����B
�@�@ �@�E�� �@�E��
�@�A���Ɏ̂ĂĂ������^�C������ϋC�ɂȂ��Ă����̂ŁA��T�̂Q�U���ɖk�����암���ݎ������ɏ��u�����肢���Ă��������A��������ƃ^�C�����Ȃ��Ȃ��Ă����B���u�����Ă��ꂽ�悤���B
�@�@ �@�@����㗬�E�݂Ƀ^�C��������i�Q���Q�U���j �@�@����㗬�E�݂Ƀ^�C��������i�Q���Q�U���j
�@�@ �@����^�C�����Ȃ� �i�����j �@����^�C�����Ȃ� �i�����j
|
|
|
|
| 2013�N3��1���i���j |
| �֓��n���Ɂu�t��ԁv�� |
�@���O���]�Ԃŋ߂��ɔ������ɏo�������B�������H�����]�Ԃő����Ă���ƁA���X�������ƂȂ�A���]�Ԃ���������ꂻ���ɂȂ����B�s�u�Łu�t��ԁv�Ƃ����Ă����B�ł���������́A�܂������Ȃ�悤�ŁA��C�ɏt�Ƃ͂����Ȃ��悤���B
�@�R���ɓ������̂ŁA�̏d�̂Q�����ϒl���܂Ƃ܂����B�Q���̕��ϑ̏d�͂U�O�D�Q�����ł������B��N�̂T������^�j�^�̑̏d�v�������Ă���A���������������ɑ�������Ă��邪�A�f�[�^�[���L�����āA�e��̕��ϒl��\�����Ă����B�P�P�����ςU�Q�D�W�����A�P�Q�����ςU�P�D�X�����A�P�����ςU�O�D�T�����Ɨ��āA�Q�����ς��U�O�D�Q�����Ȃ̂ŁA�ꉞ���o���h�͂Ȃ��A���Ƃ��ێ��Ă��Ă���悤���B���T�̉Ηj���ɓ��Ȃ̒���I�Ȑf�@���邱�ƂɂȂ�A���ʂ̌��ʂ����҂������B |
|
|
|
| 2013�N2��28���i�j |
| ���₩�ȓ��a�̖����� |
�@�����͑�ω��₩�ȓ��ƂȂ����B�S����{�̋C�����������B�������X���߂��ɉƂ��o�āA���]�ԂŁA�Q���ԂقǕ�����������̖��̂�܂����牺���̌䓃�⋴�Ԃ�������葖�����B�����ԉ��t�߂ł́A�E�O�C�X�̒n�����������A��u�p���m�F�ł����B���\�Y���t�߂ł́A��Q���w�Z�̐��k���A�搶�Ɉ�������āA���t�߂̌��w�ɗ��Ă����B������������ł́A�������܂��ԂŁA��삪���͂���N�����Ă����B��J�ق����Ƃ���ł���B���̌͂ꂽ���̉͏��ł́A�c�O�~�A�L�W�o�g�A�n�N�Z�L���C���a��T���Ă����B�߂��ɂ̓W���E�r�^�L�i���j�̎p���������B������������ł́A�V���n���̎p�����������B
�@�@ �@��܂����猩����i�������j �@��܂����猩����i�������j
�@�@ �@��܂����猩����i�㗬���j �@��܂����猩����i�㗬���j
�@�@ �@�V���n�� �@�V���n��
�@�@ �@�V���n�� �@�V���n��
�@�@ �@�W���E�r�^�L�̎� �@�W���E�r�^�L�̎�
�@���ł́A�J���Z�~���S�������B���Ȃ�J���Z�~�̐��������悤�Ɋ�����B�W���E�r�^�L�̗Y�̎p���Q�������B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�̗Y �@�W���E�r�^�L�̗Y
�@�@�@ �J���Z�~�i�Y�j �J���Z�~�i�Y�j
�@�@ �@�J���Z�~�i�Y�j �@�J���Z�~�i�Y�j
�@�@ �@�J���Z�~�i���j �@�J���Z�~�i���j
�@�@ �@�J���Z�~�i�Y�j �@�J���Z�~�i�Y�j
|
|
|
|
| 2013�N2��27���i���j |
| �|�ъǗ������̉��� |
�@���������ł��邪�A�y�j���̒�ኈ���̌�����������A�����ꏊ�̈��S���m�F�A�����̗\��𗧂Ă�Ȃǂ̏���������K�v������A�J���~�P�O�������납��V����̒|�тɉ����ɂ������B��ɑ���̌͂�|�̐��������Ă�����A�����ɂQ���Ԃقǂ����Ă��܂����B
�@�C���t���ƁA�V���̂Q�K����A�N���̑傫�Ȑ�������A�u����J�l�v�u�撣���Ă��������v�ƌĂт����Ă���B�ǂ������k�̂悤���B���́u�L��v�Ƒ傫�Ȑ��œ������B���k�����́A�{�����e�B�A���|�тŊ��������Ă��邱�Ƃ�m���Ă���悤���B
�@�@ �@�V���O�̒|�сi�����ɂV���̍Z�ɂ�������j �@�V���O�̒|�сi�����ɂV���̍Z�ɂ�������j
|
|
|
|
| 2013�N2��26���i�j |
| �~�Ƀ��W�� |
�@�ߌ�A���]�ԂŁA�_��A�������̔~���ɔ~�̉Ԃ̗l�q�����ɍs�����B�u����g�v�Ƃ����i�킪��r�I�悭�炢�Ă����B�ʐ^���B���Ă�����A���W���̌Q�ꂪ����Ă����B�u�~�ɃE�O�C�X�v�͂Ƃ肠�킹�̂������Ƃ̂��Ƃ��Ɏg���邱�Ƃł���B�ł��A�ʐ^�́u�~�Ƀ��W���v�ł���B���̕����A�悭�݂�i�F�ł���B���W���͉Ԃ̂�����悭�m���Ă���悤���B�u���~�v��u�@�v�v�Ƃ����g���i��̔~���炫�n�߂Ă����B
�@�@ �@�~�Ƀ��W�� �@�~�Ƀ��W��
�@�@ �@�~�Ƀ��W�� �@�~�Ƀ��W��
�@�������ߑO���������E���̎��ӂ����]�Ԃł�����葖�����B���̎����A�������ɂ���̂́A�I�i�K�K���A�J���K���A�}�K���ł���B���Y���R�������B��Ԃ悭�����̂̓c�O�~�ł������B�N���L��ł́A�������L�Z�L���C�������B
�@�@ �@���Y �@���Y
�@�@ �@�L�Z�L���C �@�L�Z�L���C
|
|
|
|
| 2013�N2��25���i���j |
| �W���E�r�^�L�̖��� |
�@�ߑO���A���]�ԂŁA���̑����V�O���Ԃ�������葖�����B���́A������s�̂�܂��t�߂Ő����͂�Ă����B��������㗬�����A���������A���Ȃ��Ȃ��琅�͗���Ă����B
�@�@ �@����܂��t�߁@(�㗬���j �@����܂��t�߁@(�㗬���j
�@�O��s�̎����ԉ��ł́A�W���E�r�^�L�i�Y�j�����Ă����B�������A�߂��Ŏʐ^���B�ꂽ���A�����ԁi�Q�O���قǂ��j���Ă��ꂽ�B�@�}�ӂɂ́A�W���E�r�^�L�́u�q�b�A�q�b�v�Ɩ��Ə����Ă���B
�@�@ �@�W���E�r�^�L(�Y�j �@�W���E�r�^�L(�Y�j
�@�@ �@�W���E�r�^�L(�Y�j �@�W���E�r�^�L(�Y�j
�@�W���E�r�^�L(�Y)�̓���@�@�������������܂��B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lSIp2y1Mxwg
�@�����͖��t�߂łR��W���E�r�^�L�̎p���������A��������Y�ł������B���܂��܂̂��ƂƎv���Ă���B
|
|
|
|
| 2013�N2��24���i���j |
| ��ɃW���E�r�^�L�i�Y�j���E�E�E |
�@�ŋߎ���̒�ɃW���E�r�^�L���p��������悤�ɂȂ����B�Ƒ��̘b�ł́A�ߑO���P�x�����̂悤���B�����̌ߑO���́A�����Ƃɂ����̂ŁA�ʐ^���Ƃ邱�Ƃ��ł����B
�@�@ �@�W���E�r�^�L(�Y�j �@�W���E�r�^�L(�Y�j
�@�@ �@�W���E�r�^�L(�Y�j �@�W���E�r�^�L(�Y�j |
|
|
|
| 2013�N2��24���i���j |
| ���j���̒��́A�s�a�r�s�u�́u�������k�v������ |
�@�������A�s�a�r�s�u�́u�������k�v���݂��B�i��͌�~�M����A�Q�X�g�͕������`����Ɓ@�W�G�����h�E�J�[�e�B�X����B�����̘b��́u���Ď�]��k�̗��v�ł���B
�@ ����̎�]��k�ɂ��ẮA�J�[�e�B�X����́u��ۂ悩�����v�ƁA����������u�������S�z���Ă������A���܂��������Ɗ��ł���v�ƁB�����A�f�l�̈�ۂł��邪�A���܂��������悤�Ɋ����Ă���B
�@ �s�o�o�Ɋւ��ẮA�J�[�e�B�X����́A�u�A�����J���O���猾���Ă��邱�Ƃ���{������Ǝ��Ƃ������ƁB�����Ƃ��ɃZ���V�e�r�e�B����B�A�����J�́u�����ԁv�A���{�́u�āv�B�����s�o�o�Q�������߂Č�����̂������v�ƁB��������́u����͓����̘b�ł���A�e�_�̋c�_�����ꂩ��n�܂�v�ƁB
�J�[�e�B�X����́A�u�A�����J�ɂƂ��Ắu�Ń[���v�͌��O�ł���A�{���͈Ⴄ�B�ꉞ�ڕW�̓[���Ƃ���Ƃ������ƂŁA�A�����J�ɂƂ��Ắu�����ԁv���A�傫�ȃe�[�}�ƂȂ�B�N���◈�N�ɂ͌��_�o��Ƃ͎v���Ȃ��B��ʂ̃A�����J�l�͂s�o�o�̊S�͒Ⴂ�v�ƁB
�@��t���ɂ��ẮA�J�[�e�B�X����́u�����͗͂ł����āA���낢��Ƃ���Ă���B�o�����X���Ƃ邱�Ƃ���B���{����́u�K�ߕ�����́A������ŁE�E�E�v�Ƃ̔����̓o�����X���Ƃꂽ�����ł������v�ƁB
�@
�@�k���N���ɂ��ẮA�J�[�e�B�X����́u�L�[�͒����ł���B���������قɉ����Ȃ��ƈ��͂ɂȂ�Ȃ��v�B����������A�u�|�C���g�͒����ł���B�B�R�Ƃ����p�����o���邩�ǂ����ł���v�ƁB
�@�Ō�ɎɈꌾ�́A�@��������́u���{����̊�͑I���̑O�̓^�J�h�̊�A���̓o�����X���o������A���̊�͑�D���B���̊��ς��Ȃ��łق����v�ƁB�J�[�e�B�X������u�O���͐T�d�ɁB�R�{�̖�̍\�����v���A�v�����đ�����邱�Ɓv�ƁB
�@�������Ȃ���A���Ȃ����邱�Ƃ������������A���ɂȂ����B
|
|
|
|
| 2013�N2��23���i�y�j |
| �����E�I�[�L���O�i���\�Y���`�n���j |
�@�ߑO���A���𑊑\�Y������n���Ԃ��E�I�[�L���O�����B�����ԉ��ł́A�A�I�W�̎p���݂��B���x�ʂ̐l�����Ă̂ŁA���̑��̃g���͔��ōs���Ă��܂��A�c�O�ł����B
���̍����~�ɍ~���ƁA�I�I�C�k�m�t�O����z�g�P�m�U���炢�Ă����B
�@�@ �@�I�I�C�k�m�t�O�� �@�I�I�C�k�m�t�O��
�@�@ �@�z�g�P�m�U �@�z�g�P�m�U
���ł́A�����̂悤�ɁA�J���Z�~�A�W���E�r�^�L�A���Y�A�c�O�~�A�I�i�K�K���A�J���K���A�}�K���A�R�K���A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�L�Z�L���C�Ȃǂ̖쒹�̎p�������B
���z�s�̑勴�t�t�߂ɂ́A�����Q�S���ɍs����u���N���[�����v�̌f���������Ă����B
�@�@ �@���N���[����� �@���N���[�����
�R�K���̌Q�ꂪ����ɓ����܂���Ă��āA�������������Ă����B�I�i�K�K���̖����������Ƃ����邪�A�������̖����͏��߂Ă��������B�}�ӂɂ̓R�K���̃I�X�́u�s���b�s���b�v�Ɩ��A�I�X�́u�N�F�[�N�F�N�F�v�Ɩ��ƋL�ڂ���Ă���BYoutube�ŕ����Ă��������B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lnwBIglaks0
�쉈���̉Ƃ̔~�̖����ꂢ�ɍ炢�Ă����B
�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�
�n��(�b�B�X���j�Ŗ��ƕ�����A�č�w�ɏo�āA�������Œ��z�ɏo�āA�o�X�ŋA���Ă��܂����B
|
|
|
|
| 2013�N2��22���i���j |
| �_��A�������A�����l���Z���^�[ |
�@�ߑO���P���ԂقǁA�_��A�������A�����l���Z���^�[�����w���܂����B�p���t���b�g�ɂ��ƁA���̐A�����l���Z���^�[�́A�u�s���ɂ�����A�����l���ۑS����肢���������i���邽�߁A�ۑS�̂��߂̗l�X�ȋ@�\�𑍍��I�Ɉ������_�{�݂ƂȂ邱�Ƃ�ړI�ɐݗ��v����܂����B�u������ɐA���̑��l�����c�������v�Ɗ���āA�u�����W�E���M�A�ی�E���B�A����E���y�����Ɋ�����W�J�v����Ă��܂��B
�@�����̌f���łɂ́A�����̂킩��₷���ē�������Ă����B�������̐A���́A�Z�c�u���\�E�ƃt�N�W���\�E�B�w�K�قł́A�t�̎����̓��ʓW���A�w�K���ł́A�y���ɃK�C�h�c�A�[�i�P�S������S�O���قǁj���邻���ł��B
�@�@ �@�f���� �@�f����
�@�@ �@�t�̎����W �@�t�̎����W
�@�@ �@�w�K���̈ē� �@�w�K���̈ē�
�@���炢�Ă���Ԃ́A�\�V�����E�o�C�A�Z�c�u���\�E�A�t�N�W���\�E�ł������B
�@�~�̃J�����i�f�V�R��T�������A�������A�琬����Ă��邾���ł������B�����ł́A�S�ʓI�ɖ��D���悭��������Ă����B
�@�@ �@�t�N�W���\�E �@�t�N�W���\�E
�@�@ �@�Z�c�u���\�E �@�Z�c�u���\�E
�@�@ �@�~�̃J�����i�f�V�R �@�~�̃J�����i�f�V�R
|
|
|
|
| 2013�N2��22���i���j |
| �W���E�r�^�L�̗Y�������ԉ� |
�@�����A�ߌ�P��������̎����ԉ��ɍs������A�W���E�r�^�L�̗Y�������B�ŏ��͏������ꂽ�ʒu�ɂ������A�����炪�����Ƃ��Ă�����A���܂��܂����߂��ɔ��ł��āA�킸������ʒu��ς��Ȃ���A�U���قǂ̊ԁA�߂��ŁA���낢��ȃ|�[�Y�Ŏʐ^���B�点�Ă��ꂽ�B��ڈ���̃V���b�^�[�`�����X�ł������B
�@�@ �@�@�W���E�r�^�L(�Y�j �@�@�W���E�r�^�L(�Y�j
�@�@ �@�@�W���E�r�^�L�i�Y�j �@�@�W���E�r�^�L�i�Y�j
|
|
|
|
| 2013�N2��21���i�j |
| ���������g������ |
�@�@�����́A���ɒ������g���ɂ͉�܂���ł����B�悭����W���E�r�^�L�A���}�K���A�A�I�W�A�J���Z�~�A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A���Y�A�V���A�V�W���E�J���Ȃǂ����܂����B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i���j �@�W���E�r�^�L�i���j
�@�@ �@�W���E�r�^�L(�Y�j �@�W���E�r�^�L(�Y�j
�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
|
|
|
|
| 2013�N2��21���i�j |
| �_��A�������̔~�̗l�q |
�@������A�_��A�������ɔ~�̗l�q�����ɍs���Ă��܂����B�����̕��ɕ����ƍ��N�͏����J�Ԃ��x�������ł��B�ł��A�~���ł͐��{�͍炫�n�߂Ă��܂����B
�@�@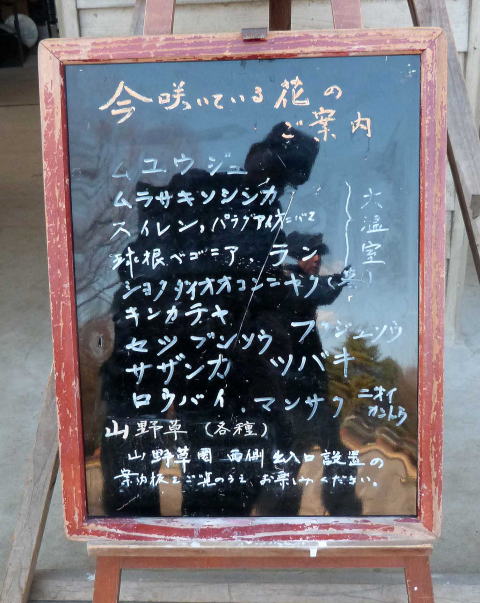 �@�ē��� �@�ē���
�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�
�@�@ �@�~�̉� �@�~�̉�
�@�~���̋߂��ɂ��郍�E�o�C�A�\�V�����E�o�C�A�}���T�N���悭�炢�Ă��܂����B�}���T�N�ɂ́A���|��ŁA�_�C�A�i�Ɩ��t����ꂽ�Ԃ��Ԃ̃��E�o�C���������B
�@�@ �@�\�V�����E�o�C �@�\�V�����E�o�C
�@�@ �@�}���T�N�i���|��F�_�C�A�i�j �@�}���T�N�i���|��F�_�C�A�i�j
���ɂ́A�t�N�W���\�E�A�Z�c�u���\�E�A�N���X�}�X���[�Y���炢�Ă����B
�@�@ �@�t�N�W���\�E �@�t�N�W���\�E
�@�@ �@�N���X�}�X���[�Y �@�N���X�}�X���[�Y
|
|
|
|
| 2013�N2��20���i���j |
| �����ӂ�T�� |
�@�����玩�]�ԂŁA�g���̂������ȏꏊ���n�V�S�����B�x�m�R�����ꂢ�ł������B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
�@��쑊�\�Y���߂����Ă����������ʂ蔲������������ցB�܂��������ɖ߂��āA���������Ŗ��ƕ����ꂽ�B��Q���Ԃ̃g�����ł������B
�@�����ԉ��ł́A�J�V���_�J�A�A�I�W�A�V���A�J���K���Ȃǂ̎p���������B����������ł́A�������~���}�z�I�W���ɂ͉�Ȃ������B�������ł́A�����̓q�����W���N�͂��Ȃ������B���ł́A�R��J���Z�~�������B�W���E�r�^�L(���X)��Y�������B�N���L��ł́A�L�Z�L���C�ƃn�N�Z�L���C�����ӂ̂����B
�@�@ �@�J�V���_�J �@�J�V���_�J
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�@�@ �@�W���E�r�^�L �@�W���E�r�^�L
�@�ߌ�A�����V����̒|�тŁA�P���Ԕ��قǒ|�т̍�Ƃ̉��������A���̂���|�Ƀ}�[�L���O�������B�߂��ɃV���n���������B
�@�@ �@�V���n�� �@�V���n��
|
|
|
|
| 2013�N2��19���i�j |
| �R�̌��ѕ� |
�@��T�̙���u�K��ł́A�u�j���сv���A����}��̂Ɏg�����B���́u�j���сv�́A�q���̂���A�o�ׂ���ו��������Ƃ��ɂ悭�g���Ă����̂ŁA���ł��o���Ă���B�ȒP�ŁA���肵�����тł���B
�@
�@�����V����̒|�тł̃{�����e�B�A�����ł́A�|����������̂Ɂu���₢���сv�������B���̂ق��Ɂu�ӂ����сv���g���B���̂Q�́A�ŋ߉��x�����K�����āA��������o�����B
�@�@ �@�@���u���₢���сv�A�E�u�j���сv �@�@���u���₢���сv�A�E�u�j���сv
|
|
|
|
| 2013�N2��18���i���j |
| ���̗��ʑ���(�Q���j |
�@�ߑO���A���̗��ʑ�����A�O��s�̂R����(�x�m���勴�A�A��j�ōs�����B������������A�ŏ��͊����������A���̂����������C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ����B��l�ő�����s���Ă���Ƌ߂��ɃJ���Z�~�����ł��邱�Ƃ�����B����l�́A�挎�̑���l�Ƃقړ������x���ł������B����ȏ�A���ʂ�������Ȃ����Ƃ��肤�B
����́A���q�𗬂��ė����𑪂���@�ő�������Ă���B��̗���ɒ��������Q�{�̃^�R�����͂�A���̊Ԋu�͂Q���Ƃ����B
�@
�@�@ �@�㗬�ł̑���̗l�q �@�㗬�ł̑���̗l�q
�����́A�T��J���Z�~�ɉ�����B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
|
|
|
|
| 2013�N2��17���i���j |
| ���ɒ����N���ʂ̑���(�Q���j |
�@�����͌ߑO���A�����s���Ă�����ɒ����N���ʑ�����P�R�����i�����`�Y�ԁj�ōs�����B���v�̗N���ʂ́A�挎�̑���l����P�O�����܂茸�����Ă����B
�@���͊������������A�W����������X�^�[�g�����B���ߎ��߂��ɖ����I���A�ق��Ƃ����B
�@���������̍����`���ʂ����ԂŁA���̗ʂ����ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ��낪����܂����B����������������A���͂�ɂȂ肻���Ɋ����܂����B
�@�@ �@�����`���ʂ����Ԃ̖��̗l�q �@�����`���ʂ����Ԃ̖��̗l�q
|
|
|
|
| 2013�N2��17���i���j |
| �߂��̌����Ƀq�����W���N���E�E�E |
�@�Q���قǑO�ɏ������������Ă������A�����̌ߌ����ƃq�����W���N�ɉ���Ă��܂����B�@
�@���̃g���́A�~���Ƃ��ēn���Ă��āA�Q��Ă��邱�Ƃ������悤�����A�߂��̌����ɂ͌Q��ł����P�H�����̂܂c���Ă���悤���B�}�ӂɂ��ƁA�̂͑����A�Z���A���̐�͐Ԃ��A�������H�𗧂ĂĂ��邱�Ƃ����������ł���B�̎���̎�����H�Ƃ��Ă��邻���ł���B�߂��̌����ł́A�Ԃ�����H�ׂĂ��܂����B�����L�`�W���E�\�E�̎����Ƃ������܂��B
�@�@ �@�q�����W���N �@�q�����W���N
�@�@ �@�q�����W���N �@�q�����W���N
�@�@ �@�L�`�W���E�\�E�̎� �@�L�`�W���E�\�E�̎�
|
|
|
|
| 2013�N2��16���i�y�j |
| ��Ύ��̙���u�K��O��s�x���������� |
�@�����������A�₽�������B�O��s�ł��������̖k���ɂ���x�����������ŁA�ԂƗ̂܂��O��n�������Â̙���u�K��������B����̃e�[�}�́A�L�����N�Z�C�ƃJ�C�Y�J�C�u�L�Ȃǂ̏�Ύ��̎}��������ł���B����P�U�����Q�������B
�@�@ �@�u�K��̗l�q �@�u�K��̗l�q
�@���A�u�K���ɑ����������̂ŁA���Ԃ�����A�߂��̂i�q�������̓S���ɏオ���Ă݂��B�����͕x�m�R���������茩�����B���Ɏ������̋߂��ɏZ�݁A���̓S������݂�O��̕��i���y�����������A�����x�m�R���������Ƃ��낤�Ƒz�������B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
|
|
|
|
| 2013�N2��15���i���j |
| ��̓����R�������̔N�ԃp�X�|�[�g |
�@�����́A�m��\���̏����ł���B���܂Ȃ������ɂƒ�������ɕ�����Ŗ����ɏ��ނ��o�ɂ������B�A�蓹�A�g�ˎ����ʂɕ����A��̓����R�����������Ă����B�����̔N�ԃp�X�|�[�g�̗����́A��ʂ͔N�P�U�O�O�~�ŁA���U�T�Έȏ�͔��z�ł���A�w��������P�N�ԗL���ł���B
�@�P�O�����ɕ������ɓ������̂ŁA����҂͂قƂ�nj��������A�E�������������Ă���p�����邾���ł������B�E��̃J���V�J�A���N�V�J�����Ă���A�A�W�A�]�E(�Ԏq)���݂��B�ŏ��́A�Ԏq�͕����̊O�ɂ������A�������Ă���ƁA���炭���ĕ����ɓ����Ă��܂����B���������w�ł���̂œ����Ă݂�ƁA�E���̕��Q��������ꂽ�B�����Ă݂�ƍ����͊����̂ŁA�����ɖ߂����Ƃ̂��Ƃł������B�����͒g�[�����Ă������B
�@�@ �@�J���V�J �@�J���V�J
�@�@ �@�]�E�i�Ԏq�j �@�]�E�i�Ԏq�j
�@
�@�ׂ̔M�ђ������ł́A���߂Č���A���O�̂悭�킩��Ȃ��N�₩�ȃg�����A�傫�ȕ����Ő��펔�炳��Ă����B�T��قǂ͌��邱�Ƃ��ł����B�^���Ԃȃg���������B
�@�@ �@�M�т̃g�� �F�I�E�M�o�g �@�M�т̃g�� �F�I�E�M�o�g
�@�@ �@�M�т̃g�� �F�V���E�W���E�g�L �@�M�т̃g�� �F�V���E�W���E�g�L
�@���̌�A���X�̏��l�ɂ������Ă݂��B���������̃��X�̑��ɁA�g���̃A�J�n���R�H�A�R�W���P�C�Q�H�������Ă����B
�@�@ �@���X �@���X
�@�쒹�̐X�ł́A���낢��̖쒹�����邱�Ƃ��ł��A�o�[�h�E�I�b�`���O�̗\�K�ɍœK�ł���B�m�X���A�`���E�Q���{�E�A�A�J�n���A�V���n���A�c�O�~�A�q�o���A���W���A�R�W���P�C�A�E�\�A�x�j�}�V�R�A�L�r�^�L�ȂǕ��i�Ȃ��Ȃ����R�̏�Ԃł͌����Ȃ��g�����������炳��Ă����B
�@�ߌォ��J�̗\��Ȃ̂ŁA�����͂����ɕ��������o�āA���̓����O��w�܂ŕ����A�o�X�ŋA���Ă����B
|
|
|
|
| 2013�N2��14���i�j |
| �u���̓��v������A��̓������� |
�@�����́A�v���Ԃ�Ɂu���̓��v�i�O��w��������̓������������ʐ�㐅�����̓��j������A��̓������֍s�����B
�@�r���A�R�{�L�O�L�O�ق̒��q�������B�O��̔~�̖Ȃǂ̙��肪�������肵�Ă����B�悭����ꂪ����Ă����ł���B�L�O�ق̒��ł́A���L�O�L�O�ي��W�u�R�{�L�O�̕��w�C�s�v���J�Â���Ă����B�f������Ă���|�X�^�[������ƗL�O�̌��t�Ƃ��āu�������͒x����������Ȃ��B���ǂ�͂��ǂ��ǂ������낤�B�����i�ނׂ��������͎��Ⴆ�Ă͂�Ȃ�����ł���v�Ə�����Ă���B��ϋ����ł��錾�t�ł���B
�@�@ �R�{�L�O�L�O�� �R�{�L�O�L�O��
�@�@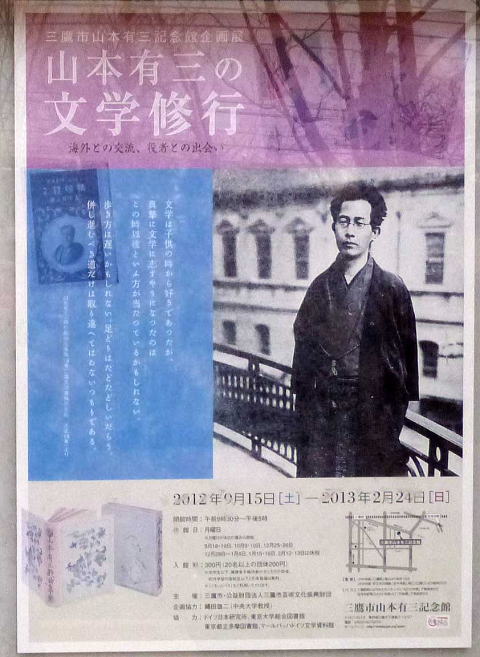 �@���W�̃|�X�^�[ �@���W�̃|�X�^�[
�@�������̋߂��̃��X�g�����u���E�z���e�v�ŃP�[�L�ƃR�[�q�ňꕞ���A���̌��̓���������������B��{�����~���悭�炢�Ă����B�r�ł́A�L���N���n�W���A�I�i�K�K���A�J���K���A�J�C�c�u���A�J���Z�~�Ȃǂ̎p�����������A���͂���Ȃɑ����͂Ȃ������B���̌����ł́A�J���ɉa�������邱�Ƃ��֎~���Ă��邱�Ƃ̂������ʂ��o�Ă��āA�����}�����Ă���悤���B�J�C�c�u���͂R�O�b�قǐ������Ă����B
�@�@ �@���E�z���e�ŃR�[�q�ƃP�[�L �@���E�z���e�ŃR�[�q�ƃP�[�L
�@�@ �@�E���̉� �@�E���̉�
�@ �@�J�C�c�u�� �@�J�C�c�u��
�@�Ō�́A�g�ˎ��w�̓���ɏo���B�����L.L.Beans�Œ��x�Q�O�������Z�[��������Ă����̂ŁA�����̂����Ă݂��B�������̓o�X�ŋA���Ă����B
|
|
|
|
| 2013�N2��13���i���j |
| �����͐��ꂽ���A�������������B |
�@��́A�\�z�ʂ菭�Ȃ��������A�����́A����Ă����������B��قǂi�}�[�g�ɁA�������ɍs�������A���������I����Ē��֏�ɖ߂��Ă���Ǝ��]�Ԃ����œ|����Ă����B�������H�𑖂��Ă��A���܋����������āA���]�Ԃ�i�߂�̂���ς������B
�@����ł́A�g�����o�Ă��Ȃ��̂ŁA�Ƃł�����肷�邱�Ƃɂ����B
�@
�@�����́A�����N���āA�m��\���̏��ނ�e-Tax�ō쐬���邱�Ƃɒ��킵���B |
|
|
|
| 2013�N2��12���i�j |
| �����s����A�ԂƗ̂܂��O��n������Ɏ��@�� |
�@�ߌ�P���߂�����A�ԂƗ̂܂��O��n������ɕ����s����u�ӂ����܊X�Â��薲�d�|���l�m�v�Ǝs�̌����Βn�ۂ���v�P�O���قǂ̕������@�ɂ����܂����B�n������̕����A�P���Ԕ��قǂ����A�@�n������ݗ��̂������A�A�{�����e�B�A�����ɂ��Đ������ꂽ�B
�@�@�O��s�́A��̓������A�������A���ۊ����w�A�����V����Ȃǂ̑傫�ȗ������Ă���B�A�R�̗�(���A�ےr�A����̗�)������B�B���̑��̂Q�Q�X�̌����́A�P�O�O�������[�g���ȉ��̏����ȂƂ��낪�����A���̎��̌��オ�ۑ�ł���A�|�̐������������B
�@���̌�̎���̈ꕔ���邽�߁A�������{�����e�B�A�Q���i�Ԓd�{�����e�@�C�P���Ɨ̃{�����e�B�A�P���j���A���Ȃ��A����ɓ������B��X�ւ̎���́A�@�{�����e�B�A�����ɎQ���������@�́H�@�A�O��s�́u�ԂƗ̂܂��v�Ƃ�����̂��H�ł������B
�@�Ō�ɁA�n������̑O�ŊF�ŋL�O�B�e�����Ă���A���^�̃o�X�ɏ��A�@�R�~���j�e�B�K�[�f���i�X�|�b�g�K�[�f���j�A�@�A�����V����|�сA�B�ԂƗ̍L��̂R�����̌��w�ɍs���ꂽ�B
�@�@ �@�n������̐����̗l�q �@�n������̐����̗l�q
�@�ȏ�A�n���������A����̎��@�ɂȂ��O��s��I�ꂽ�̂��ɂ��Ă����������ۂɂ́A�������Ƃ��āA�@�O��s�ŊJ�Â��ꂽ�u�K�[�f�j���O�t�G�X�^�[�v�̍��q���������ƁA�A�O��́u�Z�݂����܂��v�̃����L���O���������Ƃ�������ꂽ�B
|
|
|
|
| 2013�N2��12���i�j |
| ��̐���ɁA�쒹������Ă���B |
�@�~�͐��������������A�g���̐��ꂪ���Ȃ��Ȃ�̂ŁA���N�O�����ɐ��������Ă���B��A�́A�V�W���E�J���A���W���A�q���h���A���N�h���Ȃǂł��邪�A���܂ɂ́A�L�W�o�g�A�c�O�~�A�W���E�r�^�L�A�V���A�V���n���Ȃǂ̎p���݂邱�Ƃ�����B�������A�������X�������āA�������ւ�����A�������W���ƃV�W���E�J��������Ă����B���ނ����łȂ��A�����̂ɐ����т�����B
�@�@ �@���W�� �@���W��
�@�@ �@���W�� �@���W��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
|
|
|
|
| 2013�N2��11���i���j |
| �����́A���E�������E��������������A�g����T�� |
�@�����́A�W���߂��Ɏ��]�ԂʼnƂ��o�āA���̑��\�Y���߂��̎����ԉ������āA���������R�ώ@���A����������A�������`�C�a�n��A������̐X�����A���z��s��̃v���y���J�b�t�G�A���̑�`��܂��ԁA����������A�������Ɖ�����B��������ɂ͐��ʂ��R�����A���ړ��ẮA�x�j�}�V�R�A�R�C�J���ɂ͉�Ȃ������B�W���E�r�^�L(���X)�A�V���n���A�L�Z�L���C�̎ʐ^���Ƃꂽ�̂͂��ꂵ�������B
�@�@ �@�W���E�r�^�L �@�W���E�r�^�L
�@�@ �@�V���n�� �@�V���n��
�@�@ �@�L�Z�L���C �@�L�Z�L���C
�@���R�ώ@���ł́A�t�N�W���\�E�ƃZ�c�u���\�E���悭�炢�Ă����B�X��������͂܂��悭�炢�Ă��Ȃ��������A�P�Q���߂��ɂQ�x�ڂɍs�����Ƃ��ɂ́A�悭�炢�Ă����B�Ԃ���͐Q�Ă���̂ł��ˁB
�@�@ �@�t�N�W���\�E �@�t�N�W���\�E
�@�@ �@�Z�c�u���\�E �@�Z�c�u���\�E
�@
�@�v���y���J�b�t�G�ׂ̗ł́A���{�ōŌÂ�Cessna150c�^��s�@�i�P�X�U�R�N���j���A���ʂɓW������Ă����B�悭��������A���ł���Ԃ��Ƃ��ł��邻���ł���B
�@�@ �@���{�ŌÂ�Cessna150C�^��s�@ �@���{�ŌÂ�Cessna150C�^��s�@
�@���������g���́A�R�T�M�A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�I�i�K�K�K���A�q�h���K���A�o���A�L�W�o�g�A�J���Z�~�A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�q���h���A�W���E�r�^�L�A�V���n���A�c�O�~�A���}�K���A�V�W���E�J���A���W���A�J�����q���A�}�q���A�V���A�X�Y���A���N�h���A�n�V�{�\�K���X�A�n�V�u�g�K���X�ł����B
|
|
|
|
| 2013�N2��10���i���j�@ |
| �����́A�������̗쉀�ɍs���Ă��܂����B |
�@�����́A�@���Ő������̗쉀�ɏo�����Ă��܂����B�K���A�����Ȃ��A���₩�ȓ��a�ł����B�@�v�̂��ƁA�����s�̏��a�̐X�t�I���X�g�C�����a�قP�e�́u���a�̐X�ԉ��v�Ɉړ����A��H�����܂����B�z�e���̈�p�ɂ��邱�̃��X�g�����́A�������������͋C�̂��X�ŁA�����̂ЂƎ����߂������Ƃ��ł��܂����B���̃z�e���ɂ͏����w�k������V���g���o�X���^�s����Ă��܂��B
�@�@ �@��ȗ����̈ꕔ �@��ȗ����̈ꕔ
|
|
|
|
| 2013�N2��9���i�y�j |
| �����́A�������Ŗ쒹�ώ@�� |
�@�ߑO�X���A���������R�ώ@�Z���^�[�O�ɋߗׂ̎s�����R�V���W�܂�A�{�����e�B�A�̃X�^�b�t�P�O���ƈꏏ�ɖ������̓~����T���쒹�ώ@��s��ꂽ�B�����t�C�[���h�X�R�[�v�������āA�X�^�b�t�Ƃ��ĎQ�������B���R�ώ@���A�������a�n��A�`�n����A�Q���Ԕ������Ă܂��A�g����T�����B
�@�@ �@�Q���҂̗l�q �@�Q���҂̗l�q
�@
�@�����́A�V���̐��������������A�a�n��Ń����r�^�L(���X)������A�g�߂Ƀ��}�K���������B��ɂ̓g�r�A�I�I�^�J�A�m�X���A�`���E�Q���{�E���p�������A�S���łR�P����m�F�ł��A�y�����ώ@��ƂȂ����B�����̃|�X�^�[�̎ʐ^�Ɏg�����A�I�W�ƃL�Z�L���C�����邱�Ƃ��ł��Ăق��Ƃ����B�����R�ώ@���ł́A�Z�c�u���\�E�A�U�[���\�E�A���E�o�C��}���T�N�̉Ԃ��炢�Ă���B
�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��
�@�@ �@�U�[���\�E �@�U�[���\�E
�@�ߌ�A�S�������Ă���쒹�ώ@��̃|�X�^�[���������̂V�����ɒ���ւ����B
�@�@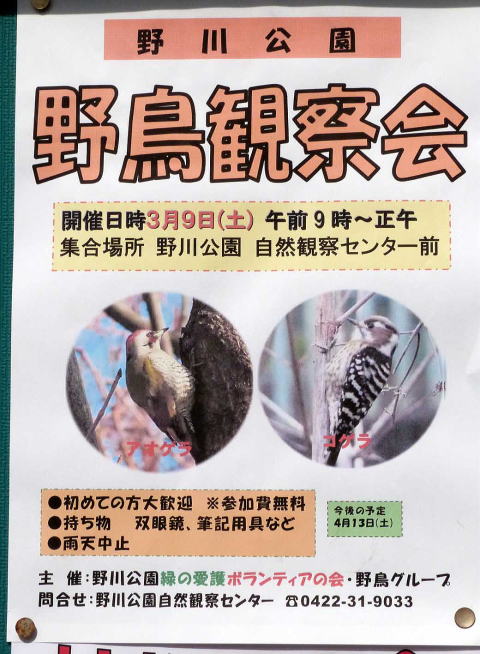 �@�R���̖쒹�ώ@��|�X�^�[ �@�R���̖쒹�ώ@��|�X�^�[
�@�������ɐݒu����Ă���J���X�̃g���b�v�Ƀm�X���������Ă���Ƃ̘A����������K�˂Ă��Ă��邨�q���炠�����B�h�W�ȃm�X���ł���B
�@�@ �@�m�X�������܂����J���X�̃g���b�v �@�m�X�������܂����J���X�̃g���b�v
|
|
|
|
| 2013�N2��8���i���j |
| �����E�I�[�L���O�A���\�Y���`�n���� |
�@���A�������芦���������A�X���߂��ɉƂ��o�āA�����A���\�Y���i�l���X���t�߁j����n���i�b�B�X���j �܂ŕ����܂����B�A��́A�������̎č�w���璲�z�w�ɏo�āA���c�}�o�X�ŋA���Ă��܂����B��P�R�O�O�O���̃E�I�[�L���O�ł����B
�@�����ԉ��ɂ́A�W���E�r�^�L(�I�X)�̎p������܂����B�����̂ʼnH����c��܂��Ă���悤�ł����B�W���E�r�^�L�́A���p�������ł��ˁB���ɏ���������A���̊��F���ڗ����A���ꂢ�ł��B
�@�@ �@�W���E�r�^�L(�I�X�j �@�W���E�r�^�L(�I�X�j
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�I�X�j �@�W���E�r�^�L�i�I�X�j
�@���ł́A�J���E���A�H���L���Ċ������Ă��܂����B�H�͐��ɂʂ�₷�������ŁA���̂��ߐ������ɑf�����ړ����ł���d�|���ɂȂ��Ă��邻�����B���ɂʂꂽ�H�́A���������Ƃ��ǂ����Ă��K�v�ɂȂ�B�������Ƃ��A�������Ƃ�����J���E�̉H�ł���B�ڂ��悭����ƁA��̂悤�Ȑ��ڂ����Ă���B���������������ʂ�ڂł���B�R�Ԃ̐����Ɠ����F�̖ڂƂ������l������B�ʐ^���悭���Ă��������B
�@�@ �@�J���E �@�J���E
�@�@ �@�J���E �@�J���E
�@���������܂��B
�@�J���E�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XyngDYptrno
�@���̉͌��ł́A�z�g�P�m�U��i�m�n�i���炫�n�߂Ă����B
�@�@ �@�z�g�P�m�U �@�z�g�P�m�U
�@�@ �@�i�m�n�i �@�i�m�n�i
|
|
|
|
| 2013�N2��7���i�j |
| �Q������쒹�ώ@�������� |
�@�����́A�������̈���{�����e�B�A�̉�쒹�O���[�v�̌���쒹�ώ@�̓��A�{�����e�B�A�P�T�����A�X������Q���Ԕ��A���R�ώ@���A�������a�n��A�`�n������A�쒹���ώ@�����B�����ώ@�����쒹�͂Q�X��ł������B�V���A�J�����q���̌Q��A�c�O�~�̎p����������ꂽ�B�K�x�̎��x������A�C������������C�̒��A�����̗ɕ�܂ꂽ�ЂƎ��́A�����̂ЂƎ��Ɗ������B
�@���R�ώ@���ł́A�Z�c�u���\�E�A���E�o�C���悭�炫�A�t�N�W���\�E���炫�n�߂��B
�@�@ �@�Z�c�u���\�E �@�Z�c�u���\�E
�@�@ �@���E�o�C �@���E�o�C
�@�@ �@�t�N�W���\�E �@�t�N�W���\�E
|
|
|
|
| 2013�N2��6���i���j |
| ��͗\�z�قǂł͂Ȃ������B |
�@���݁A�O��ł́A�ׂ����J�������~���Ă�����x�ł���B������n�ʂ́A������Ŕ����������Ă��邪�A�ϐ�͂P�������x�ł���B��ʋ@�ւɂ͎�e�����������悤�����A���͉߂����B
�@
�@�@ �@�߂��̐�i�F �@�߂��̐�i�F
�@����A�ϐ��Ƃ��āA�O�ɏo���Ă������|�b�g�A���̃t�W�o�J�}�i��R�T���j�ƃJ�����i�f�V�R�i��X�O���j���A���̒i�{�[���ɓ���āA�Ƃ̒��Ɉړ�������A���̉��Ɉړ�������̑�������B����܂ŏ����Ɉ���Ă���̂ŁA���������̊ԁA�ی삵�Ă��������B�Q���ɂP��̐����͌������Ȃ��B�S���ɂȂ�A�|�b�g����n�A���ɑウ��\��ł��B
�i���̖�쎩���̃t�W�o�J�}�̂������ɂ��ẮA�P���Q�Q���̓��L�����Ă��������B�j
�@�@ �@�t�W�o�J�} �@�t�W�o�J�}
�@�@ �@�J�����i�f�V�R �@�J�����i�f�V�R
|
|
|
|
| 2013�N2��5���i�j |
| �R�C�J������������� |
�@�����͕�������A���������B��������A�����ԉ��łP���Ԃقǃg����҂������A���ړ��Ẵg���͌���Ȃ������B��������A�I�W�̃y�A���A�����߂��̐��ӂɂ����B
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
�@�����́A���]�Ԃł������̂ŁA���̌�A����������ɏo�������B�������R�C�J�������Ă���Ƃ̂��ƂŁA�������吨�̃J�����}�����W�܂��Ă����B���̒��ɓ���Ă�����āA���Ƃ��ʐ^���B�Ƃ�܂����B�C�J���̌Q��ɃR�C�J�����Q�H�������Ă����B�߂��ɂ̓V���������B�Ί݂̃A�L�j���ɖɂ́A�J�����q���̌Q�ꂪ�Ƃ܂��Ă����B���ɂ̓}�q���������܂����Ă���悤�������B
�@�@ �@�R�C�J�� �@�R�C�J��
�@�@ �@�R�C�J�� �@�R�C�J��
�@�@ �@�R�C�J���A�C�J���A�V�� �@�R�C�J���A�C�J���A�V��
�@���������܂��B
�A�I�W�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BnUylfIT880
�R�C�J���@http://www.youtube.com/watch?v=Fu1eoZLn2N0&feature=player_detailpage
|
|
|
|
| 2013�N2��4���i���j |
| ����Ă����̂ŁA���E����������� |
�@�����́A�\������������V�C�ɂȂ����B����Ă��āA�E�I�[�L���O�ɂ͂��������ƂȂ����B���E��������������B���������R�ώ@���́A�����͋x�����ł��������A�����ł́A���E�o�C���悭�炢�Ă����B
�@�@ �@���E�o�C �@���E�o�C
�@�������ł́A�W���E�r�^�L�i���X�j�ƃr���Y�C�̎ʐ^���Ƃꂽ�B�r���Y�C�͓~�ɂ͒g�n�̏��тɑ����B
�@�@ �@�W���E�r�^�L(���X�j �@�W���E�r�^�L(���X�j
�@�@ �@�r���Y�C �@�r���Y�C
�@�N���L��ɂ̓L�Z�L���C�������B
�@�@ �@�L�Z�L���C �@�L�Z�L���C
�@�����̔������t�߂ŃN�C�i�̎p���������B���̎����A�N�C�i�͉��{�̊�������Ԃ��B�k�C���Ɩ{�B�k���ŔɐB���A���̏H�~�̎����ɂ́A�{�B�����ȓ�ɂ��ړ����Ă���B
�@�@ �@�N�C�i �@�N�C�i
�@���������܂��B
�W���E�r�^�L�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BpHwO6VGaUs
�r���Y�C http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eJ9wIe8f1PI
�N�C�i�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DHTuO_Pgu-8
���������Ƃ�́A�S�C�T�M�A�R�T�M�A�}�K���A�J���K���A�I�i�K�K���A�L�W�o�g�A�J���Z�~�A�R�Q���A�N�C�i�A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�r���Y�C�A�q���h���A���Y�A�W���E�r�^�L�A���}�K���A�V�W���E�J���A���W���A�A�I�W�A�J�����q���A�V���A�X�Y���A���N�h���A�n�V�{�\�K���X�A�n�V�u�g�K���X�@
|
|
|
|
| 2013�N2��3���i���j |
| ���̃E�I�[�L���O�A�n���`���\�Y���� |
�@�����́A���A���̑��\�Y������n���Ԃ��E�I�[�L���O�����B�i��P�R�O�O�O���j
�@���̐��͏��Ȃ��Ȃ��Ă����B�c�O�~�͒P�Ƃōs�����Ă��邪�A���̎p�͑��������B�J���Z�~�ɂ͂T��ł������B
�@�@ �@�J���Z�~�@���Z���t�� �@�J���Z�~�@���Z���t��
�@�@ �@�J���Z�~�@�������t�� �@�J���Z�~�@�������t��
�@�@ �@�J���Z�~�@�t�� �@�J���Z�~�@�t��
�@
�@�J���E�ɂ�����ł������B��T�R�T�M���߂��ɂ����B�n���㗬�ł́A�J���E���R�H��������Ă��āA�Ō�͏㗬�̕��ɔ��ōs�����B
�@
�@�I�i�K�K����J���K�����A�|���̉a�����Ă����B���\�Y���߂��̎����ԉ��ł́A�W���E�r�^�L(�I�X)�ƃS�C�T�M(��)
�������B
�@�@ �@�I�i�K�K���̓|���̉a �@�I�i�K�K���̓|���̉a
�@�@ �@�W���E�r�^�L�@�����ԉ� �@�W���E�r�^�L�@�����ԉ�
�@�@ �@�S�C�T�M(��j�@�����ԉ� �@�S�C�T�M(��j�@�����ԉ�
�@���������܂��B
�W���E�r�^�L�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Or2boXjgTOI
�S�C�T�M�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fE6hNDCYXaY
�@���������g���́A�J���E�A�R�T�M�A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�I�i�K�K���A�L�W�o�g�A�J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�q���h���A���Y�A�W���E�r�^�L�A�c�O�~�A�E�O�C�X�A�V�W���E�J���A�J�����q���A�X�Y���A���N�h���A�n�V�u�g�K���X�ł����B
|
|
|
|
| 2013�N2��2���i�y�j |
| �����V����̒|�тŗ̃{�����e�B�A���� |
�@�����́A�����̍����V����̒|�тł̖��x�Ǘ��{�����e�B�A�������ł������B��Â͉ԂƗ̂܂��O��n������ł���B��Q�O���̗̃{�����e�B�A���W�܂��āA�ߌ�̂Q���ԁA��ɁA�͂ꂽ�|�̏����ƁA���x�Ǘ��̂��߂̔��̍�Ƃ��s�����B
�@
�@�����O�̒|�т��A���ɋ߂��Ƃ��납��A�`�A�a�A�b�A�c�A�d�̂T�̃]�[���ɕ����Ă���B�ŏ��ɒ��肵���`�A�a�]�[���͂��Ȃ�|�̖��x���������āA������������悤�ɂȂ��Ă����B
�@�@ �@�`�]�[�� �@�`�]�[��
�@�@ �@�a�]�[�� �@�a�]�[��
�@�Ō�̃~�[�e�B���O�����Ă������ɁA��������I�I�^�J����B
|
|
|
|
| 2013�N2��1���i���j |
| ���������_�C�G�b�g�̓r���o�� |
�@�O��́i�P�Q���S���́j���Ȃ̒���f�f�̍ۂɁA���A�a�ɊW����w���O���r���g���`�P���̒l�́A�������������Ă���悤�ŁA���������o�ߊώ@������B�������������ƂɊւ��ẮA�N��ƂƂ��ɍ����Ȃ邪�A�������T���A�̏d���P�����قnj��点�A���Ȃ���P����Ƃ̘b�ł������B
������āA�S�̂Ƃ��đ̏d���������炷���Ƃ����S�����B
�@�̏d�����炷���߂ɂ́A���������_�C�G�b�g���s�����Ƃɂ����B�܂��A�ԐH�����炷�B��H�̂��т̗ʂ����炷�B�������ڂ��ێ����邱�ƂƂ����B�̏d�̓^�j�^�̑̏d�v�Ŗ������肵�āA�����ϒl�����߂��B
�@���ʂ́A�����Q�S�N�P�P���̌����ϑ̏d�́A�U�Q�D�W�����A�P�Q���͂U�P�D�X�����A�����Q�T�N�P���͂U�O�D�U�����ƂȂ����B�����ɁA���̂Q�����ԂŁA�����ϑ̏d�́A�Q�D�Q�������������B�����̑̏d�͂T�X�D�X�����ł���B�����_�ł́A�Q�D�X�����̌����ł���B�`���b�g���炵�߂���������Ȃ��Ǝv���Ă���B
�@���݂a�l�h�l�́A���x�Q�Q�D�O�ł���B
|
|
|
|
| 2013�N1��31���i�j |
| �}�q�� |
�@�����A����������ɍs������}�q���̌Q�i�Q�T�H�قǁj�ɏo����Ƃ��ł��܂����B�����A�L�j���̖��Ǝv���܂����A�Q������H�ׂĂ��܂����B
�@�@ �@�}�q�� �@�}�q��
�@�@ �@�}�q�� �@�}�q��
�@���������܂��B
�@
�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nv4E7lATZGk
�������ł́A�r���Y�C�����܂����B
�@�@ �@�r���Y�C �@�r���Y�C
���R�ώ@���ł́A�Z�c�u���\�E���炫���߂Ă��܂����B
�@�@ �@�Z�c�u���\�E �@�Z�c�u���\�E
|
|
|
|
| 2013�N1��30���i���j |
| �V���n���A�A�J�n�����������R���Βn |
�@�ߑO���́A�����V����̒|�тɁA�����̉����ɂ������B�|�тɂ̓V���n���̎p���������B
�@�@ �@�@�V���n�� �@�@�V���n��
���̂���\��̒|�Ƀe�[�v��}�[�L���O�Ƃ����B�����A�͂�ē|�ꂽ�|�A�͂ꂽ�|�A�V��|�̏����Ŕ��̂���B
�@�ߌ�A���]�ԂŁA���ɏo���B�㗬�̂�܂��̏�����܂ōs���A�����Ԃ��āA���ŁA���Ɨ���A�����������ړ������B�G�S�m�L�Ƀ��}�K�������Ă����B
�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��
�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��
�@�@���}�K���̓��������܂��B
�@�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gEgG22yU818
�x�m���勴�����Ŗ��ɏo�āA�����Ɍ��������B���\�Y�������̑��̗��ł́A�A�J�n���̎p���������B
�@�@ �@�A�J�n�� �@�A�J�n��
�@�@ �@�A�J�n�� �@�A�J�n��
��Ŗ��ƕ�����A����ɋA���Ă����B
|
|
|
|
| 2013�N1��29���i�j |
| �x�j�}�V�R�������ԉ� |
�@�O��s�̑��̃z�^���̗��O�鑺�t�߂ɂ́A���R���ۑS�n��ƂȂ��Ă��鎩�R�сA�����T�r�c�A�c�ށA�����ԉ��Ȃǂ�����A�悢���R�����c���Ă���B�V���ɂ́u�z�^���Ϗ܂̗[�ׁv���s���A�q�������Ɍ��������R���ɂ��邱�������Ă銈���Ƃ��āA�c�A���A���A���n�Ղ��s���Ă���Ƃ���ł���B�����͎��̖��U���̍ۂɗ������ꏊ�ł���B
�@�����A���U���̓r���ɗ���������A���̎����ԉ��ŁA�v���������x�j�}�V�R�i�g���q�j�ɂ������B���̖��O�̗R���́A���̊�̂悤�ȐԂ��F�����Ă���g�����痈�Ă���B���̒����o���F�̃A�g���Ȃ̃g���ł���B�ŏ�����ňꌩ�����Ƃ��냂�Y�̂悤�����A�F���Ԃ��Ɗ������B�ɐB�n�͖k�C����X���̈ꕔ�ł��邪�A�z�~�n�͖{�B�ȓ�ł���B
�@�@ �@�x�j�}�V�R �@�x�j�}�V�R
�@�@ �@�x�j�}�V�R �@�x�j�}�V�R
�@�܂��A�����́A�r���̍������R�����~���K�i����́A�R�W���P�C�S�H�̎p�����邱�Ƃ��ł����B
�@�@ �@�R�W���P�C �@�R�W���P�C
�@���������g���́A�R�T�M�A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�I�i�K�K���A�L�W�o�g�A�J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�q���h���A���Y�A�W���E�r�^�L�A�V���n���A�c�O�~�A�V�W���E�J���A���W���A�A�I�W�A�x�j�}�V�R�A�V���A�X�Y���A���N�h���A�n�V�u�g�K���X�A�R�W���P�C�ł������B
|
|
|
|
| 2013�N1��28���i���j |
| �쒹�u�E�\�v���A���R�ώ@���̏㗬�̌����� |
�@��]���q���A���R�ώ@���̏㗬�̌����ŎB�e�����쒹�u�E�\�v�̎ʐ^���A���̂g�o�u�V�j�A����v�̌f���ɓ��e���Ă����������Ă��܂��B���Ќ��Ă��������B���L��URL�Ō����܂��B
�@�@�@�@http://8926.teacup.com/adam/bbs
|
|
|
|
| 2013�N1��28���i���j |
| �ϐ�̖��E����������� |
�@���U�������납��Ⴊ�~��o�����B�܂��͈�ʔ���̐��E�ɕς����B�\�肵�Ă������̈�ė��ʑ���𒆎~�����B��͂����Ɏ~�B�W���O�Ƀv���X�`�b�N�E�S�~���Ƃ̑O�ɏo���āA���������E�������̎U���ɏo���B�����V����̒|�тɂ��Ⴊ�ς����Ă����B
�@�@ �@�����V����̒|�� �@�����V����̒|��
�������R���̊K�i�������Ă����ƁA���R���ۑS�n��ŁA��̒��V�����H�ו���T���Ă����B
�@�@ �@�V�� �@�V��
�K�i������āA���ɏo�āA�����ԉ����̂����ƁA�A�I�W�A�W���E�r�^�L�̎p���������B
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
�@�@ �@�W���E�r�^�L �@�W���E�r�^�L
����k��A�N���L����o�Ď��R�ώ@�Z���^�[�ɂ�������ŁA��U���ƕ�����A�������a�n�������B�c�O�~���A�����t���������������T���āA�H�ׂĂ����B����������Ƃ���ł́A��͂��������Ă��܂��Ă����B
�@�@ �@�c�O�~ �@�c�O�~
�@�܂��A���ɖ߂��āA�����ԉ����̂�������A�����܂ŕ������B��Ŗ��ƕ�����A����ɋA���Ă����B
|
|
|
|
| 2013�N1��27���i���j |
| ���A���������U�� |
�@���A�X�����ɉƂ��o�āA���A���������U������B�����V����k���̓��ŁA�J�����q�������������B�ŏ��͒n�ʂɍ~��Ă������A�����߂Â��Ă����̂ŁA�}�ɔ�т������āA���̂܂܂��炭���Ă��ꂽ�B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
�@�@ �@�J�����q�� �@�J�����q��
�J�����q���@����
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pYermv1J0EA
�@
�@�����̑O��ʂ�A�������R���̂P�O�Q�i�̊K�i���~��A���ɂł��B�K�i�̍���̎��R���ۑS�n��ŁA�R�W���P�C�ƃA�J�n���̎p�����������B���ł́A�����̃I�i�K�K���A�J���K���A�R�T�M�Ȃǂ������B�������ɓ���A���R�ώ@�Z���^�[���`���b�g�̂����A���̌㎩�R�ώ@���������肵���B�V���̎p�𑽂����������B�q�h���K���́A�����͂��Ȃ������B
�@�@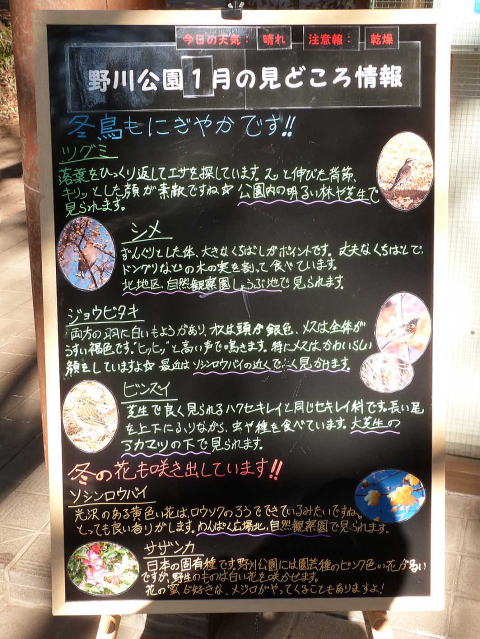 �@���R�ώ@���̈ē��u�P���݂̂ǂ���v �@���R�ώ@���̈ē��u�P���݂̂ǂ���v
�@�@ �@�@�@�V�� �@�@�@�V��
�@�@ �@�V���i��H�j �@�V���i��H�j
�@�������a�n��ł́A�G�S�m�L�Ƀ��}�K���������B
�@�@ �@���}�K�� �@���}�K��
�A��ɂ܂���������������ԉ��ł́A�W���E�r�^�L�������B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�I�X�j �@�W���E�r�^�L�i�I�X�j
�@��Ŗ��ƕ����ꒋ�߂��ɁA�ƂɋA�����B
���������g���́A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�I�i�K�K���A�L�W�o�g�A�J���Z�~�A�L�Z�L���C�A�n�N�Z�L���C�A�q���h���A���Y�A�W���E�r�^�L�A�A�J�n���A�c�O�~�A���}�K���A�V�W���E�J���A���W���A�J�����q���A�V���A�X�Y���A���N�h���A�n�V�u�g�K���X�A�R�W���P�C
|
|
|
|
| 2013�N1��26���i�y�j |
| �̃{�����e�B�A�u���ŏI�� |
�@�O��s�ł́A�W�N�O�̕����P�U�N���疈�N�H����~�ɂ����āA�ԂƗ̂܂��O��n������A�̃{�����e�B�A�u�����J�Â��Ă���B�u���́A�S�U��ŁA�i�T�ˌ��Q��́j�A���u������\������Ă���B�@�e�[�}�́A���̈琬�A����A�G�ؗт̊Ǘ��A�|�т̊Ǘ��A���؊ώ@�Ȃǂł���B�C�����ɂ͗l�X�ȃt�B�[���h����Z�̌����ڎw���Ƌ��ɁA�{�����e�B�A�����ɂ��ϋɓI�ɎQ�����Ă��������Ă���B
�@�����́A���̖{�N�x�ŏI��ŁA�_����ד����_�Ƒ�w�����ɂ��u���u�G�ؗтƐl�Ԃ̐����v�Ǝ��K�u�V��ےr�����̎��؊ώ@�v���s��ꂽ�B
�@���́A�u���C�����Ƃ��āA�ߑO���̍u�`�ɏo�Ȃ����Ă����������B
�@�@ �@�u�`�̗l�q�@ �@�u�`�̗l�q�@
�@�A�蓹�A���ɂ́A�q�h���K���̎p���������B
�@
�@�@ �@�q�h���K�� �@�q�h���K��
|
|
|
|
| 2013�N1��25���i���j |
| ���̗��ʑ���i�P���j |
�@�ߑO���A���̗��ʑ�����A�O��s�̂R����(�x�m���勴�A�A��j�ōs�����B����l�́A�挎�̑���l�̖��ƂȂ��Ă����B���ꂩ��R������܂ł́A�X�Ɍ����X�����������̂Ǝv���B
����́A���q�𗬂��ė����𑪂���@�ő�������Ă���B��̗���ɒ��������Q�{�̃^�R�����͂�A���̊Ԋu�͂P�D�T���܂��͂R���Ƃ��Ă���B
�@
�@�@ �@������ł̑���̗l�q �@������ł̑���̗l�q
������ŁA�͑��ɊԂő������I�I�C�k�m�t�O�����Ԃ����Ă����B
�@�@ �@�I�I�C�k�m�t�O�� �@�I�I�C�k�m�t�O��
�쐅���㗬�ł́A�J���Z�~�̎p�������B
�@�@
|
|
|
|
| 2013�N1��24���i�j |
| ������E��썇���_�t�߂Ŗ쒹���ώ@���܂����B |
�@�����́A����̉��₩�ȓ��ƂȂ����B�������쒹�O���[�v�̒T����ŁA���A������ŁA�쒹���ώ@�����B
�@
�X���ɋ����������s���w�ɏW�����A�����Βn��ʂ���E�݂ɏo�āA�����ɏ��������A�ӂꂠ�����Ő��̍��݂Ɉړ����āA������Ƃ̍����_�߂��ɂ܂ŕ����A���x�́A������E�݂��㗬�ɃO�����h�܂ŕ����B�ώ@�����g���̊m�F�����ĂP�Q����������U�����B�A��̓��m���[���̖��莛�w���痧��ɏo�āA�A���Ă����B
�@������������A���́A�傫�ȉ͐�~�������Ă���B�܂����ł̓_�C�T�M�A�J���E�̎p�����������B�z�I�W���A�J�V���_�J����R����ꂽ�B������ł̓I�I�^�J�A�m�X���A�g�r�Ȃǖҋחނ�����ꂽ
�@�@ �@�J���E�ƃ_�C�T�M����� �@�J���E�ƃ_�C�T�M�����
�@�@ �@�m�X���������� �@�m�X����������
|
|
|
|
| 2013�N1��23���i���j |
| ����̖�여��A����Ȃ��Ƃ����� |
�@����A�k�����암���ݎ������ʓ���c���ŁA��U����여��A����Ȃ��Ƃ�����̉������A�����o�Ȃ����B���̑S���悩��ψ��������o�Ȃ��A�����s���lj͐암�v��ۂ⎖���ǂ̖k�����암���ݎ�����������S���҂��o�Ȃ����B
�@�c���
�P�j���̂Ȃ��Ƃ����ʂ̐ݒ�
�Q�j�͐���}�쐬�̂��߂̃t�C�[���h���[�N�i�R���ځj�ɂ���
�R�j���̑�
�ł������B
�@���́A���̑��̋c��ŁA�u�O��n��ɂ�������̗��ʂ̔N�ԕω��ɂ��āv�Ɓu�O��n��ɂ�������ɒ����N���ʂ̔N�ԕω��ɂ��āv�̕������Ă����������B
���݂�̂́A���L�̂t�q�k����A�o�c�e�̕��������邱�Ƃ��ł��܂��B
http://www.mitaka-sns.jp/modules/d/diary_view.phtml?id=322676&o=&l=30
|
|
|
|
| 2013�N1��23���i���j |
| �g���G�K�����A�������t�t�߂ɗ��Ă��܂��B |
�@�g���G�K���͓~���Ƃ��Ĕ��邪�A���͑����Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B�I�X�̊�ɉ����F�Ɨ��F�̔b�`�̔��䂪����A���ꂪ���O�̗R���ł���B���̃g���G�K�����A��N�̖�����A�������t�߂ɗ��Ă���B�������A���R�ώ@���̒r�ɂ��܂����B����������Ƃ̂��Ƃł��B�߂��̖��Ǝ��R�ώ@���̒r�ɍs���������Ă���Ɛ������Ă��܂��B�ŏ��́A���ł݂��Ƃ̒m�点����N�̕��̂Q�X���Ɏ܂����B���ꂩ��A�����Ԍo���܂����A�܂����炭���Ă��������ł��ˁB
�@�@ �@�g���G�K���i�I�X�j �@�g���G�K���i�I�X�j
�������ł́A�J�����q���̌Q���n��ɍ~��āA���܂����B
�@�@ �@�@�J�����q���̌Q�� �@�@�J�����q���̌Q��
���ł́A�W���E�r�^�L�i���X�j�ɂ���܂����B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i���X�j �@�W���E�r�^�L�i���X�j
|
|
|
|
| 2013�N1��22���i�j |
| ��Ŋ뜜�A���t�W�o�J�} |
�@�t�W�o�J�}�͏H�̎����̂ЂƂł��邪�A���ł͊��Ȃ̐�Ŋ뜜�U�ސA���Ɏw�肳��Ă���M�d�ȐA���ł���B���N�āA���Ŏ������Ă����t�W�o�J�}�������A��N�H�Ƀt�W�o�J�}�̎���̎킵�āA����ŃZ���|�b�g�Ɏ���܂��Ĕ��肳�������̂��A�P���X���Ƀ|�b�g�ɈڐA�����B���������ł���̂ŁA��́A�s�D�z�ň͂��đ�ɂ��Č�����Ă���B
�@�ڐA��Q�T�ԋ߂��o�߂������A�����l�Ŗ����Ɉ���Ă���B���̂܂܈���Ă����A�ꕔ���O��s�̎��R���ۑS�n��ɈڐA�����Ă����������Ƃ�\������Ă���B�������肪�����ꏊ������̂ŁA���N�̏H���y���݂ɂȂ�B
�i���݃t�W�o�J�}�̖��Ŏs�̂���Ă�����̂̑����́A�t�W�o�J�}�ƃT���q���h���̎G�킾�����ł��B�j
�@�������A�����쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c���A�����ꏊ�ɈڐA�����Ă����������Ƃ�\�肵�Ă���B
�@
�@�@ �@�@�t�W�o�J�} �@�@�t�W�o�J�}
�@�@ �@�@�J�����i�f�V�R �@�@�J�����i�f�V�R
|
|
|
|
| 2013�N1��21���i���j |
| ���ɒ����N���ʂ̑���i1���j |
�@�����́A�����s���Ă�����ɒ����N���ʑ�����P�R�����i�����`�Y�ԁj�ōs�����B���v�̗N���ʂ́A�挎�̑���l����S�O���قnj������Ă����B
�@���͊������A�X���߂�����X�^�[�g�����B�ߌ�1���߂��ɏI���B����ł������Ƃ�Ƃ���قNJ��������Ȃ��̂ŏ�����B�r���A�W���E�r�^�L�i�I�X�j�̎p���������B
�@�@ �@����̗l�q �@����̗l�q
�@�@ �@�@�W���E�r�^�L�i�I�X�j �@�@�W���E�r�^�L�i�I�X�j
|
|
|
|
| 2013�N1��20���i���j |
| �f�G�ȁA��҂ݎ�܂̑��蕨 |
�@�Ƒ����A�f�G�Ȗ͗l�́A�ю��̎�܂��A�҂�ŁA�v���[���g���Ă��ꂽ�B��ς��ꂵ���B���������Ȃ��ĕ��i�ɂ͎g���Ȃ��A�]���s���̍ۂɁA�g������ł��B
�@�@ �@��� �@���
|
|
|
|
| 2013�N1��20���i���j |
| �C�J���`�h���������� |
�@���A����������B�����ŁA�������C�J���`�h�������������B
�@�@ �C�J���`�h�� �C�J���`�h��
�J���Z�~�A���Y�̎ʐ^���B�����B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�@�@ �@���Y �@���Y
���������g���́A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�}�K���A�J���K���A�I�i�K�K���A�C�J���`�h���A�J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�q���h���A���Y�A�W���E�r�^�L�A�c�O�~�A�V�W���E�J���A�A�I�W�A�J�����q���A�V���A�X�Y���A���N�h���A�n�V�{�\�K���X�A�n�V�u�g�K���X
|
|
|
|
| 2013�N1��19���i�y�j |
| �G�i�K�̌Q�ꁗ�����V����\�� |
�@�����́A�ԂƗ̂܂��O��n�������Ẫ̗{�����e�B�A�u����S��ځu�|�т̊Ǘ��v�ł������B�u���̂n�a���Q�����āA�u���̎x�����s�����B�ߑO���͍u�`�A�ߌオ����ł̎��K�ƂȂ��Ă����B
�@�ߌ�P������V����̍\���ɂ͂���ƁA���ɂ��܂��������܂�ɃG�i�K�̌Q�ꂪ�~��Ă��āA��������ł����B�i�ʐ^�͂ڂ��Ă��Ă��݂܂���j
�@�@ �@�G�i�K�̌Q �@�G�i�K�̌Q
�@�@ �@�G�i�K�̌Q �@�G�i�K�̌Q
|
|
|
|
| 2013�N1��18���i���j |
| �A�I�W�������ԉ� |
�@���A�x�m�R�����ɂ��ꂢ�ł������B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
�@��쑊�\�Y���߂��̎����ԉ����̂����Ă݂��B�ؓ��ɃA�I�W�̎p�����������A�������ōs���Ă��܂����B�����́A�����̂ŁA�U���̐l���Ȃ��A���炭�����Ƃ��Ă�����A�W���E�r�^�L�i�I�X�j���������������Ă��ꂽ�B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i�I�X�j �@�W���E�r�^�L�i�I�X�j
�@�@����ɁA�Q�H�̃A�I�W���A��̏�ɂ���A�����H�ׂ������B�H�ׂ邱�ƂɖZ�����A�����Ƃ��Ă����玄�̎p�ɂ͔�r�I�q���ł͂Ȃ��A���Ȃ�߂��Œ����Ԃ��Ă��ꂽ�B
�@�@ �@�A�I�W�i�y�A�j �@�A�I�W�i�y�A�j
�@�@ �@�A�I�W�i�y�A�j �@�A�I�W�i�y�A�j
�@�@ �@�A�I�W�i�I�X�j �@�A�I�W�i�I�X�j
�@�@ �@�A�I�W�i���X�j �@�A�I�W�i���X�j
�@�@�A�I�W�y�A�̓��悪����܂��B
�@�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8JQqg_B0emg
|
|
|
|
| 2013�N1��17���i�j |
| ���̐�i�F |
�@�Ⴊ�~���Ă���A3���ڂł��邪�A�܂��O��ł́A�����قǐႪ�̂����Ă����B
�@�@ �@���̐�i�F�i���������j �@���̐�i�F�i���������j
���R�ώ@���̒��̃��E�o�C���炫�n�߂��B
�@�@ �@���E�o�C �@���E�o�C
�c�O�~�A�V�����n��ɍ~��A��̂Ȃ��Ƃ���ŁA�a��T���Ă����B
�@�@ �@�V�� �@�V��
�������̗N���L��ł́A�L�Z�L���C�A�Z�L���C���A�a��T���Ă����B
�@�@ �@�L�Z�L���C �@�L�Z�L���C
�J���Z�~�������Ȗ̎}�̏ォ��A�����Ɛ�̒������Ă����B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
���������g���́A�V���A�c�O�~�A�V���n���A�A�I�W�A���W���A�V�W���E�J���A�W���E�r�^�L�A���Y�A�R�Q���A���N�h���A�q���h���A�X�Y���A�I�I�^�J�A�g�r�A�n�N�Z�L���C�A�L�Z�L���C�A�R�T�M�A�J���K���A�I�i�K�K���A�}�K���A�R�K���A�J���E�A�J���Z�~�A�n�V�u�g�K���X�ł����B
|
|
|
|
| 2013�N1��16���i���j |
| ���s�̂��y�Y�F���q�̋��ώρE���Е� |
�@�e�ʂ���A���s�̂��y�Y�Ƃ��Č��q�̋��ώρu�ق��邱�v�Ƌ��Е��u�Ԃ��Ԃ������Ёv�Ȃǂ����������Ă����B
�@�����ł���u�ق��邱�v�́A���X�̃p���t���b�g�ɂ�Ɓu�ׂ��������킩�߂̌s�ɎR���Ə����̂����Ⴑ�����킦�A���R�̕������������Đ����������q�Ɠ`�̒ώρv�A�u�ق��邱�̗R���́A�R���̐��������炿��ƌ�����̂��A���ɕ����z�^���Ɍ����Ă��܂��v�Ƃ̂��Ƃł��B
�@�M�X�̂��͂�ŐH�ׂ�ƁA�~�܂�܂���B
�@�@ �@�ق��邱 �@�ق��邱
�@�@ �@�Ԃ��Ԃ������� �@�Ԃ��Ԃ�������
�@�@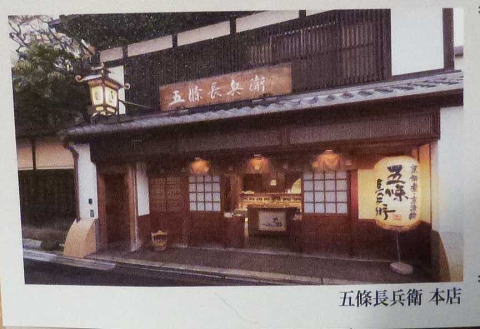 �@���q�{�X �@���q�{�X
�@�@http://www.gojochoubei.co.jp/tenpo.html
|
|
|
|
| 2013�N1��13���i���j |
| �����쎩���̃J�����i�f�V�R�̃|�b�g�ւ̈ڐA |
�@�����͌ߌ�A��������đ�Ɉ�ĂĂ��鑽���쎩���̃J�����i�f�V�R�̕c���Z���|�b�g����|�b�g�ɈڐA�������B��܂��Ɏg�������̂Ɠ����y�i��܂���c�|�y�j���g���Ē��a�P�O�D�T�����قǂ̃|�b�g�T�O�ɈڐA�������B
�@�@ �@�J�����i�f�V�R �@�J�����i�f�V�R
�@�ߑO���A���̑��\�Y�����牺���̑��܂ł�������B�g���͂�������n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�J���K���A�}�K���A�I�i�K�K���A�R�T�M�A�J���Z�~�A�V���A�c�O�~�A���Y�A���W���A�W���E�r�^�L�A�A�I�W�A�V�W���E�J���A�L�W�o�g�A�I�i�K�A���N�h���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�ł����B
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
�@�@ �@���W�� �@���W��
|
|
|
|
| 2013�N1��12���i�y�j |
| �쒹�ώ@��̃|�X�^�[�f�� |
�@�����́A�ߑO���A�������쒹�ώ@��J�Â��ꂽ�B��ẤA�������̈���{�����e�B�A�̉�쒹�O���[�v�ł���B�W���ꏊ�́A���R�ώ@�Z���^�[�O�A�ߑO�X���ŁA��ʎs�����S�O����Q������A�{�����e�B�A�̃X�^�b�t���P�O���قǎQ�������B���́A���̃|�X�^�[��S�����Ă���̂ŁA�����̌ߑO���A�쒹�ώ@��̓r���Ŕ����āA���������V�����Ɍf�������Ă��܂����B
�@�@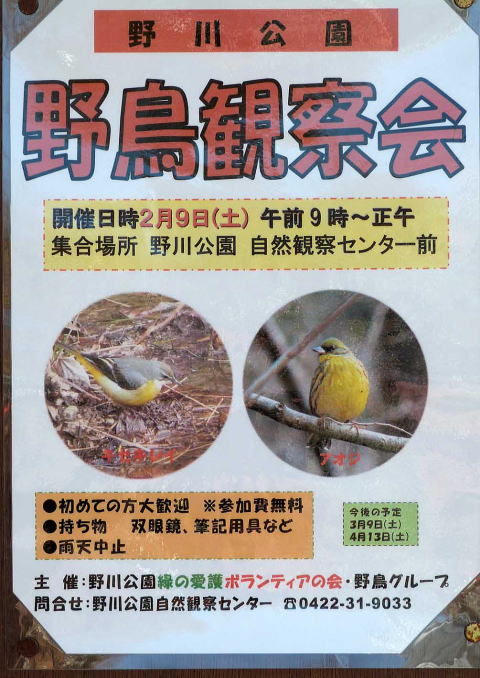 �@�쒹�ώ@��|�X�^�[ �@�쒹�ώ@��|�X�^�[
�@�����̖쒹�ώ@��ł́A�V����c�O�~�̌Q�ꂪ��ь����p���݂܂������A�C�J�����R�H�p�������Ă��ꂽ�B���̃O���[�v�́A�A�I�Q���������l�������B�W���E�r�^�L�̃��X���p���������B����Ɠ~���̊ώ@���y���������ɂȂ��Ă�������������B
�@
�@�@ �@�C�J�� �@�C�J��
|
|
|
|
| 2013�N1��11���i���j |
| ���̕s�E�r |
�@�����͌䒃�m���̕a�@�̋A��ɓ����V�_�Ə��s�E�̒r�ɏo�����Ă��܂����B�����ł͖쒹�������l�ɂȂ�Ă���A���Ȃ�߂��Ŋώ@���邱�Ƃ��ł���B�����̂́A�����J�����A�E�~�l�R�A�L���N���n�W���A�z�V�n�W���A�q�h���K���A�I�i�K�K���A�n�V�r���K���A�o���A�I�I�o���A�J���E�A�R�T�M�A�c�O�~�A�X�Y���A���N�h���ł����B
�@�@ �@�����V�_ �@�����V�_
�@�@ �@���̕s�E�r �@���̕s�E�r
�@�@ �@���̕s�E�r �@���̕s�E�r
�@�@ �@���̕s�E�r �@���̕s�E�r
�@�@ �@�@�����J���� �@�@�����J����
�@�@ �@�E�~�l�R �@�E�~�l�R
�@�@ �@�I�I�o�� �@�I�I�o��
�@�@ �@�o�� �@�o��
�@�n�V�r���K���ƃI�I�o���̓��������܂��B
�@�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fFauTdzu7C4
|
|
|
|
| 2013�N1��10���i�j |
| �P������쒹�ώ@�������� |
�@�����́A�������{�����e�B�A����쒹�ώ@�̓��ł������B�X�����R�ώ@�Z���^�[���o�����ĂQ���Ԕ��قǁA���R�ώ@���A���������a�n��A�`�n��Ȃǂ�������B�m�F�ł����g���͂Q�U��ł����B
�@�~���̃V���ƃc�O�~���Q��Ŕ�т����Ă����B�G�i�K�ƃV�W���E�J���̍��Q�ɂ�����B�܂����ŃA�I�Q�������邱�Ƃ��ł����B�N���L��ł́A�L�Z�L���C�������B
�@�@ �@�A�I�Q�� �@�A�I�Q��
�@�@ �@�W���E�r�^�L�i���X�j �@�W���E�r�^�L�i���X�j
�@�@ �@�L�Z�L���C �@�L�Z�L���C
���������܂��B
�A�I�Q���̓���@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gxn8-xrtMZQ
�L�Z�L���C�̓���@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3ei7HExbVl8
����ώ@�I����A�V�N����s�����B
|
|
|
|
| 2013�N1��9���i���j |
| �t�W�o�J�}�̕c���|�b�g�ɈڐA |
�@�����́A��������đ�Ɉ�ĂĂ����쎩���̃t�W�o�J�}�̕c���Z���|�b�g����|�b�g�ɈڐA�������B��܂��Ɏg�������̂Ɠ����y�i��܂���c�|�y�j���g���Ē��a�P�Q�����قǂ̃|�b�g�R�O�ɈڐA�������B����܂ł͖�͉Ƃ̒��ɓ���Ă������A��������́A�Ƃ̊O�ŁA�s�D�z�������ė₦�����Ȃ��悤�ɕۉ�������B
�@�@ �@�t�W�o�J�}�i�Z���|�b�g�j �@�t�W�o�J�}�i�Z���|�b�g�j
�@�@ �@�|�b�g�ɈڐA�����t�W�o�J�}�̕c �@�|�b�g�ɈڐA�����t�W�o�J�}�̕c
|
|
|
|
| 2013�N1��8���i�j |
| ����k��A�������܂ŕ����B |
�@�W�����ɉƂ��o�āA���\�Y���̎����ԉ������āA����k��A�������A�����������ʂ�A�㗬�̍������̒��J�ˋ��܂ŕ����܂����B�����ŁA���ƕ�����āA�������s��������A�a���J�˒뉀�����āA�i�q�ŋA���Ă��܂����B�P�T�S�O�O���ł����B
�@���̔����ŁA�����s�̋Ǝ҂��A�����~�̎�����̂��Ă��܂����B
�@�����ԉ��ł́A�I�i�K�A�J�V���_�J�A�A�I�W�i���X�j�Ȃǂ����܂����B�������ł͍������V���ƃc�O�~�̌Q�ꂪ���܂����B������������ł́A���̕\�ʂ������Ă���Ƃ��낪����܂����B
�@�a���J�˒뉀�ł́A���E�o�C�������炫�n�߂Ă��܂����B�c���u�L����R�����Ă��܂����B�J�����i�f�V�R���Q�ւقNj����炫�����Ă��܂����B���̋߂��ŁA�A�I�W�̃I�X���P�H���܂����B
�@�@ �@�I�i�K �@�I�i�K
�@�@ �@�J�V���_�J �@�J�V���_�J
�@�@ �@�A�I�W�i���X�j �@�A�I�W�i���X�j
�@�@ �@�A�I�W�i�I�X�j �@�A�I�W�i�I�X�j
�@�@ �@���E�o�C �@���E�o�C
�A�I�W�̓��������܂��B
�A�I�W�i���X�j�����ԉ��@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JHZnfT5dgok
�A�I�W�i�I�X�j�a���J�˒뉀�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yzr5VOxoXsw
�@���������g���́A�n�N�Z�L���C�A�J���K���A�}�K���A�I�i�K�K���A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�A�I�T�M�A�J���Z�~�A�V���A�J�V���_�J�A�c�O�~�A���Y�A���W���A�E�O�C�X�A�W���E�r�^�L�A�A�I�W�A�V�W���E�J���A�L�W�o�g�A�I�i�K�A���N�h���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�ł����B
|
|
|
|
| 2013�N1��7���i���j |
| �������V�b�J��������F���������_�C�G�b�g |
�@�����l���C������ȏŁA��t�̊��߂�����A��N�P�Q�����A�������ʂ��邱�Ƃɂ��܂����B�s���Ă��邱�Ƃ́A�ԐH��啝�ɐ����A����܂��H�ׂ�A���т̗ʂ����炵�A�S�̂Ƃ��ĕ��W���ڂɕۂ��Ƃł���B��͓��������_�C�G�b�g���ł��邪�A�Ⴄ�͎̂��b�₽��ς������قǂقǂɗ}���Ă���B
�@���̌��ʂ������āA�̏d�����́A���܂ł̂Ƃ���A�P�P�����ςU�Q�D�W�����A�P�Q�����ςU�P�D�X�����A�P���i�V���܂ł́j���ςU�P�C�O�����Ɗm���Ɍ������Ă��Ă��܂��B
�@
���킹�āA�E�I�[�L���O�ő̂����Ă��܂��B����ɂ��傢�Ɋ��҂����Ă܂��B
�@���́A���̂悤�Ȍ��ʂ��A���낢��ȂƂ���ŕ���p���o�Ȃ����킩��Ȃ��_�ł��B���炭�T�d�ɗl�q������K�v������܂��B�ł��A�E�I�[�L���O�̐��ʂ��A�̒��������悤�Ɋ����Ă���̂͂��ꂵ�����Ƃł��B
|
|
|
|
| 2013�N1��7���i���j |
| �߂��̖������E�������邫�܂����B |
�@�P�O���O�ɉƂ��o�āA�������A�����������U�A�g�����������܂����B�����́A�P�S�O�O�O���ł����B
�x�m�R�́A���̕��ɉ_���������Ă��܂������A����͂��ꂢ�ɂ݂��܂����B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
�V����̖k���̓��ŁA�A�I�W�Q�H�����܂����B���ɋC���t���Ĕ�ї����܂������A�P�H�͂܂��߂��̖̎}�ɂ��܂����B
�@�@ �@�A�I�W �@�A�I�W
���������R�ώ@���́A�����͊J�����Ă��܂��A�Â��Ȋώ@���̒��ł́A�c�O�~�ƃV���̌Q�ꂪ�ڗ����܂����B���ł́A�J���Z�~�̎p������܂����B
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
��������Ɉꎞ�ʂ�A��������������܂����B�W���E�r�^�L�A�V���A�J�����q�����Ⴂ�ʒu�ɂ��Ă���܂����B�̎���H�ׂ邽�߂ɒn��ɍ~��Ă����悤�ł��B
�@�@ �@�W���E�r�^�L �@�W���E�r�^�L
�@�@ �@�V�� �@�V��
�@�@ �@�J�����q�� �@�J�����q��
�@�@ �@���Y �@���Y
�V���ƃ��Y�̓��������܂��B
�V���i�}�̏�j�̓���@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=H_7e9Jm1Sr4
�V���i�n��j�̓���@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=04SdazFIL98
���Y�̓���@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=uMA_vQDFvbM
���������g���́A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�J���K���A�}�K���A�I�i�K�K���A�R�T�M�A�J���E�A�J���Z�~�A�V���A�J�����q���A�c�O�~�A���Y�A���W���A�W���E�r�^�L�A�A�I�W�A�V�W���E�J���A���N�h���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�ł����B
|
|
|
|
| 2013�N1��6���i���j |
| ���̍ʼn����̕��ɋ��܂ŕ����܂����B |
|
|
|
| 2013�N1��5���i�y�j |
| �����̓����A�����E�I�[�L���O�i�����ԋ��܂ʼn����j |
�@�����͏����i���̓���j�A�����������A�撣���āA����������B����牺�����c�J��܂ł��Ȃ��������ŁA������W���ɏo�����A�r���ō��z��Y��Ă������ƂɋC���t���A�����ċA���Ƃ���܂ŕ����A�����Ԃ����ƂɌ��߂��B�厸�s�I�@���ǁA�b�B�X���̎ԋ��ŁA�����Ԃ��Ă����B��Q���Ԕ��A�P�S�O�O�O���ł������B
�@�@ �@���̕��i�i�ԋ����牺��������A�d�Ԃ͋������j �@���̕��i�i�ԋ����牺��������A�d�Ԃ͋������j
�@�J���Z�~�ɉ�����̂͂T��ł��������A�S��̓I�X�̃J���Z�~�ł������B���X�͂P���B�ǂ��������Ƃ��A���R�͎��ɂ͕�����Ȃ��B
�@�@ �@�J���Z�~�i���X�͉��̂��������Ԃ��j �@�J���Z�~�i���X�͉��̂��������Ԃ��j
�@�@ �@�J���Z�~�i�I�X�j �@�J���Z�~�i�I�X�j
�@�A�I�T�M�ɂ��o������B�������Ƃ�������ŁA�l����_���Ă������A��x���Ƃ�Ȃ������B
�@�@ �@�A�I�T�M �@�A�I�T�M
����A�I�T�M�́@http://youtu.be/-VU58HX8JXg�@�ł݂Ă��������B
���������������A�����o������g���́A���Ȃ��A�A�J�n���A���N�h���A�q���h���A�L�W�o�g�A�c�O�~�A�X�Y���A�J���K���A�R�K���A�}�K���A�J���Z�~�A�R�T�M�A�A�I�T�M�A�n�N�Z�L���C�A�n�V�u�g�K���X�����ł������B
|
|
|
|
| 2013�N1��4���i���j |
| ���𑊑\�Y������č�w�܂ŕ��� |
�@�������V�b�J���������B�����́A���𑊑\�Y������ԋ��܂ŕ������B�P�R�S�O�O���ł������B
�@�����͂X���ɉƂ��o�āA�V����̖k�����Ƃ���A�V���̊K�i������Ė��ɏo�āA���\�Y������ԋ��܂Ńg����T���āA�����܂����B�������̎č�w����͓d�ԂŒ��z�w�ɂłāA�o�X�ŋA���Ă��܂����B
�@�������ŁA�������R���̏ォ��́A�x�m�R�����ɂ��ꂢ�Ɍ����܂����B�����������邽�߂��A�g���͏��Ȃ������܂����B�ł��A���������������̍����~�ł́A�����������܂���ł����B�ł��邾���A�����V�b�J���R�肾���āA�����悤�ɓw�߂܂����B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
�@�@ �@�I�i�K�K�� �@�I�i�K�K��
�@�@ �@�L�Z�L���C �@�L�Z�L���C
���������g���́A���Y�A�L�W�o�g�A�V���n���A�W���E�r�^�L�A�c�O�~�A�J���K���A�I�i�K�K���A�}�K���A�R�K���A�J���Z�~�A�n�N�Z�L���C�A�L�Z�L���C�A�J���E�A�����J�����A���N�h���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�ł������B
|
|
|
|
| 2013�N1��3���i�j |
| �������V�b�J��������F���Ɛ_��A�������U�� |
�@���A�����̂悤�ɖ��𑊑\�Y�����牺���̋��ꋴ�܂ŁA�g����T���Ȃ�������A�[�厛�o�R�Ő_��A���������w�����B���������A�����������A���������Ă���ƁA�������g����������悤�ɂȂ��Ă����B
�����́A�x�m�R���ƂĂ����ꂢ�������B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
������Ń��Y�ɂ����܂����B
�@�@ �@�@���Y �@�@���Y
�c�O�~���g�߂ɋ߂Â��Ă��܂����B
�@�@ �@�c�O�~ �@�c�O�~
�c�O�~�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kRzY8r5PhZg
�_��A�����͂Q������J�����Ă���A�V�t�̃{�^���W���s���Ă��܂����B���́A�c�o�L�̉Ԃ��炢�Ă��܂����A�Ԃ͏��Ȃ��A���ɂ́A���E�o�C�������炢�Ă��邾���ł����B
�@�@ �@�_��A�����̌f���� �@�_��A�����̌f����
�@�@ �@�{�^���W �@�{�^���W
�@�@ �@���E�o�C �@���E�o�C
�@�@ �@�p���p�X�O���X �@�p���p�X�O���X
�����݂��g���́A���W���A���Y�A�W���E�r�^�L�A�c�O�~�A�A�I�W�A�V�W���E�J���A�J���Z�~�A�L�W�o�g�A�q���h���A���N�h���A�X�Y���A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�I�i�K�K���A�}�K���A�R�K���A�J���K���A�R�T�M�A�n�V�u�g�K���X�A�n�V�{�\�K���X�ł����B�������͖̂�Q���Ԕ��A�P�S�P�O�O�������܂����B
|
|
|
|
| 2013�N1��2���i���j |
| ���U��F�g�������̐H�����i |
�@�ߑO�X������Ƃ��o�āA�V����̖k����ʂ�A�V���e�̊K�i������āA���̔ɏo���B�����ԉ����̂����āA���\�Y�����牺���ɁA���Ŗ쒹��T���Ȃ���U��B�䓃�⋴�ň����������A��Ŗ��ƕʂ�A�A���Ă����B��Q���ԁA�P�O�Q�O�O���ł����B
�@�߂��ŁA�J���Z�~�ƃ_�C�T�M���l�����Ƃ�Ƃ���������B�W���E�r�^�L�̎p���������B
�@�@ �@���W�� �@���W��
�@�@ �@�_�C�T�M �@�_�C�T�M
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
�@�@ �@�W���E�r�^�L �@�W���E�r�^�L
������Ayoutube�ɓo�^���܂����B
�_�C�T�M�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xlpHIgHlqUc
�J���Z�~�@http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tN04HHI5ens
�@�����������g���́A�I�i�K�A�V���n���A���W���A�_�C�T�M�A�R�T�M�A�I�i�K�K���A�J���K���A�}�K���A�R�K���A�n�N�Z�L���C�A�Z�O���Z�L���C�A�J���Z�~�A�V�W���E�J���A�W���E�r�^�L�A�c�O�~�A���Y�A���N�h���A�q���h���A�X�Y���A�n�V�u�g�K���X�A�n�V�{�\�K���X�ł����B
|
|
|
|
| 2013�N1��1���i�j |
| �V�N���߂łƂ��������܂��B |
�@�ނ�ŐV�N�̂��c�т�\���グ�܂��B
�@�{�N����낵�����肢�������܂��B
�@���A�[�厛�ɏ��w���܂����B�V������[�厛�ɂ��܂������A���Ȃ�̐l�����w�ɗ��Ă��܂����B
�@�@ �@�[�厛 �@�[�厛
�Q�q��A�P��ɂ��Ă��邨�݂����������܂����B���N�͑�P��g�ł����B�u���݂����ɂ����l�悭���l�ɂ��Ƃ܂����A�V���������Ҍ��X��������҂Ȃǂ��Ă��悢��g�v�Ə�����Ă��܂����B�M����킯�ł͂Ȃ������N���悢�B
�@�P�O�����납��A�Q���Ԃقǎ��]�ԂŖ��ɏo���B�������R���̏ォ��x�m�R�����ꂢ�Ɍ����܂����B
�@�@ �@�x�m�R �@�x�m�R
���ł́A�V���A�J���Z�~�A�I�i�K�K���A�}�K���A�J���K���A�R�K���A�R�T�M�A�n�N�Z�L���C�A�J���Z�~�A
���Y�A���W���A�W���E�r�^�L�A�X�X���A�q���h���A���N�h���A�n�V�u�g�K���X�����܂����B
�@�@ �@�V�� �@�V��
�@�@ �@�V�� �@�V��
|
|
|
|
| 2012�N12��31���i���j |
| ���N�̖��ł̊�����U��Ԃ��� |
�@���N���A��N�ԁA���𒆐S�ɂ��낢��̂��Ƃ�����܂����B
�@�݂������̉�̖��̊O���A���i�A���`�E���A�I�I�u�^�N�T�Ȃǁj�̋쏜�̊����́A�n���Ɋ������p�����A�T�N�ڂ̊����������܂����B�O��s�̕x�m���勴����䓃�⋴�Ԃ̖�Q�����̖��̐��ӂł́A�I�I�u�^�N�T�ƃA���`�E���̖��x���啝�Ɍ������܂����B�ڂɌ����鐬�ʂ�B�����邱�Ƃ��ł��܂����B
�A��여��A����ł͐��������ȉ�ɑ����A���c�J�A������A�������A�ȂǂŊ����������Ă���O���[�v�̕��X�Ƃ̖��Ɋւ���������́A��ϗL���ł������Ɗ����Ă��܂��B
���̂ق����ōs����N�Q��́u���̐������̊ώ@��v�ɂ́A�X�^�b�t�Ƃ��ĎQ�����܂����B
�B�������R���̗N���Ɩ��̗��ʂ̖����������R�N�ԑ����܂����B�������̗������[�܂�܂����B ��Q�N�Ԃ͑��������ł��B
�C�ԂƗ̂܂��O��n������̃{�����e�B�A����̍����V����̒|�і��x�Ǘ������́A�Q�N�ڂ������A�������������i�݁A�|�т����邭�Ȃ����Ɗ����Ă���܂��B
�D�������{�����e�B�A���U�N�ڂɂȂ�A�쒹�O���[�v�ɑ����A���N�́A�쒹�ώ@��̃|�X�^�[����S�����܂����B
�@
�E�����s�̐V�̐E���̃C���^�[�����C�ŁA���̊O���A���쏜�̎��K�̎x�����s���܂����B
�@���낢��̊������s���Ă��܂������A�̗͓I�ɂ������Ȃ��Ă����̂ŁA���N�́A���������������i�肽���ƍl���Ă���܂��B
�@�ߑO���A�����Q���Ԃقǎ��]�Ԃʼn��܂����B����g���́A�V���A�c�O�~�A�J���Z�~�A�q���h���A�X�Y���A�A�I�T�M�A�R�T�M�A�n�N�Z�L���C�A�L�Z�L���C�A�I�i�K�K���A�}�K���A�J���K���A�R�K���ł����B���ɃJ���Z�~�ɂ͂T���܂����B
�@�@ �@�@�V�� �@�@�V��
�@�@ �@�J���Z�~ �@�J���Z�~
|
|
|
|
| 2012�N12��30���i���j |
| �����쎩���̃t�W�o�J�}�ƃJ�����i�f�V�R�̕c����Ă� |
�@���̎���ł́A������̎�����̃t�W�o�J�}�ƃJ�����i�f�V�R�̎���Z���|�b�g�ɂ܂��A�c����ĂĂ��܂��B���������Ŋ뜜�킾�����ł��B
�@�c����ĂA�ۑS�ɊS������l�ɏ����āA��ĂĂ��炢�A�L���邱�ƂŁA�n��ł��̕ۑS��}���Ă��������ƍl���Ă��܂��B�D�揇�ʂ́A�ꉞ�A�@���R���ۑS�n��A�@������R�~�Z���̂悤�Ȍ����I�ȏꏊ�A�B�l�̒�̏����ōl���Ă��܂��B�ۑS�̂��߂ɂ́A���|��Ȃǂƌ�z�������Ȃ����ł��邱�Ƃ��K�v�����ł��B���������Ȃ��ŁA���������i�߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�@���N�́A�S�X���i�V���V���j�̃Z���|�b�g�Q���Ɏ���܂��Ă��܂��B�J�����i�f�V�R�̔��藦�͂����i�X�O���ȏ�j�̂ł����A�t�W�o�J�}�̔��藦�����x�ł��B�c�O�Ȃ���A���N�́A�c�O�Ȃ���t�W�o�J�}�́A�����̕c�͊��҂ł��܂���B
�@�@ �t�W�o�J�}�̉萶�� �t�W�o�J�}�̉萶��
�@�@ �@�J�����i�f�V�R�̉萶�� �@�J�����i�f�V�R�̉萶��
|
|
|
|
| 2012�N12��30���i���j |
| �߂��̐�ɁA�g���G�K�������܂��� |
�@����A�߂��̎��R�ώ@���̉����ɁA�g���G�K�������Ă����悤�ł��B���͂܂����ɍs���Ă��܂��A�����̉J�ŁA�����܂ł��Ă���邩�s���ł��B��ϒ��������Ƃł��B
�@�ʐ^�́A���̂g�o�@�u�V�j�A����v�@http://homepage2.nifty.com/adam-san/index.html�@�̌f���ɁA��X���q���A���e���Ă��������Ă��܂��B���L�̂t�q�k���猩�Ă��������B
http://8926.teacup.com/adam/bbs
�@�@ |
|
|
|
| 2012�N12��30���i���j |
| ���j���̒��́A�s�a�r�s�u�́u�������k�v������ |
�@�������A�s�a�r�s�u�́u�������k�v���݂��B�i��͌�~�M����A�Q�X�g�͖쒆�L������Ɣ����ꗘ����B�����̘b��́u���N�̏d��j���[�X�v�ł���B
�܂���R�ʂ���B�@��������́��w�����h���I�����s�b�N�ő����̃��^���l���x���B��������́u�܂����{�̍��͂͂܂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��Ɗ������v�ƁB
�@�쒆��������w�����h���I�����s�b�N�őI�肪����x���B
��Q�ʁ@�쒆����́��w�R�������m�[�x���܂���܁x���B�쒆����́u�䂪���̉Ȋw�̐i���Ɏh����^���Ă����v�ƁB
�@��������́A���w����}���玩���}�ւ̐������x���B��������́u���a�̗��j���v���o�����B���a�P�T�N��R�T��I���ŁA�����̐��}���o�Ă��đ������̂��v���o�����B���̌�吭���^��ɂȂ��ꍞ�B�ϊv����������Ȃ��v�ƁB
��P�ʁ@�쒆����́A���w���I���ɂ����鐭�����x���B�@�쒆����́A�u�����̐��_���ꋓ�ɓ����悤�ɂȂ�Ɗ댯�v�Ǝw�E�A��������́A�u�I���ŁA�O���E���������_�ɂȂ�Ȃ������̂͂��������v�ƁB
�@�S�s����������}�ւ̃A�h�o�C�X�Ƃ��ẮA��������́u���[�_�V�b�v���Ȃ��B�Q�d�i�������g��Ȃ��Ƃ��߁v�ƁB
��������́A��P�ʂ́��w��t���œ����W�̈����x�B��������́u���{����������������Ă��܂����B�܂����v�ƁB�@
�@
�Ō�ɁA���N�̏d��Ƀ��[�X�́A��������́u�Q�c�@�I�����������ƍl���ē��[���Ăق����v�ƁB�쒆������������u�Q�c�@�I���v�ŁA�u�����ƍ����Ƃ̊W��z�����Ɓv
�@�������Ȃ���A���j�Ɋw�Ԃ��Ƃ��������Ƃ��v�����B
|
|
|
|
| 2012�N12��29���i�y�j |
| �L�N�C�^�_�L�������� |
�@�P�Q���Q�P���ɖ������a�n��̃e�j�X�R�[�g�ɋ߂��G�ؗтŁA�q�K���̌Q���W���̌Q����݂��ۂɁA���܂�͂����肵�Ȃ��ʐ^�ł��������A�悭�悭����Ƃǂ����L�N�C�^�_�L�̂悤�ȃg�����ʂ��Ă����B���̌�A�쒹�ɏڂ������ɔ�������肢���Ă������A��͂�L�N�C�^�_�L�Ƃ̂��Ƃł������B�L�N�C�^�_�L�́A���{�ł݂���쒹�̒��ł́A�ł������ȃg���ł��邻�����B
�@�@ �@�L�N�C�^�_�L �@�L�N�C�^�_�L
�������ŁA�L�N�C�^�_�L���������邱�Ƃ͒������B
|
|
|
|
| 2012�N12��29���i�y�j |
| �W���E�r�^�L���A����̒�ɗ��Ă���܂����B |
�@�����́A�������|���B�܂������W����̑|���A�����ő��K���X���B�O����̑|���Ƒ����E�E�E
�@���ь�A��ɃW���E�r�^�L�̎p���@�m�����̂ŋ}���ŃJ���������������B���z���ɔ~�̎}�Ɏ~�܂����W���E�r�^�L�̎p������ƃJ�����Ɏ��߂��B�V�W���E�J�����t�G���X�ɂƂ܂��Ă�������݂Ă����B
�@�@ �@�W���E�r�^�L�̃I�X �@�W���E�r�^�L�̃I�X
�@�@ �@�V�W���E�J�� �@�V�W���E�J��
�쒹�̂��߂ɐ��������Ă���̂ŁA�~�͂��낢��̃g���������݂̂ɗ��Ă���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
|
|
|
|
| 2012�N12��28���i���j |
| ���U�� : �쒹�����̐H���̕��i |
�@���Ō�������쒹�����́A���낢��ȐH����H�ׂĂ���B������U��̐܂Ɍ��������l�q��iyoutube�j�ł��Љ�܂��B
�@�����̔㗬�̐��ԏ����̑O�ŁA�J���Z�~���_�C�r���O���āA������_���Ă���l�q���������܂����B���̂Ƃ��͂S��قǃ_�C�r���O���܂������A�Ƃ�܂���ł������E�E�E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4UwE6tsiqwU
�@�����̏����㗬�́A���̓c�ނ̑O�ɃI�i�K�K������R���ނ낵�Ă��܂����B�͂�����͕�����܂��A�쑐��H�ׂĂ���悤�ł����B�Ƃɂ������H���̂悤�ł��B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9clOO4H8BXw
�@���c�O�~�����̖쐅�������ŁA���̐������݂ɗ��܂����B���ɂ́A���낢��̃g�����������݂ɗ��܂��B
http://www.youtube.com/watch?v=QZohTZd1lWE&feature=player_detailpage
�@���܂��A��㗬�ł́A�c�O�~���J�L�̎���H�ׂĂ��܂�
���B
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=geLhkIpdqbo
�@���܂������ɂ́A���낢��ȃg��������H�ׂɂ��܂��B���W���A���N�h���E�E�E
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tij7Z8pV2qs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SHzMYd1mtsk
�������̑��ɂ��A�S���łQ�U�̓�����uokinatokyo�v�ŃA�b�v���Ă܂��B�O�[�O���ȂǂŌ������āA�A�N�Z�X���Ă݂Ă��������B
http://www.youtube.com/user/okinatokyo/videos
|
|
|
|