| <<新しい日記 古い日記>> |
|
|
| 2016年12月31日(土) |
| カワラナデシコの花 |
季節はすれですが、自宅庭のカワラナデシコが、今年二度目の花を、二輪つけています。種を蒔いて、育てた、自生種のカワラナデシコです。
 カワラナデシコ「の花 カワラナデシコ「の花
 カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え
|
|
|
|
| 2016年12月31日(土) |
| 富士山 |
今朝も 、富士山は、よく見えています。
 富士山 富士山 |
|
|
|
| 2016年12月30日(金) |
| オジロビタキ |
武蔵野公園のオジロビタキです。長くいますね。
 オジロビタキ オジロビタキ
|
|
|
|
| 2016年12月30日(金) |
| 富士山 |
お早うごじます。今朝の富士山です。少し雲がかかって4います。
 富士山 富士山
|
|
|
|
| 2016年12月29日(木) |
| マンリョウの赤い実 |
年末の掃除で、今日も忙しい一日でした。ホット一息ついて、書いてます。我が家の庭には、マンリョウの赤い実が沢山ついています。万両のように重くて、実は、すべて下を向いています。ネットで調べてみると、花言葉の、「寿ぎ(ことほぎ)」は、お正月の縁起物として飾られる赤い実にちなんでつけられたようです。また、「金満家」は、実が熟してもなかなか落ちない様子の例えだそうです。
 マンリョウ マンリョウ |
|
|
|
| 2016年12月28日(水) |
| 寒い朝の野川付近 |
朝、野川公園自然観察園は、まだ、開園していなかった。入り口近くで鳴き声で気がついたジョウビタキは、寒いので、朝日の中、羽根を膨らませて、丸くなっていた。
 ジョウビタキ ジョウビタキ
 ジョウビタキ ジョウビタキ
動画は、https://youtu.be/7Tirs6fG3yAです。
武蔵野の森公園のセンダンの実をムクドリの群が食べていた。ハンドブック「野鳥と木の実」には、センダンの実は苦みが強いようだが、ヒヨドリが群がって食べて居る。
 ムクドリ ムクドリ
武蔵野公園には、今朝も、オジロビタキがいた。さすがにカメラマンの数は少なくなって来た。
 オジロビタキ オジロビタキ
 オジロビタキ オジロビタキ
野川では、アオサギ、ダイサギをよく見かける。丁度コサギもいて、3種のサギが近くにいただ、コサギは、飛び去って行った。
 野川に、アオサギ、ダイサギ、コサギ 野川に、アオサギ、ダイサギ、コサギ
 アオサギ アオサギ
 ダイサギ ダイサギ
 コサギ コサギ |
|
|
|
| 2016年12月28日(水) |
| 今朝の富士山 |
今朝は、寒いが、富士山がよく見えます。
 富士山 富士山
|
|
|
|
| 2016年12月27日(火) |
| 私のおすすめ動画(野鳥) |
|
|
|
| 2016年12月26日(月) |
| 薬が多すぎ困ったことだ。 |
| 今日は、御茶ノ水の病院まで、慢性腎臓病の定期診察に出かけました。11月末に栄養指導を受けて、塩分管理等に、苦労していますが、果たして結果はどうかと、少し期待して出かけましたが、敵は、強敵です。期待通りには行かず、逆に、先生より、「血液検査の結果では、まだカリウムが多いので、薬を出します。便秘になりやすいので、その薬も出します」といわれて、薬の種類が3種類増えた。あまり薬をもらってもうれしくはないが、仕方がないというのが、正直なところです。薬局で、新しい薬をもらってびっくり、42日分だが重い。家に帰って重さを量ったら、1.15kgもあった。 |
|
|
|
| 2016年12月24日(土) |
| オジロビタキ |
近くの公園に、オジロビタキが、来ています。珍しい鳥のようで、もう1ヶ月ほどもいて、沢山のカメラマンを楽しませてくれています。私も時々、見に行っています。今日は、良い天気で、撮影日和でした。
今日は、動画も撮れました。 https://youtu.be/ftNY1cDEIiQ







 カメラマンたち カメラマンたち
|
|
|
|
| 2016年12月23日(金) |
| 野川散策 |
今日は、冬とは思えない穏やかな天気となりました。少し雲がかかっていましたが、富士山が、きれいにみえました。
 富士山 富士山
野川公園自然観察園で、今年初めてジョウビタキ♀にあいました。とても愛嬌のある目の表情をしています。
 ジョウビタキ♀ ジョウビタキ♀
 ひょうたん池 ひょうたん池
武蔵野公園には、今日もまだオジロビタキがいました。沢山のカメラマンが、構えていました。すぐに、移動するので、写すのは大変です。我慢強い人たちです。野川では、アオサギの姿が目立ちます。
 オジロビタキ オジロビタキ
 カメラマンたち カメラマンたち |
|
|
|
| 2016年12月22日(木) |
| 野川公園自然観察園にて |
午前中、野川公園自然観察園にでかけた。今日も顔見知りのボランテァイの方が活動をしていたが、今にも雨が降りそうで、一般の訪問者はほとんどいなかった。園内のロウバイは咲き始めた。ほたるの里近くを歩いていたら、人の気配に気がついたのか、1羽の野鳥が動き、ICU側のフエンスにとまった。後ろ姿であったが、時々、顔を横に動かす。アカハラでした。
 ロウバイ ロウバイ
 アカハラ アカハラ
野川では、カワセミ、ユリカモメの飛んでいる姿を見たが、写真には撮れなかった。マガモ、オナガガモ、ダイサギの写真はとりました。
 マガモ マガモ
 オナガガモ オナガガモ
 ダイサギ ダイサギ |
|
|
|
| 2016年12月21日(水) |
| カワラナデシコの花 |
庭のカワラナデシコが1輪、今日の暖かさで、今年2度目の花をつけました。

|
|
|
|
| 2016年12月21日(水) |
| 12/19の野川流域連絡会生きもの分科会 |
19日(月)夜、調布市文化会館「田作り」で、野川流域連絡会生きもの分科会が開催されました。
主な議題は、
1.冬季「野川の生きもの観察会」の開催について
2.「野川の生きものガイドブック」の改訂に」につぃて
でした。
冬季「野川の生きもの観察会」は、平成29年1月22日(日)10時に野川公園自然観察センター前に集合して、近くの柳橋左岸のほたる川や野川で、水中生物を採取して、観察します。生きものは、観察後に、またもとの川に戻します。定員は40名で、すでに募集は終了しています。
また、議題2の「野川の生きものガイドブック」の改訂は、すでにたたき台ができ、大分イメージが出来てきました。足らない写真や説明を、分担して、作って行きます。私は、野鳥を仲間と一緒に担当しています。 |
|
|
|
| 2016年12月20日(火) |
| 吉夢 |
今朝、御茶ノ水の病院に歯科の治療に出かけました。予約時間より、早くつきすぎたので、看板につられて、近くの妻恋神社にお詣りしました。果たして、ごりやくは如何でしょうかね?
この神社は、ヤマトタケルノミコト、オトタチバナヒメノミコ、ウガノミコノミコトの3神を祭っているそうです。
 吉夢の看板 吉夢の看板
 妻恋神社入口 妻恋神社入口
 妻恋神社 妻恋神社
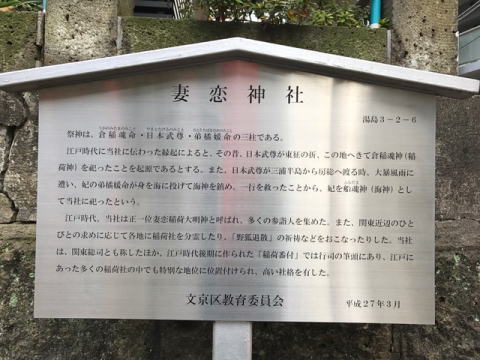 妻恋神社の由来 妻恋神社の由来 |
|
|
|
| 2016年12月19日(月) |
| 富士山 |
残念ながら今朝は、富士山は、うっすらしか見えなかった。
 富士山 富士山 |
|
|
|
| 2016年12月18日(日) |
| ロウバイ |
神代植物公園の梅園では、ロウバイが咲き始めていました。また、数カ所で、万両の赤い実を見かけました。
 ロウバイ ロウバイ
 ロウバイ ロウバイ
 マンリョウ マンリョウ
今朝は、まだ少し雲が残っていて、富士山の邪魔をしていましたが、その内晴れたようです。武蔵野の森公園のエノキには、シメが1羽いました。多分この辺に住み着いてしまったようです。メジロも来ました。
 富士山 富士山
 シメ シメ
 シメ シメ
 メジロ メジロ
|
|
|
|
| 2016年12月17日(土) |
| 富士山 |
今朝は、雲一つなく、富士山がすっきりと見えました。武蔵野公園では、まだオジロビタキがいました。沢山のカメラマンが集まっていました。
 富士山 富士山
 オジロビタキ オジロビタキ
 オジロビタキ オジロビタキ |
|
|
|
| 2016年12月16日(金) |
| 今日の富士山 |
冷え込んだので、富士山がきれいだと思って。朝早く、国立天文台裏の国分寺崖線の上から富士山を見てきました。

|
|
|
|
| 2016年12月15日(木) |
| 冬の一日 |
寒い朝、まず、国立天文台の裏から富士山を見てから、自転車で、武蔵野の森公園、野川公園、武蔵野公園を回ってきました。その後、国際基督教大学の学食で、昼食をいただきました。午後は、自宅のカイズカイブキの剪定をしました。
 富士山 富士山
 シメ シメ
 モズ モズ
 オジロビタキ オジロビタキ
 ゴンズイの実 ゴンズイの実 |
|
|
|
| 2016年12月14日(水) |
| ヒドリガモ |
毎年、冬になると、武蔵野の森公園修景池は、100羽以上のヒドリガモに、占領される。ヒドリガモの採餌は、夕方からだそうで、日中は、池で休息している姿をよく見かける。昨年は、アメリカヒドリガモが1羽だけ群れに混じっていた。今年は、なぜか、ホシハジロが1羽群れにまじっている。
動画は https://youtu.be/HHNmYkbzOrM です。
 ヒドリガモ ヒドリガモ
 ヒドリガモペアー ヒドリガモペアー
 ヒドリガモ群れ ヒドリガモ群れ
|
|
|
|
| 2016年12月13日(火) |
| 野川の流量測定(12月) |
昨日と一昨日で、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年1月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしています。今月の流量は、9月を今年のピークに、継続して減少しています。これは、野川に注ぐ湧水量と同じ傾向です。
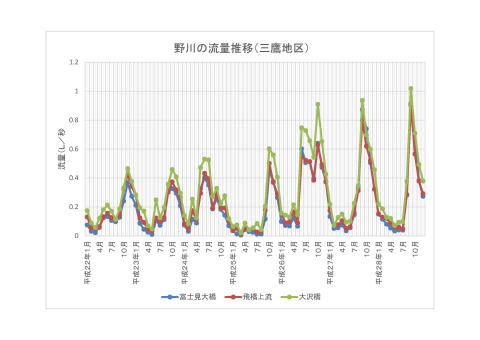 流量推移 流量推移
 富士見大橋での測定の様子 富士見大橋での測定の様子
 飛橋での測定の様子 飛橋での測定の様子
 大沢橋での測定の様子 大沢橋での測定の様子 |
|
|
|
| 2016年12月13日(火) |
| カワウ |
今朝、武蔵野の森公園の修景池に、ヒドリガモの群れの中に、1羽のカワウがいました。岸に上がったカワウは、すぐ羽根を広げて、干していた。カワウの羽根は、あまり水をはじかないので、水から出ると、羽根を広げて、乾かす必要があるようです。
動画は、 https://youtu.be/_gaf177Lc0A です。
 カワウ カワウ
 カワウとヒドリガモ カワウとヒドリガモ
 カワウ カワウ |
|
|
|
| 2016年12月12日(月) |
| 野川の野鳥 |
今日も、野川には、また、ユリカモメがいました。モズにも会いました。
 モズ モズ
 ユリカモメ ユリカモメ |
|
|
|
| 2016年12月12日(月) |
| 武蔵野の森公園の野鳥たち |
武蔵野の森公園の大きなエノキに、今日は、シメ、オナガ、ツグミ、ヒヨドリがいました。さかんに実を食べていました。先日は、アカハラ、メジロもいました。
修景池には、ヒドリガモの群れ(100羽程度)がいつもいます。バン、オオバン、カイツブリも住みついているようです。
 シメ シメ
 オナガ オナガ
 ヒドリガモ ヒドリガモ
 ツグミ ツグミ |
|
|
|
| 2016年12月12日(月) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(12月) |
| 昨日、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、9月をピークに、減少しています。
7年間のデーターを見ても、湧水量は、この3年間、その前の4年間より、増加しています。。
三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川12.6 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場42.5L/秒、③飛橋上流水車小屋向い18.5L/秒、④野水橋・榛澤橋間10.12L/秒でした。
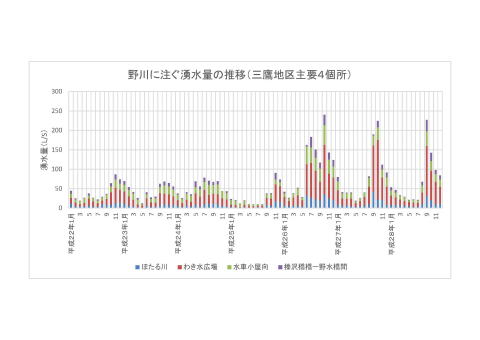 湧水量の推移 湧水量の推移
 湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子
|
|
|
|
|
|
| 2016年12月11日(日) |
| 今朝の富士山 |
今朝は、冷え込んだので、富士山がきれいに見えました。
 富士山 富士山 |
|
|
|
| 2016年12月8日(木) |
| オジロビタキ |
比較的近くの公園に、珍しい鳥がきました。スズメ目ヒタキ科のオジロビタキです。図鑑で調べると日本には、旅鳥または冬鳥として飛来するが、希なようです。沢山のカメラマンが、集まっていました。あまり良いところには止まってくれないので、良い写真は撮れませんでしたが、証拠写真程度です。


|
|
|
|
| 2016年12月8日(木) |
| 富士山 |
今朝は、冷え込んだので、予想通り、富士山がきれいに見ました。国立天文台裏の国分寺崖線上から撮影し、た。今年一番の富士山です。

|
|
|
|
| 2016年12月7日(水) |
| シメ |
今日は、曇り空でしたが、野川公園に出かけると、シメの群れにあいました。高い木の上に群れていました。シメは、今年初見です。ツグミも、数が増え、この実を食べていました。
 シメ シメ
 シメ シメ
 シメ シメ
 モミジ モミジ
|
|
|
|
| 2016年12月6日(火) |
| カメラの無料修理 |
今日は、午後、御茶ノ水の病院の歯科の治療を予約していたので、ついでと、早めに家を出て、外神田のカメラ修理工房にカメラの修理をお願いに出かけた。午前10時過ぎに、修理工房に到着して、修理をお願いしたら、受付のスタッフが、技術者と相談して、2時間後の12時半に受取りに来るようにと引換証を発行してくれた。1年間の無償期間内であったので、無償修理出来ますとのことでした。
実は、先月の野川の流量測定の際に、カメラは水をかぶった後、調子が悪くなり、そのうち全く動作しなくなった。簡易防水型であるが、なかなか難しいようだ。 保証期間を3週間ほど残ていることには、昨夜、気がついた。ぎりぎりの時間に気がついて、間に合ってよかった。
 修理工房 修理工房
聖橋近くのイチヨウは、あざやかに色づいていました。
 イチョウ イチョウ |
|
|
|
| 2016年12月5日(月) |
| 今朝の富士山 |
今朝は、少し曇っていて、富士山は、やっと見えました。

|
|
|
|
| 2016年12月5日(月) |
| 野川公園の朝 |
野川公園の朝です。イチヨウか色づいています。野川公園の場所は、戦後、国際基督教大学のゴルフコースがあったところを、東京都が購入して、公園になりました。今でも、その名残が残っています。
 イチョウ イチョウ
 昔のゴルフコースの後そのまま 昔のゴルフコースの後そのまま |
|
|
|
| 2016年12月4日(日) |
| 第48回社会教育会館のつどい |
昨日今日の2日間、三鷹市社会教育会館で、「つどい」が開催されています。今日の朝、見に行ってきました。社会教育会館を利用している団体が、日頃の活動の成果を、発表、展示しています。私が受講している28年度市民大学総合コースの受講生たちも日ごろの学習の様子を、全紙2枚の大きさの紙にまとえて、展示をしています。
尚、この社会教育会館も、来年から新らしい場所に出来た建物(三鷹市中央防災公園・元気創造プラザ)に引越をするので、ここでのつどいは最後です。

|
|
|
|
| 2016年12月3日(土) |
| 野鳥たち |
今日は、野川、野川公園、武蔵野の森公園を回ってきました。武蔵野の森公園の大きなエノキには、アカハラ、ツグミ、メジロ、ヒョドリがいました。アカハラは、最近はこのあたりではあまり見かけなかったので、うれしい事です。また、モズ、ヒドリガモ、カワセミ、アオサギにも会いました。フユザクラが咲いていました。調布飛行場からは、小型機が、離着陸していました。
 アカハラ アカハラ
 ツグミ ツグミ
 メジロ メジロ
 モズ モズ
 ヒドリガモ ヒドリガモ
 カワセミ カワセミ
 アオサギ アオサギ
 フユザクラ フユザクラ
 フユザクラ フユザクラ
 調布飛行場 調布飛行場
https://youtu.be/RIJd7NBF5y4
|
|
|
|
| 2016年12月3日(土) |
| 今日の富士山 |
雲がかかっていましたが、今日も富士山がみえました。

|
|
|
|
|
|
| 2016年12月2日(金) |
| 富士山 |
今朝は、富士山がよく見えました。野川を見て、国際基督教大学学食で牛丼を食べました。塩分は2gです。
 富士山 富士山
 野川 野川
 野川 野川
 牛丼 牛丼
|
|
|
|
| 2016年12月2日(金) |
| 今朝のNHK「あさいち」で |
朝、NHKのあさいちのプレミアムトークに俳優の永山絢斗さんが出ていました。話は、朝ドラ「べっぴんさん」になる。永山さんについてのスタッフの手紙が紹介された。スタッフとは、なんとディレクター安達もじりさんであった。すぐにカメラをもってTVの画面を撮影した。親戚の安達みじりさんが、活躍している姿をみてうれしいかぎりです。


|
|
|
|
| 2016年12月1日(木) |
| 男の料理 肉じゃが |
今日は、久しぶりに肉じゃがを作ってみました。

|
|
|
|
| 2016年11月30日(水) |
| 野川を下り、馬橋(甲州街道)まで歩く |
今日は、晴れ、体調もよかったので、野川を飛橋から甲州街道の馬橋まで歩き、更に京王線の国領駅まで歩き、電車とバスで帰ってきました。15000歩ほど歩きました。
飛橋近くでツグミを見かけました。今年初見でした。野川ではオナガガモ、コガモの姿が増えました。オオバンやバンの姿も見かけました。甲州街道の近くでキセキレイを見かけました。その他、写真にとれなかったものも含め、カワセミ、マガモ、カルガモ、ダイサギ、コサギ、カワウ、ハクセキレの姿も見かけました。
 ツグミ ツグミ
 オナガガモ オナガガモ
 コガモ コガモ
 キセキレイ キセキレイ
 オオバン オオバン |
|
|
|
| 2016年11月29日(火) |
| お茶ノ水の病院に栄養指導を受けに行ってきました。 |
今日は、内科(腎臓)の医師の指示で、御茶ノ水まで、出かけ、栄養士から栄養指導を受けてきました。御茶ノ水の聖橋付近は、イチョウが色づいていました。

2年ほど前から専門医より慢性腎臓病(CKD)の治療を定期的(約2ヶ月ごと)に受けていますが、塩分、熱量、タンパクの管理が必要で、2年ぶりに栄養指導を受けました。3日分の食事内容を詳細に記録して、提出をし、栄養士は、その記録から、熱量、タンパク質量、塩分量を計算して、管理目標値内に入っているかをチエックし、食事内容についてコメントをいただける。一応自分の食事は、自分で管理をしているので、私一人で、受講していても大丈夫です。
熱量とタンパク質の量は、医師に指示された管理値内に収まっていたが、塩分が、(管理目標値が6グラム/日であるが)少し多いようだ。注意をしていたが、まだ、努力不足で、もっと塩分管理に努めれば、腎臓機能の改善の余地があるということと受けとめたい。
|
|
|
|
| 2016年11月28日(月) |
| 野川の流量測定(11月) |
昨日・今日の2日間、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしています。今月の流量は、9月を今年のピークに、大幅に減少しています。これは、野川に注ぐ湧水量と同じ傾向です。
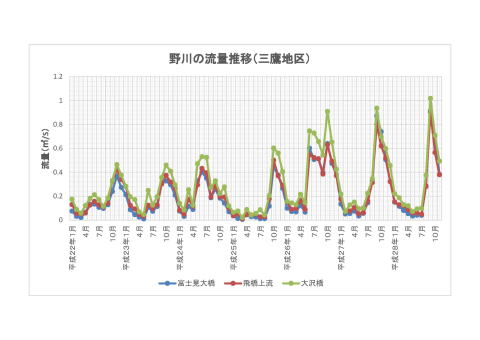 野川の流量推移 野川の流量推移 |
|
|
|
| 2016年11月28日(月) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定((11月) |
昨日と今日、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。やはり、湧水量は9月をピークに大幅に減少しました。 7年間のデーターを見ても、年間では10月前後にピークがあり、その後減少しています。
また、湧水量のピークは、この3年間が、その前の4年間より、増加しています。一般的には都市化により、雨水の地下への浸透量がへり、湧水量は、減少傾向にあると思われていましたが、そう単純ではないようです。
三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回約7年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川9.3 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場58.4.0L/秒、③飛橋上流水車小屋向い19.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間10.1 L/秒でした。
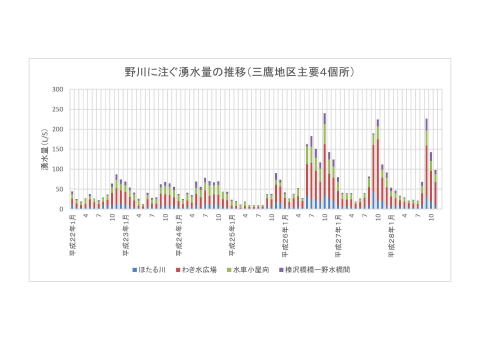 湧水量の推移 湧水量の推移
 湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子 |
|
|
|
| 2016年11月26日(土) |
| 野川の風景 |
晴れた今日も、富士山見えず、野川では雪が少し残っていました。武蔵野の森公園には、100羽を超えるヒドリガモが、今年も来ています。オオバンが、池の上を走っていました。カイツブリの鳴き声がしますが、姿は見えませんでした。岸辺では、赤いマユミの実が、沢山ついていました。
 野川くぬぎ橋上流 野川くぬぎ橋上流
 ヒドリガモ@武蔵野の森公園 ヒドリガモ@武蔵野の森公園
 オオバン@武蔵野の森公園 オオバン@武蔵野の森公園
 マユミの赤い実@武蔵野の森公園 マユミの赤い実@武蔵野の森公園 |
|
|
|
| 2016年11月25日(金) |
| 市民大学で、青山学院大学羽場久美子教授の講義を受講 |
今日は三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「歴史」コースで、青山学院大学教授羽場久美子教授の2回目の講義を受講した。先生の今日のテーマーは、「EC/EUの成立と、EUの拡大」及び「BREXIT英国のEU離脱」であった。大変密度の高い講義であり、学ぶところはおおかったが、講義を聴きながら、私が記憶にとめたところだけ、少し記してみたい。
(1)「欧州、アメリカは仲がいいから統合出来るということは偽り」で、戦争と対立の歴史であったが、戦争と3700万人の死者と殺戮への反省から、「銃をペンに、戦場を投票場に」と民主主義、選挙制度が生まれた。第2次大戦後、「敵との融和」「戦争の原因であるエネルギーの共有」から、石炭鉄鋼共同体の理念が生まれ、ようやく2000年の戦争が終わった。クーデンホーフ・カレルギーの妻は日本人(光子)であった。その2番目の子がミヒャエル(栄二郎)で、統合の父である。母光子は、多民族や階級憎しみの無意味さを子に示した。
(2)欧州統合は、西欧・中東だけの連合で、連合国、ソ連、ポーランド、チエッコなどを排除していた。これは冷戦の開始であった。
(3)戦争の欧州を60年間不戦の欧州にした意義は大きいが、課題として、①域内格差(南北、東西の格差)、②移民に対するゼノフォビア(外国人嫌い)、③主権の制限と、ナショナリズムの拡大、④成長するアジアとの対抗と共存(中国への接近)である。この分裂と統合の揺らぎをどう乗り切るかが問われる。
(4)Bregret。離脱後の可能性?イソップ寓話の肉を落とした犬に例えられる。EUから出た英国は、もはや重要な国とは言えない。イギリスは中国に接近するだろう。だが、中国は、イギリスよりもEUを重視するだろう。
(5)日本は、イギリスとは100年を超える付き合いがある。米英日露中ともにナショナル化の恐ろしさがある。日本にとっては、米英が混迷し、中国の地位の向上となり、試練の時となる。日本の地位は衰退の方向か? 大変重要な時期に入って行きそうである。 |
|
|
|
| 2016年11月24日(木) |
| 御茶ノ水の病院まで、内科の定期診断に |
雪の日でしたが、今日は、内科(腎臓)の定期診断日であり、御茶ノ水の病院まで出かけてきました。
1ヶ月前に、喘息で一晩横になれず、大変な思いをましたが、幸い近くのクリニックの処置がよく、その後も、いただいた吸入薬を毎日飲んでいるせいか、ゼーゼーいわずに、呼吸の調子がよく維持されている。
今日は、腎臓病の診察ですが、指標になるクレアチニン値が、1年ぶりに改善し、前の値に戻りました。医者は、何も薬を与えていないのに、そこまで改善する事には懐疑的で、1ヶ月後にもう一度検査をすることになりました。尚、カリウムが少し悪く出たので、もう一度栄養指導を受けるようになった。とはいえ、クレアチニン値がよくなったことは、良いことで、このままのレベルを維持し出来れば、万歳です。


|
|
|
|
| 2016年11月24日(木) |
| 初雪 |
三鷹にも雪が降っています。初雪です。庭のサザンカが寒そうです。

|
|
|
|
| 2016年11月23日(水) |
| 野川散歩 |
今朝、野川を歩き、調布で一服しています。


|
|
|
|
| 2016年11月22日(火) |
| 野川公園にて |
朝、国立天文台裏の国分寺崕線の上から、富士山が見えました。野川公園自然観察園では、リンドウ、ムサシアブミの実、アワコガネギク、サナカズラの実、シロヨメナを見ました。野川公園では、カエデが色づいてきました。
 富士山 富士山
 リンドウ リンドウ
 ムサシアブミの実 ムサシアブミの実
 アワコガネギク アワコガネギク
 サネカズラ サネカズラ
 シロヨメナ シロヨメナ
 カエデ カエデ |
|
|
|
| 2016年11月21日(月) |
| フジバカマの芽生え |
11月3日にセルポットに種を蒔いたフジバカマは、18日に一個だけ芽生えが生じたが、それ以降には、後続の芽生えが生じていない。少し気をもんでいいます。
 フジバカマの芽生え フジバカマの芽生え
他方、同日に種を蒔いたカワラナデシコは、芽生えが50%以上になっています。大きな差があります。
 カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え |
|
|
|
| 2016年11月21日(月) |
| 国際基督教大学構内の秋景色 |
曇りの日であったが、国際基督教大学構内では、モミジの真っ赤な紅葉、大きなイチョウの黄葉、ラクウショウの紅葉が見られます。木々は色づき、教会の十字架の上にカラス3羽がいました。
 モミジ モミジ
 モミジ モミジ
 モミジ モミジ
 イチョウ イチョウ
 イチョウ イチョウ
 ラクウショウ ラクウショウ
 ラクウショウ ラクウショウ
 木々 木々
 十字架上のカラス 十字架上のカラス |
|
|
|
| 2016年11月20日(日) |
| 野川の紅葉 |
朝の野川は、昨夜の雨で霧が立ちこめていましたが、徐々に晴れて行きました。木々が色づいてきました。
 くぬぎ橋下流 くぬぎ橋下流
 野川公園 野川公園
 野川紅葉橋付近 野川紅葉橋付近
 武蔵野公園 武蔵野公園
 武蔵野公園 武蔵野公園
 湧水広場 湧水広場
 くぬぎ橋下流 くぬぎ橋下流 |
|
|
|
| 2016年11月17日(木) |
| 野川自転車散策 |
病み上がりですが、お天気がよかったので、自転車で野川・野川公園に出かけました。富士山は、うっすらと見えていました。野川公園自然観察園では、アワコガネギク、シロバラアブラギク、シロヨメナが咲いていました。2度咲きのカワラナデシコも1輪だけ咲いていました。エナガがいました。野川では、アオサギが朝日を受けていました。
 富士山 富士山
 野川相曽浦橋下流 野川相曽浦橋下流
 野川くぬぎ橋下流 野川くぬぎ橋下流
 アワコガネギク アワコガネギク
 シロバナアブラギク シロバナアブラギク
 シロヨメナ シロヨメナ
 カワラナデシコ カワラナデシコ
 エナガ エナガ
 アオサギ アオサギ |
|
|
|
| 2016年11月17日(木) |
| 下弦の月 |
スパームーンから3日が過ぎましたが、今朝6時半頃。青空の西の方に下弦の月が明るく見えました。
 下弦の月 下弦の月 |
|
|
|
| 2016年11月15日(火) |
| 千枚漬け |
寒いこの季節になると、京都の千枚漬けが恋しくなる。昨日、親戚より千枚漬けに、すぐき、しば漬け、ちりめん山椒をつけて、送られて来た。うれしいことです。
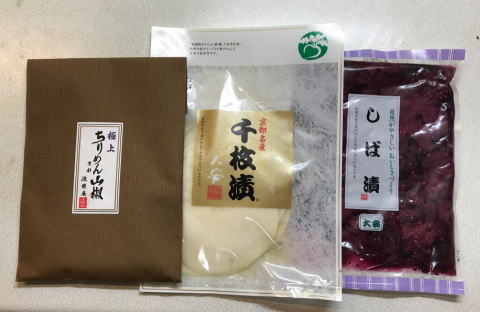
|
|
|
|
| 2016年11月14日(月) |
| 朝ドラ「べっぴんさん」 |
NHK朝ドラ「べっぴんさん」が、好調です。視聴率は、20%を確保しています。楽しみですね。

|
|
|
|
| 2016年11月14日(月) |
| カワラ」ナデシコの芽生え |
11月3日にセルポットに種を蒔いた自生種のカワラナデシコが、今朝見ると、双葉が芽生えていた。同じ日に蒔いたフジバカマは、まだ芽生えの気配はない。毎年かなり遅れる。
 カワラナデシコの芽生え カワラナデシコの芽生え |
|
|
|
| 2016年11月13日(日) |
| 日立中央研究所の庭園公開 |
今日は、日立製作所中央研究所の秋の庭園公開日でした。年に2回、公開されており、多くの人が見学します。この庭園では、国分寺崖線からの湧水が見られ、湧水の池、大池があり、野川の源流となっています。また多く(約26000本)の樹木が保全されています。
 大池 大池
 湧水点 湧水点
 コブハクチョウ コブハクチョウ
 10月桜 10月桜
 見所 見所 |
|
|
|
| 2016年11月11日(金) |
| みたか環境ひろば |
| 1昨日、うれしいメールが市役所の環境政策課から届いた。内容は、みたか環境ひろば(平成29年4月発行第59号)に寄稿させていただけるとのことです。内容は、自生種フジバカマの保全についてという500字程度の記事を考えている。
みたか環境ひろばは、平成20年6月に第1号が発行され、平成28年10月号に第57号が発行された。最初は月1回、途中から3ヶ月に1回の発行となった。A4サイズ裏表2頁の小冊子で、内容は、みたか環境活動推進会議の委員が、まちで見つけた三鷹の様々な環境情報などをお知らせしています。平成20年、私が、みたか環境活動推進会議の委員であった時に、提案をして、スタートした経緯があり、委員を辞めた今日でも、発行が継続されていることは、うれしいことです。
「みたか環境ひろば」は、下記のホームページでダウンロードできるほか、各市政窓口・図書館・コミュニティセンターなどの公共施設でも入手できます。
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/011/011626.html
|
|
|
|
| 2016年11月11日(金) |
| 喘息の治療は、継続が大事 |
| 今朝、雨の中、近くのクリニックに出かけた。病院はすいていた。1週間前には、血中酸素濃度が、93であったが、今日は99と良好であった。まだ咳は出て、痰は切れないが、夜、横になっても苦しくない。「喘息は、慢性病なので、喘息症状が治まっても、気管の炎症が治まるまで、吸入ステロイド剤は継続使用することが必要です」と、先生から指摘された。
お薬手帳を調べてみると、5年前からこれまで、季節の変わり目に、8回ほど、吸入ステロイド剤を先生から処方されていた。でも、いつも、約30日分を使い切ったら、それ以上継続してこなかった。それがまずかった事を思い知った。今回は、症状が一番ひどかった。再発しないように、これからは、治療を継続していくことにした。
また、先生から「呼吸が浅いので、よく吐き出したください。」ともいわれた。自分でも自覚していた事なので、大変有難い指摘であると感じた。呼吸法の一つとして、「口から、ゆっくりと深く吐き出し、鼻から吸う。」事を意識的に実施することを試みたい。
|
|
|
|
|
|
| 2016年11月5日(土) |
| のんびりと秋の日和 |
今日は、静養で、自宅で一日のんびりと過ごす予定です。朝、日課の体重測定で、一日で体重が0,8kg減少したことを知った。昨夜はぐっすり寝られた。でも、起きると、時々、深い咳がでる。少しは痰が切れて出るが、まだ少しだけです。
最新の学士会報を読んでいると東大名誉教授の原實氏が異文化の理解に関連して、「視点の多様性」と「視点の複雑化」について述べておられた。『「食べられる物」と「食べられない物」という唯一の基準を基にしてもし植木屋が庭園を見るならば、彼はあたら美しい花も、香りのよい花も切ってしまうであろう。人生を見る視点は多ければ多いほどよいので、「視線の多様化」は人生をより豊かなものにする所以であった。』と述べておられる。また、「視点の多様化」については、『自国の文化、それを培つた視点だけから物ごとを見ていると、それしか見えない事となるから、そこには自分だけを絶対視する危険が孕まれている。それはまた「汝と己」という他人の理解、思いやりにも通じるものがあるであろう。』とも述べておられる。この歳になっても、物事の理解が足らないことを、感じている自分です。歳をとって、動きがゆっくりとなっただけ、いろいろと考える時間だけは、あることは、良いことです。
庭に、今も咲いているのは、コムラサキ(小紫)、タイワンホトトギス、サザンカ、小菊(沢山種類があり同定は難しい)、ショウジョウソウ(猩々草)などです。暖かい日の光を浴びて、のんびり過ごすのは、良いことです。
 コムラサキ コムラサキ
 タイワンホトトギス タイワンホトトギス
 サザンカ サザンカ
 小菊 小菊
 ショウジョウソウ ショウジョウソウ
|
|
|
|
| 2016年11月4日(金) |
| 喘息で昨夜はよく寝られず |
昨日昼ごろから喉がおかしくて、咳が出だした。呼吸が荒い。夜になるともっとひどくなって、横になって睡眠をとろうとすると、息苦しい。仕方なく、椅子に座ったままほとんど夜を過し、朝までほとんど寝られなかった。
朝になって、かかりつけのクリニックに出かけて、診察していただいた。喉を見て、聴診器で胸を見て、指で血中酸素濃度を測った医者は、血中酸素濃度が大変低いことを確認して、「喘息がひどと、点滴と吸入を処方」してくれた。気管支を広げる吸入薬、アレルギーをおさえる薬、タンの切れをよくする薬、気管支を広げる飲み薬、咳喘息を抑える薬など6種の薬の処方箋をいただいた。
家の帰ってから、かなりよく昼寝をすることが出来、気分は少しはよくなってきた。ほっとしています。毎年秋寒くなる頃、よく喘息気味になっていたが、今回は、もっともひどかったようだ。 |
|
|
|
| 2016年11月3日(木) |
| 自生種フジバカマとカワラナデシコの種まき |
今朝は、暖かい日でしたので、セルポットに自生種のフジバカマとカワラナデシコの種をまいたピンセットで種をつかみ、2個づつ、セルにまいた。発芽には、水分と暖かさが必要です。毎年、この時期に種を蒔いているが、例年通りだと、どちらも2週間ほどすると、芽生えが出てくる。
 セルポットにフジバカマの種まき セルポットにフジバカマの種まき
 フジバカマの種 フジバカマの種
 カワラナデシコの種 カワラナデシコの種 |
|
|
|
| 2016年11月2日(水) |
| 御茶ノ水の病院までお出かけ |
今日は 、お茶の水の病院にきています。虫歯の治療と耳鼻科の診察です。終わって、肉の万世で遅めの昼食を食べました。
 病院 病院
 肉の万世 肉の万世
 食後のホットコーヒ 食後のホットコーヒ |
|
|
|
| 2016年11月1日(火) |
| 予報通り |
予報通り午後からお天気となりました。青空です。
 ICUのロータリーです。 ICUのロータリーです。
 野川の富士見大橋上流 野川の富士見大橋上流
 野川の飛橋上流 野川の飛橋上流 |
|
|
|
| 2016年10月31日(月) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
今日は、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。フジバカマはすでに花期が終わったので、刈り取りをしてきました。
フジバカマのすぐ隣では、キチジョウソウ(吉祥草)の花が咲いて、赤い実がなっていました。今までキショウブだと思い込んでいたところに、キチジョウソウが、入り込んでいたようです。
湧水点近くの湧水の流れには、ツワブキが咲いています。大池には12羽のマガモがいました。今日もコブハクチョウは、丘に上がっていました。
 キチジョウソウ キチジョウソウ
 キチジョウソウ キチジョウソウ
 ツワブキ ツワブキ
 刈り取り後のフジバカマゾーン 刈り取り後のフジバカマゾーン
 マガモ マガモ
 コブハクチョウ コブハクチョウ |
|
|
|
| 2016年10月30日(日) |
| サザンカ |
朝庭のカイズカイプキの剪定をした、まだ一部が終わっただけだが、身体が温まった。庭では、いまサザンカが咲き始めた。小菊も咲いている。
 サザンカ サザンカ
 小菊 小菊
|
|
|
|
| 2016年10月29日(土) |
| 市民大学「歴史」コース「反知性主義とアメリカの宗教的伝統」 |
午前中、三鷹市教育会館主催の市民大学総合コースで、国際基督教大学学務副学長森本あんり先生の「反知性主義とアメリカの宗教的伝統」の講義を受講した。私が理解した内容のメモは、次のようでした。
1.オバマ大統領の悲願
8年前大統領になったオバマはunited states を作るのが悲願であったが、8年後の今も、このオバマの悲願は進んでいない。「アメリカの牧師は、大統領のように語る。大統領は、牧師のように語る。」これがアメリカの伝統である。アメリカであなたの宗教はなにかと問われて応えられないとアメリカ人ではない。オバマほど、自分の宗教を語った人はいない。でも、アメリカ人で、オバマの宗教を知らない人が多い、29%はイスラム教徒と答える。共和党員に聞くと43%は、イスラム教徒と答える。トランプ支持者は、54%がイスラム教徒と信じている。オバマは、プロテスタントである。そのことは、大学卒の63%が知っている、大卒でないと28%しか知らない。オバマは、父がイスラム教徒、母がキリスト教徒で、ハワイで生まれて、インドネシアで少年時代を過ごし、大人になってキリスト教徒になった。シカゴで地域活動をするNGOで働いていた時、シカゴの黒人教会で洗礼を受けた。今年オバマは広島を訪問した。「和解」と「癒やし」を語る、典型的な大統領である。
2.アメリカの反知性主義
自分の信じるように、物事を考える人、知性的に物事を考えない人が、アメリカにはいる。それが反知性主義である。けんかをした時、仲直り出来るのは、なぐられた方です。オバマは、黒人のくせにと反発をうける。昔から、アメリカ大統領は、頭の良い人がなっていたわけではない。むしろ頭が切れすぎると反発を受ける。ジャクソン、アイゼンハワー、ブッシュなどを見てもそうである。アメリカの出発点では、世の中を、ピューリタ二ズムの極端な知性主義が支配していた。それへの反発から反知性主義がすすんだ。
3.反権力の原動力としての宗教
630年にマサツユセッツに移民がやってきて、6年目に大学(ハーバード大学)を作っている。それは牧師の養成が目的であった。でも誰もがインテリ社会でやっていける訳ではない。難しい話はいやだと言う人々がいた。そのために別のタイプの伝道師が生まれた。「神の行商人」ジョウジ・ホイットフイールドが活躍した。エスタブリッシュメントへの反感。知性と権力との固定的な結ぶつきへの反発。ゼロからの「たたき上げ」こそが善との考え方が出てきた。親のコネに頼るのは、アメリカではみっともないことである。トランプも自分の力で、稼いで、やっている。トランプがいわれたくないのは、親も不動産業であったということである。
4.アメリカ社会の構造に組み込まれた宗教
アメリカは、出発点では、非宗教的性格を持っていた。人々が宗教に充ち満ちていることができるように、国家は宗教に手を出さない。アメリカは、そのような「政教分離」である。日本の「政教分離」とは、異なっている。
5.アメリカは「キリスト教の本場」か?
アメリカにとって、キリスト教は、外来宗教である。ヨーロッパから伝わったピューリタンのキリスト教は、アメリカで土着化し、変異した。第一次大戦時にはナショナリズムとキリスト教が一体化した。単純で内向き、生硬で直線的、自己肯定的と自己慶賀、この世における成功は神の祝福と受け取る。「民の声はすなわち神の声」トランプはキリスト教的な生活をしていない。酒、タバコ、コーヒ、カジノはしない。だが女性関係はむちゃくちゃ。それでも、まじめな福音派の人々の1/3は、トランプを支持している。トランプは、あれほど成功を収めているので、神の目から見たら、どこかに良いところがあるに違いないと考えているからである。アメリカ的な精神の根源をとらまえるには、どうしても神学の理解が必要とされる。
6.アメリカの宿命
宗教は、本来超越的で、彼岸的である。リンカーンは、アメリカをいつでも祝福してくれている神ではないことを知っていた人であった。それが「南北戦争」につながった。アメリカは、今でも自由の建設途中である。アメリカンは元々移民の国であった。今後の姿、未来の姿が、アメリカ統一の焦点である。(ちなみに、日本は、昔に返れば、統一国家であった。そこが違う)これまでは、世界中をアメリカのような国にしなければ、アメリカは安全出ないと考えていた。内向きの論理である。しかし、世界がアメリカのようにならなくても、アメリカは良いと、知り始めたようだ。この考えも、まだアメリカの内向きの論理であることには変わりない。トランプは、「Make America Great Again」といっているが、アメリカの内だけで、greatであれば良いと考えているようだ。 以上
よりよく反知性主義を理解するには、森本あんり著「反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体」新潮選書が良いようだ。
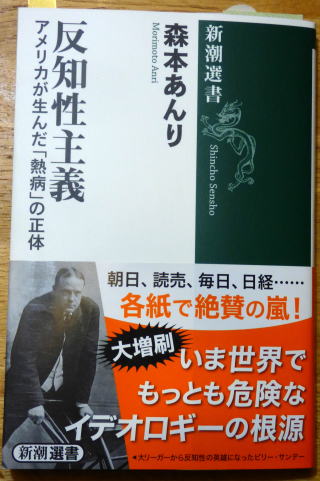
|
|
|
|
| 2016年10月27日(木) |
| 野川のフジバカマ・ゾーンの除草 |
フジバカマの花期も終わったので、午前中に、野川のフジバカマゾーンの除草を行った。先日の10月18日には、フジバカマの種を採種しておいた。今日は、草丈の低いものは少し残したが、花期の終わったフジバカマを、すべて刈り取りました。他のいろいろな草も一通り、草刈りを行いました。
除草作業をしていると、偶然、東京都の北多摩南部建設事務所の主任(Iさん)が、フジバカマのゾーンを通りかかり、「これから10分ほどしたら、新人研修で、今年採用の東京都の新人職員数名が研修で野川を見学して、ここにも来るので、自生種のフジバカマのことを少し説明してほしい」との急な依頼があり、OKしました。
しばらくして、顔なじみの東京都北多摩南部建設事務所の主任さん2名(Oさん、Nさん)が引率をして、数名の新人職員がやってきた。10分ほど、①私の野川とのつきあい、②野川の流量の年間変動、②絶滅が危惧されている自生種のフジバカマの保全、④フジバカマに来るアサギマダラなどの説明を一通り行った。
今日の除草ゴミは、90Lゴミ袋5個ほどになり、いつもお願いしている、先ほどの北多摩南部建設事務所のIさんに回収をお願いするつもりです。
 除草後のフジバカマ・ゾーン 除草後のフジバカマ・ゾーン
 除草「ゴミ 除草「ゴミ
 野川を見学中の東京都新人職員 野川を見学中の東京都新人職員
|
|
|
|
| 2016年10月26日(水) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(10月) |
今日は良い天気で、暖かそうだったので、朝、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。やはり、湧水量は9月をピークに大幅に減少しました。
7年間のデーターを見ても、年間では10月前後にピークがある。
三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回約7年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川20.1 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場76.0L/秒、③飛橋上流水車小屋向い24.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間21.5 L/秒でした。
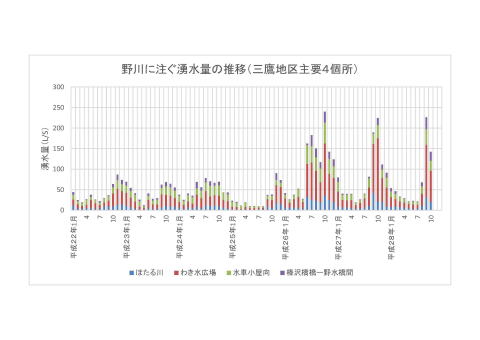 湧水量推移 湧水量推移
 ほたる川(湧水の小川)での測定の様子 ほたる川(湧水の小川)での測定の様子 |
|
|
|
| 2016年10月26日(水) |
| 冠雪の富士山 |
今朝は、少し霞んではいましたが、冠雪した富士山が見えました。丁度、調布飛行場から小型機が飛び立っていきました。

|
|
|
|
| 2016年10月25日(火) |
| iPhone7Plusを買いました! |
予約から3週間待って、17日(月)にやっとiPhone7Plusを入手しました。初めてのスマートホーンので、苦労しています。でも、ガイド本を読みながら、電話、メール、SNS、写真、検索などは何とか使えるようになりました。地図アプリからGPSで、位置情報が把握できて、重宝しています。音楽、ビデオはこれからです。
いろいろな機能があり、アプリを購入すると、便利に使えそうで、高齢者にも便利です。文字入力だけは、キーボードが小さくて、入力ミスが多く、不便です。その内、音声入力なども検討したいと思っています。通信費がどれくらいになるか、気にしながら使っています。
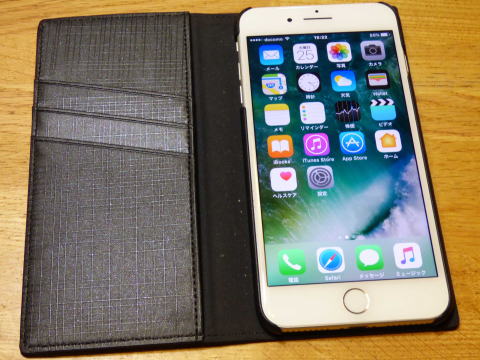

|
|
|
|
| 2016年10月25日(火) |
| タイアザミ(大薊) |
タイアザミ(大薊)は、別名、トネアザミ(利根薊)ともいわれ、関東地方に多く、大きなアザミです。特にタイ(国)とは関係がないようです。神代植物公園植物多様性センターで咲いていました。
 タイアザミ タイアザミ
よく咲いているので、ハチなどの昆虫が密にひかれて花に来ています。
 タイアザミに来た昆虫 タイアザミに来た昆虫
 タイアザミに来た昆虫 タイアザミに来た昆虫 |
|
|
|
| 2016年10月24日(月) |
| 野川の流量測定(10月) |
今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしています。今月の流量は、先月を今年のピークにして、大幅に減少し始めました。
今日、測定中、川の中で、けつまずいて前のめりに倒れました。服はぬれましたが、ケガはなく、測定を続けました。7年間で初めての経験です。高齢となり大分足腰が弱くなってきているのが原因と考えています。このような活動は、そろそろ潮時か・・・
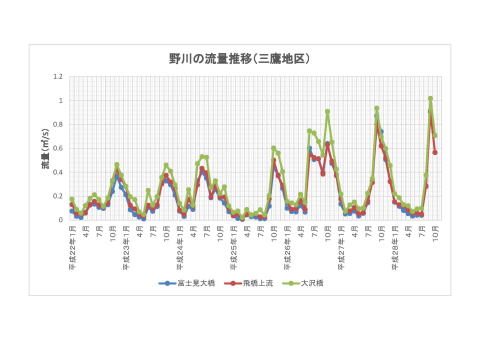
|
|
|
|
| 2016年10月23日(日) |
| 秋の野川の風景 |
天文台通りで、シュウメイギクが咲いてた。野川では、今日は、大沢の里で、餅つきが行われていた。いつもイベントでは交通整理をしている交番の巡査が、請われてこれから丁度餅つきをする順番であるようだ。大沢の田圃で収穫した餅米をつかっている。ついた餅は、田圃の田植え、稲刈りなどで手伝った人々(子どもたちを含む)に配られる。前の野川では、子どもたちが川で遊んでいた。
国際基督教大学では、昨日に続き、今日もfestivalが行われていた。今日は、泰山荘の見学をさせてもらった。
 シュウメイギク シュウメイギク
 シュウメイギク シュウメイギク
 餅つき 餅つき
 野川の人々 野川の人々
 野川の人々 野川の人々
 ICU泰山荘の書院 ICU泰山荘の書院
 ICU泰山荘の書院 ICU泰山荘の書院 |
|
|
|
| 2016年10月22日(土) |
| ICU Festival 2016 |
今日と明日は、国際基督教大学の学園祭(ICU Festival)です。毎年楽しみにしています。今年のテーマは「1Exploring Differential」だそうです。「違いをお互いに認めあう」ことをテーマーに掲げているようです。特に、本館での学生たちのアイルランドの音楽、クラッシック音楽、ジャズの生演奏のブースを楽しんでいます。
沢山の屋台も出ます。
 バカ山ステージ バカ山ステージ
 上からの風景 上からの風景
 ジャズの演奏 ジャズの演奏 |
|
|
|
| 2016年10月22日(土) |
| チャノキの花@国立天文台 |
昨日午後と今日は、国立天文台の一般公開日です。正式には「三鷹・星と宇宙の日2016」です。毎年見学しているが、昨日、見学に出かけました。構内を歩ける貴重な日です。太陽塔望遠鏡(アインシュタイン塔)や奥の方にある太陽フレア望遠鏡などを見学した。途中旧図書館近くにチャノキの花が咲いているのに気がついた。
 チャノキの花 チャノキの花
 アインシュタイン塔への道 アインシュタイン塔への道 |
|
|
|
| 2016年10月20日(木) |
| ゴンズイの赤い実 |
ゴンズイの赤い実は美しい。ミツバウツギ科の樹木で、学名はEuscaphis japonica。前のEuscaphisは、ギリシャ語の良い小舟の意味だそうで、赤い実が美しいことに由来するらしい。花期は5~6月で、秋に紅色の袋の中から黒い実が現れる。材としては用途がなく、役に立たない魚とされる「権瑞(ごんずい)」になぞらえられた。別名は、「狐の茶袋」とも、「黒臭木(くろくさぎ)」ともいわれているらしい。
 ゴンズイの赤い実 ゴンズイの赤い実
|
|
|
|
| 2016年10月20日(木) |
| フジバカマの花 |
私が提供したフジバカマの花が、神代植物公園植物多様性センターで初めて咲きました。看板がいていました。うれしいことです。
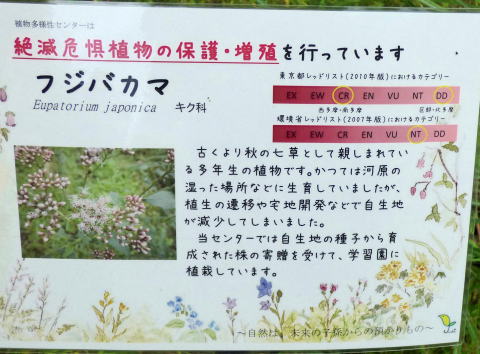
|
|
|
|
| 2016年10月18日(火) |
| ICU festival 2016 |
ICUの裏門に今年もICU festivalの看板が出ていた。10月23日(土)と24日(日)の2日間だそうです。
毎年この日を楽しみにして、見学している。学外者は普段は入れないが、この日ばかりは、大丈夫です。詳しくは、次のサイトを見てください。 http://icu-fes.com/
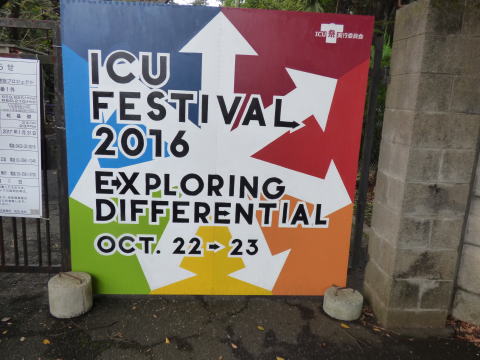
|
|
|
|
| 2016年10月18日(火) |
| 野川のキセキレイ |
今朝、野川で、今年初めてキセキレイを見かけました。野川には、ハクセキレイ、セグロセキレイとキセキレイと3種のセキレイがいます。その中では、キセキレイは、黄色が鮮やかで、一番人気があります。冬の時期に見かけます。セキレイは、いつも、長い尾を振っています。
動画もあります。 https://youtu.be/iPSaFeyUBHQ
 キセキレイ キセキレイ
 キセキレイ キセキレイ |
|
|
|
| 2016年10月17日(月) |
| 大(旧)田無農場訪問 |
雨のかな、根本正之先生に会いに、東大(旧)田無農場に出かけた。土日月は、正門及び横の通用門が閉まっているので、どうしょうかと思っていたが、約束の10時に、先生が正門で待つていてくださったので、有難かった。5分ほど歩き、本館会議室で30分ほどお話できた。先生より「日本らしい自然再生ハンドブック(草木編)」出版の計画を伺った。私が保全活動をしているフジバカマの写真などで、協力が出来そうで、うれしいことです。
私の方からは、最近野川のフジバカマの標本を作って、牧野標本館にお納めしたことなどをお話した。先生は、乾燥マットを使用することで素早い乾燥が可能となる植物標本作成法には関心を示された。
 正門 正門
 奥に本館 奥に本館 |
|
|
|
| 2016年10月16日(日) |
| バラフエスター@神代植物公園 |
午前10時半から、ボランティアによるばらガイドツアーに参加して、ボランティアのIさんに2時間ほどばら園の説明を受けた。まずばらの系統を理解するために、野生種(ワイルドローズ)・オールドローズ園を見学。ここには、モダンローズの第1号のラ・フランスがある。これより先がオールドローズです。また、ここには中国の野生種のばら2種、日本のものは、ノイバラ、テリハイバラ(つるバラ)、ハマナスもある。その後、バラ園本園で、多くのモダンローズを楽しみました、これらは、オールドローズから交配で作出されたバラで、匂いを楽しみ、花の形を楽しんだ。
 ラ・フランス ラ・フランス
午後は、「現在バラに至るバラの系統・系譜~原種・オールドローズ・現在バラの歴史とその魅力」と題する野村和子さん(NPOバラ文化研究所理事)を2時間の講演を聞いた。
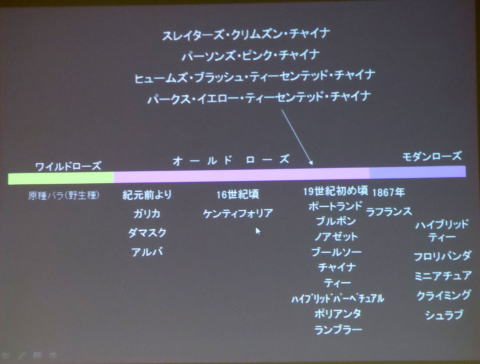 バラの系譜 バラの系譜
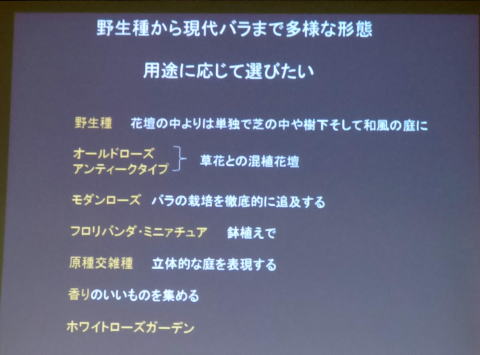 バラの選び方 バラの選び方 |
|
|
|
| 2016年10月15日(土) |
| 久しぶりの富士山 |
秋晴れの今朝9時頃、期待して、国立天文台裏の国分寺崖線の上に、富士山を見に行ったが、この時期は、まだ雪のない富士山は、余りはっきりは見えなかった。それでもかすかに見えたのでまずまずか・・
 富士山 富士山
蔵野の森公園にはヒドリガモ約20羽がきていました。野川には、アオサギ、ダイサギ、コサギがいました。ヤクシソウやキバナコスモスにはツマグロヒョウモンが・・
 ヒドリガモ ヒドリガモ
 アオサギ アオサギ
 ダイサギ ダイサギ
 コサギ コサギ
 ヤクシソウ ヤクシソウ
 キバナコスモス キバナコスモス |
|
|
|
| 2016年10月14日(金) |
| 市民大学「アフリカ 文明の道」 |
今日金曜日、午前中三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「混沌とした現在の源は」の第14回「ブリテン帝国3 アフリカ 文明への道」を受講した。講師は青山学院大学文学部史学科教授平田雅博先生です。平田先生の講義は、今日までで5回の講義があり、19世紀から20世紀の世界の動きを、産業革命を成し遂げ,世界へと展開していったブリテン帝国を中心に学んできました。世界システムというのは、「近代世界が経済的には単一の分業体制に組み込まれており、諸国の経済はこの世界システムの構成要素としてしか機能しえない」と見る世界史の見方です。最初の2回は、ブリテン帝国と世界システムで、3回目から、アメリカ、インド、今回のアフリカと3回講義があった。
アフリカは、人類の先祖はアフリカで生まれたが、18世紀頃、インドに似て、その一部はイギリスの植民地であった。今日のテーマは、①大西洋奴隷貿易、②イギリスとフランスなどによるアフリカの分割である。
大西洋奴隷貿易では、アフリカから総計数千万人ともいわれる奴隷が、カリブ海やアメリカ大陸のプランテイションの労働力として運ばれ、砂糖、タバコ、綿花やコーヒと交換され、ヨーロッパに運ばれ、ヨーロッパからはアフリカに武器や日用品が運ばれた。この武器は、アフリカで、部族間の闘争などに使われるものでした。このように奴隷貿易で、働き手を失ったアフリカは、人口が20世紀に入るまでは、低いレベルにと止まった。アフリカが発展する大きな足かせになった。
暗黒の大陸ともいわれたアフリカは、熱帯の風土病の特効薬が開発普及されたことで、内部までの探検が進み、ヨーロッパ人の奥地への進出が可能になり、19世紀の末にはアフリカの分割が進んだ。イギリスは縦断政策、フランスは横断政策をとった。20世紀初めまでに、エチオピアとリビアなどをのぞき、アフリカの全域がヨーロッパに列強の支配下に置かれることになった。
後半には、アフリカに於ける英語の普及についての説明があった。1961年にウガンダのマケレレで開催された「第2言語としての英語教育についてのブリテン連邦会議」の報告書が出た。学校で用いられる言語に英語が導入されることが賢明であるとの立場(英語至上主義)であった。 |
|
|
|
| 2016年10月12日(水) |
| 神代植物公園植物多様性センターにて |
今日は、秋晴れの良い天気でした。植物多様性センターに、フジバカマの標本を持っていったついでに、センター内を歩いてみました。イヌショウマがきれいでした。カワラノギク、ユウガギク、シラヤマギク、ハマコンギク(小笠原の植物)などキク科の花が沢山咲いていました。
 イヌショウマ イヌショウマ
 カワラノギク カワラノギク
 ユウガギク ユウガギク
 シラヤマギク シラヤマギク
 ハマコンギク (小笠原の植物です) ハマコンギク (小笠原の植物です)
「武蔵野のくさはら」という名の観察小道が整理されました。昔の武蔵野の草原を再現する試みのようです。ススキを優先種にして、アキノノゲシ、イヌタデ、ウシハコベ、キツネノマゴ、フジバカマ、ナンバンギセル、ツユクサなどが咲いていました。
 ススキ ススキ
 アキノノゲシ アキノノゲシ
 イヌタデ イヌタデ
 ウシハコベ ウシハコベ
 キツネノマゴ キツネノマゴ
 フジバカマ フジバカマ
 ナンバンギゼル ナンバンギゼル
 ツユクサ ツユクサ |
|
|
|
| 2016年10月11日(火) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
|
|
|
| 2016年10月10日(月) |
| 野川散策 |
午前中野川を歩きました。水辺には、ミゾソバの花が沢山咲いていました。赤トンボの姿を見かけました。自然観察園の中では、シュウメイギク、ヤクシソウ、カントウヨメナ、シモバシラの花をみました。
 ミゾソバ ミゾソバ
 赤とんぼ 赤とんぼ
 ヤクシソウ ヤクシソウ
 ヨメナ ヨメナ
 シュメイギク シュメイギク
 シモバシラ シモバシラ |
|
|
|
| 2016年10月10日(月) |
| 朝ドラ「べっぴんさん」 |
先週からNHK朝ドラ「べっぴんさん」がはじまった。「べっぴん」とは、「別品」と書きます。特別な品の意味だそうです。つくるひとの思いがこもった一品が、一番です。神戸の子供服のファミリアの創業者がモデルになっているそうです。
この朝ドラはNHK大阪で製作している。演出は3名が交代で担当している。その一人の安達もじりさん(親戚)が、今週の演出を担当している。応援しています。

|
|
|
|
| 2016年10月8日(土) |
| 東京水道あんしん診断 |
午後、東京都水道局指定工事店が、水道あんしん診断に来てくれました。水道水をビーカーに取って、10分ほどで簡易測定をいてくれました。結果は、①漏水はなし、水質調査では、②外観異常なし、③電気伝導度200μS/cm、④残留塩素0.4mg/Lでした。東京都は、伝染病の病原菌から守るため、塩素を注入しており、残留塩素濃度は、0.1~0.4mg/Lに管理しているとのことのようです。今日の我が家の値は0.4mg/Lは、その上限になります。もう少し少ないことが望ましいと感じました。いずれにしても、東京都が初めて我が家の残留塩素濃度を測ってくれたことは、評価したいと思います。
|
|
|
|
| 2016年10月7日(金) |
| 秋のバラフエスタ@神代植物公園 |
明日10月8日から10月30日まで、秋のバラフエスタが、神代植物公園で開催されます。バラ園コンサート、香りのモーニングツアー、講演会、ボランティアによるバラ園ガイドなど、いろいろのイベントがあります。
前日の今日の午後、そっとバラ園をみてきました。まだすいていて、新鮮なバラがよくさいていました。
 バラ うらら バラ うらら
 バラ 錦絵 バラ 錦絵
 バラ 秋月 バラ 秋月
 バラ 朝雲 バラ 朝雲
 バラ 花霞 バラ 花霞
 バラ ブルーリバー バラ ブルーリバー
 バラ ブルーバュー バラ ブルーバュー |
|
|
|
| 2016年10月5日(水) |
| 牧野標本館@首都大学東京 |
今日は、八王子市南大沢にある牧野標本館の見学にでかけて来ました。加藤英寿先生の案内で、1時間ほど標本庫、供覧室、標本製作室などを見学させていただきました。電動式標本庫には、約50万点の標本が収蔵されています。私は、関心を持っているフジバカマ(Eupatorium
fortunei )標本数点を見させていただきました。
また、今日は、私が作製した野川のフジバカマの標本を、持参し、牧野標本館に提供し、保管をお願いすることが出来ました。牧野標本館の台紙に、標本を貼り付けるなどの所定の作業を経た後、今後、長く、標本庫に収蔵していただける予定です。
写真は、私が作製した野川のフジバカマの標本です。草丈が大きいので、一株を4分割し、4個で一組の標本になります。新聞紙に挟んだ状態で、牧野標本館に提出しました。
 標本① 標本①
 標本② 標本②
 標本③ 標本③
 標本④ 標本④
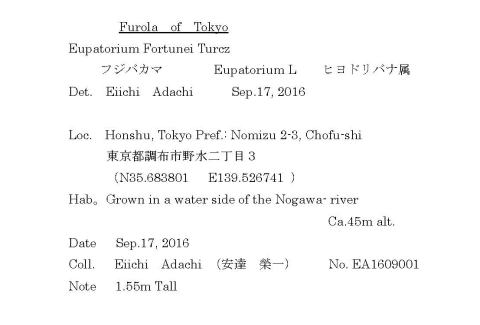 ラベル ラベル
|
|
|
|
| 2016年10月4日(火) |
| ジュガツザクラ(十月桜) |
野川公園では、ジュウガツザクラが、咲き始めました。



|
|
|
|
| 2016年10月4日(火) |
| シラヤマギク(「白山菊) |
シラヤマギクが、ICU校内に沢山咲いている。別名はムコナ。ヨメナに対してついた名前。カントウヨメナ、ユウガギク、ノコンギクなどよく似た野菊の仲間があります。

|
|
|
|
| 2016年10月3日(月) |
| 人間ドック |
今日、お茶の水の病院まで、人間ドック(半日)に行ってきました。20年近く、同じ病院で人間ドックを受けており、長い期間のデーターが蓄積されているので、費用は自費であるが、引き続き同じ病院で行ってもらっている。苦手の胃カメラも受けた。いつもは、強い拒否反応が出るが、今日は、それほど出なく、比較的楽にすんで、ほっとしている。オプションで前立腺検査、直腸肛門検査もうけた。今日行った血液検査の結果に基づき、医師との面談があったが、昨年の結果とほぼ同じレベルで、そんなに悪くなったところはなさそうでした。でも、年ごとに少しずつ悪くなっていくことは、避けられない。当面、気にして行かなければならない点は、まずは腎臓機能の維持、慢性的な貧血への対応のようだ。いずれも食事内容が重要なようです。高脂質、糖尿は、今飲んでいる薬をづけることでよいとしよう。
新たなオプション検査の案内は、①肺がん検診、②脳MRI・MRA検査、③VSRAD検査(早期アルツハイマー型認知症診断支援システム)、④ピロリ菌検査といろいろがあるが、とてもやっておれない。金もかかる。
今日の詳しい結果の報告は、一月後になるそうだ。 |
|
|
|
| 2016年10月3日(月) |
| 蝶(ツマグロヒョウモン)の睡眠 |
家の玄関先に鉢植えのフジバカマがおいてある。草丈が120cmにも成長していて、今花が沢山ついている。道を通る人にもなるべく見てもらえるようにしている。
そのフジバカマの花に、今朝、6時半ごろ、ツマグロヒョウモンがぶら下がっているのにきがついた。近づいても逃げない。試しに、ちよっと触って見ても、動かない。どうもお休みのようだったので、そっとしておいた。
 フジバカマ フジバカマ
 ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン |
|
|
|
| 2016年10月2日(日) |
| 秋の野川の一日 |
今日は、晴れたので、8時からフジバカマ・ゾーンでアサギマダラを待った。なかなか現れないので、まずは、フジバカマ・ゾーンの草刈りを少し行った。カントウヨメナが咲いていた。ツマグロヒョウモンが沢山来たが、アサギマダラは現れなかった。野川公園自然観察センター近くにヤクシソウが咲いていた。11時半まで待って、昼食に、ICUの学食に出かけた。午後は、また、野川でアサギマダラを待った。午後は、対岸の野川公園自然観察園内で、月1回の野草観察会が開催された。沢山の人々が、数グループに分かれて、ボランティアのガイドで、自然観察園内を回って、観察していた。午後3時になっても残念ながらアサギマダラは現れなかったので、あきらめた。
 野川 野川
 フジバカマ フジバカマ
 カントウヨメナ カントウヨメナ
 ヤクシソウ ヤクシソウ
 ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン
 野草観察会の人々 野草観察会の人々 |
|
|
|
| 2016年9月29日(木) |
| 未来へつなぐ植物標本講座 |
9月27日と29日の午後に開催された神代植物公園植物多様性センター主催の未来へつなぐ植物標本講座を受講した。講師は、首都大学東京牧野標本館の加藤英寿先生でした。 植物の標本の作り方の基礎を教わった。作業は、①植物採取、②乾燥、③ラベル作製、④台紙に貼り、保管するからなります。実際に、植物多様性センターに生育している草本を少しだけ採取して、乾燥マットを用いて乾燥、ラベルを作成して、台紙に貼りました。
植物の記録としては、文字による、写真による記録もあるが、標本による記録は、面倒ではあるが、実物の証拠資料としての価値は最も高い。また標本は、保存状態が良いと100年、200年先まで記録を残すことが出来ます。私たちが標本を残しておけば、今、そこにその植物があったことを、疑いなく証明してくれることでしょう。そう教わりました。 |
|
|
|
| 2016年9月28日(水) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
午前中、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。今、フジバカマは花期ですが、今年は雨が多かったためか、草丈の高いフジバカマは、頭が重くて、お辞儀をしてしまいました。先日、少し手当をしましたが、今日は、材料をそろえ、手当をしてきました。
フィジバカマは、湧水の小川の水辺に植えてあります。その湧水の小川は、大池に注いでいます。 https://youtu.be/VfhHhtsvq4U
庭園では、キンモクセイの甘い良い香りがします。花が咲き始めました。1本ある10月桜が、小さな花をつけていました。大池では、コブハクチョウが、コイと一緒に、食事中でした。
今年の秋の庭園の一般公開日は、11月13日(土)と(春の一般公開日に)予告されています。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 キンモクセイ キンモクセイ
 キンモクセイ キンモクセイ
 10月サクラ 10月サクラ
 大池 大池
 コブハクチョウ コブハクチョウ
|
|
|
|
| 2016年9月27日(火) |
| 私のYou-tubeの動画 |
|
|
|
| 2016年9月26日(月) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(9月) |
早朝に野川に出かけ、野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。やはり、湧水量は大幅に増加しました。。 7年館のデーターを見ると、年間では10月前後にピークがある。
https://youtu.be/Rekkl1-S5QU
三鷹だけでも、野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回約7年間定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川31.0
L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場128.5L/秒、③飛橋上流水車小屋向い38.0L/秒、④野水橋・榛澤橋間29.0 L/秒でした。
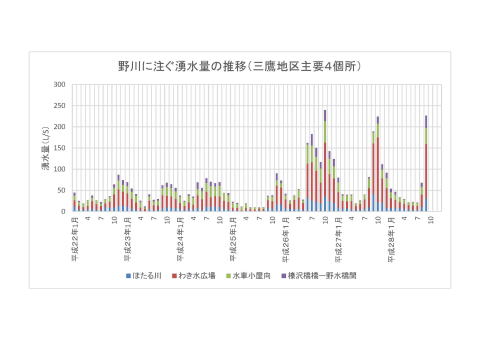
|
|
|
|
| 2016年9月25日(日) |
| 野川の流量測定(9月) |
今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。平成22年月から毎月1回約7年間、定期的に測定をしていますが、今月の流量は、大幅に増加し、大沢橋下流で1.0㎥ / 秒を超えた。初めてのことです。
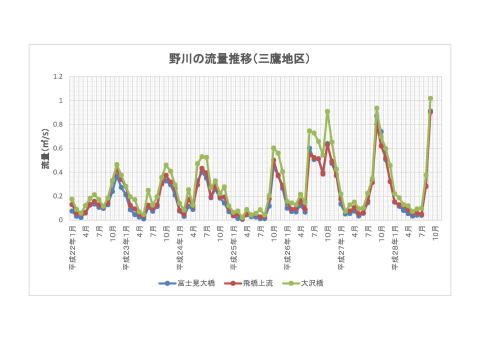
|
|
|
|
| 2016年9月24日(土) |
| ガーデニングフエスタ2016 |
今年も、ガーデニングフエスタが三鷹市市役所中庭で、開催された。今年は、136個の写真の応募があった。わたしの庭部門(自薦部門)、私の緑のお気に入りスポット部門(他薦部門)の2個の部門があり、私も私の緑のお気に入り部門に応募した。桜の季節の野川の写真である。当日写真展示コーナーがあるほか、立派な写真集として発行される。市長より応募者全員に記念品が贈呈される。
当日、他にも、竹細工体験コーナ、花緑名前あてクイズ、ガーデニング相談コーナー、ガーデニング講座、風船配布、はしご車体験乗車、など多くのお楽しみが体験できるコーナーが出来、多くの来場者を迎える。
午前中は、曇り空であったが、残念なことに、午後から雨となってしまった。
 市長より記念品の贈呈 市長より記念品の贈呈
 私の応募写真 桜の季節の野川 私の応募写真 桜の季節の野川
 竹細工コーナー 竹細工コーナー |
|
|
|
| 2016年9月24日(土) |
| 市民大学総合コース「ヨーロッパの移民・難民とナショナリズム」 |
昨日は、三鷹市社会教育会館の市民大学総合コース「歴史コース」で、青山学院大学大学院教授羽場久美子先生の「ヨーロッパの移民・難民とナショナリズム」を受講した。
始めに、先生のモットーは「汝の馬車を星につなげ」であると紹介して、皆さんと共有したいと話された。
ヨーロッパへの経済移民は2億5千万人で、その内半数が女性である。世界中の難民は年間で6000万人になる。シエンゲン協定で、EC内で人、もの、金、サービスは自由に移動可能になった。イギリスは、EUには入っているが、このシエンゲン協定にはいってない。戦後の1952年、平和を実現するためにEC6カ国(独仏イタリア+ベネルックス)が石炭、鉄鋼、原子力を共同管理する「不戦共同体」を作った。その後、2013年にはEUは28国にまで拡大した。それとともにヨーロッパへの移民・難民が増加した。①境界の開放により、周囲の貧しい国より、大量に流入が始まり、②賃金格差、不安定化が生じ、③近年の先進国の経済停滞、移民流入への不満から、ヨーロッパの中心でも極右が広がりだし、スエーデン、フイーンランド、スイスのも広がっている。デンマーク、イギリス、フランスでは右翼ポピユリスト政党は、今や25%ほどの支持率を確保している。移民が大量に入ってきて、安い賃金で働くので、中産階級の下層部の収入が落ち、生活の保証まで不安が出ている。彼らは、物理的な壁は作れないので、心理的壁を作っている。これがナショナリズム勃興の原因である。
「パックス・デモクラシティア」を書いたB.Russettによると分析の結果、①民主主義国同士は、戦争しない、②非民主主義国を民主化すれば、戦争はなくなる。③民主主義、市場化、市民社会は、価値として西から東へと移動した。またM.Mannは、民主主義の拡大が、多民族社会に不安定化をもたらす。すなわち多数者による支配が生じ、常時少数者は、テロしか手段がない。
中国は、民主化が、多民族国を解体させることを危惧し。天安門で「民主化」を弾圧した。旧ソ連諸国から、中東、アフガニスタン、イラクなど民主化とともに不安定化している。民主化は、多民族社会、多元的社会に不安定をもたらす。そこにゼノフォビア(外国人嫌悪)が生じ、広がる。市民及び移民双方の不満が増大し、対立と敵対が、まず底辺層同士で、次いで、移民、労働者、社会保障をめぐって、下層から中間層へ波及する。アメリカのトランプ現象、日本のヘイトスピーチも根は同じである。
日本の人口は、2060年には、労働力人口が半減、65才以上が40%となる。移民問題は、少子化日本にも現実問題となってきている。 |
|
|
|
| 2016年9月21日(水) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
今日は、国分寺にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。フジバカマは、草丈が平均で160cmにもなっていました。花も咲き始めていました。
しかし、このところの雨続きで、草丈の高いものは、お辞儀をしていました。お天気になれば回復すると思いますが、しばらくは、つっかえ棒をすることにしました。来月の初めが見頃かと思います。
(中研)新聞に、フジバカマを紹介していただけるようで、担当者が写真をとりに見えました。フジバカマがもっともっと増えて、その香りに惹かれて、ここのフジバカマにもアサギマダラが来てくれるとうれしいですね。
コブハクチョウは、午前中は丘に上がっていましたが、午後見ると池にいました。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 コブハクチョウ コブハクチョウ
|
|
|
|
| 2016年9月21日(水) |
| 次のNHK朝ドラ「べっぴんさん」 |
|
|
|
| 2016年9月20日(火) |
| 植物標本の製作(その後) |
17日に採集したフジバカマの標本は、取り敢えず新聞紙1頁サイズ(A2)に挟んで、しばらく乾燥していたが、牧野標本館に収蔵する植物標本にするために、サイズの制約があるのか気になってきた。また、根の部分は、ついていることが不可欠か、台紙などはどうするのか?など、心配点がいろいろと出てきた。
それで。今年の2月に植物標本講座で指導をいただいた牧野標本館の加藤先生にメールで、問い合わせてみたら、すぐに返事が来た。大変有難いことだ。サイズはA3サイズまで。絶滅危惧種の場合、根こそぎの採取はおすすめしない。台紙は、標本館ごとに規格があるので、乾燥後、新聞紙に挟んだ状態で提出くださいとのことでした。
従って今日は、標本つくりを一歩するめることにした。講習会で教わった時に使用した「原色植物標本作成キット」を使って、おこなった。特徴は、乾燥マットを使うことで、早く乾燥できる点である。
https://www.oshibana.com/herbarium/catalog.html

|
|
|
|
| 2016年9月19日(月) |
| 映画「海峡」を見る |
| NHKBS3で、1982年公開の映画「海峡」を見た。高倉健、吉永小百合、森繁久彌、三浦友和など豪華な出演陣を揃えている。本州と北海道をつなぐ、海底トンネルの物語である。何事も大きなことを成し遂げることは、大変なことだ。いろいろと犠牲も出た。ちよっとのつもりが、最後までみてしまった。 |
|
|
|
| 2016年9月17日(土) |
| フジバカマの植物標本つくりをスタート |
今日は、野川の自生フジバカマの標本作製のために、午前中野川に出かけました。草丈が高いもので170cmもありますが、今日は、①155cmと②130cmのフジバカマ2本を選んで、茎の根元から切り取り、3個に切ったり、折り曲げたりしてから、新聞紙に挟んで、それを更に野冊には挟んで、自宅の持ち帰った。仕上げに、花や葉を丁寧に並べ直し、乾燥のために更に新聞紙を重ねて、堅く、大きな板に挟んで、ひもでしっかり縛り、しばらく置いて、乾燥させる。
本格的な植物標本づくりは初めてなので、近く専門の先生に見ていただいて、標本のレベルを上げていくつもりで、今日はその第1歩です。
http://ada.c.ooco.jp/report/nogawafujibakamaWEB2016-9-8.pdf
 野川のフジバカマ 野川のフジバカマ |
|
|
|
| 2016年9月16日(金) |
| レッドデーターブック東京2013 |
先日9月2日、神代植物公園植物多様性センターにおいてあった「レッドデーターブック東京2013」を見ると、フジバカマは、南多摩、西多摩は、カテゴリー区分がCR(絶滅危惧IA類)となっていたが、北多摩と区部では、DD(情報不足)となっている。また、環境省のカテゴリー区分では、EN(準絶滅危惧)である。私が保全活動をしている野川の自生フジバカマの情報を、是非レッドデーターブック東京の東京都環境局の部署に提供する必要があると感じた。
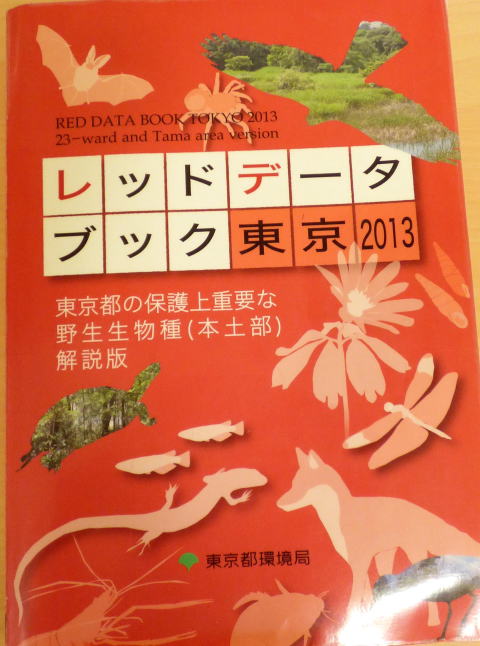 レッドデーターブック2013 レッドデーターブック2013
すぐに植物多様性センター並びに東京都環境局担当部署に平行して問い合わせた結果、「東京都の保護上重要な野生生物種」情報記入シートという様式があり、それに記入して、提出すると、次回の改定時に反映される仕組みであることが分かった。情報記入シートには、①生物名、②確認年月日、③確認場所、④確認方法、⑤生息・生育状況の概要、⑥その他の記載欄がある。
植物多様性センター経由で、東京都に提出していただくことにして、数日かけて(9月8日に)データーシートを何とかまとめ、まず植物多様性センターに送付した。
念のため植物多様性センター長のチエックを頂いた後、今日の午後、植物多様性センターに伺い、打合せをおこない、すぐに東京都に提出をしていただいた、これで、次期のレッドデーターブック改定時には、フジバカマはカテゴリー区分がDD(情報不足)にはならずに、適切なカテゴリー区分が与えられることになることと思います。
尚、この際、多様性センターのご支援を頂き、フジバカマの、いい植物標本を作製して、しかるべきところ(例えば牧野標本館)に保管をしていただくようにすることも、植物多様性センターと話し合った。何とか一歩進んだ感じがする。 |
|
|
|
| 2016年9月15日(木) |
| 腎臓内科の定期診察 |
今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。朝何も食べずに、午前中に血液採取・尿採取行い、午後の医師の診断時には、その検査結果に基づいて判断を聞かせていただいた。今日も、懸案のクレアチニン値が、前回より若干よくなり、また5ヶ月前の値近くに戻っていて、一安心でした。医師からも「大分落ち着いてきた」とのコメントをいただいた。
4ヶ月前より、食事の内容や、塩分の摂取にはあらためて注意をしている。また2年前から飲んでいる血圧を下げる薬(ミカルデス錠)をやめている。それでも、血圧はかなり安定している。医者は、塩分管理が出来ているので、血圧が安定しているとの見なしでした。私の方から、1日の塩分摂取量を測定していただくようお願いした。可能とのことで、準備が出来たら、実施することになった。 次回は、2ヶ月後に、診察を受けることになった。 |
|
|
|
| 2016年9月13日(火) |
| 市長への手紙「野川に自生するフジバカマについて」 |
三鷹市星と森と絵本の家は、10日(土)に来館者が25万人を達成し、清原三鷹市長を迎え、記念品の贈呈式が行われた。その際、式が終わってから、森と星と絵本の家の入り口付近で花が咲き始めているフジバカマを市長に見ていただいて、市長は「子どもの頃はよく見ましたが・・・」と云っておられました。
充分説明する時間が不足であったと感じたので、翌11日(日)に、「野川に自生するフジバカマについて(ご参考)」との資料を作成して、メールで三鷹市秘書室気付けで、清原市長宛にお送りした。お暇な時にでも見てくださいとのお願いでした。
http://ada.c.ooco.jp/report/lettertoKiyiharaWEB16-9-11.pdf
主な中身は 私がいつも考えて、このブログにも書いていることと同じで、...
1 昔の自然環境
2 偶然残っていた絶滅寸前のフジバカマ
3 フジバカマの苗を育てる
4 京都の藤袴プロジェクト
5 日本らしい自然再生の意義
でした。
今日13日(火)午後、三鷹市秘書課長から、清原市長からのメッセージとして、「先日は、お久しぶりにお目にかかれてうれしく思います。引き続き、お元気にご活躍いただき感謝申し上げます。子どもたちが多く来館する「絵本の家」にフジバカマが立派に根付いていることは何よりです。今後も、ご健勝にてご活動のご継続をお願いいたします。」とのメッセージが伝えられてきました。
お忙しい市長が、こまめにすぐメッセージを伝えてくださったことは、大変うれしく思いました。
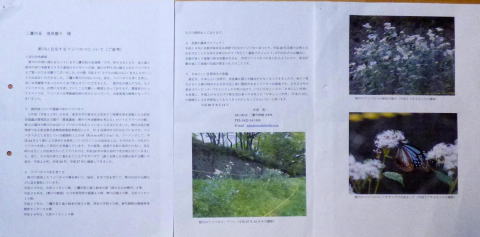
|
|
|
|
| 2016年9月12日(月) |
| 光回線終端装置(ONU)が故障。困った! |
| 昨日午後6時過ぎ、BS3で大河ドラマ真田丸を見ている途中で、急にTVが見えなくなった。インターネットもつながらない。大変困りました。日曜日だが、NTTに電話をしたら、録音で受け付けてくれました。そして今日午後修理に来てくれました。光回線終端装置(ONU)の電源部が故障のようだが、全部取り替えてくれた。ここまではNTTの貸出し装置になっており、勿論使用料は払っているので、今回の修理は無料で、時間も5分程度で無事修了した。
ものは考えようで、昨夜は、TVもインーネットもなければ、それに奥様もお出かけで、とても静かなひとときとなりました。でも、こんな時スマホがあると助かるのではないかとも思いました。
|
|
|
|
| 2016年9月10日(土) |
| 三鷹市星と森と絵本の家の来館者が25万人に |
私の家から近い三鷹市星と森と絵本の家は、国立天文台構内にあった旧天文台台長の木造の古い官舎を利用して、七年前に作られた。絵本の閲覧だけでなく、読み聞かせや、森のクラフトづくり、星空観望会もあり、家族づれで楽しめる場所として人気が高い。今日午後、来館者が25万人達成し、清原三鷹市長を迎え、記念品の贈呈式が行われた。丁度25万人目になったのは、三鷹市民ではなく、川崎市から来館されたご家族でした。市長より記記品と花束が贈呈された。
 25万人目の来館者家族と市長 25万人目の来館者家族と市長
式が終わってから、森と星と絵本の家の入り口付近に植えてあるフジバカマは、花が咲き始めているので、説明して市長に見ていただいた。市長は、「子どもの頃にはよく見ましたが・・・」と云っておられました。
 フジバカマの花 フジバカマの花 |
|
|
|
| 2016年9月4日(日) |
| ショウジョウソウ(猩々草) |
自宅に鉢植えのショウジョウソウがある。今日、その花に蝶が止まっていた。図鑑で見るとハマヤマトシジミに似ている。
ショウジョウソウは、トウダイグサ科の1年草で、花期には花の周辺の葉の一部が赤く染まってくる。北アフリカ原産で、コンクリートの隙間に落ちた種も成育するほど繁殖力がある。和名は猩々草であり、オランウータン草の意味だそうです。



|
|
|
|
| 2016年9月3日(土) |
| 今年もカワラナデシコの種を採取 |
5年前に多摩川の河原で採種されたカワラナデシコの種から育てられ、今年で5年目の秋になる我が家のカワラナデシコから、今年も沢山の種を採取した。種のサイズは、長い方で2mm程度です。
 カワラナデシコの種 カワラナデシコの種
教えていただいたところによるとカワラナデシコは、自家不和合性とかで、両性花をつける個体と雌個体が混生していて、他個体の花粉が受粉されないと有効な種はできないようである。我が家では、数株が植わっていて、有効な種が採種できています。自宅の庭のカワラナデシコの花には、クロウリハムシと言う昆虫が毎年どこからともなくやって来て、カワラナデシコの受粉を助けてくれています。大切な虫です。 |
|
|
|
| 2016年9月2日(金) |
| キアゲハ |
今日、野川沿いの道を自転車で走っていた時、近くにキアゲハが飛んでいるのに気がついた。自転車を止めて、キアゲハ♂が止まるのを待っ、写真を撮らせていただいた。
 キアゲハ♂ キアゲハ♂
 キアゲハ♂ キアゲハ♂
|
|
|
|
| 2016年9月2日(金) |
| 花と緑のまち三鷹創造協会事務所の移転 |
8月26日より、花と緑のまち三鷹創造協会が移転先で業務を再開するとの連絡をいただいていたので、今日午前中、三鷹市役所で東京都シルバーパスの更新を済ませてから、新事務所に伺った。三鷹図書館横の元ボランティアセンターのあった建物が、全面的に建て替えられ、三鷹市上連雀分庁舎となっていて、その建物の3階に事務があった。市役所とは近くなって、アクセスはよく、仕事もしやすくなることと感じました。皆さんがんばってください。
 三鷹市上連雀分庁舎 三鷹市上連雀分庁舎
 新事務所の内部 新事務所の内部 |
|
|
|
| 2016年9月1日(木) |
| タイワンホトトギス |
自宅の庭で、タイワンホトトギスが咲き出しましました。日本では、観賞用に栽培されていて、我が家も知人から株をいただいて育てています。よく繁殖するので、困るぐらいです。
 タイワンホトトギス タイワンホトトギス
|
|
|
|
| 2016年9月1日(木) |
| 野川のミソハギ |
野川で毎年ミゾハギがさくところがあります。今年は、咲くのが遅く、やっと咲き始めました。早速、チョウが来ていました。
 ミソハギにツマグロヒョウモン ミソハギにツマグロヒョウモン
 ミソハギにモンキチョウ ミソハギにモンキチョウ
 ミソハギ ミソハギ |
|
|
|
| 2016年9月1日(木) |
| ヤマボウシの赤い実 |
神代植物公園植物多様性センターでヤマボウシに赤い実が沢山ついていました。私は食べたことがないですが、美味しいそうです。ジャムにしたり、果実酒にもする使うようです。


|
|
|
|
| 2016年8月31日(水) |
| ナンバンギゼル(南蛮煙管) |
神代植物公園植物多様性センターでナンバンギゼルの花をを見てきました。ナンバンギセルはススキなどの根に寄生して、そこから養分を取る寄生植物です。筒状の、淡い紅紫色の花をうつむきかげんに咲かせます。名前の由来は、かつて南蛮人が使っていたマドロスパイプに見立ててたものだそうです。

|
|
|
|
| 2016年8月29日(月) |
| 星と森と絵本の家のフジバカマが開花 |
国立天文台構内にある三鷹市星と森と絵本の家のフジバカマが開花しました。3年前からはじめて、星と森と絵本の家には、場所を変え、フジバカマが3個所に植えてあります。自生種のフジバカマは成育環境が適してないとなかなか成長しないようで、3個所の内、昨年正門付近に植えたフジバカマが、成長が順調で、今年は草丈が160cmほどになっています。今朝見に行ったら、もう花が咲きはじめていました。多分、花の見頃は、9月下旬頃と考えています。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ |
|
|
|
| 2016年8月27日(土) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(8月) |
9時頃から雨の予報が出ていたので、早朝に野川に出かけ、5時過ぎから野川に注ぐ湧水量の測定を行いました。測定個所は、主要4個所だけ。先月まで、梅雨に入っても、湧水量は若干しか増加しませんでした。でも今月22日の9号台風で、1時間当り100mmの大雨が降り、湧水量は、大幅に増加しました。
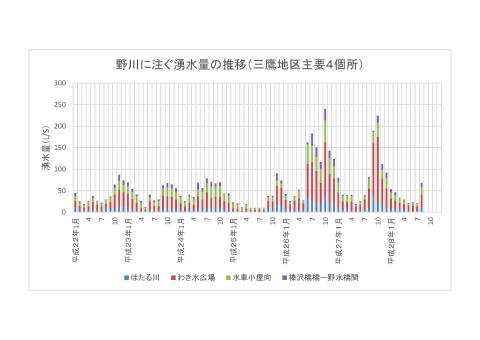 湧水量の推移 湧水量の推移
 湧水広場の湧水 湧水広場の湧水
 湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間以上、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川10.8 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場29.3L/秒、③飛橋上流水車小屋向い18.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間8.9 L/秒でした。 |
|
|
|
| 2016年8月26日(金) |
| 野川に咲く花 |
暑い時期ですが、今、野川に咲いている花です。ゲンノショウコ、クズ、イヌキクイモ、キツネノマゴ、ゲンノショウコ、ツユクサ、ツルボです。
 ゲンノショウコ ゲンノショウコ
 クズ クズ
 イヌキクイモ イヌキクイモ
 キツネノマゴ キツネノマゴ
 ユウゲショウ ユウゲショウ
 ツユクサ ツユクサ
 ツルボ ツルボ |
|
|
|
| 2016年8月26日(金) |
| 稲穂 |
野川沿いの大沢の里の田圃の稲穂が頭を下げていました。秋の気配が少しずつ近づいてきています。残暑は、もうしばらくです。健康には気をつけ、暮しましょう。
 大沢の里の田圃の稲穂 大沢の里の田圃の稲穂 |
|
|
|
| 2016年8月25日(木) |
| 野川の流量測定(8月) |
今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。22日の台風9号などの影響もあり、流量は、増加をはじめた。
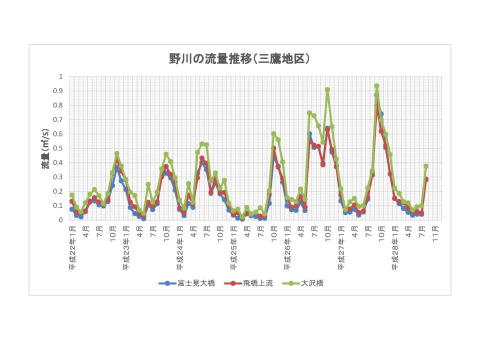

|
|
|
|
| 2016年8月23日(火) |
| 庭園のカワラナデシコ |
今日は、国分寺にある企業の庭園の見学に出かけました。お目当ては、大池の近くに、4株育っているカワラナデシコの開花の様子です。先週見学したときには、開花前のつぼみが少しついていたので、楽しみにしていたのでが、台風の雨で、開花には至らなかったようです。残念でした。来年を期待します。
大池のコブハクチョウは、今日は丘に上がって、草を食べていました。動画は、you-tubeで見ることができます。 https://youtu.be/STZAsKPO4Zc
 コブハクチョウ コブハクチョウ
 コブハクチョウ コブハクチョウ |
|
|
|
| 2016年8月23日(火) |
| 台風一過の野川の朝 |
野川のフジバカマが心配で、朝早く、自転車で野川の様子を見に行きました。昨日は、1時は、1時間100mmの雨も降りましたが、野川のフジバカマゾーンは、大丈夫で、安心しました。下流の方には、カワセミとアオサギの姿がありました。
 野川の朝 野川の朝
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 カワセミ カワセミ
 アオサギ アオサギ |
|
|
|
| 2016年8月22日(月) |
| 台風9号関東を通過 |
昼前千葉県館山に上陸した台風9号は、関東にも1時間100mmを超える雨を降らせ、関東から北に去った。三鷹でも、一時、野川(三鷹市大沢の測定点)の水位は氾濫危険水位を超えた。我が家では、風は、それほどでもなかった。
明日も、台風一過の快晴とはならないようですが、久しぶりに、関東に水を恵んでくれ、節水を余儀なくしていた貯水池の水位も上がることは、有難い。
野川の水位は、http://suii.ezwords.net/id/0332900400064.html で見ることができます。
|
|
|
|
| 2016年8月21日(日) |
| 野川のフジバカマ |
フジバカマは、秋の七草のひとつです。日照りには弱いようで、水辺に生育しています。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ・ゾーン フジバカマ・ゾーン
前にも書きましたが、5年前の秋に野川の水辺の法面に、フジバカマが自生しているとこらがあることがわかりました。野川の河川管理者の東京都北多摩南部建設事務所にお願いして、翌年からフジバカマ付近だけを業者に草刈りをしないようにしていただいています。
そのフジバカマ・ゾーンの面積は、約120㎡(幅約4m、長さ約30m)あり、野川が降雨で増水しても冠水しない位置にあります。その後も毎年、草刈りは除外していただいており、その代わり市民が草刈りをしています。
花の見頃は9月下旬から、10月上旬ですが、今年も、フジバカマはつぼみがつき、一部の成長がよい株は、草丈が約160cmにもなり、すでに開花が少しだけ始まっているようです
今朝は、フジバカマ付近のオオブタクサの除草を、1時間ほど行い、いい汗をかきました。 |
|
|
|
| 2016年8月20日(土) |
| 雨後の野川 |
午後、雨がやんだので、自転車で野川の様子を見に行った。野川の水は、増え、濁っていた。一時は高水敷まで水位は上がって、普段はテニスコートになっている大沢の調整池には水がたまっていた。
オアサギ、ゴイサギ、コサギ、カルガモ水辺にいて、流れを見ていた。
 野川の飛橋上流 野川の飛橋上流
 大沢の調整池 大沢の調整池
 アオサギ アオサギ
 ゴイサギ ゴイサギ
 コサギ コサギ
 カルガモ カルガモ |
|
|
|
| 2016年8月20日(土) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
昨日は、国分寺にある企業の庭園のフジバカマの手入れに出かけてきました。フジバカマには、草丈も平均で145cmほどに成長していました。つぼみも大分ついていました。今年は、うどんこ病は免れたようです。花期は9月から10月です。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
いつもは静かな大池に浮かんでいるコブハクチョウは。今日は、陸に上がって、静かに草を食べていました。池には、アオサギ、カイツブリ、カルガモの姿が確認できました。
 大池 大池
 コブハクチョウ コブハクチョウ
 アオサギ アオサギ
池の近くのカワラナデシコは、残念ながら、今日は、花が咲いていませんでした。仔細に見てみると、すでに咲き終わったものがあったようですが、これから咲きそうなつぼみも多くありました。来週また確認にでかける予定です。
 カワラナデシコ カワラナデシコ |
|
|
|
| 2016年8月19日(金) |
| 都立殿ヶ谷戸庭園 |
今日の午後、国分寺市にある都立殿ヶ谷戸庭園を見学しました。今見頃は、レンゲショウマ、ツリガネニンジン、キキョウ、オミナエシなどでした。
 レンゲショウマ レンゲショウマ
 ツリガネニンジン ツリガネニンジン
 キキョウ キキョウ
 オミナエシ オミナエシ |
|
|
|
| 2016年8月17日(水) |
| ヤマシャクヤクの実 |
神代植物公園植物多様性センターでは、ヤマシャクヤクの実が出来ていた。ヤマシャクヤクは、ボタン科の多年草。4月~6月頃、白い花が開く。秋に実が熟すと結実しない赤色と結実した黒色の種子ができるそうだ。和名の由来は、山地帯に生え全体がシャクヤクに似ていることによる。
 ヤマシャクヤクの実 ヤマシャクヤクの実
 ヤマシャクヤクの実 ヤマシャクヤクの実
 ヤマシャクヤクの花(2015年4月撮影) ヤマシャクヤクの花(2015年4月撮影) |
|
|
|
| 2016年8月16日(火) |
| 朝の野川 |
朝、1時間ほど、野川の大沢橋下流右岸の水辺のオオブタクサの除草を行った。これで、大沢橋・清水橋間右岸の除草はほぼ終わった。
 除草後の野川の様子 除草後の野川の様子
野川では、イヌキクイモが咲き始めた。オニグルミには実がついていた。フジバカマのつぼみも、大分白くなってきて、開花の準備が進んでいるようだ。
 イヌキクイモ イヌキクイモ
 オニグルミ オニグルミ
 フジバカマ フジバカマ
どこからか飛んで来た、コオニヤンマが、自転車のハンドグリップに止まった。指を出すと、指に止まってくれた。なぜか人なつっこいコオニヤンマだ。
 コオニヤンマ コオニヤンマ
 コオニヤンマ コオニヤンマ |
|
|
|
| 2016年8月16日(火) |
| 京都の五山送り火 「大文字」 |
今日8月16日は、京都の「五山送り火」の行われる日である。古くからある京都の夏の大切な行事である。久しく見ていないが、子供のころには、毎年、近くの小学校の屋上に上がり、家族で、この「大文字」を見たことが大変懐かしい。
京都の「五山送り火」は、如意ヶ岳の「大文字」の送り火が一番有名で、単純に「大文字」と呼んでいる。午後8時に最初に「大文字」が点火され、続いて、五山の「妙」「法」が、次いで「左大文字」、「舟形万灯篭」が点灯される。お盆に帰って来られた死者の霊をあの世に送り届ける行事である。 真夏の京都の風物詩です。
京都市観光協会のHP http://www.kyokanko.or.jp/okuribi/index.html で、「五山送り火」の写真と詳しい説明を見ることができます。NHKBSプレミアムで、今日、午後6時から生中継されます。 |
|
|
|
| 2016年8月15日(月) |
| 錦織、銅メタル! おめでとう! |
オリンピック男子テニスシングルスの3位決定戦で、錦織がナダルを6-2,6-7,6-3で下し、銅メタルを獲得した。おめでとう!
オリンピック・アントワープ大会の男子シングルスで熊谷一弥、同ダブルスで熊谷、柏尾誠一郎組が銀メダルを獲得して以来、日本勢96年ぶりの表彰台だそうだ。
真夜中の試合で、ねむい、ねむい。 |
|
|
|
| 2016年8月14日(日) |
| 神代植物公園水生植物園 |
午前中、野川でオオブタクサの除草を1時間ほどしてから、神代植物公園水生植物園に出かけた。早くもフジバカマが咲き初めていた。草丈が高いもので1.65mほどあった。ここのフジバカマが、毎年一番よく育つている。ミソハギも沢山咲いていた。他には、ジュズダマ、ミソハギ、ミズキンバイ、センニンソウ、ハスが咲いていた。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
 ジュズダマ ジュズダマ
 ミソハギ ミソハギ
 ミズキンバイ ミズキンバイ
 センニンソウ センニンソウ
 ハス ハス
 ハス ハス |
|
|
|
| 2016年8月13日(土) |
| さすがのオオブタクサも少雨には降参 |
昨日、午前中、野川を歩きました。草丈が1m程度に延びたオオブタクサが、しなだれていた。暑さの中、水不足が原因にようだ。こんな光景を見るのははじめてです。野川の水もなかなか増えてこない。東京都ではダムの水が少なくなってきた、新知事がビデオで節水を訴えていた。でも、中洲のハナトラノオには、キタテハが止まっていた。
 オオブタクサ オオブタクサ
 ハナトラノオに止まるキタテハ ハナトラノオに止まるキタテハ |
|
|
|
| 2016年8月12日(金) |
| 夏のバラ |
神代植物公園では、夏でもバラがさ咲いています。気に入ったバラをご紹介します。ダブル・デライト、うらら、シャルダン・ド・フランス、スヴエニール・ド・アンネ・フランクです。
 ダブル・デライト ダブル・デライト
 うらら うらら
 シャルダン・ド・フランス シャルダン・ド・フランス
 スヴエニール・ド・アンネ・フランク スヴエニール・ド・アンネ・フランク |
|
|
|
| 2016年8月11日(木) |
| ムクゲ(木槿) |
神代植物公園にはムクゲ園があり、今が花の見頃です。ムクゲは中国原産の植物で、室町時代から茶花として大切にされ、江戸時代には多くの園芸品種が作られました。一重咲、半八重咲、八重咲などの花形があります。
 白一重 白一重
 赤一重 赤一重
 光花笠(半八重咲) 光花笠(半八重咲)
 紫盃(一重咲) 紫盃(一重咲) |
|
|
|
| 2016年8月9日(火) |
| センニンソウ(仙人草) |
野川公園自然観察園では、センニンソウ(仙人草)が咲いていいました。センニンソウは、キンポウゲ科のつる性の多年草です。花には、4枚の白い花弁があります。(でも、本当は花弁ではなく、実は萼片だそうですが・・・)名前の由来は、果実に白い毛があり、これを仙人のヒゲに見立てたことに由来します。また有毒の植物のようです。

|
|
|
|
| 2016年8月9日(火) |
| スイフヨウ(酔芙蓉)の花 |
今朝、野川沿いの道に、スイフヨウ(酔芙蓉)の花がさいていました。一日花ですが、朝のうちは白、日に当り、午後から夕方にはだんだんと赤みが増す。名前は、酒飲みと関係があります。

|
|
|
|
| 2016年8月9日(火) |
| 体操男子団体金メタル 万歳! |
日本が3大会ぶりのオリンピック体操男子団体で見事金メタル。
おめでとう! 万歳


|
|
|
|
| 2016年8月7日(日) |
| 夏季・野川の生きもの観察会 |
午前中、野川の柳橋付近で、野川流域連絡会生きもの分科会主催の「夏季・野川の生きもの観察会」が開催され、私もスタッフの一人として参加した。参加者(予定)は、大人33名、子供27名で、親が参加されている方が多かった。スタッフは約20名であった。
10時から、準備運動を行った後、湧水の小川(ホタル川)の補修作業を30分、野川とホタル川の生きものの採集30分、最後に採集した生きもの説明が、委員の平井さんからあった。ホタル川では、ホトドジョウ、フタスジモンカゲロウ、オニヤンマのヤゴ、コオニヤンマのヤゴ、ガガンボ、カワニナ、タイワンシジミなどが、野川本川では、ドジョウ、シマドジョウ、メダカ、アメンボ、アメリカザリガニ、タモロコ、ヒラタドロムシ、ミナミヌマエビなどが今年も採取できました。最後に、採取した生きものを川に戻して、正午過ぎに解散した。
 補修作業の説明 補修作業の説明
 生きもの採取 生きもの採取
 生きものの説明 生きものの説明 |
|
|
|
| 2016年8月6日(土) |
| ハナトラノオ |
野川の中洲にハナトラノオが群生していた。雨が降ると、水をかぶる、こんなところで見かけるのははじめてです。ハナトラノオは、北アメリか原産の宿根草で、非常に繁殖力がすごいようだ。花も綺麗です。
 ハナトラノオ ハナトラノオ
 ハナトラノオ ハナトラノオ |
|
|
|
| 2016年8月6日(土) |
| 二子玉川再開発地区 |
昨日、二子玉川ライズの東京都市大学二子玉川夢キャンパスで、第9回雨水ネットワーク全国大学が開催され、雨水セミナがあったので、参加しました。
初めに、九州大学教授島谷幸宏さんの特別講演「雨水活用で防災・減災」があり、水の自立と分散、多世代共創の大切なことを強調されました。
その後、話題提供として、①「世田谷区における住民参加の公園づくり」世田谷区稲垣豊さん、②「二子玉川のまちづくり」東京急行電鉄都甲義教さん、③「災害時農水利用」福井工業大学笠井利浩さん、④「下水道施設における雨水利用について」国土省岩井聖さん、⑤「グリーンインフラへの取組み『多自然川づくり』から日本型グリーンインフラのあり方を考える」国土省堂菌俊多さん、がありました。
二子玉川地区は、自然との調和をコンセプトにして、33年かけて再開発によるまちづくりは行われました、水と緑と光が大切にされていいます。雨水をため、ビルの上層階からまた流して、屋上にはルーフガーデンが作られていました。再開発地区の隣には、大きな世田谷区立二子玉川公園も作られました。はじめて見学をして、驚かされました。 |
|
|
|
| 2016年8月6日(土) |
| 広島原爆の日 |
今日は、71年前に広島に原爆が落とされた日です。今年は、オバマ大統領の広島訪問を受け、「核兵器のない世界を追求する勇気」を共有することを、広島市長は、平和宣言で訴える予定だそうです。オバマ大統領も、「核実験禁止」の国連安保理事会決議を模索しているとの新聞報道もある。
暑い夏の日の今朝、私も平和を祈り、黙祷を捧げたい。 |
|
|
|
| 2016年8月5日(金) |
| 赤とんぼの逆立ち |
神代植物公園植物多様性センターで赤とんぼが逆立ちをしていました。顔まであざやかな赤色。翅が透明で全身が赤い。体型は小型で、太短い。ショウジョウトンボです。近くにはシオカラトンボもいました。
 ショウジョウトンボ ショウジョウトンボ
 シオカラトンボ シオカラトンボ |
|
|
|
| 2016年8月3日(水) |
| 朝の野川 |
今朝は、野川の大沢橋下流右岸のオオブタクサを1時間だけ除草しました。9月になり種が沢山落ちると大変です。作業のBefore/Afterの写真をおみせします。少しずつですが、野川を守って行きたいとの気持ちです。
 野川の様子(除草前) オオブタクサが繁茂。 野川の様子(除草前) オオブタクサが繁茂。
 野川の様子(除草後) 野川の様子(除草後)
 除草ゴミ (オオブタクサのゴミ) 除草ゴミ (オオブタクサのゴミ) |
|
|
|
|
|
| 2016年8月3日(水) |
| フヨウ(芙蓉) |
芙蓉(芙蓉)がいよいよ咲きはじめました。朝咲いて夕方にはしぼむ1日花ですが、つぼみが沢山あり、毎日次々と開花します。昔から、「美しい人」にたとえられている美しい花です。
 フヨウ フヨウ |
|
|
|
| 2016年8月2日(火) |
| 12年目のモミジアオイ |
今朝、自宅庭で、モミジアオイが一輪咲きました。 北アメリか原産の宿根草です。
鮮やかな赤い大きな夏の花です。 葉っぱがモミジににています。12年前の2004年に神代植物園の売店で買ってきて、庭の隅に植えた。それ以来、毎年咲いています。咲き始めの日は
2005年8月17日
2006年7月30日 ...
2007年7月31日
2008年7月30日
2009年7月31日
2010年8月4日
2011年8月5日
2012年8月6日
2013年7月26日
2014年8月2日
2015年7月24日
2016年8月2日(今年)
です。今年は例年並みの時期に咲きました。
毎年咲いてくれて、うれしいことでです。
 モミジアオイ モミジアオイ
|
|
|
|
| 2016年8月1日(月) |
| 盛夏の健康法 |
梅雨が明け、暑い日がやってきました。暑さに負けない健康法として、早朝1時間だけは、戸外で体を動かして、汗をかいてます。シャワーを浴びたあと、日中は、冷房のきいた部屋で、静かにしています。
一作日、昨日と、今朝は、羽沢小学校横の野川の水辺のオオブタクサの除草に汗をかきました。明日はどうするか、その日の気分で決めます。
野川の岸辺の木にはアブラゼミが鳴いていました。
 除草後の野川の様子 除草後の野川の様子
 除草ゴミ 除草ゴミ
 アブラゼミ アブラゼミ |
|
|
|
| 2016年7月31日(日) |
| ミヤマアカネ(深山茜) |
日本で最も美しい赤トンボと言われるミヤマアカネ(深山茜)です。ミヤマアカネは体長が35~39mm程度の小さなトンボで、前後翅に広い帯を持ち、赤トンボの仲間です。縁紋が赤い。成熟した♂は、頭も赤い。

|
|
|
|
| 2016年7月29日(金) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
今日は、国分寺にある企業の庭園のフジバカマの手入れに出かけてきました。フジバカマには、つる性の植物が少し絡んでいましたので、取り除きました。草丈も平均で120cmほどに成長していました。一部にはつぼみもつき始めていました。花期は8月末から9月です。この夏は、池の水は少ないようです。梅雨は明けましたが、あまり雨が降らなかった影響があるようです。いつもは静かな大池に浮かんでいるコブハクチョウが、陸に上がっていました。静かに草を食べていました。池の近くに試験的に自生種のカワラナデシコを植えてみました。4株だけが、なんとか根付きました。つぼみがつき、もう10日もすれば開花すると思います。来年は、もう少し株数を増やすつもりです。
 フジバカマ フジバカマ
 大池 大池
 コブハクチョウ コブハクチョウ
 カワラナデシコ カワラナデシコ
|
|
|
|
| 2016年7月28日(木) |
| 近くの自生種カワラナデシコ |
カワラナデシコの様子を見てきました。花はよく咲いてきました。
 自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ
 自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ
 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ
 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ
 羽沢小学校花壇のカワラナデシコ 羽沢小学校花壇のカワラナデシコ
 大沢コミセンのカワラナデシコ 大沢コミセンのカワラナデシコ
植物多様性センターのカワラナデシコ
自然観察園のカワラナデシコ
花の数では、
①野川公園自然観察園 3輪咲きはじめました。 (昨日7/27 確認)
②自宅庭 349輪とよく咲いています。
③三鷹市星と森と絵本の家 202輪
④羽沢小学校花壇 141輪
⑤大沢コミセン花壇 23輪
⑥神代植物公園植物多様性センター 44輪
です。
①から⑤は、いずれも、苗を、私がそだてて提供し、植えてもらいました。 |
|
|
|
| 2016年7月28日(木) |
| レンゲショウマ |
神代植物公園植物多様性センターでは、レンゲショウマ(蓮華升麻)が咲きはじめました。
 レンゲショウマ レンゲショウマ
|
|
|
|
| 2016年7月28日(木) |
| ユウガギク「柚香菊」 |
野川公園至善観察園で、ユウガギクが咲いています。カントウヨメナ、ノコンギク、リュウノウギクなどとよく似た野菊の仲間です。ユズの香りがするとの命名ですが、香りはよく分かりません。
ユウガギクは、若い葉を茹でて、和え物、おひたしなどにすると美味しいとされています。
 ユウガギク ユウガギク |
|
|
|
| 2016年7月27日(水) |
| ガガイモの花 |
野川公園自然観察園では、ガガイモの花が咲いていた。ガガイモはキョウチクトウ科のつる性多年草です。ハート型の葉を持ち、白い軟毛が密生した花をつける。秋になり果実には、沢山の種が入っていて、種には細長い毛が生えていて、風に飛ばされて、広がる。
 ガガイモの花 ガガイモの花
 ガガイモの実 2010年10月撮影 ガガイモの実 2010年10月撮影
 ガガイモの種 2007年11月撮影 ガガイモの種 2007年11月撮影 |
|
|
|
| 2016年7月26日(火) |
| 野川のフジバカマ |
今朝は比較的涼しかったので、野川のフジバカマゾーンの除草を1時間半ほど行った。90Lのゴミ袋に4個分の除草ゴミが出た。これは、東京都北多摩南部建設事務所の担当部署に連絡をして回収していただく予定です。
フジバカマも草丈が高いもので1.5mほどになっている。つぼみの形も見えてきた。
 フジバカマゾーン フジバカマゾーン
帰り道、野川の飛橋付近で、カワセミとアオサギの姿を見た。近くにはミクリの群落があり、少しだけだが花が見られた。
 カワセミ カワセミ
 アオサギ アオサギ
ミクリ |
|
|
|
| 2016年7月26日(火) |
| クサギ(臭木) |
三鷹市の大沢の里の隅にクサギ(臭木)の花が咲いていました。葉には強い匂いがあって、それが名前の由来でですが、花は良い香りを感じます。秋には赤います形のガクに囲まれた藍色の実をつける。
 クサギの花 クサギの花
 クサギの実 (昨年10月撮影) クサギの実 (昨年10月撮影)
|
|
|
|
| 2016年7月25日(月) |
| 第135回井の頭かんさつ会「かいぼり後の井の頭池」 |
昨日(7月24日)第135回井の頭かんさつ会「かいぼり後の井の頭池」が開催されました。私も一般参加者の一人として参加しました。
井の頭かんさつ会は、12年ほど前から、毎月1回、井の頭公園の身近な自然の観察会を実施している市民団体です。併せて、井の頭池の復活を目指して、餌やり禁止、外来魚駆除の活動などに長年熱心に取り組んできています。井の頭観察会のメンバーたちは、今回の井の頭池の「かいぼり」実現に向けても熱心に取り組み、井の頭池を深く見守っています。詳しくは、井の頭かんさつ会HP(http://kansatsukai.net/)をご覧ください。
昨日の観察会では、10時に井の頭池ボート乗り場前に集合して、七井橋→柳の広場→池尻のひょうたん池と回り、仕掛けた網に捕まった池の生きものを参加者みんなで観察しました。
井の頭池の「かいぼり」は、平成25年度(かいぼり25)と平成27年度(かいぼり27)とこれまで2度実施されました。そのよい結果として、弁天池の湧水、貴重な水草の復活、在来種の稚魚の大発生、カイツブリの雛多数などが確認されています。反面、残念なことには、駆除を狙ったブルーギルとアメリカザリガニなどの繁殖が確認されています。
井の頭池は、かいぼり後一旦は、透明度が良くなった池の水も、先月(6月)ころからアオコが発生して、透明度が下がってきています。まだまだ安心は出来ません。でも池には、ツツイトモが沢山発生していて、トンボのヤゴなどのすみかとなっているようでした。
ボート池の岸辺に設置されてオダアミに捕まっていたのは、在来魚(クロだハゼとモツゴ)ばかりが目立ちました。池尻に仕掛けたあった網には、在来魚(クロダハゼ、モツゴ)のほかに、スジエビ、ブルーギルの稚魚、アメリカザリガニが沢山入っていました。中には、ドジョウ、ナマズ、フナの少数入っていました。ツイイトに中には、ヤンマのヤゴ、イトトンボのヤゴが見つかりました。勿論かんさつ後は池の返します。
また、池では最近カワウの姿も見かけるようになりました。
 ボート池の岸辺に仕掛けたオダアミを引き上げる。中には、在来魚が沢山。 ボート池の岸辺に仕掛けたオダアミを引き上げる。中には、在来魚が沢山。
 オダアミの中には在来魚(クロダハゼとモツゴ)いっぱい。 オダアミの中には在来魚(クロダハゼとモツゴ)いっぱい。
 池尻のアミには、外来魚のブルーギルの稚魚が入っていました。 池尻のアミには、外来魚のブルーギルの稚魚が入っていました。
 池尻では、ドジョウとナマズも捕れました。 池尻では、ドジョウとナマズも捕れました。
 トンボのヤゴ トンボのヤゴ
 イトトンボのヤゴ イトトンボのヤゴ |
|
|
|
| 2016年7月24日(日) |
| 井の頭公園池のカイツブリ |
今日、井の頭かんさつ会に参加するために井の頭公園に出かけました。2回のかいぼりの結果、井の頭公園池にはカイツブリの必要な在来の小魚(クロダハゼなど)が沢山もどってきて、カイツブリの子育てに良い環境が生まれたようだ。今年は、池では6組のつがいが、雛をそだてたことを聞いた。先日、ボート池の池尻では、6羽の雛を育てていたが、その内5羽の雛が無事育ったとのこと。良かった。今は、すでに2回目の巣作りをしたいた。
今、池には、今朝帰った雛、少し前に孵った雛、大分大きくなった雛と、いろいろな発育段階の雛が、まだ親に餌をもらいながら育っている。
 カイツブリの巣@ボート池池尻 カイツブリの巣@ボート池池尻
 今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻 今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻
 今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻 今朝生まれたカイツブリ雛@ボート池池尻
 弁天池のカイツブリ雛 まだ縦縞が残っている 弁天池のカイツブリ雛 まだ縦縞が残っている
 御茶ノ水池のカイツブリ親子 もう縦縞はない。 御茶ノ水池のカイツブリ親子 もう縦縞はない。
 御茶ノ水池のカイツブリ若鳥。 御茶ノ水池のカイツブリ若鳥。 |
|
|
|
| 2016年7月23日(土) |
| イヌゴマ(犬胡麻) |
野川公園自然観察園では、イヌゴマ(犬胡麻)が咲き始めました。シソ科の多年草です。湿性の高い草地などに生育します。夏に淡紫色の唇形花を輪生状に多くつけます。葉は、細い披針形で茎に対生します。日本各地に分布しますが、比較的稀少です。
 イヌゴマ イヌゴマ |
|
|
|
| 2016年7月22日(金) |
| 梅原猛著「人類哲学序説」 |
今、91才の哲学者・梅原猛の「人類哲学序説」を読んでいる。岩波文庫で、2013年4月に出版された本です。本書のタイトルでは、「人類」と「序説」ということばがまず目についた。氏は、若い頃「西洋哲学」を勉強し、40才で「日本文化」の研究に入られ、その中に、「人類文化」を発展させる原理を見出し、本書「人類哲学序説」を書かれた。「人類哲学本論」は、しばらく中断していた「西洋文化」についての研究を行った後で、書かれるようだ。
日本文化の原理は「草本国土悉皆成仏」である。生きとし生けるものと共生する哲学であり、科学と科学技術は、そのような哲学にうらづけられなければならないと強調されている。
深く考えさされる本です。
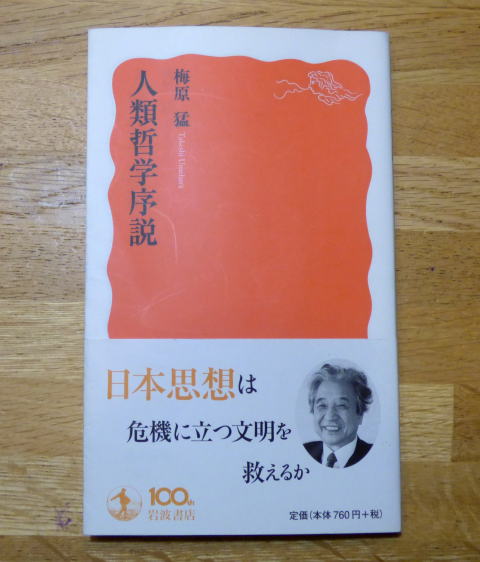
|
|
|
|
| 2016年7月21日(木) |
| 腎臓内科の定期診察 |
今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。11時過ぎに病院に入り、受付、血液採取・尿採取をすませて、午後の医師の診断時には、その検査結果に基づいて判断を聞かせていただいた。今日も、懸案のクレアチニン値が、また5ヶ月前の値近くに戻っていて、一安心でした。医師からの「大分落ち着いてきた」とのコメントをいただいた。
2ヶ月前の診断では、クレアチニン値が悪かったので、食事の内容や、塩分の摂取にはあらためて注意をした。 その上、医師の判断で、血圧が下がり過ぎてもいけないので、2年前から飲んでいる血圧を下げる薬(ミカルデス錠)をやめている。それでも、血圧はあまり大きくならず、クレアチニン値は落ちついてきた。まずまずの状況です。
次回は、少し間隔をおいて2ヶ月後に、診察を受けることになった。 |
|
|
|
| 2016年7月20日(水) |
| あやまってお札を洗浄 |
| 封筒にお札(野口栄世)3枚入れて、ズボンのポケットに入れていたが、間違ってそのまま洗濯してしまった。乾燥してから気がついてびっくりしたが、封筒はぼろぼろになっていたが、幸いお札3枚は、変化なし。よっぽど丈夫な紙が使われていることに、またまたびっくりした。でも2度と同じ過ちはしないと決心しました。 |
|
|
|
| 2016年7月19日(火) |
| 近所の自生種カワランデシコの花 |
17日と18日の2日間で、近隣の自生種カワラナデシコの様子を見てきました。大分花の数が増えてきました。
 植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ
 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ
 羽沢小学校のカワラナデシコ 羽沢小学校のカワラナデシコ
 大沢コミセンのカワラナデシコ 大沢コミセンのカワラナデシコ
 自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ
 自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ
花の数では、
①神代植物公園植物多様性センター 47輪(18日)
②三鷹市星と森と絵本の家 50輪(17日)
③羽沢小学校花壇 47輪(18日)
④大沢コミセン花壇 15輪(17日)
⑤野川公園自然観察園 未開花(開花は8月初めごろか?)
⑥自宅庭 69輪 (18日)
です。②~⑥は、苗を、私がそだてて提供し、植えてもらいました。
|
|
|
|
| 2016年7月18日(月) |
| 神代植物公園植物多様性センターにて |
暑い日でしたが、自転車で神代植物公園植物多様性センターに出かけました。ツリガネニンジン、ハマゴウ、カワラサイコ、カワラナデシコの花が咲いていました。
 ツリガネニンジン ツリガネニンジン
 ハマゴウ ハマゴウ
 カワラサイコ カワラサイコ
 カワラナデシコ カワラナデシコ
帰りにホオズキ祭りが行われている深大寺の前を通り、水生園を見てきました。ミゾハギ、ハスの花が咲いていました。
 深大寺ホオズキ祭り 深大寺ホオズキ祭り
 ミソハギ ミソハギ
 ハス ハス |
|
|
|
| 2016年7月17日(日) |
| ヤマユリ |
野川公園自然観察園で、ヤマユリを見ました。日本原産のユリ。大型(花の直径20cm以上)の豪華なユリ。花は、香りも強い。珍しく写生をしている人がいた。

|
|
|
|
| 2016年7月17日(日) |
| オニユリ |
都道天文台通りにオニユリがよう咲いていました。よく見るとムカゴがついていました。
 オニユリ オニユリ
 ムカゴ ムカゴ |
|
|
|
| 2016年7月16日(土) |
| 野川の注ぐ湧水量の測定(7月) |
今朝、野川に注ぐ湧水量の7月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。5月まで湧水量は、昨年の10月をピークに、ずっと減少していましたが、梅雨に入って、6月の湧水量も若干増加の気配が見えたかに思いましたが、7月の湧水量は、一昨日かなり雨が降ったのも係わらず、横ばいでした。
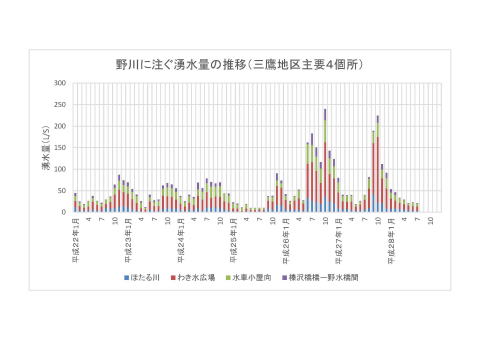 湧水量の推移 湧水量の推移
 湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間以上、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川4.0 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場9.4L/秒、③飛橋上流水車小屋向い6.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間1.2 L/秒でした。 |
|
|
|
| 2016年7月15日(金) |
| 雨後の野川のカルガモ一家 |
6月30日に初めて見た野川のカルガモ一家(雛1羽)を、雨後の野川で、久しぶりに見かけました。昨夜の雨では、野川は、高水敷まで水位が上がったらしく、高水敷の野草はみな下流側に倒れていました。カルガモ一家は、水位が下がった中州で休んでいたが、橋の上から見ていた私の姿に気がつき、下流の方に移動をしていきました。雛は少しは大きくなっていましたが、母親はつききりで、その1羽の雛を見守っていました。




動画は、ここです。 https://youtu.be/lArt73MJJ4w
|
|
|
|
| 2016年7月14日(木) |
| ミクリの花 |
今日、流量測定で長靴をはいて野川にはいって、やっと見つけたミクリの花。花期は6月から8月ですが、花が少ない。
ミクリは、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧に分類されている、多年生の抽水植物で、地下茎を伸ばして株を増やします。
 ミクリ ミクリ
 ミクリの花(雌頭花) ミクリの花(雌頭花)
 ミクリの花(雄頭花) ミクリの花(雄頭花)
|
|
|
|
| 2016年7月14日(木) |
| 野川の流量測定(7月) |
今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。すでに梅雨に入ったが、三鷹では余り多くの雨が降らないので、流量は、まだそれほど変化はない。
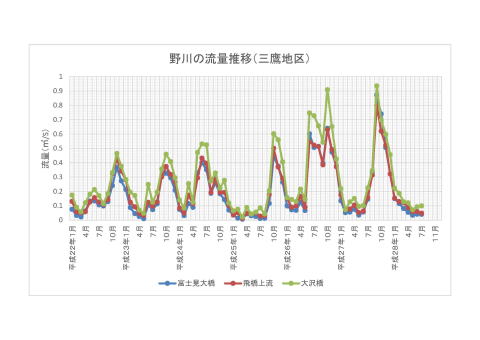 野川の流量推移 野川の流量推移
 大沢橋下流での測定の様子 大沢橋下流での測定の様子
|
|
|
|
| 2016年7月13日(水) |
| 今日の三鷹市市民緑化推進委員会 |
第8期三鷹市市民緑化推進委員会委員の任期2年は、来月8月末までです。今日今期(第8期)の最後の緑化推進委員会が開催された。主な議題は
(1)ガーデニングフエスタ2016プレイベント「花のまち交流会」の実施報告について
(2)ガーデニングフエスタ2016について
①応募状況について
②実施概要について
であった。
6月11日に開催されたプレイベントの来場者は93名、スタッフ(緑化推進委員、市職員、創造協会職員、花壇ボランティア)は38名であった。講師の山田香織さんの講演と公開講座ともわかりやすく、好評であった。
ガーデニングフエスタの写真の応募は、わたしの庭部門88件、私の緑のお気に入りスポット部門48件で、合計136件あった。昨年よりも1件多い応募でした。
ガーデニングフエスタは、9月24日(土)市役所中庭で開催される。応募者写真の展示、交流コーナー、花緑名前あてクイズ、体験・展示コーナー、模擬店、ガーデニング講座、ボランティアイベントゾーン、風船配布などが計画されている。詳しい内容は、9月第1週の三鷹市市報に掲載されるので見てください。
最後の委員会であったので、最後に各委員が一言発言する機会が作られた。私は、①楽しく委員としての活動が出来て良かったこと、②植物だけではなく、植物、生きもの、水を含めた「グリーンインフラ」としてとらえ、対処することの必要なこと、③個人としては、在来植物(フジバカマ、カワラナデシコ)の保全に取り組んでいくことをお話した。 |
|
|
|
| 2016年7月13日(水) |
| カワラナデシコの花 |
7月1日最初の花1輪が咲いてから、少しずつ増えてきた自宅庭のカワラナデシコの花は、今日の夕方には18輪となった。
 自宅庭のカワラナデシコ 自宅庭のカワラナデシコ
三鷹市星と森と絵本の家庭のカワラナデシコも9輪が咲いています。
 星と森と絵本の家のカワラナデシコ 星と森と絵本の家のカワラナデシコ |
|
|
|
| 2016年7月12日(火) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
今朝、国分寺市にある企業の研究所庭園のフジバカマの世話に行ってきました。 フジバカマの草丈はすでに平均110cmにもなっていました。フジバカマ付近の雑草の除草をしました。
 フジバカマ フジバカマ
大池には、コブハクチョウが、ゆったり浮かんでいました。私の気配に気がついて、池の中央から私の方に近づいてきました。そろそろ餌がもらえる時刻なのでしょうか?
 大池 大池
 コブハクチョウ コブハクチョウ
動画は、 https://youtu.be/rbMDdxopBIg です。 |
|
|
|
| 2016年7月11日(月) |
| 小学生による野川の通信簿 |
今日、平成28年度河川愛護月間行事として第14回小学生による「野川の通信簿」が、野川の小金井新橋付近で行われました。主催は野川流域連絡会で、小金井市南小学校(6年生約70名)と、スタッフ約35名(野川流域連絡会委員、東京都北多摩南部建設事務所職員、防災ボランティア他)が参加した。私も、スタッフの1名として、小学生グループの誘導を行った。
小学生は、4班わかれ、野川の①水質、②水生生物、③鳥・昆虫、④植物の4項目を、インストラクターの指導で、観察した。 教室に戻ってから、各自が野川の通信簿を作成する。
今日の野川の水の透明度は、流量も少ない時期なので40cmほどであった。採取した水中生物は、ギンブナ、オイカワ、モツゴ、タモロコ、アメリカザリガニ、カワニナ、ミナミヌマエビなどであった。植物は、110種ほどが、採取された。その内外来種は29種でした。残したい植物のカントウヨメナ、セリ、タブカンゾウ、カラスビシャクなども含まれていた。暑い時期なので、鳥や昆虫は少なかった。
この行事は、毎年1回実施されており、今年が14回目で、私も10年ほど前から、参加しています。
 水生生物調査 水生生物調査
 植物調査 植物調査 |
|
|
|
| 2016年7月10日(日) |
| カイツブリの巣 |
昨日昼、吉祥寺のレストランで会合があり、井の頭公園の七井橋を通った。橋の下流側には、水草が大変目立った。また、ボート池の橋からよく見えるところで、カイツブリが巣を作っていた。その巣の材料には、細い水草が、沢山使われていて、これまで見てきたカイツブリの巣とは、感じが違っていて、きれいでした。現在抱卵中のようで、「かいぼり」後の井の頭池で、カイツブリは、子育てに大変忙しそうに見えました。
 カイツブリの巣 カイツブリの巣
 カイツブリの巣 カイツブリの巣
 水草 水草 |
|
|
|
| 2016年7月8日(金) |
| 自生種カワラナデシコの花 |
自宅の庭では、今、カワラナデシコが8輪咲いている。花の一部は1週間ほど前に咲き、すでに花の盛りが過ぎている。つぼみは沢山あるので、今月下旬が楽しみです。
 自宅庭のカワランデシコ 自宅庭のカワランデシコ
一昨日(7/7)見た神代植物公園自然観察園では、カワランデシコの花がすでに沢山30輪以上)咲いていた。
 植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ
 植物多様性センターのカワラナデシコ 植物多様性センターのカワラナデシコ
今日見た回ったところでは、大沢コミセンの花壇ではカワラナデシコが3輪咲いていた。また、国立天文台構内の三鷹市星と森と絵本の家の花壇では、開花直前のつぼみが2個あった。明日にでも咲きそうでした。羽沢小学校の花壇のカワラナデシコは、小さなつぼみはあるが、開花までには10日ほどかかりそうに見えた。
 大沢コミセン花壇のカワラナデシコ 大沢コミセン花壇のカワラナデシコ
 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ(開花直前) 三鷹市星と森と絵本の家のカワラナデシコ(開花直前)
これらは、いずれも同じ時期に多摩川の河川敷で、種が採取され、その種から育てられたカワラナデシコです。
|
|
|
|
| 2016年7月6日(水) |
| 不在者投票 |
今日、参議院議員選挙の不在者投票を、三鷹市役所でしてきました。帰りに、市役所の地下の食堂で、1杯100円のセルフサービスのコーヒをー杯飲んできました。昼食時にはまだ早く、食堂はすいていて、ゆっくりと出来ました。
 100円コーヒー 100円コーヒー
帰りに、神代植物公園正門で、七夕の短冊を書いて、飾ってきました。明日は、七夕です。
 七夕の短冊 七夕の短冊
 七夕飾り 七夕飾り |
|
|
|
| 2016年7月6日(水) |
| キアシナガバチの巣 |
一昨日、夕方、またまたキアシナガバチが巣を作り始めていました。今度は、前回の場所より1mほどしか離れていない場所(雨戸の上です)。今度も、防虫剤を使わないで、移動をしていただくために、何とか巣を取り除きました。取り除いた巣は、大きさ3cm程度の、こんなものでした。
 キアシナガバチの巣作り キアシナガバチの巣作り
 キアシナガバチの巣作り キアシナガバチの巣作り
 キアシナガバチの巣 キアシナガバチの巣
動画は https://youtu.be/4kmtA2Az6I8 です。 |
|
|
|
| 2016年7月5日(火) |
| アカンサス |
神代植物公園で、アカンサスの花をみました。アカンサスはキツネノマゴ科の多年草で、地中海沿岸原産です。ギリシャの国花だそうです。日本には大正時代に渡来しました。草丈は、人の背丈以上にもなります。開花時期は、6月と7月。古代ギリシャ建築に使われた、コリント様式の柱の頭の部分は、このアカンサスが題材となっているそうです。
 アカンサス アカンサス
 アカンサス アカンサス |
|
|
|
| 2016年7月5日(火) |
| バラの花 |
神代植物公園バラ園では、バラの見頃がつづいています。名前にひかれて花の写真を撮ってみました。
 モナリザ モナリザ
 エレガント レディ エレガント レディ
 ブルームーン ブルームーン
 ダブルディライト ダブルディライト |
|
|
|
| 2016年7月4日(月) |
| クチナシの花 |
昨日、神代植物公園で、八重咲きのクチナシの白い花がさいていました。とても良い香りです。
実の口が開かないところから ”口無し”の名になったそうです。
 クチナシ クチナシ |
|
|
|
| 2016年7月4日(月) |
| カライトソウ |
バラ科の植物。日本固有種。主に高山や亜高山の草原に自生します。いわゆる山野草の仲間ということになります。昨日、神代植物公園でみました。夏から秋にかけて、動物のしっぽのような形のピンクの花が咲きます。花は目立つ花びらはもっていませんが、雄しべが紅紫色で1cmほどの長さがあります。カライトソウの名前はこの雄しべを唐糸(絹)に見立てたもののようです。
 カライトソウ カライトソウ |
|
|
|
| 2016年7月3日(日) |
| 神代植物公園にて |
神代植物公園の正門を入ったところで、ガガブタの水槽とアサザの水槽がおいてあった。いずれも貴重なミツガシワ科アザミ属の多年草で、水草です。池では、熱帯性スイレンが沢山咲いていた。ハスは、一部咲いていたが、まだつぼみが多かった。
 ガガブタ ガガブタ
 アサザ アサザ
 熱帯性スイレン 熱帯性スイレン
|
|
|
|
| 2016年7月2日(土) |
| ムクゲ(木槿) |
都道天文台通りの家で、今年もムクゲ(木槿)が咲きはじめた。
開花時期は、 これから、10月中旬ごろまでです。中国原産。平安時代に渡来。
韓国では、国花になっている。
 ムクゲ ムクゲ
 ムクゲ ムクゲ |
|
|
|
| 2016年7月1日(金) |
| 庭のカワラナデシコ1輪開花 |
自宅の庭のカワラナデシコは、昨日夕方から1輪のつぼみがほころび、今朝は、しっかり咲いていた。例年より少し早い。でも後続は、しばらく後になりそうだ。

記録をみると、
2015年は、7月12日
2014年は、7月8日
2013年は、7月18日
2012年は、7月27日
に1輪開花しました。
|
|
|
|
| 2016年6月30日(木) |
| カルガモ雛1羽 |
昨日、雨後の野川で、はじめてカルガモ雛1羽の家族を見かけた。同じところに今朝もいた。事情はよく分からないが、母親は、1羽の雛を大事そうに見張っている。近くに別のカルガモ姿もある。父親だろうか?
 カルガモ雛 カルガモ雛
 カルガモ雛 カルガモ雛
 カルガモ雛 カルガモ雛 |
|
|
|
| 2016年6月29日(水) |
| ミソハギ(禊萩) |
野川公園自然観察園で、ミソハギが咲いていた。旧暦のお盆(7月15日)の頃に咲き、ミソハギの枝を水に浸して、仏前の供物に禊ぎ(みそぎ)をしたそうだ。
 ミソハギ ミソハギ
 ミソハギ ミソハギ |
|
|
|
| 2016年6月29日(水) |
| ネムノキ(合歓木) |
野川公園のネムノキ(合歓木)の花が咲き始めました。繊細で美しい花です。長く伸びた糸状のものはおしべです。花弁が発達せず、おしべが花を構成している。ネムノキの葉は、夜閉じる。
 ネムノキ ネムノキ
 ネムノキ ネムノキ |
|
|
|
| 2016年6月28日(火) |
| 「ネジ」をまかないネジバナ |
玄関に置かれた植木鉢からネジバナが4本出てきた。その内、1本は、なぜかネジを巻いていない。
尚、ネジバナは、たくさんの小さな花が「ネジ」のように螺旋を描いて付いているために、この名前がついた野生ランです。でも、「ネジ」をまかないネジバナもあるのですね。
 ネジバナ ネジバナ |
|
|
|
| 2016年6月28日(火) |
| 白色のキキョウ |
庭のキキョウが、咲き始めました。これは紫色ではなく、白色の花をつけています。
 キキョウ キキョウ
 キキョウ キキョウ |
|
|
|
| 2016年6月27日(月) |
| キアシナガバチの巣 |
先日、庭の植木の中に巣を作っていたアシナガハシですが、1週間後今度は、庭のパーゴラについている照明器具に巣を作り始めました。昼ごろ庭に出ようとして数羽のハチが飛び出してきてびっくりしました。遠くから見ると、巣を作り始めていました。
 キアシナガバチの巣 キアシナガバチの巣
おっかなびっくりで、巣をたたき落としましたが、その後もハチは戻ってきます。市役所に相談して、写真よりキアシナガバチであることが分かりました。また『これらの肉食蜂は幼虫にほかの昆虫を狩って与えるので、ガーデニングをするには必要な益虫です。葉を食い荒らす青虫などを捕ってくれます。巣に人が触れる場所でなければ駆除の必要はないと思います。ハチも暮らしやすい場所だから巣を作っているのです。』との助言を頂き、防虫剤で駆除するというよりは、どこかに引っ越してもらうことにしました。防備を固めて、巣に近づき、巣があった照明装置を薄いビニール袋で覆い隠してしまいました。様子を見ていますが、これで大丈夫なようです。
 対策として照明器具を覆う 対策として照明器具を覆う |
|
|
|
| 2016年6月26日(日) |
| キョウチクトウ(夾竹桃) |
キョウチクトウ(夾竹桃)の花が咲き始めました。見かけたのは、白色一重咲きの花です。よく見かけるのはピンク色で八重のものです。原産弛はインドで、日本には江戸時代に中国経由で渡来したようです。有毒植物で、大気汚染に強いので、公園樹などとして用いられている。夏の間咲き、サルスベリ(百日紅)と同じ時期に花が見られる。
 キョウチクトウ キョウチクトウ |
|
|
|
| 2016年6月26日(日) |
| サルスベリ(百日紅) |
都道武藏境通りの街路樹サルスベリ(百日紅)が咲き始めました。咲いたのは真っ白い花です。百日紅の名前のように、長い夏の間ずっと咲いてくれる、うれしい花です。
 サルスベリ サルスベリ
 サルスベリ サルスベリ |
|
|
|
| 2016年6月25日(土) |
| 植物多様性センター |
昼前、雨がやんできたので、神代植物公園植物多様性センターに出かけました。トモエソウ、カワラサイコ、チダケサシ、キキョウ、ハマナデシコ、カワラナデシコ、スカシユリ、ヤマラン、ヒメオオギズイセンなどが咲いていました。
 トモエソウ トモエソウ
 カワラナデシコ カワラナデシコ
 カワラサイコ カワラサイコ
 チダケサシ チダケサシ
 キキョウ キキョウ
 ハマナデシコ ハマナデシコ
 スカシユリ スカシユリ
 マヤラン マヤラン
 ヒメオウギズイセン ヒメオウギズイセン |
|
|
|
| 2016年6月24日(金) |
| 井の頭池で、絶滅危惧種の水草が復活! |
|
|
|
| 2016年6月23日(木) |
| 腎臓内科の定期診察 |
今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。午前中に血液を採取して、午後の医師の診断時には、その結果に基づいて判断を聞かせていただける。今日は、懸案のクレアチニン値が、また4ヶ月前の値近くに戻り、一安心でした。
1ヶ月前の診断では、クレアチニン値が悪かったので、食事の内容や、塩分の摂取には引き続き注意をした。 その上、医師の判断で、血圧が下がり過ぎてもいけないので、2年前から飲んでいる血圧を下げる薬(ミカルデス錠)を1ヶ月間やめてみた。それでも、血圧は大きくならず、クレアチニン値は改善した。「血圧を下げる薬をやめて、クレアチニン値が良くなった」ので、万歳です。
このまま、また1ヶ月後に、診察を受けることになった。 |
|
|
|
| 2016年6月22日(水) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
小雨の中、今朝、国分寺市にある企業の研究所庭園のフジバカマの世話に行ってきました。 庭園では、研究所創立60周年(2002年)記念のナツナツツバキの白い花が咲いていました。
 ナツツバキ ナツツバキ
フジバカマの草丈はすでに1mにもなっていました。心配したうどんこ病の気配もなく、順調に成長していました。
 フジバカマ フジバカマ
湧水も少し増え、雨の大池には、ウグイスの鳴き声が響き、コブハクチョウが、ゆったりと身繕いをしていました。
 湧水 湧水
 大池 大池
 コブハクチョウ コブハクチョウ
コブハクチョウの動画は、こちらです。 https://youtu.be/nV3tjJSKnug
庭園に下りる小道の両側には、アジサイが沢山咲いていました。
 アジサイ アジサイ
 アジサイ アジサイ
 アジサイ アジサイ
 アジサイ アジサイ |
|
|
|
| 2016年6月21日(火) |
| 第7期野川流域連絡会全体会 |
昨夜、調布の文化会館たづくりで、第7期野川流域連絡会第3回全体会が開催された。都民委員、団体委員、行政委員など約40名が参加した。
主な議題は、
1)第7期活動報告
水環境分科会、生きもの分科会、なっとく部会、研究部会よりの報告と意見交換
2)話題提供 「低地の河川とにぎわいの創出につぃて」
建設局河川部計画課、野川流域連絡会事務局
3)グループディスカッション
テーマ「野川の河川敷のあり方」を、5班に別れて、話し合いと報告
でした。
野川流域連絡会も、平成12年8月に第1期がスタートし、14年間の活動が継続してきた。私は、第3期平成18年4月から都民委員として、参加してきて、あっという間に10年間がたってしまった。 |
|
|
|
| 2016年6月20日(月) |
| アシナガバチ現る |
今朝、庭の除草をした。この時期、雑草がすぐに伸びるので、忙しい。ついでに、ツツジの剪定をしようと思ったいたら、ハチが数匹現れた。おそるおそる様子をうかがうと、アシナガバチが、数羽かたまってる。状況は私にはよく分からないが、巣を作られると大変なことになる。だが、まだそこまではいっていないようだ。
慎重に装備をかため、まずホースで水をまいて、アシナガバチがいないことを確認した上で、 ツツジを刈り込んだ。これで、当分は大丈夫と思う。
 アシナガバチ アシナガバチ
 アシナガバチ アシナガバチ |
|
|
|
| 2016年6月19日(日) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(6月) |
今朝、野川に注ぐ湧水量の6月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。先月まで湧水量は、昨年の10月をピークに、ずっと減少していましたが、梅雨に入って、湧水量も若干増加の気配が見えてきました。
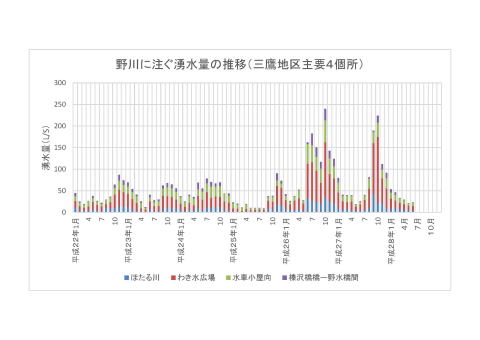 湧水量の推移 湧水量の推移
 湧水広場での測定の様子 湧水広場での測定の様子
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間以上、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今朝の測定結果は、①柳橋ほたる川3.1 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場11.1L/秒、③飛橋上流水車小屋向い7.7L/秒、④野水橋・榛澤橋間0.9 L/秒でした。
|
|
|
|
|
|
| 2016年6月18日(土) |
| ICUキャンパス自然観察教室 |
ICUの生涯学習講座に「ICUキャンパス自然観察教室」全3回があり、今日は、その第1回目が行われた。講師は、多田多恵子さんです。(「身近な草本の実とタネハンドブック」の著者) 2時間ほど、ICUのキャンパス内を歩いて、その自然を観察した。アナグマで高名な上遠岳彦先生も同行してくださって、説明をいただいた。2時間、たっぷりICUキャンパスの自然を楽しみました。
写真は、ミズキの葉でお遊び(ばらばら)、アナグマの巣穴、カラスビシャク、アマチャズル、ネジバナ、オトシブミ、サトキマダラ、ムラサキシジミ、ヒカゲチョウ、ウラナミアカシジミです。
 ミズキでお遊び(ばらばら) ミズキでお遊び(ばらばら)
 アナグマの巣穴 アナグマの巣穴
 カラスビシャク カラスビシャク
 アマチャズル アマチャズル
 ネジバナ ネジバナ
 オトシブミ オトシブミ
 サトキマダラヒカゲ サトキマダラヒカゲ
 ムラサキシジミ ムラサキシジミ
 ヒカゲチョウ ヒカゲチョウ
 ウラナミアカシジミ ウラナミアカシジミ |
|
|
|
| 2016年6月18日(土) |
| アサガオ |
今朝、家のアサガオが2輪咲いた。昨年の種を蒔いて、そだてたものです。昨年は7月15日、一昨年は7月4日に咲いた。今年は、種を蒔いた時期も早かったためか、随分早かった。
 アサガオ アサガオ
|
|
|
|
| 2016年6月17日(金) |
| 読書用LEDスタンド購入 |
本年度は、毎週金曜日の午前、市民大学総合コースで、歴史コース(大英帝国・世界システム論)を受講していて、関連する世界史の本をいろいろと読んでいるが、最近白内障がかない進んできたようで、明るい照明でないと小さい字は読みづらい。
今日の市民大学の帰り道、大型家電販売店にたちより、卓上用のLEDスタンドをチエックしてみた。小型で、スマートなものがあり、気に入った。価格も安かった。試しにスウィッチを入れて、点灯し、本がどの程度楽に読めるか試してみて、OKだった。善は急げと、買って帰った。
これで、読書が楽しくなりそうだ。 |
|
|
|
| 2016年6月16日(木) |
| 野川の流量測定(6月) |
今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。先月(5月)までは、昨年の9月をピークに流量は減少していたが、今月は、梅雨に入ったので、流量は少し増加してきた。
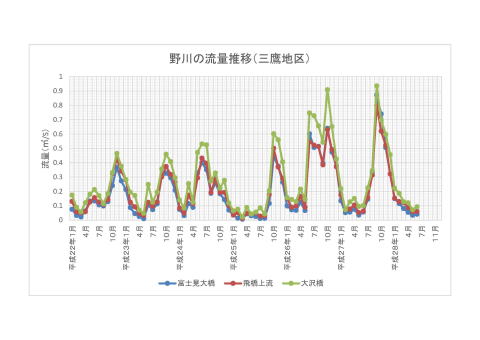 野川の流量推移 野川の流量推移
 大沢橋下流での測定の様子 大沢橋下流での測定の様子 |
|
|
|
| 2016年6月15日(水) |
| ハンゲショウ(半夏生) |
神代植物公園植物多用性センターでは、ハンゲショウ(半夏生)の葉が真っ白でした。今年は少し早いのでしょうか?
 ハンゲショウ ハンゲショウ
暦の上では、今年は、6月21日が夏至です。(夏至は、一年中で一番昼が長い日です。)それから11目が半夏生です。今年は、梅雨の初めは、空梅雨で、平年よりは、貯水池の水も不足しているようで、心配です。 |
|
|
|
| 2016年6月14日(火) |
| 野川流域連絡会生きもの分科会 |
昨夜、調布市の文化会館たづくりで、野川流域連絡会生きもの分科会があり、出席した。主な議題は
1)野川の生きものハンドブック改訂について
2)今期の活動報告について
3)野川・生きもの観察会について
であった。
夏季の野川・生きもの観察会は8月7日(日)午前10時から12時、都立野川公園内野川およびほたる川(小川)で行われる予定。詳しくは、近く野川流域の各市の広報に掲載される予定です。 |
|
|
|
| 2016年6月13日(月) |
| 星と森と絵本の家のフジバカマとカワラナデシコ |
雨の中、国立天文台構内の三鷹市星と森と絵本の家に出かけた。構内には、アジサイが咲いていた。
 アジサイ アジサイ
絵本の家の入り口のところに昨年植えたフジバカマは、今年は良く育っている。草丈も1m近くになっている。うどんこ病の気配もない。守衛さんが良く水をあげているようだ。今年の秋(9月末)の開花が楽しみだ。
 フジバカマ フジバカマ
少し入ったカツラの木の下のカワラナデシコも大分育ってきた。これは最初3年前に植えたものです。その後も補植しています。7月末の開花が楽しみです。
 カワラナデシコ カワラナデシコ |
|
|
|
| 2016年6月12日(日) |
| 野川の風景 |
野川の近くで、クチナシの花が咲いていた。飛橋上流では、風景画を描いている人がいた。高水敷では、モンシロチョウ、ツマグロヒョウモンなどが飛んでいた。アオサギの姿もあった。ところどころに残っている外来植物オオブタクサの草丈が大分伸びてきた。アレチウリも出て生きた。野川でも、そろそろ東京都の第1回目の草刈りが始まるようだ。
 クチナシの花 クチナシの花
 絵を描く人 絵を描く人
 モンシロチョウ モンシロチョウ
 ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン
 アオサギ アオサギ |
|
|
|
| 2016年6月11日(土) |
| 「花のまち交流会」 |
今日(6/11)午後、ガーデニングフエスタ2016プレイベントである「花のまち交流会」が、三鷹市公会堂さん館3階で、午後1時半から行われます。
講師は、盆栽家の山田香織さんで、第1部は山田香織さん講演「手のひらで楽しむガーデニング〜はじめて出会う彩花盆栽の魅力〜」、第2部は公開授業「小さな彩花盆栽をつくります」です。主催は、三鷹市市民緑化推進委員会、三鷹市です。
申訳ありませんが、参加は事前申し込み(定員120名)で、すでにすんでいます。私は、委員の一人として、運営のお手伝いをします。
http://hanakyokai.or.jp/news/767
|
|
|
|
| 2016年6月10日(金) |
| 市民大学総合コース 「ドイツ帝国」「ロシア革命とソヴィエト連邦」 |
先週と今週、市民大学総合コース「混沌とした現在の源は?」では、第3回「ドイツ帝国の興亡」、第4回「ロシア革命とソヴィエトン連邦の光と影」の小林克則さんの講義が終わった。
講義は、生徒30名が5班に別れて、討論・発表の形式で行われたので、予習が必要であった。私も図書館で借りた4冊の本にざっと目を通して、事前に与えられた討論のテーマについて、自分ながらの案を持参して、出席した。討論時間の制約があるので、不充分な点はあったが、最近、使っていなかった脳を、充分使った点では、満足でした。
先生が、最後に江戸時代の儒学者・佐藤一斉の「三学戒」のことば、
『少(わかくし)て学べば、則(すなわち)壮(そう)にして為(な)すこと有り
壮にして学べば、則ち老いて衰えず
老いて学べば、則ち死して朽ちず』
を紹介し、今回は『楽しく講義をさせていただきました』との謙虚な態度には、感じるところがあった。 |
|
|
|
|
|
| 2016年6月7日(火) |
| 梅雨時の庭 |
今日は、小雨が降っている。梅雨に入って、恵みの雨だ。雨の庭では、アジサイ、キンシバイ、ムラサキツユクサが咲いています。
 アジサイ アジサイ
 キンシバイ キンシバイ
 ムラサキツユクサ ムラサキツユクサ
仕方なく、午前中、傘を持って、バスに乗り、調布駅前まで買い物に出かけてきました。午後は、三鷹創造協会で、緑のボランテァイの安全講習会があります。
|
|
|
|
| 2016年6月6日(月) |
| 大沢の里の田圃の田植え |
三鷹市の大沢の里には、今でも、地域住民「ホタルの里三鷹村」の村民により田圃が保全されていて、梅雨時になると、近所の小学生・中学生も手伝って、村民総出で田植えが行われる。今年は、まだ本格的な梅雨の雨が降ってないが、国分寺崖線から湧出る湧水の水を利用して、田圃に引いている。どうもこの6月4日(土)と5日(日)に田植えはおこなわれたようで、今朝、通りかかるとすでに田植えはすっんでていた。田植え後の田圃には、早速カルガモがやってきた。ツバメも飛び、シオカラトンボの姿もあった。
 ほたるの里三鷹村の田圃 ほたるの里三鷹村の田圃
 田植えが終わった田圃 田植えが終わった田圃
 田圃にカルガモ 田圃にカルガモ |
|
|
|
| 2016年6月6日(月) |
| 新宿柿傳で会食 |
昨日は、新宿東口にある京懐石の「新宿柿傳」で、家族で、京懐石を楽しみました。最後に、「くずきり」までいただき、大満足でした。
「京都柿傳」というお店が京都の上京区西洞院丸太町上がるにあります。京都では、茶席などに出向いて調理する出張専門の料理店なので、店自体に客人を迎える座敷は設けていません。その流れをくむ、東京の「新宿柿傳」では、甲州街道の安与ビルの8階で懐石料理がいただけます。
尚、9階には茶室があり、7階のホールでは、大人数の宴席をお願いできる。 |
|
|
|
| 2016年6月3日(金) |
| 野川の自生種フジバカマの保護 |
フジバカマは、秋の七草の一つですが、現在は環境省のレッドリストでは、準絶滅危惧種に位置づけられている貴重な多年生の在来植物です。
5年前(平成23年)の秋に野川の水辺の法面にフジバカマが自生していることが分かり、北多摩南部建設事務所と相談して、翌年からフジバカマ付近だけを草刈りをしないようにして頂いたところ、秋には花が咲き、種も採取することができました。フジバカマを好む蝶アサギマダラもここに来てくれました。このゾーンで、フジバカマを保全するために、その後も、引き続き都の草刈りを除外して頂いています。その代わり市民が草刈りをしております。フジバカマ・ゾーンの面積は、約120㎡(幅約4m、長さ約30m)です。フジバカマは、野川が降雨で増水しても、冠水しない位置に生育しています。秋には、草丈は、高いもので170cm程度になります。花期は、9月下旬から10月下旬です。
今年も草刈りを除外していただくために、今日の午後、現場で北多摩南部建設事務所と草刈り業者と私の3者で、ゾーン4隅を確認して、杭をたてました。後でロープを張ってくれることになっています。
野川で採取したフジバカマの種を蒔いて、毎年苗を育てて、付近の公園などに苗を提供しています。平成25年は、大沢コミセン7株、三鷹市星と森と絵本の家(国立天文台構内)6株、平成26年は、日立中研究所の庭園45株、野川公園30株、大沢コミセン10株、平成27年は、三鷹市星と森と絵本の家30株、羽沢小学校30株、神代植物公園植物多様性センター30株などの提供をしております。今年(平成28年)も大沢コミセンに10株を提供しました。
 現場でくい打ち 現場でくい打ち |
|
|
|
| 2016年6月2日(木) |
| 久しぶりの予習 |
明日、三鷹市の市民大学総合コース「混沌とした現在の源は!?」の第3回目の講義がある。テーマは、「ドイツ帝国の興亡 ~統一からブエルサイユ体制まで~ 」です。講師から、「テーマを6個示され、プリントを読んで考えておいてください。斑をつくって、討論していただきます」と間接的にいわれている。事前にいただいたレジメを読んでも、簡単すぎてピンとこない。仕方なく、中公新書の安部謹也著「物語ドイツの歴史」を入手して、読むことにした。本当は、わかりやすい講義をしていただき、その上で質問の時間をとっていただくのが、これまでのやり方であり、我々高齢者には、望ましいやり方と思っています。
今日は、ICUの学食を使わせていただいて、3時間ほど読んできた。ここだと、1杯100円のコーヒを飲みながら、落ち着いて読書に没頭できる。
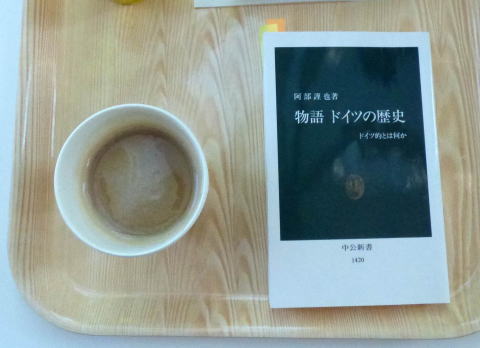
|
|
|
|
| 2016年6月1日(水) |
| 庭園のフジバカマ |
今日は、午前中、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。
フジバカマは、植えてから3年目で、今年も順調に成長していて、草丈は平均で85cmになっていた。今日もフジバカマのゾーンの除草を行った。茂り過ぎたように見えるところは、フジバカマを少し間引いて、風通しをよくしておいた。
池の近くには、セイタカアワダチソウ(外来生物法で要注意外来生物に指定されている侵略的外来植物です)が群生しているゾーンがあり、気になっていたが、前回の訪問時に除草し、今回もまた除草をした。これで目立たなくなると思っている。
静かな大池には、コブハクチョウ1羽がいて、池の縁を移動していた。庭園では、アジサイが咲いていた。
 フジバカマ フジバカマ
 コブハクチョウ コブハクチョウ
 アジサイ アジサイ |
|
|
|
| 2016年5月31日(火) |
| カイツブリの雛6羽@井の頭公園池 |
井の頭公園のボート池には、今朝、カイツブリの雛が6羽元気にいました。この池も、2度の「かいぼり」が実施され、最近は、水の透明度も良くなり、カイツブリの餌の小魚も多く育っているようで、今年は、6個の卵を産み、5月21日に最初の雛が孵り、その後だんだんと増えて、5月28日には6羽目が孵った。その後も、天敵が狙っている中、親鳥たちの必死の育児で、今日も6羽が元気でした。このまま無事に育つことを祈るばかりです。



動画は https://youtu.be/XEyr0v5mBgQ です。 |
|
|
|
| 2016年5月30日(月) |
| フジバカマの挿し芽 |
フジバカマの苗を増やすためにこれまでは種をセルポットに蒔いて、育てていいました。今年は、始めて、挿し芽もためしてみることにしました。
今月初め(5月3日)に、15cmのポットに、3個の挿し芽をしてみた。フジバカマの茎を、先から15cmほどの長さを切って、下の方の葉だけをおとしただけで、土に差し込んで、水をたっぷり与えた、その後の毎日のように水を与えた。それでも、1ヵ月ほどたってみると、3個とも、新しい芽生えがあった。植物の生命力の力には、驚きです。1個は茎の先端から、1個は茎の途中から、1個は土の中から、そっれぞれ新しい芽生えがあった。無事発根したものと思われる。
 フジバカマの挿し芽 (5/3) フジバカマの挿し芽 (5/3)
 フジバカマの挿し芽 (5/3) フジバカマの挿し芽 (5/3)
 フジバカマの挿し芽 (5/3) フジバカマの挿し芽 (5/3)
昨日は、新たに5個の挿し芽を試してみることにした。今度は、発根しやすいように、①30分ほど茎をメネデールを溶かした水につけて、充分水揚げをしておき、②土に差し込む前に、ルートンをつけて、発芽しやすい状態にしておいた。1ヶ月後、どうなっているか、楽しみです。
 フジバカマの挿し芽(5/29) フジバカマの挿し芽(5/29) |
|
|
|
| 2016年5月29日(日) |
| カラタチの実 |
今日、国立天文台構内でカラタチの青い(緑色)実を見た。直径3cmほどの球形の緑色の実である。春には白い花が咲き、秋にはこの実は黄色くなる。カラタチには鋭い刺があり、外からの進入を防げるので、昔は生け垣によく使われたそうであるが、現在ではまり見かけない。
 カラタチの実 カラタチの実
 カラタチの実 カラタチの実
 カラタチの花 (2014年4月17日撮影) カラタチの花 (2014年4月17日撮影)
 カラタチの実 (2015年9月3日撮影) カラタチの実 (2015年9月3日撮影)
よく知られている北原白秋作詞、山田耕作作曲の「からたちの花」には、
からたちの花が咲いたよ。
白い白い花が咲いたよ。
からたちのとげはいたいよ。
青い青い針のとげだよ。
からたちも秋はみのるよ。
まろいまろい金のたまだよ。
からたちのそばで泣いたよ。
みんなみんなやさしかつたよ。
と歌われている.。 |
|
|
|
| 2016年5月29日(日) |
| ニオイウツギ(匂い空木) |
神代植物公園植物多様性センターでは、ニオイウツギが咲いていました。スイカズラ科の落葉小高木で、伊豆七島の固有種です。ハコネウツギの変種ともいわれています。花は、香りがあり、咲き始めは純白で、徐々に淡紫色に変わっていくそうで、白と淡紫色の花が混ざって咲いていました。


|
|
|
|
| 2016年5月28日(土) |
| 今日の野川 |
野川公園内の野川桜橋付近では、子どもたちが、沢山、野川に入っていた。湧水広場では、ヤマボウシの白い花が目立っていた。大沢の里の田圃には、水が張られていた。もうすぐ田植えのようです。
 野川の人々 野川の人々
 ヤマボウシ ヤマボウシ
少し下流の野水橋付近で、少年がウシガエルを捕まえてうれしそうでした。お願いして、橋の上から、ウシガエルの写真を撮らせていただいた。
 ウシガエル ウシガエル
大沢コミセンでは、今日と明日、コミセンまつりが開催されていて、沢山の自転車が臨時駐輪場に置かれていた。私も自転車も置かせていただいて、コミセン内を一巡した。今年も環境部が、①大気汚染測定結果と②ナガミヒナゲシについての展示をしていた。野川の水は、今は少なくなっているが、もうすぐ梅雨がくるのでまた増えることを期待したい。
|
|
|
|
| 2016年5月26日(木) |
| 腎臓内科の定期診断 |
今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。午前中に血液を採取して、午後の医師の診断時には、その結果に基づいて判断を聞かせていただける。今日は、ヘモグロビンA1Cが前回より良くなったが、クレアチニン値が、今までになく悪化した。前回、約3ヶ月前の定期診断では、両方とも少し悪かったので、食事の内容を見直して、塩分の摂取には特に注意をしていて、毎日自宅で測定する血圧の推移は良好で、基準内に収まり、低すぎるほどであったので、今回のクレアチニン値の悪化は意外だった。
医師の判断は、血圧が下がり過ぎてもといけないので、2年前から飲んでいる血圧を下げる薬はやめて、1ヶ月後に、再度、様子を見ることになった。「過ぎたるは及ばざるがごとし。」人間の体もなかなか難しいシステムです。①血圧を下げる薬をやめて、クレアチニン値が良くなれば、万歳ですが、1ヶ月後が、勝負です。
尚、現在は、②コレステロールの薬と③糖尿病の薬は続けて飲んでいます。これもやめられれば、万々歳ですが、なかなか難しそう。 |
|
|
|
| 2016年5月24日(火) |
| カイツブリの雛 |
今日は、久しぶりに神田川を久我山から井の頭公園まで歩いた。井の頭公園のボート家では、カイツブリの雛が、3羽ほど孵っていて、あと2個の卵を抱卵中でした。たしかカイツブリは、毎日1個づつ卵を産むので、雛は一度ではなく、少しづつ孵って行く。抱卵は、雌と雄が交代して行う。年に1-3回、1回に4-6個の卵を産み、抱卵期間は20-25日程度だそうだ。
今日は、私が現場に到着して直後に、抱卵の交代をしたようだ。雛は、生まれてしばらくは、親の羽根の中に隠れていて、時々出てくる。私は、雛を3羽、卵は2個を確認できたが、じっと観察していた人に聞くと4羽の雛がいるとのことであった。
人は、近づけないところですが、アオサギやカラスが、狙っているようで、無事に育つことを祈るばかりです。


|
|
|
|
| 2016年5月23日(月) |
| ヒルガオ(「昼顔) |
日当りがいい、野川沿いの道端で、ヒルガオが、咲いていました。ヒルガオ科のツル性の多年草。日本、朝鮮半島、中国に分布する。花期は、6月から8月。
 ヒルガオ ヒルガオ
|
|
|
|
| 2016年5月23日(月) |
| アジサイ(紫陽花) |
アジサイの花が咲きはじめた。花期は、梅雨期と重なるそうだ。日本原産。花色は、いろいろあるが、開花から日を経ると共に、変化する。
 アジサイ アジサイ
 アジサイ アジサイ
|
|
|
|
| 2016年5月23日(月) |
| タチアオイ(立葵) |
野川沿いの道で、タチアオイの花が咲いていました。アオイ科の多年草。日本には、古く中国から伝来し、平安時代には「唐葵」と呼ばれ、江戸時代から「立葵」と呼ばれるようになったようだ。原産地は、中国ともトルコ、東ヨーロッパともいわれている。梅雨入りの頃に咲き始め、梅雨明けの頃には花期が終わる。よく見ると葉が太陽の方に向うそうだ。今度確認してみよう。
 タチアオイ タチアオイ |
|
|
|
| 2016年5月23日(月) |
| 神代植物公園大温室 |
神代植物公園では、バラフエスタが開催されているが、リニュウアルオープンの大温室を見学した。中央にラン類、ベゴニア類の展示室が増築され、世界遺産小笠原の植物やサボテンなどの乾燥地の植物の展示室も新設された。今日は、順路通り、熱帯草木室、ラン室、ベゴニア室、熱帯スイレン室、小笠原植物室、乾燥値植物室の順で見学した。
公園では、アジサイが咲きはじめていた。
 ラン科の植物 ラン科の植物
 ラン科の植物 ラン科の植物
 ベゴニア ベゴニア
 ベゴニア ベゴニア
 熱帯スイレン 熱帯スイレン
 熱帯スイレン 熱帯スイレン
 アジサイ アジサイ |
|
|
|
| 2016年5月21日(土) |
| 市民大学「ブリテン帝国と世界システムⅠ」 |
昨日(5/20)から市民大学総合コース「混沌とした現代の源は!?~19から20世紀大英帝国の展開を軸に~」の講義が始まった。講師は青山学院大学文学部教授平田雅博先生です。「ブリテン帝国と世界システム1」と題する講義でした。
事前にいただいたコース趣旨によると「激動する現代。その源は、産業革命以降に確立されていった『世界システム』の中にあると思われます。19世紀から20世紀の世界の動きを、産業革命を成し遂げ、いち早く世界へと展開して行ったブリテン帝国を中心に学びます。それと共に、大国の帝国主義の展開の中で生じて行った様々な問題を掘り起こし、混沌とした現代の『源』にあるものを見つめ、考えてゆきます。」と説明されていた。
今日の講義は、まず、イギリス料理はから始まった。イギリス料理は朝だけ美味しい。それは中国産の茶と黒人奴隷を使って生産したカリブ海の砂糖を18世紀から19世紀の初めにはすでに使える、社会システムが出来ていたことによる。
国別の発展論を批判したアメリカの社会学者ウォーラーステインが唱えた世界史の見方を陸上競技のトラックのオープンコースをイメージするとわかりやすいとのことだった。各国の発展の歴史は、あたかも、他のランナーに影響を受けながら、走っているのだ。
世界システム全体のヘゲモニーを握る国が出現する。歴史上は、17世紀のオランダ、19世紀のイギリス、20世紀のアメリカ合衆国がそれに当る。生産、流通、金融をおさえている国がヘゲモニーを握る。
近代の世界システムは、中心に工業製品を担う「中核」と食料・原料・労働力を担う「周辺」がシステムを構成していて、密接な関係を結んでいた。詳しく見ると中間に「半周辺」があって、エレベータに乗って、周辺から中核へ、逆に中核から周辺に移っていくイメージがわかりやすいそうだ。中核―周辺関係は、不等価交換による経済的余裕の搾取、政治的支配を伴う植民主義があり、この関係は、近代資本主義世界の根幹をなす構造であるため、つねに再生産され、解消されることはない。
このような世界システム分析のメリットと批判について、まずメリットとしては、これまで一国史観で分析されてきたフランス革命や産業革命も再検討されることなどがあげられ、批判点としては、アジア史の対置、近代以前の世界システムの存在、歴史を担う主体の不在の指摘などがある。
後半、大英帝国の歴史を概観した。1540年代の著述家が、イングランドとスコットランドの王国は「グレート・ブリテンの帝国」の名の下に統合されるべきだと、始めて述べた。1763年のパリー条約で、大英帝国は完成を見た。この大英帝国の特徴は、プロテスタンテイズムの帝国、海上支配の帝国、自由と帝国の概念が結合した帝国だった点にあるとのこと。
アメリカ13植民地の喪失後、重心はインドに移っていく。19世紀末にはアフリカへ、1882年にはエジプト、1899年にはスーダンを管理下に置いて、フランスと激しく対立した。第1次大戦後は、ドイツの植民地を吸収し、「太陽没することなき」史上最大の帝国となった。第2次大戦後は、脱植民地の時代に入った。イギリスの海外領土は今日でも、ジブラルタルやカリブ海にその残渣を残して居が、過去のものとなった。
質問の時間約15分あり、5人が質問できた。これか1年間の学習が始まる。先生の「イギリス帝国と世界システム」を購入することにした。 |
|
|
|
| 2016年5月21日(土) |
| ガウラ |
今朝、野川の防護柵付近にガウラの花がさいていました。ガウラは、北アメリカ原産の多年草です。別名は、白蝶草。ピンクががった白い花が、風に揺れて蝶が舞うように見えることから白蝶草と呼ばれるそうで、風情が感じられます。
 ガウラ ガウラ
 ガウラ ガウラ
|
|
|
|
| 2016年5月21日(土) |
| ムクドリの餌 |
今朝、庭でムクドリが、何かをくわえていました。少し大き過ぎるらしく、しばらく格闘していましたが、そのうち、くわえて、どこかへ飛び去りました。写真を拡大して見て、ヤモリのようだったと思っています。
ムクドリは雑食性で、昆虫を好んで食べる野鳥だそうです。
 ムクドリ ムクドリ |
|
|
|
| 2016年5月21日(土) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(5月) |
今日の朝、野川に注ぐ湧水量の5月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、昨年の10月をピークのその後はずっと減少しています。
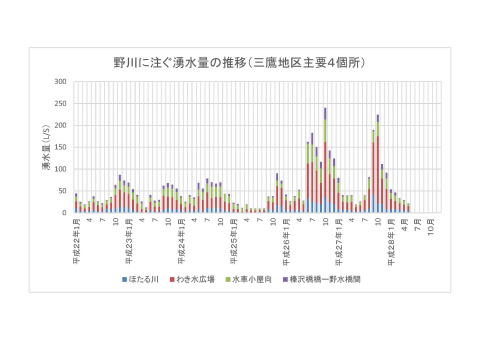 湧水量の推移 湧水量の推移
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今日の測定結果は、①柳橋ほたる川5.1 L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場10.4L/秒、③飛橋上流水車小屋向い4.6L/秒、④野水橋・榛澤橋間1.0 L/秒でした。 |
|
|
|
| 2016年5月20日(金) |
| 昨夜の野川流域連絡会なっとく部会(第5回) |
昨夜、北多摩南部建設事務所の別棟2会会議室で、野川流域連絡会の第5回なっとく部会が開催された。
主な議題は
①なっとく流量調査のまとめについて
②6月20日の全体会での発表資料について
③今後の活動予定について
であった。
①について、なっとく流量調査は、委員が分担して野川流域全体の27地点で、平成18年12月から10年間、ほぼ年4回野川の流量測定を行ってきた。平成22年度からは、流量について測定者の主観的な「なっとく度」を、同時に記録してきた。その記録を整理して、「なっとく度」と流量の一次近似式から、「なっとく流量」を一応決めてみた。それを、流域全体で、上流から下流へと並べた図をつくってみた。これをどう見るかについて、意見を交換した。まとまった結論には至ってないが、更に意見交換を続けて、なっとく流量測定のまとめの報告書を作成し、なっとく流量測定は一応の区切りをつけることに決まった。
尚、③の今後の活動予定については、8月頃次期の委員が決まってから、その次期委員で決めることにした。
|
|
|
|
| 2016年5月20日(金) |
| 昨日の三鷹市市民緑化推進委員会 |
昨日午後、三鷹市公会堂さんさん館で、三鷹市市民緑化推進委員会が行われた。
主な議題及び議事は
①ガーデニングフエスタ2016プレイベント「花のまち交流会」の実施について
平成28年6月11日(土)13時30分から、盆栽家山田香織さんを講師に迎え、
第1部で、講演会「手のひらで楽しむガーデニング ~始めて出会う彩花盆栽の魅力~」
第2部で、公開授業 「小さな盆栽をつくる」
が開催されます。参加申込の締め切りは20で終わったが、まだ若干定員に余裕があるようです。ダメ元で
花と緑のまち三鷹創造協会に問い合わせて見てもありかと思います。
②ガーデニングフエスタ2016について
三鷹市内の「街かどの庭、緑の街なみ」写真の募集は、6月30まで行われている。皆さんの応募をお待ちしています。尚、本体のイベントは、9月24日(土)11時か15時 三鷹市役所中庭で実施される予定です。
③花いっぱい運動について
6月3日に市内46箇所の花壇に、コリウス、へチュ二アの苗が配布され、植えられる予定です。
④平成28年度事業(誕生記念樹の配布)について
7月8日に、市役所本庁舎1階ホールで、キンモクセイ、ゲッケイジュ、サルスベリ、カンツバキ、パキラが、新生児に配布される。(事前申込が必要)
であった。
|
|
|
|
| 2016年5月18日(水) |
| センダン |
センダンが、今、淡紫色の小さな五弁の花を沢山つけている。


|
|
|
|
| 2016年5月18日(水) |
| ヤマボウシ(山法師) |
ミズキ科の落葉樹、花のように見えるヤマボウ白いのは、総苞片で、名前は、これを山法師の頭巾に見立てた。花はその中央部にある。秋につく赤い果実のかたちから、ヤマグワの別名もある。


|
|
|
|
| 2016年5月18日(水) |
| 庭にもツマグロヒョウモンがきています。 |
今日は、快晴で、気持ちのいい日でした。庭にも、チョウがきます。今日は、ツマグロヒョウモンとアゲハでした。ツマグロヒョウモンは、バラ(バレリーナ)の花やフジバカマの葉にとまっていました。アゲハは、サンショウの周りをとんでいました。
 フジバカマにとまるツマグロヒョウモン フジバカマにとまるツマグロヒョウモン
今日も、フジバカマの苗10株が、無事、近くのコミセンの花壇にお嫁入りしました。 |
|
|
|
| 2016年5月17日(火) |
| 昨夜の野川流域連絡会 |
| 昨夜、調布市の文化会館「たどころ」で、野川流域連絡会研究部会の報告会があり、参加した。テーマは進行中の「野川のグリーンインフラ(GI)研究」の中間報告であった。
国土省の資料によると、「グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境の有する多様な機能(生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温抑制等)を活用し、持続可能で魅力ある国土つくりや地域づくりをすすめるもの」「グリーンインフラの取組みを推進することで、地域の魅力・居住環境の向上、生物多様性の保全、防災・減災が可能」「これにより、自然環境の保全・再生と併せて、居住人口や交流人口の増加、土地の価値の向上が図られ、地域の活性化やそれに伴う雇用の増加をに資する」と説明されている。
この説明では、いいことずくめで、なかなかグリーンフラの具体的なイメージが直ぐには浮かんでこないが、先行している欧州やアメリカでの取組みを見ると、欧州では「多様な生態系サービスの享受をするために、デザインされ、管理されている自然環境・半自然環境エリア及びそのほかの環境要素(動植物、景観など)をつなぐ戦略的に考えられたネットワーク」と定義されていて、生態系ネットワークの形成とGIの多目的性に主眼があかれているようだ。アメリカでは、雨水管理に主眼が置かれていて、「水系の保護と暮しやすい地域社会の構築に関する戦略的行動計画」としてまとめられているようだ。日本ではまだ始まったばかりである。
昨夜の次第は
1 挨拶 加藤麻里子(国土交通省国土管理企画室専門調査官)
2 報告
神谷 博(法政大学兼任講師)野川流域のGIにおける公園緑地の役割
江 暁歓(千葉大学博士課程)アメリカにおける水管理の用語の変遷
滝澤恭平(水辺総研)野川流域のGI資産としての水路の評価
土屋一彬(東京大学助教)世田谷区民の『自然との関わりをはかる
佐藤裕太・麥田準希(東京大学修士課程)環境・防災から見た2040年の世田谷区
中田由和(NPO法人SuperMap倶楽部)野川GIのGISベースマップ
3 意見交換
4 閉会
であった。若手の研究者の報告が多く、野川の取組みに新しい風を感じる、いい報告会でした。司会者のまとめでの発言では、次回の報告会では、私が係わっている「野川自生種のフジバカマ」も事例として、小さな話題の一つになりそうな雰囲気でした。
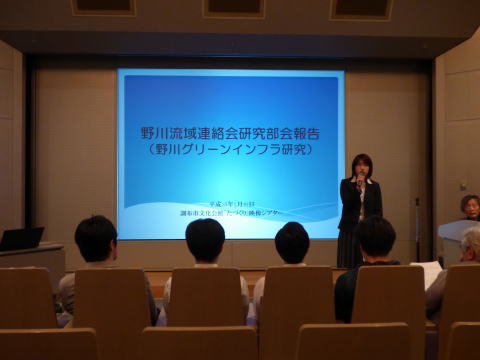 挨拶 挨拶
|
|
|
|
| 2016年5月16日(月) |
| 野川の流量測定(5月) |
今日午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。昨年の9月をピークに流量は減少している。梅雨に入れば雨もあり、多分、今が今年の流量の底でしょう。
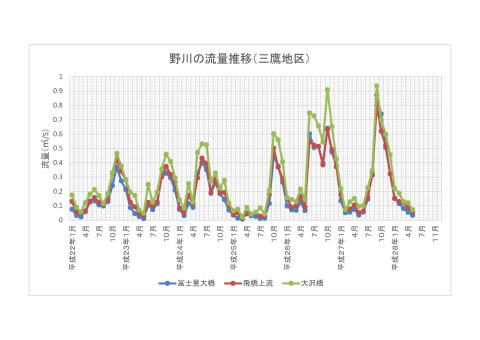 野川の流量推移 野川の流量推移 |
|
|
|
| 2016年5月15日(日) |
| 神代植物公園 |
今日、春のバラフエスタが開催されている神代植物公園は、天候にも恵まれ、沢山の来園者があり、正門前には入場券を購入するための長い行列ができていた。でも内は広くて、そんなに混んではいない。
今、見頃は、バラの他にも、シャクヤクが見頃でした。
 バラ園 バラ園
 バラコンサート バラコンサート
 バラ つるスカイフエース バラ つるスカイフエース
 バラ ゴールデンセプター バラ ゴールデンセプター
 バラ イングリット・バーグマン バラ イングリット・バーグマン
 シャクヤク 桜重 シャクヤク 桜重
 シャクヤク 面影 シャクヤク 面影
 シャクヤク園 シャクヤク園 |
|
|
|
| 2016年5月15日(日) |
| 錦織惜敗 |
朝、3時から、テニスイタリア国際の錦織VSジョコビッチ戦をTVで見た。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160515/k10010521581000.html
第1セットは、出だしの2ゲーム目でジョコビッチがメヂカルタイムアウトをとる。錦織が3ゲームと7ゲームをブレークして第一セットは錦織が6-2でとった。
第2セットは、第8ゲームをブレークされて、4-6で落とし、セットカウントは1-1となった。
第3セットは、錦織は第2ゲームをブレークされたが、第7ゲームでブレークバックした。5-5、12ゲームで錦織ラブゲームでキープし、フアイナルゲームは、タイブレークに入った。錦織痛恨のダブルホルト。続いて狙ったショットはもアウトし、5-6まで行ったが、後一歩で錦織は敗れた。本当に惜しかった。
|
|
|
|
| 2016年5月14日(土) |
| 同期会 |
昨日は、第2の職場の同期会が、市ヶ谷の中華料理店であった。仕事はISOの品質・環境システムの審査であった。約20年前に、その年に、拡大中の審査部門に入構したのは10名でしたが、主に関東地区にすんでいる人7名が集まった。年齢に幅があり、私のように10年以上前に仕事をやめたもの、まだ現役の人もあるが、毎年1度は集まって、近況などをはなしてあっている。とにかく楽しいひとときを過ごせたことはうれしいことです。
|
|
|
|
| 2016年5月13日(金) |
| 市民大学総合コースが開講 |
今日から、平成28年度の三鷹市社会教育会館の市民大学総合コースが開講しました。コースは金曜日3コース、土曜日2コースで、私は、金曜日の「混沌とした現代の源は!?~19から20世紀~大英帝国の展開を軸に」全30回を受講します
詳しくは、 http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/057/057423.html を見てください。
私とこの市民大学総合コースとの係わりは、平成18年に「心豊かに安心してみたかで生きる~生活者の視点からしくみと環境を考える~」でを初めて受講した時からです。メイン講師は、ICUの西尾隆先生でした。平成20年度は、メイン講師農工大の小倉紀雄先生の「身近な水と地球環境~コップ1杯の水から考える~」を受講しました。それ以来、受講出来なかった年度も3回ありましたが、今年で8回目の受講です。
平成19年度と20年度の2回は、企画委員を務めました。市民が講座の内容を自主的に企画し、運営していくことに、大変いい伝統が育っていることを学びました。...
三鷹市では、この社会教育会館主催の市民大学総合コースが、48年間続いています。すごいことです。
「平成28年度市民大学総合コース学習の手引き」によると、
「三鷹市の市民大学総合コースは、開設以来、今年で48年目を迎えますが、当初から『学習の主体は市民にある』という命題を掲げ、市民自らが主体となって、築き上げてきた社会教育会館主催の講座です」、
開設準備にあたっては、市民の学習要望を踏まえた5コースを、公募市民と会館の職員とで、企画委員会を立ち上げ、約7ヶ月をかけ、各コースのテーマーにふさわしい講師や学習課題を検討しながら、カリキュラムを策定しています。」、
「開催後には、各コースの学習生から選出された委員と社会教育会館職員とで運営委員会を組織し、学習生の意見や要望を取りまとめ、一人一人が主体的に学習できるように運営にあたります」
「学びを通して市民としての自治能力を高め、これを地域での生活の場に活かし、コミュニティづくり、まちづくりを図ることを目指しています」と説明されています。
社会教育会館の建物が老朽化したので、新たな場所に移転する計画が現在進行しており、来年度の講座は、新たな場所で開催されます。その際、これまでの市民大学総合コースのよき伝統が、失われることがないよう、
①市民による自主的な企画・運営
②現在の5コースの継続
だけは、継続して行きたいことです。
私の考えですが、三鷹市のこの市民大学総合コースは、市民自らが企画・運営する講座であることを理解していただいた講師の先生方からは、この市民大学総合コースを高く評価していただくと共に、質の高い授業をしていただくことで、大いにご協力を頂いていると、強く感じています。三鷹市が誇れる、この半世紀の実績と伝統がある三鷹市の市民大学総合コースのこのよき伝統は、是非、残して行かなければならないものだと強く感じています。
|
|
|
|
| 2016年5月12日(木) |
| 富士山 |
今日は、富士山がきれいに見えました。

|
|
|
|
| 2016年5月11日(水) |
| エゴノキの花 |
エゴノキは、エゴノキ科の落葉高木。今、野川公園自然観察園で、直径25cmほどの白い花を沢山つけていた。実は、特に、ヤマガラが好む。
 エゴノキの花 エゴノキの花 |
|
|
|
| 2016年5月11日(水) |
| マユミの花 |
マユミはニシキギ科の落葉低木.。今朝、野川公園自然観察園では、淡緑色の4弁のマユミの花が咲いていた。花径は8mm程度の地味な花です。
 マユミの花 マユミの花
 マユミの花 マユミの花
でも秋11月から12月になると、淡紅色の鮮やかな実がなり、熟すと4つに割れ朱色の種子が顔を出す。この実は、メジロやコゲラなどの小型の鳥に好まれています。
 マユミの実 昨年11月6日撮影 マユミの実 昨年11月6日撮影 |
|
|
|
| 2016年5月10日(火) |
| 庭園のフジバカマ |
今日は、午前中、国分寺市にある企業の庭園のフジバカマの世話に出かけてきました。
フジバカマは、3年目で、今年も順調に成長していて、草丈は平均で70cmになっていた。今日もフジバカマのゾーンの除草を行った。近くには、50cmほどの草丈になったセイタカアワダチソウが群生しているゾーンがあり、気になっていたが、今日は、時間もあったので、除草をしておいた。これで目立たなくなると思っている。
静かな大池には、コブハクチョウ1羽がゆったりと浮かんでいた。
動画は、 https://youtu.be/gUlY33LgmWg です。
池の周囲ではキショウブ、ニワゼキショウ、カントウタンポポなどの花が見られた。
 フジバカマ フジバカマ
 コブハクチョウ コブハクチョウ
 キショウブ キショウブ
 ニワゼキショウ ニワゼキショウ
 カントウタンポポ カントウタンポポ
|
|
|
|
| 2016年5月8日(日) |
| ユキノシタ(雪の下) |
庭のカイズカイブキの日影で、ユキノシタ(雪の下)がひっそりと花をつけ始めた。ユキノシタ科ユキノシタ属の常緑の多年草で、雪の下でも緑が鮮やかなことから、この名前が由来するといわれています。葉は民間薬としていろいろ使われていて、生の葉を弱火にあぶり、もんで、腫れ物に貼るとか、もんだ葉っぱの絞り汁を耳につけ中耳炎の薬とするなど使用されたそうです。また、葉は天ぷらにすると美味しいと云われています。私はまだ食べたことがありませんが・・・
 ユキノシタ ユキノシタ
 ユキノシタ ユキノシタ |
|
|
|
| 2016年5月8日(日) |
| 梅の木の手入れ |
朝から、庭の梅の木の手入れをした。葉が茂って花壇の日照が悪いので、剪定の時期ではないが、すっぱりと剪定をした。梅の実もおもったより沢山収穫できた。2時間作業をしたので、少し疲れた。
 収穫した梅の実 収穫した梅の実
|
|
|
|
| 2016年5月7日(土) |
| たまには庭の除草 |
今日は、午前中、カワラナデシコの苗10株を、大沢コミセンまで自転車に積んで、もって行った。今月の活動日に花壇にスペースを確保して、カワラナデシコを植えていただく予定になっている。
その後、これまでにカワラナデシコを植えていただいている羽沢小学校の花壇、星と森と絵本の家の花壇を見に行く。気温が上がってきたので、どうしても雑草が伸びてきていて、少し心配。
午後は、久しぶりに、自宅の庭の雑草の除草を2時間ほど行った。残したい野草に気をつけながら、身長に除草をする。できあがると、さっぱりして、気持ちがいい。 |
|
|
|
| 2016年5月5日(木) |
| オダマキ(苧環) |
独特な形をしているオダマキ(苧環)の花。5枚の萼と筒状の花からなっています。色は白から紫までいろいろある。キンポウゲ科の植物。日本原産のオダマキとヨーロッパなど原産の西洋オダマキがあるそうです。写真のものは、多分日本原産でしょうか。別名は、イトクリソウ(糸繰草)。
 オダマキ@神代植物公園 オダマキ@神代植物公園
 オダマキ@自宅庭 オダマキ@自宅庭 |
|
|
|
| 2016年5月4日(水) |
| 神代植物公園にて |
昨夜の風雨もさり、昼前から晴れ間が出てきた。早速神代植物公園にでかけた。
シャクヤクは雨で、花がよくなかった。芝生広場の近くに、ホオノキ、トチノキ、ベニバナトチノキが咲いてた。バラ園も5月10日から春のバラフエスターが始まるが、大分咲き始めていた。
 ホオノキ ホオノキ
 トチノキ トチノキ
 ベニバナトチノキ ベニバナトチノキ
 バラ ダブルデライト バラ ダブルデライト
 バラ プリンセス・チチブ バラ プリンセス・チチブ
今日は、「緑の日」の祭日のため神代植物公園の入園料は全員無料でした。無料の日は年に2回あり、後秋に一回無料の日があるそうです。工事中の大温室も5月12日にリニューアルオープンするようだ。
 大温室リニューアルオープン 大温室リニューアルオープン
帰りに深大寺のナンジャモンジャを見に行ったが、昨夜の風雨で、すっかり花が落ちてしまっていて、残念でした。
|
|
|
|
| 2016年5月3日(火) |
| NHKテレビ体操 |
1ヶ月ほど前から、毎日朝、NHKテレビ体操を行っている。放送は朝6時25分から10分間で、①第1体操、②第2体操、③みんなの体操が、日ごとに組み合わせを変えて放送される。ポイント解説もある。私は、録画しておいて、時間に間に合わなくても、毎日欠かさずに行えるように努めている。
ウオーキングでは、使わない筋肉を体操で動かすことが、いいようで、40肩も快方に向っているし、何となくいい感じを持っている。続けることが大切なようだ。詳しくは、下記を見てください。
https://pid.nhk.or.jp/event/taisou/taisou.html
|
|
|
|
| 2016年5月3日(火) |
| 野川の国分寺まで歩く |
今日は、体調がいいので、家から野川の飛橋に出て、野川を遡り、国分寺市の鞍尾根橋まで歩き、そこからは野川沿いの道はないので、市道を歩いて国分寺駅まで歩きました。3時間、約16000歩の行程でした。天文台の竹林では、筍がにょきにょきとのびていました。野川は渇水期で、水は少ないが、いろいろな場所で、人々が川の中で、遊んでいました。野川公園の中で、なんじゃもんじゃの木に花がついていました。蝶の姿も見かけました。もうオオブタクサが、芽生えていました。
 人々 人々
 人々 人々
 天文台構内の竹林(七中前) 天文台構内の竹林(七中前)
 ナンジャモンジャ ナンジャモンジャ
 アゲハ アゲハ
 ツマグロヒョウモン ツマグロヒョウモン
 オオブタクサ オオブタクサ |
|
|
|
| 2016年5月2日(月) |
| 野川散歩 |
今日は、野川を三鷹市の大沢橋から、世田谷区の神明橋まで歩きました。園児たちも、水辺の道を歩いていました。 水辺では、ナノハナは、盛りを過ぎ、イネ科の植物(カラスムギなど)が、背丈ほどの草丈になっていました。調布市の細田橋では、佐須用水の水が、豊かに野川に注いでいました。下流では、ハマダイコンの花が咲いていました。野川では、カルガモ、コサギ、コガモ、カワセミの姿をみましたが、鳥の種類は、もう多くはありませんでした。
帰りは小田急線の喜多見駅から電車とバスで帰ってきました。
 水辺を歩く園児たち 水辺を歩く園児たち
 アメリカフウロ アメリカフウロ
 まだいた冬鳥のコガモペアー まだいた冬鳥のコガモペアー
 野川に注ぐ佐須用水@調布市細田橋付近 野川に注ぐ佐須用水@調布市細田橋付近
 ハマダイコンの花 ハマダイコンの花 |
|
|
|
| 2016年5月2日(月) |
| カキツバタ(杜若) |
今、野川でカキツバタの花を見ることが出来ます。野川で、誰か世話をする人がいて、毎年カキツバタが花を咲かせています。
伊勢物語で在原業平が詠んだカキツバタ(杜若)は、5から6月ごろ湿地に紫色の花をつけます。万葉のころから知られた在来種ですが、今や環境省のレッドリストでは、絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。 カキツバタの花弁の弁の元には白ないしは淡黄色のスジ模様があります。似た品種のアヤメには、網目模様があり、識別できます。また、カキツバタは、水辺に生育しますが、アヤメは、乾いた土地で生育します。
今日、野川を三鷹市の大沢橋から、世田谷区の神明橋まで歩き、小田急線の喜多見駅から電車とバスで帰ってきました。今日は17000歩ほど歩きました。
 カキツバタ カキツバタ
|
|
|
|
| 2016年5月1日(日) |
| 自然観察園にて |
野川公園自然観察園では、ハンショウズル、オドリコソウ、ムサシノキスゲ、キンラン、フタリシズカ、クリンソウ、サギゴケ、チョウジソウなどが咲いていた。
 ハンショウズル ハンショウズル
 オドリコソウ オドリコソウ
 ムサシノキスゲ ムサシノキスゲ
 キンラン キンラン
 フタリシズカ フタリシズカ
 クリンソウ クリンソウ
 サギゴケ サギゴケ
 チョウジソウ チョウジソウ |
|
|
|
| 2016年5月1日(日) |
| 今日の野川はとても賑やか |
連休に入り、初めての晴天で、今日の野川は、子連れの家族で賑やかでした。手網をもって、野川で生きものを追いかけている子どもの姿が目立った。野川沿いの道は、日本ウオーキング協会が主催する第21回ウオーキングフエスタ東京ツーデーマーチに参加する人々が、続々と、小金井公園に向けて歩いていた。
 野川公園内の野川 野川公園内の野川
 大沢の里の前の野川 大沢の里の前の野川
|
|
|
|
| 2016年4月30日(土) |
| ジャーマンアイリス |
庭に紫色のジャーマンアイリスの花が咲いています。ヨーロッパ原産の園芸種です。いろいろの色のものがあり、豪華な感じの花です。特徴は花弁のつけ根に「ブラシ状」のものがあることだそうです。名前のアイリスは、ギリシャ語で虹を指す「イリス」に由来するそうです。


|
|
|
|
| 2016年4月29日(金) |
| ドイツスズラン |
自宅庭のドイツスズラン。随分増えてきた。これは、日本原産のスズランではありません。
 ドイツスズラン ドイツスズラン |
|
|
|
| 2016年4月29日(金) |
| アマドコロ(甘野老) |
我が家の庭では、今、アマドコロがよく咲いています。根茎が、トコロ(野老)に似た形状ですが、味は甘いので、アマドコロ(甘野老)と名がついたようです。尚、トコロの根茎は、苦いとのことで、食べられません。
アマドコロに似たものにナルコユリ(鳴子百合)があります。我が家も、昔、ナルコユリと云われて購入したものですが、①アマドコロには茎に角があり、ナルコユリの茎はなめらかである、②アマドコロの花茎は茎に近いところで分岐しており、③ナルコユリの葉の方が細身ということから、最近これはアマドコロと考えるようになりました。
 アマドコロ アマドコロ
 アマドコロ アマドコロ
|
|
|
|
| 2016年4月28日(木) |
| 再挑戦 男の料理筍ご飯 |
今日、筍ご飯に再挑戦しました。前回は簡便な方法でしたが、今回は、事前に筍と油揚げを別々に煮ておいて、その煮汁を用いてご飯を炊き、炊けたご飯に、筍と油揚げを混ぜ込みました。味がよくしみて、美味しく感じました。
 筍ご飯 筍ご飯 |
|
|
|
| 2016年4月28日(木) |
| ホタルカズラ(螢葛) |
ムラサキ科ムラサキ属の多年草。螢を連想させる紫青色の花をつける。花後にランナーを出し、途中で根を出すのつる性の植物。「かずら」とは、つる草の総称です。日本から東アジアに分布。日本では、現在は、絶滅を危惧されている県もあるほど少なくなっている。
 ホタルカズラ ホタルカズラ |
|
|
|
| 2016年4月28日(木) |
| フタリシズカ(二人静) |
日本固有種。 センリョウ科チャラン属の多年草。名前は2本の花穂を能楽「二人静」の静御前とその亡霊の舞姿に例えたもの。但し、花穂は2つが多いが、1個のもの、3から5個のものまである。
 フタリシズカ フタリシズカ |
|
|
|
| 2016年4月28日(木) |
| ユウゲショウ(夕化粧) |
昨日、もう、ユウゲショウの花が咲いているのを見かけました。艶っぽい名前ですが、実際は朝から咲いています。アカバナユウゲショウとも云われます。北アメリか原産の帰化植物で、よく河川敷や道端で群落で咲いているのを見かけます。アカバナ科マツヨイグサ属の多年草。
 ユウゲショウ ユウゲショウ |
|
|
|
| 2016年4月27日(水) |
| コンロンソウとスジグロシロチョウ |
自然観察園で、コンロンソウの花にスジグロシロチョウが止まりました。

|
|
|
|
| 2016年4月27日(水) |
| キンランとギンラン |
今日、近くの公園で、キンランとギンランを見かけました。いずれもラン科キンラン属の多年草ですが、生きた植物の根の『外菌根菌』と、共生しないと生きられない植物だそうで、見られる場所が限られます。ギンランの方が見かけることが少ないようですが、そっと咲いていました。
 キンラン キンラン
 ギンラン ギンラン |
|
|
|
| 2016年4月26日(火) |
| 神代植物公園のツツジとフジ |
ツツジとフジが、今神代植物公園では、見頃でした。他にも、シャクナゲ、ボタン、シャクヤク、ハンカチノキもそうです。
 ツツジ(白琉球) ツツジ(白琉球)
 ツツジ ツツジ
 ツツジ ツツジ
 フジ(黒竜) フジ(黒竜)
 フジ(白花美短) フジ(白花美短)
 フジ(海老茶藤) フジ(海老茶藤)
 ナニワイバラ ナニワイバラ |
|
|
|
| 2016年4月26日(火) |
| 自生種のカワラナデシコの苗 |
今年も自宅で、自生種のカワラナデシコの苗を、種を蒔いて育てているが、その内30株を、今朝、野川公園ボランティアに引き渡して、自然観察園の中に植えていただいた。順調にいけば、8月頃に、花を見るのが楽しみです。
 カワラナデシコの苗 カワラナデシコの苗 |
|
|
|
| 2016年4月25日(月) |
| 都立浅間山公園 |
自転車で、多磨霊園の隣にある都立浅間山(せんげんやま)公園のムサシノキスゲの様子を見にいってきました。少しは咲き始めていましたが、本格的には5月の連休からが見ごろでしょう。キンランは、よく咲いていました。ハンショウズルが咲いていました。帰りは、武蔵野公園、野川公園内の野川沿いを帰ってきました。
 ムサシノキスゲ ムサシノキスゲ
 案内坂 案内坂
 キンラン キンラン |
|
|
|
| 2016年4月24日(日) |
| 自然観察園にて |
午後、野川公園自然観察園に出かけました。雨後の観察園では、キンラン、チョウジソウ、クリンソウ、オドリコソウ、エビネ、ジュウ二ヒトエ、ホタルカグラが咲いていた。
 キンラン キンラン
 チョウジソウ チョウジソウ
 クリンソウ クリンソウ
 オドリコソウ オドリコソウ
 エビネ エビネ
 ジュウ二ヒトエ ジュウ二ヒトエ
 ホタルカグラ ホタルカグラ
|
|
|
|
| 2016年4月24日(日) |
| 男の料理 たけのこご飯 |
ボランティア仲間からいただいた筍を用いて、たけのこごはんを作りました。筍をゆでることも含めて、全部自分で行いました。味はこれから、お楽しみです。
この時期、毎年一度は、たけのこご飯を作っています。
 筍ご飯 筍ご飯
 筍 筍 |
|
|
|
| 2016年4月23日(土) |
| 平成28年度市民大学「混沌とした現在の源は!?」受講決定 |
|
|
|
| 2016年4月22日(金) |
| 都立殿ヶ谷戸庭園 |
午後、国分寺市にある都立殿ヶ谷戸庭園を見学した。今、見頃の花は、フジ、エビネ、キエビネ、スズラン、シランなどでした。庭園には、ししおどし(鹿威し)があり、いい音を響かせていた。
 フジ フジ
 エビネ エビネ
 キエビネ キエビネ
 スズラン スズラン
 シラン シラン
 鹿威し 鹿威し
鹿威しの動画は https://youtu.be/hzPytZx7DrQ で見られます。 |
|
|
|
| 2016年4月22日(金) |
| 庭園のフジバカマの世話 |
今日は、日立中央研究所の庭園のフジバカマの世話に出かけました。いい天気でした。桜の時期は終わり、大池は、静かでした。池にはコブはクチョウが一羽、岸にあがり、休んでいました。3年前に植えたフジバカマは、しっかり根を張ったようで、草丈は50cmにも育っていました。9月の開花が待たれます。
コブハクチョウの動画は https://youtu.be/J5j6wzdPmZE で見られます。
 大池 大池
 フジバカマ フジバカマ
 コブハクチョウ コブハクチョウ |
|
|
|
|
|
| 2016年4月20日(水) |
| 大学のクラス会 |
今夜、神田学士会館で、大学のクラス会(電気工学)を行った。東京付近に住んでいる人たちだけなので、8名の出席である。毎年1度実施しているが、今回が15回目になる。学生時代に一緒だったこと、卒業後も似たような社会環境で生きて来たので、共通項が多く、話が理解しやすい。大変楽しいひとときを過ごすことができたと感じている。
 学士会館 学士会館 |
|
|
|
| 2016年4月19日(火) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(4月) |
今日の午前中、野川に注ぐ湧水量の4月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、昨年の10月をピークに減少しています。
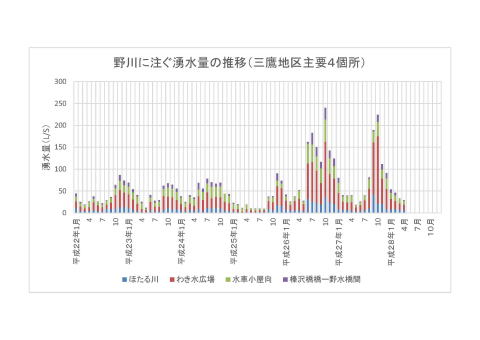 湧水量の推移 湧水量の推移
 湧水広場の湧水での測定の様子 湧水広場の湧水での測定の様子
動画もあります。 https://youtu.be/L_tgOCWGrwE
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今日の測定結果は、①柳橋ほたる川6.5l L/秒、②くぬぎ橋下流湧水広場12.1 L/秒、③飛橋上流水車小屋向い9.6 L/秒、④野水橋・榛澤橋間1.0 L/秒でした。 |
|
|
|
| 2016年4月18日(月) |
| 野川のバン |
今朝、野川でバンを見かけました。朝日を浴びて、のんびりとしていました。
 バン バン
動画は、次でみてください。 https://youtu.be/z6fJGv1Vljk
バンは、ツル目クイナ科の野鳥で、大きさはハト程度。額板が赤く、足と足指は黄色く大きい。足に水かきがないので泳ぎは得意ではなさそうだ。雑食性です。 |
|
|
|
| 2016年4月18日(月) |
| 野川の流量測定(4月) |
今朝は、大変気温が高かった。午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。昨年の9月をピークに流量は減少している。
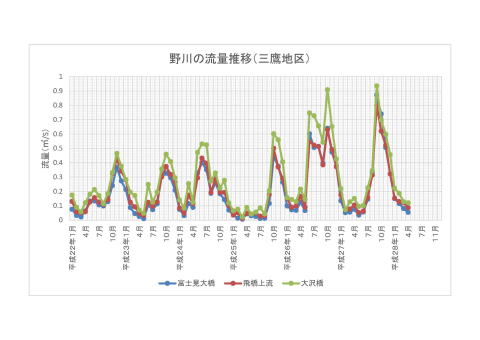 野川の流量推移 野川の流量推移 |
|
|
|
| 2016年4月17日(日) |
| アゲハ |
時折強い風が吹く今朝、庭にアゲハが舞い込んできました。風をよけるように、地面にじっとしていました。アゲハの雌のようです。
 アゲハ アゲハ |
|
|
|
| 2016年4月17日(日) |
| 炊飯器の不調 |
長く使ってきた炊飯器の調子がおかしい。時々保温が切れている。再設定をすると、また機能するということが数回あった。昨日は、いよいよ、全く保温が出来なくなった。でも炊飯はできそうだ。
長く使っていたが、調べてみると製造は2001年の製品でした。ほぼ毎日使っていて、15年間もよく動いてくれたものだと云うのが実感です。有難う。日本の家電製品の品質はすごい!
早速、ネットで調べて、同じ会社の製品を選定し、発注した。2日後には届く予定。 |
|
|
|
| 2016年4月16日(土) |
| シロツメクサとムラサキツメクサ |
野川の高水敷で、シロツメクサとムラサキツメクサが咲いていました。
 シロツメクサ シロツメクサ
 ムラサキツメクサ ムラサキツメクサ |
|
|
|
| 2016年4月16日(土) |
| ベニシジミ |
野川で、ナノハナにベニシジミが止まっていました。
 ベニシジミ ベニシジミ
 ベニシジミ ベニシジミ
|
|
|
|
|
|
| 2016年4月16日(土) |
| クサイチゴ |
国立天文台のフエンス際に、クサイチゴの花が沢山咲いていました。草と名がつきますが木です。
 クサイチゴ クサイチゴ
|
|
|
|
| 2016年4月16日(土) |
| ヤセウツボ |
今日、野川の高水敷でヤセウツボを見かけました。南ヨーロッパ原産で、日本には外来種として定着している。ハマウツボ科の寄生植物で、ヤセウツボは、地下で、他の植物の根に寄生して養分を横取りして育つ。シロツメクサに寄生することが多いようです。
 ヤセウツボ ヤセウツボ
|
|
|
|
| 2016年4月15日(金) |
| イタドリ |
野川では、水辺にイタドリが一斉に出てきた。日本を含むアジア原産の多年生植物。タデ科。繁殖すると困まる植物。別名はスカンポ。茎は中空で、若い茎は柔らかく、皮をむいて山菜として食用にする。酸味があり、あく抜きが必要。若葉をもんでかすり傷などで出血した個所に当てると多少の止血作用があり、痛みを和らげるので、「いたどり(痛取)」の名前のがある。繁殖力が旺盛で、イギリスではイギリスの在来種の植生を脅かす外来種とされている。世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。
 イタドリ イタドリ
 イタドリ イタドリ |
|
|
|
| 2016年4月15日(金) |
| トキワマンサク・アカバナトキワマンサク |
マンサク科の中低木で、原産地は主に中国、インドや日本では、自生地は、限られるようだ。マンサクとは属が異なる別の樹木。白色の花のトキワマンサクと紅紫色のベニバナトキワマンサクがある。ベニバナトキワマンサクの方が見かけることが多いようだ。
 トキワマンサク トキワマンサク
 ベニバナトキワマンサク ベニバナトキワマンサク |
|
|
|
| 2016年4月15日(金) |
| 富士山 |
からっと晴れて、久しぶりに富士山がよく見えました。
 富士山 富士山
|
|
|
|
| 2016年4月14日(木) |
| 日本一周歩こう会 |
毎日のウオーキングのデーターを登録して、記録に残してくれる「バーチャル 日本一周歩こう会」があり、私も登録しています。毎日のウオーキングを楽しく継続するために、バーチャル
で現実体験とミックスしながら楽しく健康管理をしていこうというものです。
日本一周は 8955 キロです。好きなところからスタートし、一周して出発地に帰ってきます。 47 都道府県庁をぐるっと、右回り ( 時計まわり ) で出発し、ゴールを目指します。
私は、4年前の2012年1月に東京をスタートして、4年と105日後の今日、出発地の東京にまた戻ってきました。日本一周は8955kmで、私は歩幅を60cmにしていますので、平均で1日当り9537歩歩いたことになります。
実は、これが日本一周を、2度達成しました。今後も続けて行くつもりです。
日本一周歩こう会のHPは、http://www.walk-21.com/index.html です。
|
|
|
|
| 2016年4月14日(木) |
| 野川の野草たち |
今、野川ではナノハナが一番目立つが、ハルジオン、ヘラオオバコ、スイバ、オオカワヂシャ、ナガミヒナゲシ、イモカタバミなども見られる。ハルジオンは、キク科の北アメリカ原産の帰化植物、名前は「春に咲く紫苑」の意味で、故牧野富太郎氏が命名。ヘラオオバコは、ヨーロッパ原産のキク科の帰化植物、名前は葉の形に由来する。スイバは、タデ科の多年草。在来種。名前は、葉や茎にシュウ酸が含まれるので、すっぱことに由来する。オオカワヂシャは、特定外来生物に指定されている外来の一年から多年生の植物。ナガミヒナゲシは、ケシ科の一年草。小さな種を沢山作り、タイヤに付着して運ばれるので、自動車道を中心に広がっているようだ。イモカタバミは、南アフリカ原産の帰化植物。 。
 ハルジオン ハルジオン
 ヘラオオバコ ヘラオオバコ
 ナノハナ ナノハナ
 スイバ スイバ
 オオカワヂシャ オオカワヂシャ
 ナガミヒナゲシ ナガミヒナゲシ
 イモカタバミ イモカタバミ |
|
|
|
| 2016年4月14日(木) |
| オオアマナ |
昨日、野川の高水敷で、これまで気がつかなかったオオアマナが沢山咲いているのを見かけました。かなり繁殖力が旺盛なようで、心配です。
調べてみると、ヨーロッパ原産のキジカクシ科の外来植物で、日本には明治末期に観賞用として渡来しました。それが逸出して野生化しています。有毒な植物です。英名はstar of Bethlehem で、キリストの生誕を知らせたベツレヘムの星になぞえた名前です。
 オオアマナ オオアマナ
|
|
|
|
| 2016年4月14日(木) |
| カワセミ |
野川で、カワセミ雄が雌に小魚をプレゼントしていました。春ですね。



|
|
|
|
|
|
| 2016年4月13日(水) |
| ハナミズキ |
ハナミズキが今美しい。三鷹市では、街路樹によく利用されている。花色には、白の他に、紅色もあります。ハナミズキは、桜の返礼に、1915年にアメリカから贈呈されたのが最初だそうです。実は、花のように見えるのは、苞とよばれる葉だそうです。
 ハナミズキ ハナミズキ
 ハナミズキ ハナミズキ |
|
|
|
| 2016年4月12日(火) |
| 朝の庭 |
朝日を浴びて、我が家の狭い庭にも、今、ハナカイドウ、シモクレン、ホウチャクソウ、スノードロップなどが咲いています。
 ハナカイドウ ハナカイドウ
 シモクレン シモクレン
 ホウチャクソウ ホウチャクソウ
 スノードロップ スノードロップ |
|
|
|
|
|
| 2016年4月11日(月) |
| 朝の野川 |
大沢の里には、早くも鯉のぼりが上がっていました。
 鯉のぼり 鯉のぼり
自然観察園横の野川にカワセミがいました。大きめの魚をなかなか食べられずにいました。
 カワセミ カワセミ
動画は、次で見てください。
https://youtu.be/QHh_sSvmgQk
その内飛んで行きました。水辺には、カキドウシ、タンポポなどが咲いていました。
 カキドウシ カキドウシ
 カントウタンポポ カントウタンポポ |
|
|
|
| 2016年4月10日(日) |
| 自然観察園にて |
桜が盛りを過ぎ、暖かい日となって、野川公園自然観察園では、いろいろな花が見られるようになって来ました。オドリコソウ、チゴユリ、イチリンソウ、ジュウにヒトエ、アケビ、ヤマブキ、ラショウモンカズラ、クサイチゴ、ヒトリシズカなどです。桜の花びらが浮かんだ鏡池には、珍しくダイサギがいました。ひょうたん池も桜の花びらが一面に浮かんでいます。
 オドリコソウ、 オドリコソウ、
 チゴユリ、 チゴユリ、
 イチリンソウ、 イチリンソウ、
 ジュウにヒトエ、 ジュウにヒトエ、
 アケビ、 アケビ、
 ヤマブキソウ、 ヤマブキソウ、
 ラショウモンカズラ、 ラショウモンカズラ、
 クサイチゴ、 クサイチゴ、
 ヒトリシズカ ヒトリシズカ
 ダイサギ ダイサギ
 ひょうたん池 ひょうたん池 |
|
|
|
| 2016年4月9日(土) |
| 庭のハナカイドウは、満開 |
今、自宅庭のハナカイドウが満開です。ハナカイドウは、楊貴妃にもたとえられる美しい花です。三鷹市の市の花となっています。
 ハナカイドウ ハナカイドウ
ニリンソウの花も数輪咲いてくれました。
 ニリンソウ ニリンソウ |
|
|
|
| 2016年4月8日(金) |
| 個人番号受取り |
昨日朝、雨の中、市役所に出かけ個人番号カードを受け取ってきました。すいていて、事前の予約時間よりずいぶん早く着きましたが、直ぐに受け取ることができました。住基カードも印鑑証明書もマイナンバーに統一しました。後で考えると、住基カードは、身分証明になるので、総合しない方がよかったのかもしれないと思いました。
暗証番号を新たに4個設定する必要がありました。でも、その内3種類は同一でもよかったので、結局2個の暗証番号を新たに作りました。『暗唱番号』は、すべて記憶をすることはとてもとても出来ないので、その管理をどうするか、悩ましい問題です。 |
|
|
|
| 2016年4月8日(金) |
| 太ったスズメ |
昨日、所用で新宿にある病院に出かけました。屋外のカフエで、コーヒーとドーナツを買って、椅子に座ろうとすると、直ぐ近くのテーブルにスズメがいた。よく太って、動きがゆっくりしていた。ちょっと変わっている。近くには他にも数羽はいるようだった。なぜと思ったが、直ぐに分かった。このスズメたちは、お客の食べ残したドーナツなどの栄養価の高いものを餌にしていたのでした。道理で太り過ぎ。
 太ったスズメ 太ったスズメ
 太ったスズメ 太ったスズメ
 餌に集まるスズメたち 餌に集まるスズメたち |
|
|
|
| 2016年4月6日(水) |
| フデリンドウ(筆竜胆) |
野川の法面に、フデリンドウの花が咲いていた。フデリンドウは、リンドウ科の二年草で、茎は高さ5~10cm、春3月から5月に,数個の青紫色の花をつける。日当りのよいところにはえる。最近は数が減っているそうです。
 フデリンドウ フデリンドウ |
|
|
|
| 2016年4月6日(水) |
| 今日から小学校の新年度がスタート |
野川大沢橋の羽沢小学校では、今日から新年度がスタートしました。校庭では朝の集会が行われていました。横の野川では、ナノハナと桜が満開でした。
 小学校の朝の集会 小学校の朝の集会
 野川の風景 野川の風景 |
|
|
|
| 2016年4月6日(水) |
| 野川のシマアジ |
今朝も野川にはシマアジがいました。これまでより少し下流側でした。初めて見つかったのは2月21日ですから、ずいぶんながくなります。今日はコガモの群れと一緒でした。
動画はここです。https://youtu.be/um88LFW5UeQ
尚、動画には、鳴き声(?)が録音されていますが、これ本当にシマアジの鳴き声でしょうか? 調べてみます。
 シマアジ シマアジ
|
|
|
|
| 2016年4月5日(火) |
| 野川の桜ライトアップ |
今夜、野川の榎橋から細田橋間で午後6時から9時の予定で、恒例の桜ライトアップが実施された。私は細田橋から、榎橋間の左岸をゆっくと歩き、素晴らしい桜の姿を楽しみました。







|
|
|
|
| 2016年4月4日(月) |
| 庭のハナカイドウは、開花直前 |
自宅庭のハナカイドウがもうすぐ開花です。あいにくの雨で今日は開花しなかったが、明日晴れれば、開花することでしょう。尚、ハナカイドウは、楊貴妃にもたとえられる美しい花です。三鷹市の市の花となっています。
 ハナカイドウ ハナカイドウ |
|
|
|
| 2016年4月3日(日) |
| 日立中央研究所庭園公開日 |
今日は、国分寺市にある日立中央研究所の春の庭園公開日でした。あいにくの曇り空でしたが、沢山の見学者が桜満開の庭園を楽しみました。
 大池 大池
 桜 桜
 桜 桜
 桜 桜
 ヤマツツジ ヤマツツジ
 フジバカマ フジバカマ
 コブハクチョウ コブハクチョウ |
|
|
|
| 2016年4月2日(土) |
| 国際基督教大学の桜満開 |
今、国際基督教大学の桜も満開です。この土・日は、観桜のため正門の桜並木が公開されています。






|
|
|
|
| 2016年4月1日(金) |
| 朝、野川を歩く |
今朝は、野川の飛橋から、下流の御塔坂橋までをゆっくりと歩きました。野川の桜も満開です。水辺には黄色いナノハナが一面に咲いています。散歩をする人の数が多いです。早くも花見をしてるグループも出てきました。
 桜 桜
 桜 桜
冬鳥のコガモ、マガモ、ツグミの姿をまだ見かけました。三鷹市の市の花であるハナカイドウも咲き始めました。
 コガモ コガモ
 ハナカイドウ ハナカイドウ |
|
|
|
| 2016年3月31日(木) |
| 今朝の野川の桜 |
朝早く、野川の桜を見に行きました。野川の飛橋下流の丁度東京大学馬術クラブの向かい側に、いい桜の木があります。今朝は、まだ満開の直ぐ手前との感じでした。

今日は、午前10時ごろに家を出て、西多摩の霊園に墓参りに出かけました。 |
|
|
|
| 2016年3月30日(水) |
| 植物多様性センターにて |
久しぶりに神代植物公園植物多様性センターを見学した。オオシマザクラ、ヤマザクラ、ヨコハマヒザクラが咲いていた。置いてあった資料によるとここには15種類の桜の木があるそうです。
 ヨコハマヒザクラ ヨコハマヒザクラ
 ヤマザクラ ヤマザクラ
 オオシマザクラ オオシマザクラ
ヒカゲツツジ、ゲンカイツツジ、モクレン、スモモも咲いていた。
 ヒカゲツツジ ヒカゲツツジ
 ゲンカイツツジ ゲンカイツツジ
 モクレン モクレン
 スモモ スモモ |
|
|
|
|
|
| 2016年3月30日(水) |
| 日立中央研究所 春の庭園公開 |
|
|
|
| 2016年3月29日(火) |
| 野川の桜・飛行場の桜 |
今日は、快晴ですが、野川の桜も、調布飛行場の一本桜もまだ5分咲きです。
 野川の桜 野川の桜
 野川の桜 野川の桜
 野川の桜 野川の桜
 飛行場の桜 飛行場の桜 |
|
|
|
| 2016年3月28日(月) |
| コブシの大木 |
国立天文台構内(7中前)竹林の外れ(野川側)に立っているコブシの大木に、今年は沢山の花がつきました。5年ほど前までは、放置竹林の中にあったので、日照が悪く、花は多くはつかなかったのですが、竹林が整理されるとともに花がつきだし、今年は、多くの花がついています。
 コブシ コブシ
 コブシ コブシ
 コブシ コブシ |
|
|
|
| 2016年3月28日(月) |
| 庭の水仙 |
我が家では,今、4種類の水仙が咲いています。水仙は、種類が多いので、私には正確な名前はよく分かりませんが・・・




|
|
|
|
| 2016年3月28日(月) |
| 野川の野鳥 |
今日、野川を歩いた時に見た野鳥です。モズとコガモとツグミはまだ見かけます。
 コガモ コガモ
 モズ モズ
 ツグミ ツグミ
スズメが水浴びをしていました。おかしな目(目の下)ですね。メガネでもかけているような・・
 水浴びをするスズメ 水浴びをするスズメ |
|
|
|
| 2016年3月26日(土) |
| ICUの桜 |
ICUでは、桜はまだ2分、3分咲きでした。観桜についてとの掲示版が置かれていた。それによると、『平日 ご遠慮ください。土・日 10時から17時まで。範囲 正門からバスロータリーまで』とあった。




|
|
|
|
|
|
| 2016年3月26日(土) |
| 野川の春 |
野川では、桜はまだ2分、3分咲き程度で、見頃は月末か? 今は、ナノハナが満開です。野川には、まだシマアジがいました。川縁の道には、アカバナトキワマンサクの花が咲いていた。
 野川の桜 野川の桜
 野川の桜 野川の桜
 シマアジ シマアジ
 アカバナトキワマンサク アカバナトキワマンサク |
|
|
|
| 2016年3月25日(金) |
| 三鷹市の誕生記念樹配布 |
今日は、三鷹市役所の1階ホールで、三鷹市市民緑化推進委員会主催の新生児の誕生記念樹配布がおこなわれた。これは、30年以上前から行われている。私も委員の一人なので、スタッフとしてお手伝いをした。
木の種類は、ゲッケイジュ、ウメ、ハナカイドウ、キンモクセイ、サルスベリ、カンツバキの木か、観葉植物パキラから一つ選択できる。希望の多い木は、ゲッケイジュ、ウメ、ハナカイドウの順であった。市報に、年3回ほど、お知らせがでてるいて、事前に申込をすると無償でもらえる。 今回は、約90人の方から申込があったようで、とりに来られたのは、赤ちゃんをだいた、若いママさんが多かった。


|
|
|
|
| 2016年3月24日(木) |
| 中央研究所の庭園のフジバカマ |
国分寺にある日立製作所中央研究所の庭園のフジバカマの手入れ(除草)に行ってきました。今年で3年目となりますが、フジバカマの新しい芽が元気に育っていました。
 フジバカマ フジバカマ
 フジバカマ フジバカマ
池の周りは、ユキヤナギ、ハクモクレンなどの花がきれいでした。桜は、まだこれからのようでした。今日は、コブハクチョウの姿がなく、池には、マガモとカルガモの群れがいました。
 ユキヤナギ ユキヤナギ
 マガモ マガモ
 カルガモ カルガモ |
|
|
|
| 2016年3月23日(水) |
| 自然観察園にて |
野川公園自然観察園では、フデリンドウが開花しました。ヒメウズも花をつけています。野川沿いでは、ユキヤナギが満開でした。
 フデリンドウ フデリンドウ
 ヒメウズ ヒメウズ
 ユキヤナギ ユキヤナギ
|
|
|
|
| 2016年3月23日(水) |
| ICUの桜も開花 |
三鷹の桜の名所の一つ、国際基督教大学(ICU)正門の桜並木も、咲き始めました。教会前のロータリーの桜は、一足早く咲き出しました。
 桜並木 桜並木
 桜並木 桜並木
 ロータリーの桜 ロータリーの桜 |
|
|
|
| 2016年3月22日(火) |
| 野川を下り、世田谷区の喜多見へ |
今日は、久しぶりに、野川を三鷹市の大沢橋から世田谷区の神明橋まで歩き、小田急線の喜多見駅から電車バスを乗り継いで帰ってきました。約17000歩歩きました。
野川の河川敷にはナノハナが沢山咲いていて、両岸の桜(染井吉野)は、咲き始めたところでした。川の中では、カルガモ、コガモ、コサギをよく見かけました。その他,カワウ、マガモ、ハクセキレイ、ムクドリなどを見かけました。
佐須用水からも、湧水が多く野川に注いでいました。水の量は、例年より少し多いと感じました。今月末には、桜も満開になり、野川の春もたけなわとなります。今年も「野川の桜ライトアップ」が、楽しみです。
 ナノハナ ナノハナ
 ナノハナと桜 ナノハナと桜
 桜(染井吉野) 桜(染井吉野)
 桜(染井吉野) 桜(染井吉野)
 桜(染井吉野) 桜(染井吉野)
 コガモ コガモ
 コサギ コサギ
 佐須用水 佐須用水
 馬橋(甲州街道)付近 馬橋(甲州街道)付近
 神明橋付近 神明橋付近
You-tubeの動画 佐須用水とコガモ が見られます。
佐須用水2016-3-22 https://youtu.be/T2XmWmfA8JQ
コガモ 2016-3-22 https://youtu.be/uLRnz9EXM_k |
|
|
|
| 2016年3月21日(月) |
| 春の日まつり@野川公園梅林 |
今日は、11時から15時半まで、野川公園梅園で「春の日まつり」が開催されました。移動式本屋、アーテストによるワークショップ、園内のガイドワーク、パークカフエ、スタンプラリーなど盛りたくさんのイベントがありました。子ども連れで賑わっていました。私も、梅の下でパークカフエを楽しみました。



|
|
|
|
| 2016年3月21日(月) |
| シマアジ |
野川では、今日もシマアジがいました。2月21日に初めて見つかって、もう1ヶ月にもなります。時々、どこかに飛んで行って、見つからない日もありましたが、また帰ってきてくれました。本当に、長い間、楽しませてくれました。桜も咲いたので、そろそろ移動が近づいていますね。
 シマアジ シマアジ
動画もあります。
https://youtu.be/PVfDXf4a3KE |
|
|
|
| 2016年3月21日(月) |
| 自然観察園にて |
野川公園自然観察園では、今、イカリソウ、ニリンソウ、レンゲ、コスミレ、トウダイグサ、ラショウモンカグラが咲いていました。キブシも見頃です。
 イカリソウ イカリソウ
 ニリンソウ ニリンソウ
 レンゲ レンゲ
 コスミレ コスミレ
 トウダイグサ トウダイグサ
 ラショウモンカグラ ラショウモンカグラ
野川沿いのヤナギのも新緑になりました。野川の河川敷は一面ナノハナになってきました。水辺の染井吉野も開花をしました。
 キブシ キブシ
 ヤナギ ヤナギ
 ナノハナ ナノハナ
 染井吉野 染井吉野 |
|
|
|
| 2016年3月20日(日) |
| 桜開花@神代植物公園 |
神代植物公園の「神代曙」と「しだれ桜」が今日開花していた。寒咲大島、東海桜、寒緋桜も咲いている。
 神代曙 神代曙
 しだれ桜 しだれ桜
 寒咲大島 寒咲大島
 東海桜 東海桜
 寒緋桜とヒヨドリ 寒緋桜とヒヨドリ
今日は、園長による園内ガイドが1時間ほどあり、参加させていただいた。今日のガイドは桜を中心に、1時間ほど園内を回り、シャクナゲ、カタクリ、トサミズキ、ハナモモ、ハクモクレン、最後は、ツバキ・サザンカ園の「神代都鳥」を見て終わった。
 シャクナゲ シャクナゲ
 カタクリ カタクリ
 トサミズキ トサミズキ
 ハナモモ ハナモモ
 ハクモクレン ハクモクレン
 神代都鳥 神代都鳥 |
|
|
|
|
|
| 2016年3月18日(金) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(3月). |
暖かい今日の午前中、野川に注ぐ湧水量の3月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、昨年の9月をピークに減少しています。
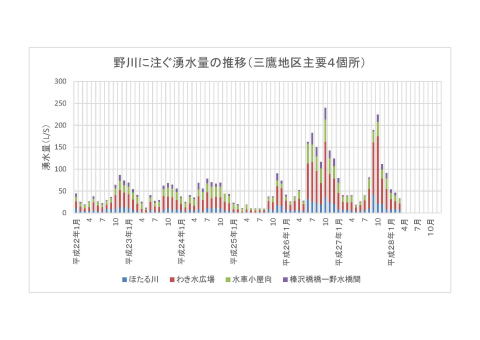 湧水量の推移 湧水量の推移
 ホタル川での測定の様子 ホタル川での測定の様子
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。 |
|
|
|
| 2016年3月17日(木) |
| 野川の流量測定(3月) |
今日は、暖い日であったので、午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。昨年の9月をピークに流量は減少している。
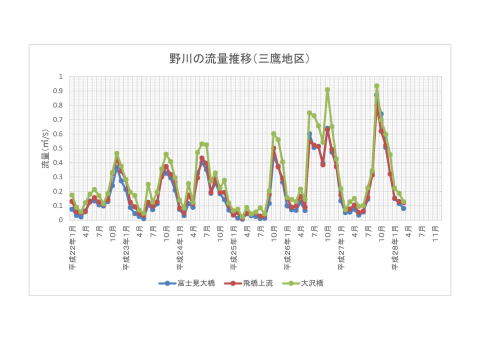 野川の流量推移 野川の流量推移
 飛橋付近での流量測定の様子 飛橋付近での流量測定の様子
野川の水辺では、この暖かさで、ナノハナが沢山さいていた。オオイヌノフグリも沢山咲いていた。 シマアジも寝ていました。
 ナノハナ ナノハナ
 オオイヌノフグリ オオイヌノフグリ
 シマアジ シマアジ |
|
|
|
| 2016年3月16日(水) |
| 自然観察園の早春の花 |
カタクリ、シュンラン、ニリンソウが野川公園自然観察園で咲いていた。春の野草の代表的な花で、これから5月頃まで楽しませていただける。
 カタクリ カタクリ
 シュンラン シュンラン
 ニリンソウ ニリンソウ |
|
|
|
| 2016年3月15日(火) |
| 自宅の梅(豊後) |
遅咲きの自宅庭の梅(豊後)の花が、よく咲いています。
 夕陽の中の梅の花 夕陽の中の梅の花
 月と梅の花 月と梅の花
 梅の花 梅の花 |
|
|
|
|
|
| 2016年3月13日(日) |
| シジュウカラの巣箱設置 |
今朝、自宅梅の木にシジュウカラの巣箱を設置した。巣箱は、三鷹市が毎年希望者に無償で提供しているもので、なかなかよく出来ています。
早速、シジュウカラが巣を使ってくれるといいのですが、期待して待ちましょう。同時に、水場も作りました。
 シジュウカラの巣箱 シジュウカラの巣箱 |
|
|
|
| 2016年3月13日(日) |
| 桜の開花予想 |
朝のNHK天気予報の時間に、気象予報士の南さんが、桜の開花予報を説明していた。今年は、東京は、南さん予想が3月18日、日本気象協会予想が3月21日となっていて、例年より早いそうです。もう一週間で開花とは、この寒さの中では、考えにくい。
 NHK桜の開花予想 NHK桜の開花予想
我が家では、やっと、遅そ咲きの梅(豊後)が、大分咲いてきた。クリスマスローズも咲いています。
 梅(豊後) 梅(豊後)
 クリスマスローズ クリスマスローズ |
|
|
|
| 2016年3月12日(土) |
| 野鳥観察会@野川公園 |
野川公園緑の愛護ボランティアの会主催の野鳥観察会があり、参加しました。この冬最後の野鳥観察会であり、多くの一般参加者がありました。寒い日でしたが、冬鳥を探して野川公園を一回りしました。
今日確認できた鳥は24種で、例年より少し少なめでしたが、ハイライトは今年初めてイカルの群れを確認できたことでした。高い枝に止まっていたので、いい写真は撮れませんでしたが、イカルであることは確認できます。
 イカル イカル
また、イカルの動画もあります。 https://youtu.be/-HOks-061a0
野川公園B地区の、遠くの木にイカルの群れがいました。そちらの方から、鳴き声が聞こえていました。映像の左上の野鳥がイカルです。残念ながら、鳴いているのは写っていない、別のイカルのようです。途中で、イヌ(?)の大きな鳴き声が入り、すみません。
|
|
|
|
| 2016年3月12日(土) |
| 三鷹創造協会での講演会&交流会 |
昨日午後、花と緑のまち三鷹創造協会主催で、佐藤方博さん(NPO法人生態工房事務局長)の「みんなで守る・学ぶ街の生物多様性」と題する講演会があり、ききに行きました。最後に参加者全員で交流会を行いました。
講演の多く時間は、井の頭公園池で行われている「かいぼり」について、経緯を説明しながら、市民と行政とNPOの協働で、この「かいぼり」が行われた経緯とその意義を大変わかりやすく説明されました。また、最近東京では、都市部で「かいぼり」が広がっていて、2013年は1件(井の頭公園)、2014年は5件、2015年は12件と増えているとのことで、その主な狙いは、水質浄化と外来種駆除であるとのことでした。
「かいぼり」のいいところは、効果が、確実で、即効性があり、様々な立場の協力者・利害関係者(行政、公園の管理運営者、ボランティア団体、工事受託者、専門団体、参加者、見学者など)が集まってくれること、ボランティアにも様々な関わり方ができることである。
井の頭公園の池は、武蔵野の三大湧水池の一つで、神田川の源流である。1965年前後に湧水が枯渇し、水生生物はほぼ全滅した。2000年頃からオオクチバスが増加した。2007年度に井の頭外来生物問題協議会が、東京都西部公園緑地事務所、井の頭自然文化園(動物園)、生態工房、井の頭かんさつ会、東京都吉祥寺ライオンズクラブ、神田川ネットワークにより設立され、定期的(月1回)な会合がもたれ、主に「外来魚」の駆除や問題に関する意見交換がされてきた。
当時公園管理者は「かいぼりはNG!」であった。その理由は、「池に水がない!」「泥が臭い!」という7苦情を懸念し、ボート運営者、茶屋との調整が必要となり、「かいぼり=浚渫工事」という認識があり、莫大な費用を懸念したし、このような「市民参加」の前例がなかったことなどによる。
2010年度になって、3年後に「かいぼり」が決定された。外来魚駆除と水質改善を目的とした、低予算でリーズナブルなかいぼりを、2017年井の頭100周年に向けて、合計3回(2013年度、2015年度、2017年度)実施し、2017年以後のい継続的にカいぼりを実施する予定と大きく前進した。
第1回かいぼり準備では、弁天池は水抜きをしないで、その他を水抜きする工事が計画されたが、その際、面倒な関係機関との調整や許可が20件ほどあった。例えば、河川法、環境確保条例、下水道法、地元消防署、地元警察署、貸しボート業者などとの調整や許可などであったが、乗り越えた。
市民参加の形としては、本体の井の頭かいぼり隊、かいぼり予備隊(おさかなレスキュー隊、体験イベント参加者など)、一般の見学者などの「予備隊」の拡大が、「かいぼり隊」の成長に繋がった。
2014年2月には、約1ヶ月の池干しが実施され、かいぼり隊などによる外来生物問題の普及啓発が行われた。
第1回かいぼり後、モツゴの捕獲数は、かいぼりをした池(ボート池とお茶の水池)では、増加し、かいぼりをしなかった弁天池では、増加しなかった。又、埋土種子の撒き出しで、水草(ハダシシヤジクモ、シヤシクモなど)が出現した。
第2回かいぼりは、2015年11月から始まり、今週の初め(3月7日)から、水を入れ始めている。現在の」ところは、地下水は使わないで、幸いにも多く湧いている湧水だけでどれだけたまるか、様子を注意深く見ているとのこと。桜の時期までには、もとの水位に戻すとのことです。
後半では、都市部で生物多様性について、説明があった。
以上、長々と、講演の要旨を書きましたが、講演は大変よくまとっまていたと思います。自分の頭の中を整理しておくためにも、少し、詳しくメモをさせていただきました。大変いい講演でした。 |
|
|
|
| 2016年3月11日(金) |
| 残って困る外国コイン |
海外に出かけ、残ってしまった外国コインは、処理に困ります。大分前から貯まったままだったのを集めて袋に入れてみると1.5kg以上あった。内訳はアジア、アメリカ、ヨーロッパと様々。寄付でもしたいのだが、どこにもっていけばいいか分からない。、探さなければと思っていました。捨てるわけもいかないので・・。
 外国コイン 外国コイン
今朝、ネットで調べたら、「ユニセフ外国コイン募金箱」を三井住友銀行の各支店で設置しているとのことがわかった。近くの調布駅前支店に電話で確認したら、設置されているとのこと。今朝もって行ってきました。「ユニセフ外国コイン募金箱」と言っても、いつもおいてあるのではなく、行員に聞いてみると、しばらく待たされて、中の方から小さな箱をもってきた。とても入りきらないので、袋のまま、受けとっていただいた。
少しはお役に立てて、よかった。 |
|
|
|
| 2016年3月10日(木) |
| 今日のカワセミ |
曇りの日の野川で、目立たないところにカワセミがじっとしていた。
 カワセミ カワセミ
 カワセミ カワセミ
バンも姿を見せ、シマアジはまだいました。
 バン バン
 寝ているシマアジ 寝ているシマアジ |
|
|
|
| 2016年3月10日(木) |
| たまってしまった小銭の処理編 |
長い間、財布が重くならないようにコーヒービンにためていた小銭(10円、5円、1円)が、たまりにたまって、困っていた。やっと重い腰を上げて、10円、5円、1円に仕分けした。10円は2瓶、5円は1瓶、1円が1瓶にほぼいっぱいになった。

近くの郵便局に持ち込んで、入金していただいた。担当の職員は、いやな顔をしないで、受とり、機械で数えてくれた。10円473個、5円168個、1円529個で、合計で6099円もあった。思ったよりも沢山たまっていた。 |
|
|
|
| 2016年3月8日(火) |
| 野川の鳥たち |
野川には、今日は、もうシマアジの姿はありませんでした。飛び去ったようです。野川でバン、モズ、マガモ、カルガモ、コガモ、コサギ、自然観察園でシメ、カシラダカ、ジョウビタキにも会いました。
 バン バン
 モズ モズ
 シメ シメ |
|
|
|
| 2016年3月8日(火) |
| 庭の梅 |
庭の梅がやっと咲き始めました。遅咲きの豊後(ぶんご)です。梅とアンズを交配した品種で、いい実がとれます。今年は、徒長枝を思い切って沢山残してあるので、花が沢山咲きそうです。これまでは、いつも徒長枝を短く切っていたので、花の数が少なかったようです。
 庭の梅(豊後) 庭の梅(豊後)
近くの家では、ハクモクレンが咲いていました。
 ご近所のハクモクレン ご近所のハクモクレン |
|
|
|
| 2016年3月7日(月) |
| 近くの川に迷鳥がきました(動画) |
|
|
|
| 2016年3月7日(月) |
| 寒緋桜(かんひざくら) |
近くの天文台通りに、寒緋桜が2本あります。早咲きの桜で、今、よく咲いています。
 寒緋桜 寒緋桜 |
|
|
|
| 2016年3月6日(日) |
| 神代植物公園にて |
しばらくぶりに神代植物公園にいきました。公園では、今、河津桜と大寒桜が咲いています。15日からはさくらまつりが始まります。ハナモモも咲いています。ミツマタ、アカバナミツマタ、ハチジョウキブシも咲いていました。
 河津桜 河津桜
 大寒桜 大寒桜
 はなもも 寒日 はなもも 寒日
 はなもも 矢口 はなもも 矢口
 ミツマタ ミツマタ
 アカバナミツマタ アカバナミツマタ
 ハチジョウキブシ ハチジョウキブシ |
|
|
|
| 2016年3月5日(土) |
| 近くの川に迷鳥 |
私は気がつくのが遅かったのですが、10日ほど前から近くの川に迷鳥が来ています。シマアジという名前の鳥です。私は初めて見ました。コガモに似ていますが、顔に白い模様があります。 全長は38cm。来たのは雄のようです。



|
|
|
|
| 2016年3月5日(土) |
| モズに春の予感 |
モズは、雄雌別々の縄張りをもっています。今朝、野川で、双眼鏡でモズの雌を見ていたら、モズの雄が、飛んで来て、近くの枝に止まりました。詳細は分かりませんが、モズの雌は、小さな昆虫を、くわえていました。モズの雌は、その枝に止まったままでしたが、モズの雄は、直ぐに、離れていきました。餌を探しにいったようです。大分してから、かなり離れた枝にモズの雄がまた来ましたが、雌には近かよりませんでした。獲物が獲得できなかったようです。
 モズ2羽 モズ2羽
 モズ(雄) モズ(雄)
 モズ(雌) モズ(雌)
 モズ2羽 右上雄、左下雌 モズ2羽 右上雄、左下雌 |
|
|
|
|
|
| 2016年3月4日(金) |
| 自然観察園にて |
今朝、野川公園自然観察園にでかけました。今日もジョウビタキの雄雌が別々に姿を見せてくれました。園内では、マンサク、サンシュユが咲いていた。、キブシももうすぐ咲きそうでした。
 ジョウビタキ(オス) ジョウビタキ(オス)
 ジョウビタキ(メス) ジョウビタキ(メス)
 マンサク マンサク
 サンシュユ サンシュユ
 キブシ キブシ |
|
|
|
| 2016年3月3日(木) |
| 内科の定期診断でお茶の水まで |
今日は、お茶の水の病院まで、腎臓内科の定期診断に出かけてきました。午前中に血液を採取して、迅速に分析してくれ、、午後の医師の診断時には、その結果に基づいて判断を聞かせていただける。今回は、クレアチニン値とヘモグロビンA1Cが前回より少し悪くなったが、前にもあった値で、変動幅の範囲内であった。
「何か思い当たることはないのか」との医師の問いかけで、考えてみると、最近はコーヒに少し砂糖を入れて、よく飲んでいたことが、ヘモグロビンA1Cによくないことに思い当たり、自粛をすることにした。 ドリップ式の濃いコーヒーは、私にはよくないようだ。
帰り道、神田明神に家内安全を参拝してきた。途中のみちで、アセビやジンチヨウゲの花を見かけた。
 神田明神 神田明神
 アセビ アセビ
 ジンチョウゲ ジンチョウゲ |
|
|
|
| 2016年3月2日(水) |
| 昨日の三鷹市市民緑化推進委員会 |
昨日(3月1日)午後、三鷹市市民緑化推進委員会が開催されました。主な議題は、
①ガーデニングフエスタ2016プレイベント「花のまち交流会」について
②ガーデニングフエスタ2016「写真募集」と「秋のイベント」について
③花と緑のまち三鷹創造協会の理事の推薦について
④「花いっぱい運動」について
⑤「誕生記念樹の配布」について(3/25)
であった。
①の「花のまち交流会」は、今年の6月11日(土)午後、公会堂さんさん館3Fで実施されることとなった。講師は山田香織さん(盆栽家)。募集方法などの詳細は、5月1日の三鷹市報に掲載される予定。
②の三鷹市内街角の庭、緑の街なみの「写真募集」は、募集期間が5月2日~6月30日で、昨年と同様に、「私の庭部門(自薦部門)」「と私の緑のお気に入りスポット部門(他薦部門)」がある。募集案内は、三鷹市報3月15日号に掲載される予定。ポスターの掲示もある。昨年、一昨年は、私も「私の緑のお気に入りスポット部門」に応募しました。
ガーデニングフエスタ2016「秋のイベント」は、9月24日に市役所中庭で実施される予定です。
⑤の赤ちゃんに誕生記念樹の配布は、3月25日で、事前申込が必要です。期限は明日(3/3) .
詳しくは三鷹市報や下記を見てください。 (http://hanakyokai.or.jp/news/53)
25日午後には、私も配布のボランティアとして、お手伝いをします。 |
|
|
|
| 2016年3月1日(火) |
| 自然観察園の野鳥たち |
今朝は、富士山がとてもきれいでした。野川では、カワセミに会いました。
 富士山 富士山
 カワセミ カワセミ
早朝の野川公園自然観察園では、シメの群れが、地上におりていました。人の気配で、一斉に飛び上がり、木の枝に止めって、人気が無くなるのをじっと待っているようでした。
 シメ シメ
 シメ シメ
 シメ シメ
 シメ シメ
今日も、ジョウビタキの雄雌とモズがいました。
 ジョウビタキ(オス) ジョウビタキ(オス)
 ジョウビタキ(メス) ジョウビタキ(メス)
 モズ モズ |
|
|
|
| 2016年2月29日(月) |
| 自然観察園の池 |
野川公園自然観察園には、5つの池があります。しょうぶ池、ほたる池、まる池、ひょうたん池、かがみ池です。
しょうぶ池、ほたる池、まる池には、ICUから湧水が流れ出て、3つの水路に別れた湧水が、それぞれの池に入ります。この3つの池は、お互いに水路で繋がっています。この水路からは、もう一つ地下に埋めたパイプでひょうたん池に湧水の一部が導かれています。
 しょうぶ池 しょうぶ池
 ホタル池 ホタル池
 まる池 まる池
 ひょうたん池 ひょうたん池
かがみ池は、独立の池です。ICUから湧水が導かれて、かがみ池に注ぎます。時にはかがみ池の水が涸れることもありました。
 かがみ池 かがみ池
そこに、今度もう一つ池が加わりました。2月27日にボランティアたちが作業をしていたところに、28日には、水が張られていました。まだ池の名前は表示されていませんが、そのうちに、分かったら、またお知らせします。
 新しい池 新しい池
|
|
|
|
| 2016年2月29日(月) |
| 今日も庭にジョウビタキが・・ |
今日も、昼過ぎに、ジョウビタキ(オス)が、自宅の庭に姿を見せてくれました。ガラス越しに撮影したので、もう一つですが、見ていただきましょう。
 ジョウビタキ(オス) ジョウビタキ(オス)
 ジィウビタキ(オス) ジィウビタキ(オス) |
|
|
|
| 2016年2月29日(月) |
| プリンターの買い換え |
| 数年間使用したキャノンのインクジェットプリンターMP610は、今朝「インク吸収体が満タン」との表示が出たが、メーカーに修理を依頼すると、修理部品の保管期間5年間が2年も前に終了していて、もう修理が出来ないとのことです。いよいよ使い捨ての時代だと云うことを実感した次第です。仕方なく、急いでメーカーの薦める機種MG6930に買い換えた。今度は無線LANで接続して使うつもり。プリンター本体は割安感があり、インクで稼いでいることがよく分かる。 |
|
|
|
| 2016年2月28日(日) |
| カシラダカ |
野川公園自然観察園で、カシラダカの群れが、枯れ葉をかき分けて、何かをさがしていた。草食性です。
ふとした機会に数羽が飛び上がって、その内1羽が、近くの木の枝に止まってくれた。その際に写真がとれた。カシラダカは、スズメ目ホオジロ科ホオジ属で、冬鳥として大陸から日本に渡ってくる。頭頂に冠羽があるのが特徴。よく似ているホオジロには冠羽がなく、留鳥です。
 カシラダカ カシラダカ
 カシラダカ カシラダカ
|
|
|
|
| 2016年2月27日(土) |
| 野川公園自然観察園にて |
今朝も、富士山がきれいに見えた。
 富士山 富士山
野川公園自然観察線では、今、ウグイスカグラ、キクザキイチゲ、ミスミソウ、セツブンソウ、フクジュソウが咲いている。
 ウグイスカグラ ウグイスカグラ
 ウグイスカグラ ウグイスカグラ
 キクザキイチゲ キクザキイチゲ
 ミスミソウ ミスミソウ
 ミスミソウ ミスミソウ
 セツブンソウ セツブンソウ
 セツブンソウ セツブンソウ
 フクジュソウ フクジュソウ
ボランティアの方々が園内のまる池の手入れをしていた。その中に、最長老のIさんがおられたので、挨拶し、今何歳かと伺った。85歳との返事が返ってきた。歳のわりには、お元気な姿に感心した。
 まる池の手入れをするブランティアたち まる池の手入れをするブランティアたち
|
|
|
|
| 2016年2月26日(金) |
| 梅の花とサンシュウの花 |
国際基督教大学構内のバカ山広場では、今、梅の花がよく咲いていて、きれいです。近くにはサンシュウの木も1本あり、これにも花が咲き始めていました。
 梅 梅
 梅 梅
 梅 梅
 サンシュウ サンシュウ
 サンシュウ サンシュウ
|
|
|
|
| 2016年2月26日(金) |
| ジョウビタキ |
今日は、ジョウビタキによく会いました。野川公園自然観察園には、ジョウビタキのオスと、ジョウビタキのメスがそれぞれに縄張りを作っているようで、今日は、オスとメスともに会いました。
 ジョウビタキ(オス)@自然観察園 ジョウビタキ(オス)@自然観察園
 ジョウビタキ(メス)@自然観察園 ジョウビタキ(メス)@自然観察園
昼食をICUの学食で食べていたとき、食堂から見えるところに、ジョウビウタキのがきました。近くまで行ってみるとジョウビタキのメスでした。
 ジョウビタキ(メス)@ICU ジョウビタキ(メス)@ICU
 ジョウビタキ(メス)@ICU ジョウビタキ(メス)@ICU
また、昨日は、この冬初めて、我が家の庭にもジョウビタキ(オス)が現れました。
 ジョウビタキ(オス)@自宅庭 ジョウビタキ(オス)@自宅庭 |
|
|
|
| 2016年2月26日(金) |
| 今朝の富士山 |
昨夜は、冷えたので、予想通り、今朝は富士山がすっきりと見えました。
 富士山 富士山
|
|
|
|
| 2016年2月25日(木) |
| シジュウカラの巣箱配布 |
|
|
|
| 2016年2月24日(水) |
| 植物標本講座2回目 |
昨日、神代植物公園植物多様性センター主催の植物標本講座の第2回目があり、受講した。講師の先生は、第1回目と同じく首都大学東京の牧野標本館・加藤英寿氏である。今日の主な内容は①標本ラベル作成と、②前回採取して乾燥マットに挟んで7日間乾燥してあった標本を台紙に貼る作業であった。但し②の台紙に貼る作業について、標本を標本館に寄贈する場合には、新聞紙に標本とラベルを挟んだ状態で、標本を台紙に貼らずに、標本館に提出すればよい。その理由は、標本館ごとに台紙の規格が異なるためだそうです。
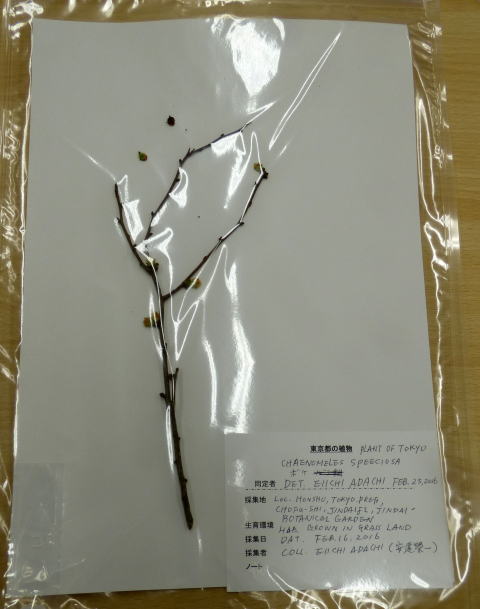 私の標本 ボケ 私の標本 ボケ
今回の講座では、最も重要なラベルの作成に時間が多く割かれた。また、台紙に貼らずに、ストックパックに台紙、植物標本、ラベルを入れて、手動の排気ポンプで、空気を抜き、簡易的な標本の保存を行った。これらについては、日本ヴォーグ社から「原色植物標本キッと」(価格は約3万円)がすでに市販されていて、それを利用することが出来る。今回の講座でも、そのキッとを使用して実習を行った。キッとは、牧野標本館が監修しているようだ。 講座の最後に「東京都博物誌のための植物標本収集プロジェクト」への参加のお誘いがあった。今回の講座も、そのために開催されたことを感じました。
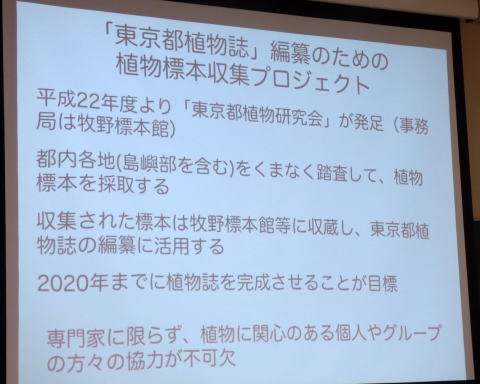 東京都植物誌 東京都植物誌
|
|
|
|
| 2016年2月23日(火) |
| 昨夜の野川流域連絡会生きもの分科会 |
昨夜、府中の北多摩南部建設事務所の別館会議室で、野川流域連絡会生きもの分科会が開催され、出席しました。主な議題は、①冬季・生きものかんさつ会、②野川の生きものガイドブックの改定について、であった。
生きものガイドブックは、初版が2004年3月に出来て、もう10年以上にもなり、改定しようとのことになり、野鳥、植物、水生生物、昆虫に別れて、内容の検討を始めている。個人的には、改定が出来るまでには、1年ほどはかかるのではと思っている。
今年の夏季・生きもの観察会は、8月7日(日)に実施する予定となった。
会議が終わって帰る頃には、天気予報通り、小雨がふってきた。 |
|
|
|
| 2016年2月23日(火) |
| オナガガモペアーの怪しい行動 |
昨日、初めて、オナガガモペアーの怪しい行動を見ました。あっという間の1分ほどの短い間でした。
野川で、オナガガモのペアーが、仲良く採餌をしていました。倒立採餌でした。私は、オナガガモのオスとメスの別々の写真を撮っていました。雄雌が分かりわかりやすいように、野川の生きものハンドブックに載せるためでした。なかなか2羽の距離はが離れませんでした。気がつけば、オスがメスの体の上にのり、メスの体が、頭を残して、水中に沈みました。そのままの姿勢で、水平に円弧を描くように、360度回転して、2羽の体は元の向きになり、2羽の体は離れました。
状況をよく理解出来なかったので、帰ってからインターネットで検索して、「交尾」とか「疑似交尾」と言う言葉を見つけました。これからシベリヤへ北帰行をする、冬のこの時期、オナガガモには卵ができると、困ることになる。どうなっているのだろうか、自然には分からないことが多い。
 写真1 写真1
 写真2 写真2
 写真3 写真3
 写真4 写真4
 写真5 写真5
 写真6 写真6 |
|
|
|
| 2016年2月21日(日) |
| 井の頭かんさつ会「かいぼり中の池底」 |
午前中、第130回井の頭かんさつ会があり、一般参加しました。今日のテーマーは「かいぼり中の池底」です。かいぼりで水がなくなり、露出した井の頭池の池底に、長靴履いて降りたち、池の中を見学させていただく又とない機会でした。
池の中の湧水、鳥や動物の足跡、水に張り出した植物の根、復活した水草などと興味津々でした。
参加者は、小学生から、私のような後期高齢者まで(定員50名)5斑に分かれて、井の頭かんさつ会のメンバー他のボランティアのスタッフ14名が、2時間ほど案内役を果たしてくれました。今日は、大変お世話になり、有難うございました。
井の頭池のかいぼりは、今回で2回目、2年後にもう一度計画されているとのことです。
 弁天池 弁天池
 弁天池の見学者 弁天池の見学者
 お茶の水池 お茶の水池
 私@お茶の水池 私@お茶の水池
 ボート池 ボート池
 ボート池 ボート池
 アオサギ@ボート池 アオサギ@ボート池
 アズマヒキガエルの卵 アズマヒキガエルの卵
 井の頭かんさつ会のメンバー(中央) 井の頭かんさつ会のメンバー(中央)
 マンサク マンサク |
|
|
|
| 2016年2月20日(土) |
| 『小説土佐堀川 広岡浅子の生涯』を読む |
NHK朝ドラ「あさが来た」は、毎日楽しく見ている。このドラマの原案本である『小説土佐堀川 広岡浅子』を入手して、読み始めた。
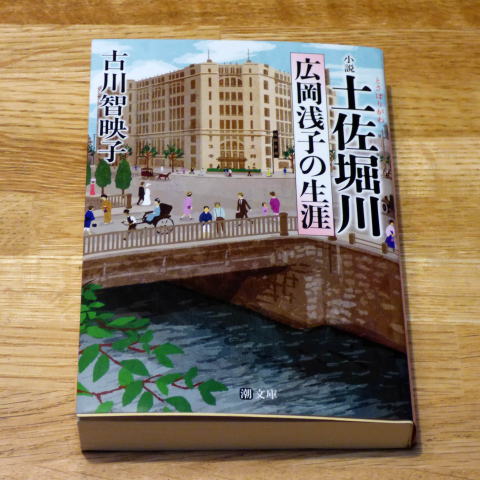 小説 土佐堀川 広岡浅子の生涯 小説 土佐堀川 広岡浅子の生涯
 NHK朝ドラ「あさが来た」 NHK朝ドラ「あさが来た」
まず、あとがきの「解説」を読むと、この本の簡潔な説明があり、大変参考になる。広岡浅子は、慶応元年京都の三井家から、大阪の豪商加野屋に嫁いだ。その加野屋を、両替商から、炭鉱業を始め、近代的な「銀行」業務へ変身させ、大同生命の設立、日本女子大学の前身の開学と大きな夢を次々と実現させていった。大正8年数え71歳で永眠した。
ウイキペディア「広岡浅子」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B2%A1%E6%B5%85%E5%AD%90
が参考になる。 |
|
|
|
| 2016年2月19日(金) |
| 朝の野川自転車散策 |
今朝も富士山がよく見えた。
 富士山 富士山
野川公園自然観察園へは、開門一番乗りで、園内に入りました。園路を少し歩くと、ICU側の茂みに降りていたカシラダカ20羽ほどが、私の気配に感じで一斉に飛び去りました。幸い1羽だけが、近くの木の枝に止まってくれ、何とか写真が撮れました。ジョウビタキの雄がいました。逆光の中でしたので、シルエットだけとなりました。ザゼンソウも大分膨らんで来ました。
 自然観察園 自然観察園
 カシラダカ カシラダカ
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 ザゼンソウ ザゼンソウ
野川では、久しぶりにカワセミに会いました。下くちばしが赤いので雌でした。モズもいました。帰りに神代植物公園の喫茶室(グリーンサロン)でコーヒを一杯頂き、一息つきました。
 カワセミ(雌) カワセミ(雌)
 モズ モズ
 ちょっと一息 ちょっと一息 |
|
|
|
| 2016年2月18日(木) |
| 武蔵野の森公園の朝 |
寒い朝の武蔵野の森公園修景池には、冬鳥のヒドリガモが沢山います。池の遠くの端にいたたヒドリガモの群れが、私の方に移動をしてきたが、途中で移動を止め、離れた位置にとどまった。私の感じたことは、誰かが餌を与えていて、私のことを勘違いして近づいてきたが、そうでないことに気がついて、とどまったようだと言うことです。同じことは、オナガガモで何度も経験済みです。
 ヒドリガモの群れ ヒドリガモの群れ
池の水辺には、アオサギが休んでいました。バン2羽も、餌を探していました。
 アオサギ アオサギ
 バン バン |
|
|
|
| 2016年2月18日(木) |
| 冬の野鳥観察会@野川公園付近 |
毎年冬の野鳥が多いこの時期、NPO法人花と緑のまち三鷹創造協会主催の「冬の野鳥観察会」が、野川公園を会場に開催されていて、初心者に野鳥観察の楽しさを教えてくれている。私もよく参加している。
今日の講師は、日本野鳥の会の鈴木正男氏と畑島征雄氏の2名でした。鈴木正男氏は、私が知っている範囲でも、10年以上前から講師を務めていただいていて、双眼鏡の使い方、冬鳥、留鳥、漂鳥などの区分、野鳥の飛び方、食べものなど、野鳥観察の基本的な事柄を丁寧に教えてくださる。尚、鈴木正男氏は、長いあいだ多磨霊園で毎月第2日曜日に行われている日本野鳥の会東京支部の野鳥観察会で世話人を担当されているそうだ。
今日の参加者は、20名あまりで、やはり初心者が多かった。講師を含めスタッフは5名で、参加者のお世話をする。コースは、9時半に野川公園正門前に集合して、野川公園内を梅園を通過して、ゆっくり自然観察センターの方に野鳥を観察しながら移動する。センター前の桜橋を渡ってからは、野川の左岸、途中樫橋からは右岸を下り、人見街道街道にある相曽浦橋下流の三角広場で、最後に鳥あわせをして、12時半ごろ解散した。
観察できた鳥は27種でした。主なものはノスリ、トビ、ツグミ、コゲラ、モズ、シジュカラ、カワラヒワ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、カルガモ、マガモ、オナガガモ、カワウなどでした。
 観察中の参加者 観察中の参加者 |
|
|
|
| 2016年2月17日(水) |
| 野川にて |
予想通り、今朝も、富士山がきれいでした。
 富士山 富士山
野川では、久しぶりにカワセミの写真がとれました。昨日見なかったオナガガモが、数は減りましたが、4羽だ残っていました。今日もモズを見かけました。他には、ジョウビタキ、ハクセキレイ、カルガモ、カワウ、コサギ、ツグミ、ムクドリ、スズメを見ました。
 カワセミ カワセミ
 オナガガモ オナガガモ
 モズ モズ
日当りがいいところでは、カントウタンポポやホトケノザがさいていました。
 カントウタンポポ カントウタンポポ
 ホトケノザ ホトケノザ |
|
|
|
| 2016年2月16日(火) |
| 講座「未来へつなぐ植物標本」 |
午後、神代植物公園植物多様性センターで、加藤英寿氏(首都大学東京 牧野標本館)を講師に迎え、「未来につなぐ植物標本」と題する講座があり、受講させていただいた。講座は今日2月16日と2月23日との2回の連続講座で、今日はその第1回目でした。受講者は、約20名で、男性は私1名だけでした。
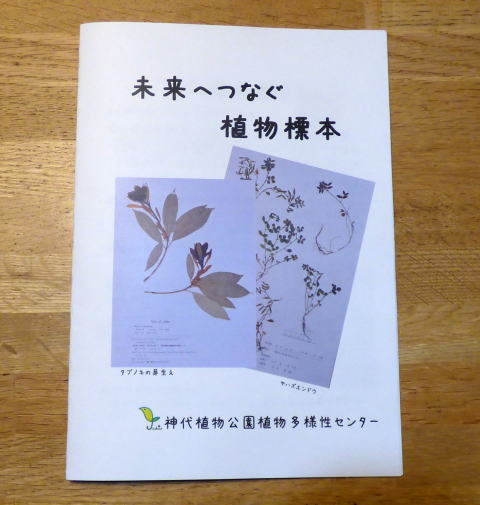 テキスト テキスト
今日、学んだことは、
『標本とは、長期的に保存可能な個体(またはその一部)だが、個体と「ラベル」の両方が揃っていないといけません。』
また、『植物標本の役割は、
①命名のための基準
②植物の名前を調べる(同定)
③植物の特徴や変異を調べる
④植物の季節的な変化を知る
⑤地域の自然環境とその変化を調べる
⑥調査研究の証拠として
利用される』とのことです。。
今日は、講義の後、実地に植物採取をして、「仮押し」までの作業を実習しました。
本講座を終了して、いい植物標本を作ると、牧野標本館に保管をしていただく可能性も開けるようで、私としては、何とか野川の自主種のフジバカマの植物標本を作りたいと考えている。
 「仮押し」 「仮押し」
|
|
|
|
| 2016年2月16日(火) |
| 野川公園梅園の梅 |
今朝、出かけた野川公園梅園では、梅の花がよく咲いていた。
 梅 梅
 梅 梅
 梅 梅
 梅 梅
野川では、カワセミ、モズ、カルガモ、ムクドリ、コサギ、ハクセキレイ、セグロセキレイなどを見かけたが、冬鳥のオナガガモとマガモの姿はなかった。この間の高い気温のせいで、すでにこの地を去ってしまったのであろうか?
 モズ モズ |
|
|
|
| 2016年2月14日(日) |
| 自生種のフジバカマとカワラナデシコの苗. |
昨年11月始めにセルポットに種を蒔いたフジバカマとカワラナデシコを、12日セルポットから、直径10cmほどのポットに植え替えました。寒いときですが、元気に育ってほしい。
 フジバカマ フジバカマ
 カワラナデシコ カワラナデシコ
今年は、日当りが悪く、数は、いずれも30株と少ないが、4月になれば、近くの公園などに移植させてもらうつもりです。
|
|
|
|
| 2016年2月14日(日) |
| ご近所の「しだれ梅」 |
東京は、春一番が吹き、南風で気温も上がりました。隣の子は、半袖姿で遊んでいました。ご近所の梅も満開で、華やかです。珍しい、ご近所の「しだれ梅」も満開です。
 しだれ梅 しだれ梅
風をひいて2日ほど、微熱がありましたが、昨日、医者に見てもらい、薬を飲んだら、今朝は、平熱になりました。
|
|
|
|
| 2016年2月11日(木) |
| 野川の朝 |
今朝の富士山は、今年一番の姿でした。
 富士山 富士山
野川公園自然観察園では、ザゼンソウが咲き始めた。
 ザゼンソウ ザゼンソウ
その近くに、カシラダカがいました。
 カシラダカ カシラダカ
 カシラダカ カシラダカ
|
|
|
|
| 2016年2月10日(水) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(2月) |
少し風がありましたが、今朝、野川に注ぐ湧水量の2月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、昨年の9月をピークに減少しています。
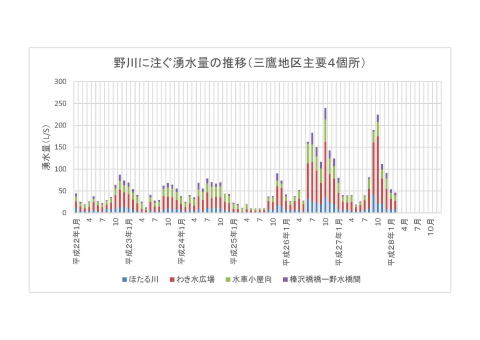 湧水量の推移 湧水量の推移
 ホタル川での測定の様子 ホタル川での測定の様子
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。
自然観察園の入り口付近で、モズの姿がありました。野川の高水敷では、ナノハナが少しですが、咲いていました。
 モズ モズ
 ナノハナ ナノハナ
|
|
|
|
| 2016年2月9日(火) |
| 野川の流量測定(2月) |
今日は、幸い暖かかったので、午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。昨年の9月をピークに流量は減少している。
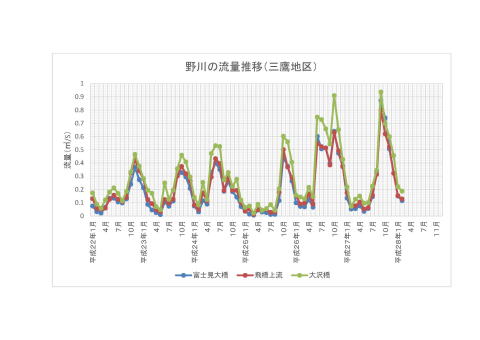 野川の流量推移 野川の流量推移
 飛橋付近での流量測定の様子 飛橋付近での流量測定の様子
飛橋上流での測定を終わり、次の測定場所に移動する途中、野川の水辺で、ジョウビタキの姿を見かけた。
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌) |
|
|
|
| 2016年2月8日(月) |
| ジンチョウゲのつぼみ@野川公園 |
今朝も冷え込んだ。でも、雲があり、富士山は見えない。野川公園の端では、春を待つジンチョウゲのつぼみが膨み始めた。
 ジンチョウゲ ジンチョウゲ
今日も、ジョウビタキ(雌)とモズに会えた。ツグミの数は多いが、今年はシメの数が少ないようだ。
 ジョウビタキ ジョウビタキ
 モズ モズ
 ツグミ ツグミ |
|
|
|
| 2016年2月7日(日) |
| 植物多様性センターにて |
神代商物公園植物多様性センターでは、花の少ない時期ですが、武蔵野ゾーンにユキワリソウが一輪咲いていました。伊豆諸島ゾーンの外側に、フクジュソウが咲いていました。教えていただいて、初めて気がつきました。ジョウビタキ(雌)が鳴いていました。
 ユキワリソウ ユキワリソウ
 フクジュソウ フクジュソウ
 ジョウビタキ ジョウビタキ |
|
|
|
| 2016年2月6日(土) |
| フクジュソウ |
国分寺市の殿ヶ谷戸庭園では、今、フクジュソウが咲いています。
 フクジュソウ フクジュソウ
 フクジュソウ フクジュソウ
|
|
|
|
| 2016年2月6日(土) |
| 国分寺市環境シンポジウム |
午後、第11回国分寺市環境シンポジウム『武蔵野の動植物~生物多様性の保全に向けて~』が、国分寺駅ビル8階の国分寺Lホールで行われた。
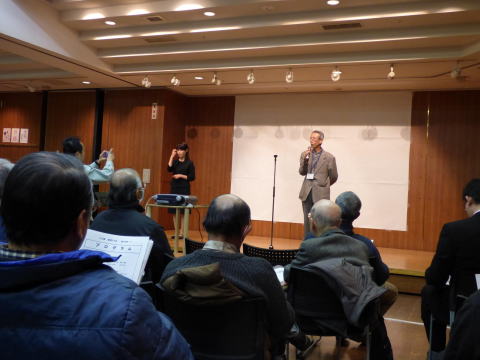 主催者挨拶 主催者挨拶
講演は①中西由美子さんの『多摩地域の自然環境の変化~植物~』、と林鷹央氏『東京の昆虫や鳥 ~身近な生きものの観察の楽しみ~』があり、併せて、環境3団体の①国分寺にふるさとをつくる会、②ミズモリ団、③緑と自然を育てる会の紹介があった。参加者も多く、大変盛会でした。
私は、せっかく国分寺市に行くので、シンポジウムの前に、西国分寺駅から、日影山、姿見の池を見て、IRの線路沿いに国分寺駅まで歩き、更に、JR中央線の南側にある、湧水が日立中央研究所の庭から、野川に流れでるためのJR中央線下のトンネルの出口を久しぶりに見学した。
 トンネル トンネル
 トンネル トンネル |
|
|
|
| 2016年2月5日(金) |
| 今朝の富士山 |
今朝は、富士山がきれいに見えました。 手前をハトの群れが飛んでいました。


|
|
|
|
|
|
| 2016年2月5日(金) |
| カシラダカ@自然観察園 |
今朝、野川公園自然観察園で、カシラダカに会いました。園内の湧水の水たまりにおりていました。近寄ると逃げてしまうので、遠くからとりました。
 カシラダカ カシラダカ
 カシラダカ カシラダカ
その他は、モズ、ジョウビタキ、ツグミ、メジロ、シジュウカラ、シロハラなどもいました。シロハラは、人の気配で直ぐに逃げてしまうので、残念ながら、なかなか写真には撮れません。
 モズ モズ
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌) |
|
|
|
| 2016年2月4日(木) |
| 今朝は、アオゲラに会いました。 |
アオゲラは日本固有種です。今朝、開園前の野川公園自然観察園の入口付近で見かけました。このアオゲラは、雄のようです。図鑑によると、雄は、頭上から後頭、顎線まで赤いが、雌は後頭から顎線が赤く、頭上は赤くないそうです。尚、アオゲラと言っても、体の上面は、青ではなく、緑(黄)色です。
 アオゲラ アオゲラ
野川の相曽浦橋下流にある湿性花園で、アオジにも会いました。足音で草地から飛び上がり、枝に止まってくれたので写真がとれましたが、草地にいると、姿を見分けるのは難しです。
 アオジ アオジ
野川では、カワセミもいました。獲物をとって、飛び去っていきました。
 カワセミ カワセミ |
|
|
|
| 2016年2月3日(水) |
| 日立目白クラブにてOB新年会 |
|
|
|
| 2016年2月2日(火) |
| 神代植物公園にて |
昼ごろ、神代植物公園にでかけた。フクジュソウとクリスマスローズが、少し咲いていた。築山では、寒桜が咲いていた。例年より早いようだ。ミツマタが開花し始めた。ウメ園では、紅鶴など早咲きのウメが咲いていた。
 フクジュソウ フクジュソウ
 クリスマスローズ クリスマスローズ
 クリスマスローズ クリスマスローズ
 寒桜 寒桜
 寒桜 寒桜
 ウメ(紅鶴) ウメ(紅鶴)
 ミツマタ ミツマタ |
|
|
|
| 2016年2月2日(火) |
| 自然観察園の朝 |
今朝は、寒かった。富士山が見えた。
 富士山 富士山
野川公園自然観察園では、寒いのにボランテァイが9時から自主活動をしていた。木の枝に止まったツグミが、寒そうに体を膨らませていた。ジョウビタキ(雌)の姿もあった。後はヒヨドリとシジュウカラなどで、今年は鳥が少ないようだ。セツブンソウは、今日も咲いていた。
 ツグミ ツグミ
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 セツブンソウ セツブンソウ |
|
|
|
| 2016年1月30日(土) |
| 80歳代になって |
| 昨年6月で満82歳になった。すっかり歳をとってしまった。70歳代に行ったことをふりかえり、けじめをつけておきたと考えている。多分これからの数年間は人生の最後の時期になろう。悔いのないように生きたい。
(全文は 80代になって で見てください。)
|
|
|
|
| 2016年1月30日(土) |
| 講演会「水と緑のまち国分寺をめざして」 |
| 今日の午後、国分寺市立いずみホールで、環境省自然環境計画課課長補佐 木村吉寿氏の「自然再生推進法及び基本方針見直しの背景」と題する講演会があり、ききに行ってきました。
今日の講演会の主催者は、NPO国分寺市にふるさとをつくる会を幹事団体として、約20の協定団体とで作る「野川源流自然再生設立準備会」で、この会は、「野川源流自然再生協議会」の設立をめざしているとのことです。国分寺市付近では、町内会、自治会を含むこんなに多くの市民団体が、野川源流の自然を守る活動をしていることには、驚きでした。
自然再生基本方針の見直しのポイントは、
①地域の産業と連携した取組み
②自然再生の継続実施
③自然再生における希少種及ぶ外来種対策
④東日本大震災の経験を踏まえた自然再生
⑤自然再生の役割
⑥全国的、広域的な視点に基づく取組の推進
⑦小さな自然再生の推進
とのことでした。⑦の小さな自然再生の推進に関して、「小さな自然再生活動事例集」が、環境省にHPで閲覧できるとのことでした。是非見たみたいし、また、我々の活動も。、この事例集に取り上げられることを望みたいと思いました。
 講演会の様子 講演会の様子
|
|
|
|
| 2016年1月28日(木) |
| 野川に注ぐ湧水量の測定(1月) |
今朝、野川に注ぐ湧水量の1月分の測定を行いました。 測定個所は、主要4個所だけ。湧水量は、昨年の9月をピークに減少しています。
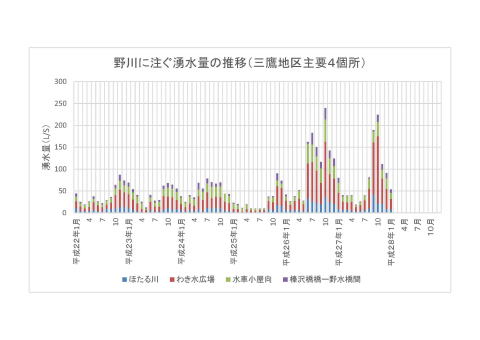 湧水量の推移 湧水量の推移
三鷹だけでも、清流・野川に注ぐ湧水は、10ヶ所以上ありますが、湧水量が多い4ヶ所(①柳橋ほたる川、②くぬぎ橋下流湧水広場、③飛橋上流水車小屋向い、④野水橋・榛澤橋間)に絞り、平成22年月から毎月1回6年間、定期的に測定をしています。測定は、野川に注ぐ直前のポイントで測っています。今年も、無理のない範囲で継続することにしました。
野川の高水敷では、ホトケノザとオオイヌノフグリが、早くも、少し咲いていた。
 ホトケノザ ホトケノザ
 オオイヌノフグリ オオイヌノフグリ |
|
|
|
| 2016年1月27日(水) |
| 野川の流量測定(1月) |
今日は、午前中、三鷹地区の野川の3箇所(上流側から、富士見大橋下流、飛橋上流、大沢橋下流の3箇所)で、流量測定を行った。昨年の9月をピークに流量は減少している。
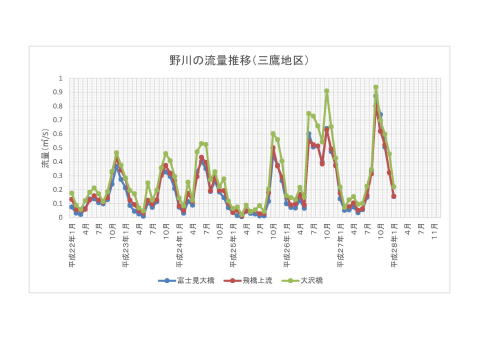 野川の流量推移 野川の流量推移
 飛橋付近での流量測定の様子 飛橋付近での流量測定の様子
この測定は、平成22年1月から、実施していて、昨年末で6年間となる。測定は、市民でも出来るような簡便な方法で行っていて、川幅3箇所、水深9箇所と、浮子を流して表面の流速を3箇所(川の中央、左側、右側)測り、流量を算出している。
月1回の野川の流量測定も、今月から7年目に入り、体調を考えて、一旦はやめようと思っていたが、体調がいいときは、測定を続けることに考えを変えた。無理のない範囲で実施することにし、今日は幸い、寒中にかかわらず、暖かかったので、実施した。
野川に入り流量測定をしていると、時には、思いがけない出会いがある。、今日は、大沢の水車小屋付近で、消防訓練が行われ、流量測定の終わり頃、直ぐ上流側で、消防車から、野川に向けて消火水の放水が行われた。
 野川への放水 野川への放水 |
|
|
|
| 2016年1月26日(火) |
| 野川公園自然観察園にて |
今日は、富士山には一条の雲がありましたが、大変きれいに見えました。
 富士山 富士山
野川公園自然観察園内では、間近にシロハラに会いました。その他、ジョウビタキ(雄)(雌)、モズ、ツグミがいました。かがみ池にカワセミの姿がありましたが、直ぐに飛び去りました。
 シロハラ シロハラ
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 モズ モズ
 ツグミ ツグミ
セツブンソウの花がきれいでした。
 セツブンソウ セツブンソウ |
|
|
|
| 2016年1月25日(月) |
| ホームページ「シニア物語」のURLの変更について |
| 2005年(平成17年)に、niftyのホームページサービスを利用して、ホームページ「シニア物語」を作ってから11年が経過した。このサービスは容量の上限が300Mbであった。写真を多く使うためには、もっと大きな容量が必要で、大きな制約となっていた。実際には、仕方なく古い写真を削除して、対応していた。
今年になって、Niftyが、容量上限10Gbの新しいホームページサービスを提供してくれることになり、古いサービスは今年の9月29日で終了するとの通知が来た。これまで月額約500円のサービスであったが、新サービスでは上限4Gbでも、月額約450円と割安になったので助かる。
今日、早速、新サービスへ切り替え作業を行った。その結果、私のホームページ「シニア物語」の新たなURLは、http://ada.c.ooco.jp/ となった。尚、これまでのURLでアクセスする際には、1年間ほどは、「移転通知」のサービスをしてくれそうで、助かる。
|
|
|
|
| 2016年1月24日(日) |
| 今朝の野川&野川公園散策 |
寒い朝でした。晴れていたが、富士山は見えませんでした。少し雪が残る野川を歩き、野川公園自然観察園で、探鳥をしました。野川公園の南側の梅園の桜も3本ほどは、寒さの中、よく咲いてきました。
 ウメ ウメ
 ウメ ウメ
自然観察園内では、今日は、ジョビタキ(雄)が、枯れ葉をかき分け、ミミズを捕まえていました。
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
遠くの園路にシロハラの姿も見かけましたが、直ぐに隠れてしまいました。その後、園内では、別のシロハラが、比較的近い木の中に隠れているところを見つけ、何とかカメラに収めました。
 シロハラ シロハラ
 シラハラ シラハラ
知らずに近づくと、ツグミが枝に飛び上がる姿をよく見かけました。
 ツグミ ツグミ
 野川 野川 |
|
|
|
| 2016年1月23日(土) |
| 自生種のフジバカマとカワラナデシコの苗 |
昨年11月10日にセルポットに種を蒔いたフジバカマを、セルポットから、直径10cmほどのポットに植え替える時期が近づいてきました。毎年、1月末から2月始めに行っています。
でも、今年は、発芽率も発育の様子も悪く、少し心配です。原因は、自宅南側に建売住宅ができ、日照が悪くなったためと思います。
 フジバカマ フジバカマ
 カワラナデシコ カワラナデシコ |
|
|
|
| 2016年1月22日(金) |
| 今日の野川散策 |
今日は、風がなく、富士山には雲一つ無く、大変きれいに見えました。野川の水辺の、日当りがよくないところには、まだ雪が残っています。
 富士山 富士山
 野川の桜橋下流の風景 野川の桜橋下流の風景
野川公園自然観察園内では、今日も、ジョウビタキ(雄)(雌)に、会いました。その他、モズ、ツグミ、それからかがみ池には、マガモのペアがいました。
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 モズ モズ
 マガモ・ペア マガモ・ペア
一度雪に埋まったセツブンソウもまた花をつけていました。
 セツブンソウ セツブンソウ |
|
|
|
| 2016年1月21日(木) |
| 井の頭公園池のかいぼり |
午後、井の頭公園に立ち寄った。昨年秋に弁天池の水を抜いて、今年に入ってお茶の水池とボート池の水抜きが行われていて、池には水がほとんど無い。予定では1月29日から2月23日の間、天日干しが行われるそうだ。その後にまた水を入れ、魚の放流がおこなわれる予定だそうです。
 御茶の水池 御茶の水池
 ボート池 ボート池
 ユリカモメとオオバン ユリカモメとオオバン
 オオバン オオバン |
|
|
|
| 2016年1月21日(木) |
| 歯のクリーニング |
今日は、6ヶ月に一回の歯のクリーニングに、御茶の水の病院まで出かけてきました。40分ほどかけて、丁寧に処置をしてくれました。最後に「よく磨けてます」との評価を頂きました。現在、自分の歯は、23本残っています。
「8020(ハチマルニイマル)運動」と言うのがあります。これは厚生省と日本歯科医師会が提唱している、「80歳で20本の自分の歯を残し、なんでもよく噛める快適な状態に保とう」という運動です。悪くならないうちに、むし歯の治療や歯みがき指導を受け、更に歯石をとってもらうなど、歯周病の予防につとめることが大切だと云われています。これからも、自分の歯を20本以上は残せるように、管理していきたいと思っています。いつまでも自分の歯でおいしく食べたいものです。 |
|
|
|
| 2016年1月20日(水) |
| 雪の野川を散策 |
晴れましたが、やはり富士山には雲がかかっていました。
今朝も、野川を歩いて、野川公園自然観察園で1時間半ほど探鳥をしました。人の姿も、鳥の姿は少なかったが、ジョウビタキの雄と雌、モズ、ツグミ、コゲラ、シジュウカラなどがいました。積雪で、とことどころ大きな枝が折れていました。折れた枝の処理が終わるまでは、自然観察園の一部は、立ち入り禁止となっていました。
 富士山 富士山
 ジョビタキ(雄) ジョビタキ(雄)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 モズ モズ
 ツグミ ツグミ
 コゲラ コゲラ |
|
|
|
| 2016年1月19日(火) |
| 積雪の野川 |
今朝は、長靴履いて、雪の野川を歩きました。国立天文台裏の国分寺崖線から102段の階段をありて、飛橋で野川に出ました。そこから、上流へ野川公園内の自然観察センター前の桜橋まで、野川の水辺を雪を踏んで歩きました。
 飛橋上流 飛橋上流
 湧水広場付近 湧水広場付近
 自然観察センター下流 自然観察センター下流
野川のくぬぎ橋(湧水広場)付近付近で、カワセミとカワラヒワに会いました。その他、ハクセキレイ、カルガモ、オナガガモ、マガモ、アオサギ、コサギ、スズメなども餌を探していました。
 カワラヒワ カワラヒワ
 カワラヒワ カワラヒワ
 カワラヒワ カワラヒワ
 カワセミ カワセミ
 ハクセキレイ ハクセキレイ
 スズメ スズメ |
|
|
|
| 2016年1月19日(火) |
| 今朝の富士山 |
雪雲が去って、今朝は真っ青な青空でした。でも風があって、国立天文台裏の国分寺崖線の上から見た富士山には雲がかかっていました。
 富士山 富士山
 富士山 富士山
国立天文台構内の竹林にも雪が積っていました。
 竹林 竹林 |
|
|
|
| 2016年1月18日(月) |
| 雪の朝 |
この冬初めて積雪があった。私の家(三鷹市)では午前6時ごろ測ったら13cmあった。でも雪は直ぐに雨になった。雨が小降りになってから、スコップで家の回りの道の雪かきをした。
庭の花壇にも雪が積ったが、端の方にパンジーが顔をのぞかせていた。
 花壇のパンジー 花壇のパンジー |
|
|
|
| 2016年1月17日(日) |
| 野川の「冬季・生きもの観察会」 |
午前中、野川の柳橋付近で、野川流域連絡会生きもの分科会主催の「冬季・生きもの観察会」が行われた。私もスタッフの一員として参加しました。今日は、野川公園ボランティアの定例活動日でもあり、集合場所の自然観察センター付近には、顔見知りのボランティアの姿もあった。
午前10時に、野川公園自然観察センターに、一般参加の親子約30名が集まり、まずは今日のスケジュールの説明と野川ルールの説明後、外に出て軽い準備運動を行った。 その後、前半は、ほたる川(湧水の小川)の補修作業(主にくい打ち)、後半は、ほたる川と野川で、生きものを採取した。最後の30分ほど、採取した生きものの説明を専門家であり委員でもある小金井の平井さんから受けた。
子供たちも、親と一緒にくい打ちをしていた。後半は、野川やほたる川に入り手網で粘り強く生きものを追いかけた。
野川では、オイカワ、タモロコ、マキガイ、カワニナ、メダカ、ミナミヌマエビ、アメリカザリガニなどを、湧水の小川(ほたる川)では、アメリカザリガニ、ミナミヌマエビ、タイワンシジミ、ガガンボウの幼虫などを採取し、観察した。
採取した生きものは、調査後に、また、元の場所に戻した。
次回は、野川の「夏季・生きもの観察会」が8月に開催される予定です。野川流域の各市の広報に案内が掲載されます。
 湧水の小川の補修作業 湧水の小川の補修作業
|
|
|
|
| 2016年1月16日(土) |
| 今朝の富士山 |
今朝は、晴れて、富士山がきれいに見えました。
国立天文台裏の国分寺崖線の上から撮影しました。
 富士山 富士山 |
|
|
|
| 2016年1月16日(土) |
| 野川公園野鳥観察会 |
午前中、野川公園野鳥観察会に久しぶりに参加しました。9時に自然観察センターをスタートし、2時間半、自然観察園内、公園南地区、北地区を回り、最後は、自然観察センター内で今日みた鳥の確認をしました。
今日は全体では30種を確認できました。主なものは、マガモ、カルガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ノスリ、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ヤマガラ、エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、カワラヒワ、シメ、カシラダカ、アオジなどでした。私もその内の数種の写真をとりました。
今日のハイライトは、国際基督教大学構内の大きな木の枝に止まっていたノスリを野川の対岸から確認出来たことでした。この木には、よくオオタカがいることがありますが、今日はノスリでした。観察会の一般参加者は、50名弱で、それを公園ボランティア約10名が案内しています。次回は2月13日(土)の予定です。
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 アオジ アオジ
 マユミの木にメジロ マユミの木にメジロ
 マユミの赤い実を食べるメジロ マユミの赤い実を食べるメジロ
 カワラヒワ カワラヒワ
 コゲラ コゲラ
 ノスリ(遠いので証拠写真程度です) ノスリ(遠いので証拠写真程度です)
 ノズリを観察する参加者たち ノズリを観察する参加者たち
 セツブンソウが開花 セツブンソウが開花 |
|
|
|
| 2016年1月15日(金) |
| 男の料理:ぶり大根 |
今夜は、ぶり大根を作りました。
 ぶり大根 ぶり大根
|
|
|
|
| 2016年1月15日(金) |
| 自然観察園の今日の野鳥 |
早朝は、野鳥の動きが比較的活発です。野川公園自然観察園で、今日は、シロハラ、ジョウビタキ、ツグミ、シメ、シジュウカラ、アオサギなどを見ました。
 シロハラ シロハラ
 シロハラ シロハラ
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 ツグミ ツグミ
 シメ シメ
 シジュウカラがマユミの木に シジュウカラがマユミの木に
 飛ぶシジュウカラ 飛ぶシジュウカラ
 アオサギ アオサギ |
|
|
|
| 2016年1月14日(木) |
| 今朝の野鳥 |
寒いので家にこもりがちになるが、今朝も、自転車で出かけ、1時間半ほど、野川公園自然観察園で探鳥をした。ツグミ、シメ、ジョウビタキ(雌)、シジュカラ、ヒヨドリ、マガモなどを見た
 今朝の富士山 今朝の富士山
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 シメ シメ
 ツグミ ツグミ
 しょうぶ池 しょうぶ池
 園路 園路
その他、帰りに、野川でモズ、アオサギ、コサギ、オナガガモ、カルガモ、
 モズ@野川 モズ@野川
 カワラヒワ@国際基督教大学グラウンド カワラヒワ@国際基督教大学グラウンド
|
|
|
|
| 2016年1月13日(水) |
| 国際基督教大学のウメ |
昼ごろ、国際基督教大学構内のウメの様子を見て来ました。すでに花が咲き始めていました。



|
|
|
|
| 2016年1月13日(水) |
| 朝、自然観察園で探鳥 |
今朝は、冷え込んだ。霜が出来たようだ。寒い中を、野川公園自然観察園に探鳥に出かけた。
 富士山 富士山
エナガの群れが木の枝を移動していた。エナガは、体は小型で、下面がぬいぐるみのようにふわふわの毛があり、長い尾羽をもっている。主に動物食で、昆虫などを食べている。よくシジュウカラ、コゲラ、メジロなどと混群を作って、移動している。
 エナガ エナガ
 エナガ エナガ
今年初めて、冬鳥のシロハラも会えました。どこからか飛んできて、園路に止まってくれたが、直ぐに飛び去ってしまった。明るいところはあまり好まないようで、見つけ難い鳥です。
 シロハラ シロハラ
 シロハラ シロハラ
今日も、ジョウビタキの雄と雌に出会った。別々の縄張りをもっていると思っていたが、今日は、一時、近い位置にいたが、直ぐに別れてしまったようだ。「ヒッ、ヒッ、ヒッ」と鳴く声で、探すと見つかることが多い。
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
自然観察園横の野川の土手の日当りがいいところで、タンポポが、咲いているのを見つけました。カントウタンポポのようでした。
 カントウタンポポ カントウタンポポ
 カントウタンポポ カントウタンポポ |
|
|
|
| 2016年1月12日(火) |
| 東京都心で初雪 |
今年初めての本格的な寒波。東京都心でも初雪があった。例年より10日ほど遅い。北海道では-23.9℃を記録したそうだ。三鷹市でも、寒く、まだ小雨であったが、雪が降ってもおかしくなかった。今夜は更に冷え込みそうだ。
今日は一日、自宅に引きこもった。午前中は、PCのHDDにある写真を、外付けのHDDに移動し、PC内のHDDの使用中の容量を減らし、PCを軽くした。沢山あったので、結構時間がかかった。
午後は、今年来た年賀状を改めて読み返し、整理をした。喪中や寒中お見舞いの人が年々増えるのは、歳相応だと感じる。高齢の方は、こちらから出しているが、年賀状をいただけないと、お元気なかと心配になる。
日頃は音沙汰ないが、年賀状で、私のHP(シニア物語など)などを見ていて、カワセミや花の写真をほめてくれる人もいて、私のブログが少しは役にたっているのがうれしい。
 野川のカワセミ(1/11撮影) 野川のカワセミ(1/11撮影) |
|
|
|
| 2016年1月11日(月) |
| 植物多様性センターにて |
今日は、神代植物公園植物多様性センターで、モズとエナガの群れにあいました。
 モズ モズ
 エナガの飛ぶところ① エナガの飛ぶところ①
 エナガの飛ぶところ②(①の直後) エナガの飛ぶところ②(①の直後)
 エナガ2羽 エナガ2羽
|
|
|
|
| 2016年1月11日(月) |
| 今朝も自然観察園で探鳥 |
今朝も、野川公園自然観察園で探鳥。今朝はやっとジョウビタキ(雄)に会えた。ツグミが、少しずつ地上に降りて、落ち葉の下の何かを食べていた。
 ジョウビタキ(雄) ジョウビタキ(雄)
 ツグミ ツグミ
 ツグミ ツグミ
今年は園内の池の水が多い。かがみ池にはマガモ5羽が、しょうぶい池にはアオサギが来ている。
 かがみ池 かがみ池
 マガモ マガモ
 しょうぶ池 しょうぶ池
 アオサギ アオサギ
早くも、今年はセツブンソウが、もう少しで咲きそうな様子だ。
 セツブンソウ セツブンソウ
|
|
|
|
| 2016年1月10日(日) |
| 神代植物公園にて |
朝、1時間半ほど、神代植物公園を見学しました。芝生広場では、カワラヒワの群れがいました。残念ながら、物音で、直ぐに飛び去りました。
 カワラヒワ カワラヒワ
 カワラヒワ カワラヒワ
梅園では早咲きの白難波が大分咲いていました。八重寒紅も少し咲いていました。ツバキ・サザンカ園では、公園自慢のツバキ「神代都鳥」の花が咲いていました。
 ウメ 八重寒紅 ウメ 八重寒紅
 ツバキ 神代都鳥 ツバキ 神代都鳥
桜園では、早咲きのコブクザクラ、ジュウガツザクラ、フユザクラが、少し花をつけていました。
 コブクザクラ コブクザクラ
 ジュウガツザクラ ジュウガツザクラ
 フユザクラ フユザクラ
冬ボタンの展示もありました。
 ボタン ボタン
 ボタン ボタン |
|
|
|
| 2016年1月10日(日) |
| 野川の朝 |
今朝は、国立天文台裏の国分寺崖線の上から富士山が大変きれいに見えました。崖をおりて飛橋から野川をみると、ユリカモメの群れ、コサギの群れ、ダイサギ、オナガガモの群れなどがいました。
 富士山 富士山
 野川 飛橋上流 野川 飛橋上流
 ユリカモメ、コサギ、ダイサギ、オナガガモ ユリカモメ、コサギ、ダイサギ、オナガガモ
野川の少し下流では、カワセミやアオサギにも会えました。
 カワセミ カワセミ
 ユリカモメ ユリカモメ
 アオサギ アオサギ
|
|
|
|
| 2016年1月9日(土) |
| 今日もジョウビタキ(雌) |
今日も、野川公園自然観察園に冬鳥を探しに出かけました。今日も、ジョウビタキ(雌)に会いました。園内の別のところに、ジョウブタキ(雄)が、縄張りを作っているようですが、私にはなかなか会えません。
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
シメ、ツグミ、コゲラ、シジュウカラもいました。
 シジュウカラ シジュウカラ
公園では、まだ10月桜が咲いていました。赤池には、水がたっぷりありました。 今日は、公園ボランティアの本年初めての定例活動日のようでした。
 10月桜 10月桜
 赤池 赤池 |
|
|
|
| 2016年1月8日(金) |
| 今日の自然観察園の野鳥 |
寒い朝ですが、今朝も野川公園自然観察園で2時間ほど探鳥をしました。マユミの赤い実にメジロが来ました。エナガの群れが、木の枝を渡っていきました。動きが早いので、写真い撮るのはなかなか難しい。
 マユミの実 マユミの実
 メジロ メジロ
 メジロ メジロ
 エナガ エナガ
シメ、ツグミ、コゲラ、ジョウビタキ(雌)にも会いました。園内のウメが咲き始めていいました。
 シメ シメ
 ツグミ ツグミ
 コゲラ コゲラ
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 ウメ ウメ |
|
|
|
| 2016年1月7日(木) |
| 野川公園自然観察園の野鳥 |
晴れたので、今朝も、野川公園自然観察園に出かけました。シメ、ツグミ、ジョウビタキ(雌)、コゲラに会えました。顔見知りのボランティアの方々が数人、自主活動をしていました。
 シメ シメ
 シメ シメ
 ツグミ ツグミ
 コゲラ コゲラ
 ジョウビタキ(雌) ジョウビタキ(雌)
 自然観察園内 自然観察園内 |
|
|
|
| 2016年1月6日(水) |
| 野川公園自然観察園にて |
今朝、曇空でしたが、野川公園自然観察園に出かけました。ツグミの鳴き声が、木の上から盛んに聞こえた。20羽程度はいるようだ。じっとしていないで、枝から枝に移動していた。
 ツグミ ツグミ
別の小さな鳥も動いた。カメラを向けるとシメであった。シメは、今シーズン初めてでした。
 シメ シメ
 シメ シメ
今日のお目当てはセツブンソウでしたが、まだまだ開花は先のようだった。
|
|
|
|
| 2016年1月5日(火) |
| 今朝の野川の野鳥たち |
今朝も、野川で鳥を探しました。お目当ては、カワセミ、アオジ、ジョウビタキでしたが、みんなだめで、粘っていたらキセキレイ、ツグミ、バンを観察出来ました。ツグミは、なぜか今年は少なく、野川では初認です。
 キセキレイ キセキレイ
 キセキレイ キセキレイ
 キセキレイ キセキレイ
 ツグミ ツグミ
 ツグミ ツグミ
 バン バン
 バン バン
今日は、ユリカモメの姿はなく、カワウを見ました。
 カワウ カワウ |
|
|
|
| 2016年1月3日(日) |
| 神代植物公園のツバキ |
神代植物公園の深大寺門近くのつばき・さざんか園には、260種のツバキがあり、一部が咲いています。初雁、乙女椿、光源氏、我妻絞、唐錦、白露錦、さかさ富士でした。
 初雁 初雁
 乙女椿 乙女椿
 光源氏 光源氏
 我妻絞 我妻絞
 唐錦 唐錦
 白露錦 白露錦
 さかさ富士 さかさ富士
|
|
|
|
| 2016年1月3日(日) |
| 神代植物公園のウメ |
神代植物公園の深大寺門近くの梅園では、70種のウメがあります。今その一部が咲き始めています。白難波、八重寒紅、冬至、蓮久などの品種です。
 白難波 白難波
 白難波 白難波
 白難波 白難波
 八重寒紅 八重寒紅
 冬至 冬至
 蓮久 蓮久 |
|
|
|
| 2016年1月3日(日) |
| 野川の野鳥 アオジ、カワセミ、キセキレイ |
今朝は、富士山がすっきり見えました。
 富士山 富士山
野川では、少し粘って、最近会うことが少ないアオジ、カワセミ、キセキレイの写真を撮りました。ユリカモメの群れはまだ飛んでいました。
 アオジ アオジ
 アオジ アオジ
 カワセミ カワセミ
 カワセミ カワセミ
 キセキレイ キセキレイ |
|
|
|
| 2016年1月2日(土) |
| 今朝の富士山と野川の風景 |
今朝も、国立天文台裏の国分寺崖線の上から富士山が見えました。
 富士山 富士山
102段の階段をおりて、飛橋で野川に出ると、だんだんと日差しがさしてきて、野川の高水敷は、少しづつ暖かい空気に包まれてきました。、正月でまだ高水敷を歩く人は少ない。よくいる鳥は、オナガガモ、カルガモ、マガモ、アオサギ、ダイサギ、コサギとハクセキレイ。今日は、ユリカモメの群れが飛んでいる。カワウが飛び去る。よく探すと、木の陰にアオジが一瞬だけ姿を見せてくれました。対岸の木の枝にはモズが止まっていました。
 オナガガモ オナガガモ
 ユリカモメ ユリカモメ
 アオジの証拠写真 アオジの証拠写真
 モズ モズ
野川公園では、ロウバイが咲いていました。
 ロウバイ ロウバイ
|
|
|
|
| 2016年1月1日(金) |
| 賀正 |
新年おめでとうございます。 今年も宜しくお願いいたします。 毎年、元旦の朝には、家族で、深大寺に初詣をしています。

|
|
|
|
 ロウバイ
ロウバイ ロウバイ
ロウバイ マンリョウ
マンリョウ 富士山
富士山 シメ
シメ シメ
シメ メジロ
メジロ